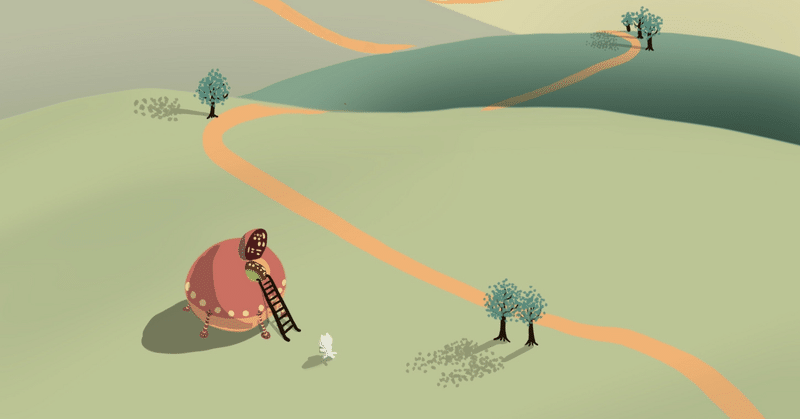
中年の危機と神秘的感覚
カート・ヴォネガット『スローターハウス5』について、もう少し。
主人公ビリー・ピルグリムは、一人娘の結婚式の日に、トラルファマドール星から来た宇宙人に誘拐される。「あらゆる瞬間は、過去、現在、未来を問わず、常に存在してきたのだし、常に存在しつづける」というトラルファマドール流の時間概念に従い、ビリーは時間と空間を自由に行き来する。そればかりか、戦争の現実とSFの宇宙という、まったく異なる世界をも股にかける。
ただし、ビリーはどんな人物かといえば、平凡な男である。事業をそれなりに成功させ、家庭を築き、社会でも私生活でも一定の責任を果たしてきた。
しかし、中年に差し掛かって身体の不調を感じるようになり、また、子供は結婚して家を出ていってしまい、それまで築き上げ守ってきたものの変化を認識せざるを得ない状況にある。その最中で異星人に誘拐されたという事件は、ビリーの人生の転換期の象徴だろう。小説の出版当時47歳だったヴォネガット自身の境遇も反映されていると思われる。
そこから先に進むには、過去と向き合う必要があったのだろう。そして、この小説で扱われている過去の出来事とは、戦争体験である。第二次世界大戦において、ヴォネガットは兵卒としてヨーロッパ戦線に加わり、ドイツ・ドレスデンで終戦を迎えている。
「ドレスデン爆撃についての小説を書いている」と長い間言い続けて、その末に書かれたものが極めて個人的な感触の短い本となったのは、彼自身の必要のために記されたものだからではないかという気がする。
時間は過去から現在、未来へと連綿と続いており、物事には因果というものがあると、普通は誰だって考えている。何事にも原因と帰結があると思っている。それはトラルファマドール星人によれば、「地球人は説明が上手」ということになる。地球の人々は何でもかんでも「なぜ?」と問いかけ、「それは……だから」と結論づける。一方で、トラルファマドール星人にとっては、すべての疑問に対する答えは「この瞬間があるから」である。むしろ、「なぜというものはない」。
けれど、地球人にも、どうしても説明がつかないことというのはある。頭の中で、適当な箱に詰めてラベルを貼って、整理棚の一隅に仕舞い込むという、一連の対処法が効かないものがある。それは自分の意識に居座り続ける。「なぜ?」と問い続けても、答えは見つからない。
そこから目を背けて、一生やり過ごすという方法もある。けれど、ヴォネガットはそうはしなかった。彼はドレスデン爆撃の記憶に対峙することを選んだ。その結果が、『スローターハウス5』である。
作中で繰り返される「そういうものだ」というフレーズがある。だれかが死んだり、なにかが無くなったりする場面で挿入される。
死は、究極の説明しようのないものだと思う。なぜ生きているのか、なぜ死ぬのか。多くの無惨な死を目にし、この問いから逃れられなかった作者の言葉が、「そういうものだ」。それは無感覚や諦念ではなく、抱えきれないものを全身で受け止める言葉だと思う。かすかなユーモアさえ含ませながら。
この点で、第二次世界大戦という具体的な歴史上の出来事を扱うこの小説が、普遍的な性格を持つことになる。
戦争体験について考え続ける必要は言うまでもないとして、この作品はそれだけではなく、人生において直面する説明不可能なもの、究極的には「死」について、作者が到達したところを示している。
それが、トラルファマドール星人の時空のとらえ方であり、「あらゆる瞬間は、常に存在していて、なぜというのはない」のである。
そんなふうに読むと、『スローターハウス5』は宗教性を帯びた小説だと思う。ただし、特定の教義に基づいているというのではない。ごく個人的な神秘的感覚が核心にあると思われる、その意味においてである。
『スローターハウス5』と並行して、『シネマのなかの臨床心理学』(山中康裕他編)という本を読んでいたのだが、その中で映画『告発』(マーク・ロッコ監督)について、宗教性の観点から論じられており、ここを書いたことを考えるにあたって参考にした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
