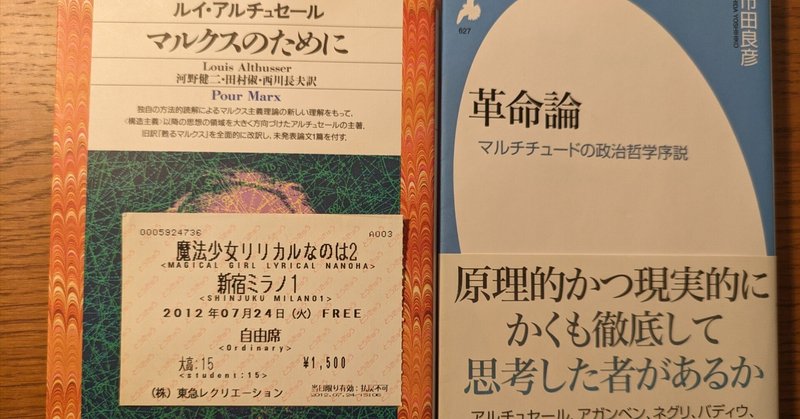
市田良彦『革命論:マルチチュードの政治哲学序説』(2012)
フランス現代思想の「政治哲学」部門のとりまとめ本。
取扱対象としてはポスト構造主義の主役たちよりひと世代後の人々で、ソ連崩壊後・新自由主義時代の哲学者たち。アガンベン、ネグリ、デリダ派(ナンシー、ラクー゠ラバルト)、バディウ、ドゥルーズ派とか。
超乱暴にまとめると、市田的アルチュセールを哲学的チャンピオンとして、それら「様々なる意匠」を撫斬りする感じの内容となっている。
かなり素晴らしい本だという印象を持っていて(そして、ハイブロウなので中身がさっぱり分からなくて)、ちゃんと読むのは3度目。記録によると、刊行直後に読み、2014年の3月10日頃に読んでいる。いまは無き新宿ミラノ座の『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's』(2012)の半券が挟まっていた。いろいろな思いが去来した。
著者の市田は京大出身。浅田彰の1年後輩。
『情況』2018年秋号の回想録(「俺が党だ」)によれば、70年代後半、竹本処分問題で学生運動の残り火が続いていた京大で同学会委員長として活動。
その後はアカデミズムに進んでフランス現代思想研究。専門はアルチュセール。2010年代には京大人文研の「ヨーロッパ現代思想と政治」研究班長として政治モノの現代思想研究を推進・紹介。最近フーコー論を出したみたい。
概要
序章 今日的時点——倫理的な政治
序章では、「革命の哲学」「政治の哲学」を考えてみる市田的モチベーションが説かれる。行論上の論敵は、当時ブームだったサンデルとかに象徴される英米流の政治理論と、レヴィナス的な超俗的普遍倫理のご高説。
市田によれば、どちらも超歴史的な点がダメである。英米系政治理論は、グローバル資本主義+リベラルデモクラシーを所与のものとして、その中での資源配分や多文化共生に問題を局限してしまっている。他方、レヴィナス派のご高説も、無限遠点の高みに坐すユダヤ的普遍倫理から俗世の罪障を一刀両断する達人剣の如きである。
要するに、かつての左翼政治理論の「現存の社会秩序に代えて、いかなる共同性を構想・構築できるか/すべきか?」という「国家と革命」の問いが閑却されている。その点が不満である、と市田は論じる。
第一章 対象としての例外、主体化する例外(その1:アガンベン)
第一章はアガンベンとネグリを市田的アルチュセールの立場から批判的に紹介する内容。スローガン的にまとめると、「アガンベンのメシア主義」と「ネグリのウルトラ主観主義」(がダメである)という感じ。
まずはアガンベン論(pp.24–44)。
アガンベン読解の中心的な典拠は『ホモ・サケル』(伊語原書1995)で、アルチュセールの方は「矛盾と重層的決定」(1965)と、70年代後半に執筆され発狂・殺人事件後に公刊された「偶然性唯物論」の諸テクスト。
市田いわく、アガンベンとアルチュセールは「規則に対する例外が常態化しているというメタ規則」という中心的テーゼを共有している。アガンベンは「法秩序からの例外(=アウシュビッツ)を範例とするような現代世界において、《アウシュビッツ後》を踏まえないような規範理論はありえない」というようなことを説き、アルチュセールは「ロシア革命も中国革命も『資本論』に反する革命であり、例外であった。逆に考えて、例外こそが規則を照らし出す《規則の規則》なのではないか?」と説く。
だが、アガンベンとアルチュセールは結論を異にする。
何の結論を? 政治哲学の使命についての。
何によって? 政治と哲学の媒介項を「存在者化」するか否かによって。
アガンベンによれば、収容所とは「法と事実のハイブリッド」(p.34)である。「収容所にならう世界では、意味も価値も事実的世界から独立自存してはいられない」(p.34)。何千匹もの蠅が血と排泄物の池の上を旋回する死体の山を見よ。「つまり収容所は、世界全体に意味を与えるのである(……)人は意味もなく殺人者となり、意味もなくただ機械的に殺されるという意味を」(p.35)。この範例としての「収容所」が、アガンベン思想では哲学と政治を媒介する蝶番として、意味と規範の開闢点として機能する。市田はこの構造を「媒介の存在者化」(p.37)と整理する。
すると、政治哲学の使命はどのようになる? 市田が描き出すアガンベンは結論においてレヴィナス主義とほとんど変わるところがないようである。アウシュビッツ後のこの世界において、可能な政治構想は、原罪性を刻印された主権権力に代わるヨリよき共同性を探し求めることに尽きる。その「救済」がどう実現されるのかは分からないのだが……。これが、アガンベンの「メシア主義」ということだ。
アルチュセールは? 彼もまた、「世界には自存的な意味も価値もない」という哲学的テーゼをアガンベンと共有している(偶然性唯物論)。だが、その世界像を政治へと接続する「収容所」のような媒介項が、アルチュセールには欠けている。
世界の形成が偶然であるから、「私たち」は「革命」から切り離される。(……)偶然は、ただ「ある」だけの原子の世界と、意味や原因や目的を生成させる「私たち」の世界の間に横たわっており、つまり両者を分離しており、〈法〉と〈事実〉の両方の不在を指し示すのである。
その帰結は、政治哲学についてのヴィジョンの相違として現れる。意味も価値もない世界において、「私たち」は例外(=革命)の前に突然引き立てられ、それを取り扱うよう求められることになる。「主体による『治療』としての政治」(p.39)。レーニンやマキャベリが、現実政治の例外性に迫られて『国家と革命』や『君主論』を書かざるをえなかったように。規範理論ならぬ「技術」的アプローチとしての哲学。——これがアルチュセールの政治哲学観だ。
以上が、市田の描き出すアガンベン対アルチュセール。だと思う。
第一章 対象としての例外、主体化する例外(その2:ネグリ)
続いてネグリ論(pp.44–56)。「ネグリのウルトラ主観主義」について。
主要な文献的典拠は初期ネグリ。70年代のレーニン論(『戦略の工場』)や『野生のアノマリー』(伊語原書1981)。
アガンベン–アルチュセールのいま見てきた対立軸において、「自身の『存在者』性を絶えず消滅させようとする媒介」(p.44)を強調するネグリはアルチュセール側だ、と市田は述べる。ネグリは「構成された権力」と「構成的権力」を区別し、後者は革命が終わるとすぐに潜性力として見えなくなってしまう、と論じるからだ。
では、ネグリはアルチュセール主義なのか、というとそうではない。「ネグリ的ウルトラ主観主義」と「アルチュセール的ウルトラ客観主義」という対立がある(p.47)。アガンベンとアルチュセール゠ネグリは、例外を存在者化するか否かにおいて分岐したが、アルチュセールとネグリは、例外の例外性の所在において分岐する。すなわち、アルチュセールはロシア革命や中国革命の例外性を「構造」(資本と労働の根本矛盾の移動)に求めるが、ネグリは「主体」(レーニンとその党)に求めるのだ(pp.48–51)。
市田的ネグリの「主体」観をもう少しだけスケッチしておく。ネグリによれば、主体は戦略を媒介として、自己自身との新たな関係を取り結んで変容する。約めれば、「ネグリにあって、主体は特異な例外でありうると同時に、『媒介』なしに『自然成長』する」(p.52)。
レーニンの戦略に「媒介」されて、ブルジョワ的/プロレタリア的、大衆的/前衛党的という区分は、一つの集団的革命主体がもつ二つの質の区分になり、ブルジョワ的な質からプロレタリア的な質へ、大衆政党から前衛党への連続的な移行が、その一つの主体の動態的実体となる。自らの質を連続的に変容させつつある存在、たえず自らに働きかけて自らを変質させつつある存在が、〔ネグリの——引用者注〕革命主体だ。
するとどうなるのか? 逆説的にも、「革命の哲学」にこれ以上付け加えるものはなく、主体が自然成長し切って革命の日が到来するまで寝て待てばよかろうということにならないか? というのが市田のネグリ評であるようだ。主体主義化されたスターリン主義。
「転覆的主体の連続性」と「物質的非連続性」との間の「内的弁証法」(……)が、彼のマルクス主義を特徴づける。「物質的非連続性」とは要するに、歴史には革命による切断がつきもの、ということであり、「内的弁証法」とは、主体の連続的な成長が非主体的なもの——生産諸条件——を次々に「転覆」する、ということにほかならない。どこかで聞いたような話である。不断に増大する生産力が既存の生産関係をやがて自らの発展にとって桎梏と見なすようになり、革命を日程に上せる、というスターリン的に公式化された唯物史観を、ネグリは主体主義化しているわけである。
第一章 対象としての例外、主体化する例外(その3:ネグリのシュミットとアレント)
第一章の掉尾、pp.56–71は、ちょっと別の話となる。正直、本論の流れの中に位置づけるのがわたしには困難だが……話題としては(ネグリにおける)シュミットとアレント、というものである。ここでの主要典拠は『構成的権力』(1992)。
テーゼ的には、こんな感じだろうか:
「例外」の思想の祖、「決断」の思想の祖としてのシュミット、という捉え方が流行っている。ネグリもシュミットを使っている。では、ネグリは左翼シュミット主義なのか? どちらかというと否。『構成的権力』を読めば、スピノザこそがネグリの根幹だと分かる。シュミット思想の役割は従属的である
70年代にネグリが属していた労働者主義派では、アレントとシュミットを使って「経済からの政治の自律」を言い、(経済成長の中でも)政治運動を展開できる/すべし、と論じていた。他方、90年代初頭のネグリは「社会革命と政治革命をまとめて追求するのが構成的権力だ」と論じてアレントを批判している。これはネグリの転向を意味するのか? 否。70年代ネグリは「政治の自律」を言うことで経済決定論的待機主義に反対していたし、90年代ネグリは「(独立したカテゴリーとしての)政治の消滅」を言うことで、資本主義+リベラルデモクラシーの枠内で条件闘争をしようという立場に反対している。要するに、アンチ客観主義という点でネグリは一貫している
わたしは不勉強なので、シュミットもネグリも読んでおらず、何を学び取ることもできなかったのだけれど、思想史的関心がある向きには、けっこう挑発的な読解が展開されているのかなと推察する。
第二章 消え去る政治、まれ(例外的)な政治(その1:デリダ派)
第二章はデリダ派とバディウ。まずは、pp.74–98でデリダ派(ラクー゠ラバルトとナンシー)。ここは全然理解できなかったので、わかったとこだけ:
デリダ派には「政治的なものの後退」そして「哲学的なものの後退」という時代認識があった(80年代初頭にそういう論集が編まれた)
主権国家と市民社会の間の媒介、「主権共同体」「明かしえぬ共同体」「無為の共同体」の後退が「政治的なものの後退」だ
デリダ派の対抗戦略は? 哲学実践を通して、「政治と哲学の本質的共属関係」を真理暴露することによって対抗
市田の評価(pp.83ff.)。ミッテラン社会党政権誕生直後の左派の浮かれムードに冷静に水を差してて、のちにミッテラン政権が新自由主義的改革に転回したことを思うと評価できそう、かに思える。が、「国家」と「市民社会」の間の「中間集団」的なものを擁護するって方向性は、フランスでは「共和主義」「共和国主義」に読み替えられて、「革命の哲学」どころではなくなっちゃう
市田の評価続き(pp.92–5)。これは単にデリダ派が共和主義的に誤読された、って問題じゃなくて、「政治と哲学の本質的共属関係」を梃子に社会と国家を「脱構築的に」構成するっていう作戦自体がダメなのである(なんでダメなのかはよく分からなかった)
アルチュセールには「政治と哲学との本質的共属関係」がそもそも無いので、脱構築派の陥穽には無縁らしい
まー、よく分からんけど、左翼っぽかった人たちが現代思想を介して新自由主義的なムードに足を取られててアカン、みたいな問題を理論的に掘り下げているのかな、と思った。
第二章 消え去る政治、まれ(例外的)な政治(その2:バディウ)
次に、アルチュセールの弟子筋で毛沢東主義者だったバディウが論じられる(pp.99–121)。主要な文献的典拠は『主体の理論』(1982)。
ただし、p.108あたりに少しエクスキューズがあり、市田は『存在と出来事』(1988)を『主体の理論』に投影した読み込みをしているらしい。
バディウは構造に例外性を帰するアルチュセールから離れ、主体に例外性を求める。ただし、「ネグリの場合には、主体の例外性はあくまで主体の自己自身への関係に由来したのに対し、バディウの場合には、それはあくまで客体の例外性と一対である」(p.99)。
どういうことか。市田の敷衍(pp.103ff.):
(宇野派的な)永久に自動運動するマシーンとしての資本主義がある。その中で、ひとつの人民大衆として自足する人々
そこにある日「叛乱」が起きる
「場」が変化して、プロレタリアート(主体)が析出される
市田は理論的に書いているのでこうは書いていないけれど、要するに、レーニンの党の戦略(ネグリ)じゃなくて、突然起きる叛乱(バディウ)が主体を生成するという違いがあるようだ。
バディウがこのように論じるのは、1968年5月の革命を擁護したいがためのようだ。アルチュセール的客観主義に抗して、あまりプロレタリアート的と言えない街頭の叛乱大衆を擁護しつつ、他方でサルトル的な「実存的〈私〉たちの叛乱」という非マルクス主義的理解も拒否するために、バディウの論は組み立てられたのではないか、とのこと(p.109)。
市田によるバディウ主義のまとめは次のようになる:
「政治と哲学」について。「政治の前に治療のために引き立てられる哲学」(アルチュセール)に対して、「外゠場に置かれた叛乱と、そんな叛乱からはじまる主体化の弁証法的プロセスは、それこそが政治であって、存在論的な哲学とは絶対に混同されてはならないものになっていくだろう」(pp.110–1)
そのコロラリー。「外゠場」について哲学的認識など不可能ということは、「外゠場は、論理では扱えない切断である『決断』の領域とされていくだろう」「彼はまさに左翼シュミット主義者である」(p.111)。
叛乱に向かって決断せよ! と説く左翼シュミット主義者バディウ、というところだろう。
さて、そのようなバディウについての市田の所感(pp.114–21)。ここはちょっとでも左翼ロマンティシズムに感じ入るところがあるところがある人にはじーんと来るところと思う。引用はしないが、バディウの無根拠な「決断」は一種の詩になるわけだけど、左翼戦線の後退と軌を一にしてそのアジテーションに元気がなくなっていく様が文献学的に跡付けられていて、もののあわれを感じさせる。節小見出しは「存在の詩——マラルメのように」。
第三章 マルチチュードの生である政治(その1:ドゥルーズ派ズーラビクヴィリ)
第三章はスピノザ哲学に霊感を得た左翼思想の紹介。
まずは、ズーラビクヴィリにより解釈された、「陽気なペシミズム」の思想家としてのドゥルーズが紹介される(pp.124–44)。
これに対し、スピノザ主義から「陽気なペシミズム」を抽き出すことはできないのではないかという市田の論が展開される(pp.144–62)。代わって導き出される政治論は、「マルチチュードの怒りを唯一の原因とする国家形成/国家解体」というもの。スピノザ読解においては、ドゥルーズやネグリに近いスピノザ学者マトロンが援用される。
最後に、そのようなスピノザ読解を採用した場合におけるドゥルーズの革命観・アルチュセールの革命観が素描される(pp.162–77)。
まずは、現代における有力なドゥルーズ派、ズーラビクヴィリによる「陽気なペシミスト」としてのドゥルーズ読解。ここは「加速主義的ドゥルーズ」という感じでかなり興味深い。
ズーラビクヴィリはドゥルーズの政治思想を、いかなる政治綱領ももたない「極左主義」と定義づけることになる
ドゥルーズ的な政治を体現する人物形象は、「無への意志」によって世界を破壊する虚無的テロリストではなく、「意志の無」のなかへ自己消滅するバートルビー(ハーマン・メルヴィルの小説のなかで文字どおり自死する主人公)であり、ドゥルーズの政治思想を一言で要約すれば「陽気なペシミズム」だということになる
この後の議論はうまく消化できなかったので逐条的な紹介を省略する。
だいたい次のようなことが書かれていると思う:
ズーラビクヴィリのドゥルーズ読解はスピノザ論に基づく
そのスピノザ論からは「ペシミズム」だけでなく、主体の自然成長性に賭けるネグリ的な「オプティミズム」を抽き出しても構わなかろう、というのが市田のジャッジ(なお、ズーラビクヴィリはこれに反対して「ペシミズム」読解のみを正当化する理論的根拠があると論じており、さらに、ペシミズム/オプティミズムどちらに与するかは世界観闘争になってしまうので不毛だとも書かれている)
ところで、ズーラビクヴィリのスピノザ論によれば「スピノザの情念論からは現にある国家の存立根拠を導くことはできるのだが、国家形成の原因を導くことはできない」となりそうである。これは、革命の「原因」「因果性」の説明をスピノザに求めてきたアルチュセール以降のスピノザ論のモチベーションに反している。よって、ズーラビクヴィリの読解を疑ってみた方が、論駁に成功した時にアリガタミがある
(第3点、わたしにはこうとしか読めないんだけど、この、なんというか不純な理論動機は現代思想業界ではアリなのか? ここはかなり引っかかりを感じた。「読み解きに成功した時のリターンがデカそうな方にベットして哲学史に臨むぜ」ってことだと思うんだけど……。pp.141–4)
というわけで、話題は反ズーラビクヴィリ的な、「政治における因果性」の説明理論が込みになっているようなスピノザ論探しへと向かう。
第三章 マルチチュードの生である政治(その2:マトロン的スピノザ)
続く箇所(pp.144–62)で、市田はスピノザ研究者のマトロンを導きの糸として、「政治における因果性」の説明が込みになっているスピノザ論を展開する。
『スピノザにおける個体と共同性』(1969)で、マトロンは『エチカ』第3巻の情念論を『政治論』に当て込んで、次のような読解を展開:「恐怖」と「希望」の情念の模倣過程のサイクルの中で国家の形成を説明
その後、90年代の諸論文で「恐怖」と「希望」のシーソーゲーム仮説を破棄。功利計算から「社会契約」により「国家を創設」するという読みを排除できず、スピノザが『神学・政治論』から『政治論』の間に「契約」概念の使用をやめたという事実を説明できないから
マルチチュードの「怒り」が、国家形成の原因でもあり解体の原因でもある、と論じられるようになる
自然状態の脅威からの「恐怖」転じて「怒り」による国家形成、というのは「存在論的説明」(理論的フィクション?)であり、スピノザにおいても史実記述を企図していなかったらしい、というのがマトロンの解釈
つまり、通常の社会契約説が、
自然状態→契約→国家
と説くところ、マトロン的市田的スピノザでは、
(理論的仮構としての自然状態)←怒り→(理論的仮構としての国家)
みたいになっているようだ。怒りの方が存在論的に根本的なので、「結果が原因に内在」する、と書かれている。いわゆる因果説明ではない謎の説明がここでは行われているらしい。
さて、読解の果てに手に入れた概念は、当初欲しかったもの(経済決定論的でも主観主義的でもない政治の説明因?)とはかなり違ったものみたいだ。この「怒り」からは、革命が出てくるかもしれないし、国家秩序の形成が出てくるのかもしれない。しかも、通常の因果性ではないから、「怒り」を煽れば革命が発生する、というわけでも無いようだ。マトロンは「困惑」し、ドゥルーズは「恍惚」としている、とか書いてある。
第三章 マルチチュードの生である政治(その3:ドゥルーズとアルチュセール)
ここから先の議論はわたしには説明不可能なので、あらましだけ。
マトロン的なスピノザ読解を受け入れた上でのドゥルーズやアルチュセールの革命観が考察される(pp.162–77)。
ドゥルーズがメタ倫理学的な道徳虚構主義か準実在論みたいな立場を取っていたという論があって、そこが非常に面白い。アルチュセールの革命論については、ブレヒト論を読め、ってことが書いてあるようだ。
走り書き的覚え書きとしてはこんな感じか:「怒り」の情念を原因として政治的共同性を創設/解体するマルチチュード、という主体が見出された。
その「怒り」の情念は、政治現象の通常の原因ではなく、いわば「物語的な」「虚構的な」原因なので、「倒錯」(ドゥルーズ)や「舞台の袖の弁証法」(アルチュセール)という戦略が希望となる。
終章 見出された自由
終章はフーコー論。これまでの論で、「主体」の概念が再召喚されてきた観があったけど、「主体の死」を宣告したフーコー思想はどうなのか? という導入。
ポイントは以下のような感じ:
フーコー権力論から発展した晩年の「統治性」論においては、「革命」概念が他の論者からはズレそうだ。すなわち、フーコーは「国家」よりも、諸主体間のパワーゲームの中から半ば自発的・内発的に生成されてくる権力現象的なもの——「牧人体制」——の方を根底的に見ているため、革命——「反牧人革命」——概念も、国家共同性の解体/再構築というより一段深いものとなっている
さて、フーコー派の一部は晩期フーコーの自由主義への注目を「統治の最小化=反牧人革命」論として読んでいる(フランソワ・エヴァルド等)。そして、福祉国家を縮小して民営化することで「統治性」に対抗しようとしている
市田によればこれは誤読であり、フーコーは「統治をギチギチにやりすぎると却って機能不全に陥るから、統治の最小化によって統治を円滑化しよう」みたいなのも「牧人体制」の戦略だって言っているらしい
市田は、古代帝国の頃から連綿と続くミクロ権力現象みたいなもの——牧人体制——をバッサリ掘り崩す「反牧人革命」についてはペシミスティックだが、そういうミクロで身体化された権力現象にも絶えざる揺らぎがある、というのは「革命」を考える根拠になるよね、みたいなことを書いて擱筆する
感想
アルチュセール論としてはけっこう独特だと思うので、他のアルチュセール論とならべて再読したいと思った。本書では「構造主義者」アルチュセールがほぼクローズアップされていないので、これだけ読むと一周廻ってただの主体性の人みたいだし、「毛沢東主義に見えるのはフロイトの影響であって、アルチュセール自身は(弟子たちと違って)あんまり毛派ではなかった」みたいな仄めかしがある(p.54)。通説の通説たる根拠みたいなのを説いている、たとえば今村のものも読んでおかないといけないのかな、と思った
pp.8–12に、英米系政治理論を批判する論拠となるメタ倫理的な所論があるのだけれど、これには賛同しかねる。いわく、普遍的な「道徳」ならぬ「倫理」は「住みか」相対的なものである。根拠は語源学。英米系政治理論はグローバル化した資本主義的「住みか」を当然視しすぎていてダメだ。他なる「住みか」に依拠した倫理をあらかじめ排除してしまっているワケだから、云々。こういう方向性は、倫理的討議についての不一致disagreementを説明不可能にしてしまうという意味論的な難点があるだろうと述べておく
ただし、にもかかわらず、ここでは重要なことが語られていると思う。最近よく考えるが、たとえばロールズ的な規範理論を無知のヴェールみたいな思考実験とかで正当化したとする。が、あれら理論は超歴史的であることを特徴とするのであって、アンシャンレジーム期のフランスに何度あれら規範理論を適用して「○○すべき」を導いたとしても、絶対に大革命後の状態への移行を正当化できないと思う。あえてナイーヴな言い方をするが、「世界史を前に進めるような共同性の創出」が、英米系の政治理論では構造的に考察の対象外になってしまっているように思える。だから、「倫理」の「住みか相対性」みたいなメタ倫理的な方向性じゃなくて、英米系規範理論の超歴史性/脱歴史性みたいな指摘として鋭いと思う
なんか、フーコーが妙に強キャラ扱いなのが意外な感じがした。アルチュセールとフーコーって、そんな食い合わせいいかな……? マンガみたいなことするなって怒られそうだが、戦闘力バトルするとこんな感じだと思う:アルチュセール≧フーコー>ドゥルーズ≧ネグリ>>>バディウ≧アガンベン≧デリダ派。わたしはネグリと加速主義的ドゥルーズが面白いじゃんという感想を抱いた
フーコー権力論を論じるあたりは、無敵の論法すぎてズルくないか? と感じてしまった。だって、市田的フーコーによれば、規律権力みたいなのが表面的に強化されてても弱化されてても、どっちにせよ「牧人体制」の強さの表れと読み解けるじゃん……。そんなの何も言ってないのと同じじゃないか?
第三章のスピノザ論のあたりは、むかし読んだ時はかなり苛々させられた覚えがあるのだが(スピノザをどう解釈するかどうかが、現代の政治哲学上の理論の有効性にどう影響するのだ!?)、なんか面白く読めた。最近、ホッブズもロックもルソーも、歴史記述じゃなく、何かわからんけど規範的もっともらしさがありそうな物語を語っているんだっていう見方がようやく腹落ちしてきて、スピノザ政治論もその仲間なのかな、という風に見えてきた。だとすれば、スピノザを語ることが即ち自説の規範的正当化にも(間接的に)なってるっていうのは別段おかしくもないかもね
市田自身もあとがきで書いているけれども、政治経済分析や階級論がないので、その辺は読み手が続きを考えないといけないのかなと感じた。とくに、マルクス主義革命論の時代遅れな部分について——当初明らかに工場労働者を念頭において使われていた「プロレタリアート」の概念や、実証的に偽(と、さすがに言っていいでしょう)な窮乏化仮説とか
「直接性/媒介」という対概念が頻用されるんだけど、わたしはヘーゲルもルカーチもバタイユもまともに読んでいないので、正直なんのこと言っているのかよく分からんという問題があった
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
