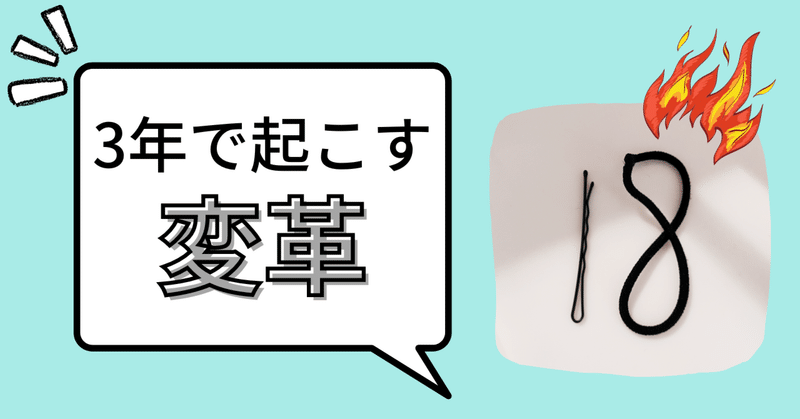
ルールメイキングに必要なこと
はじめに
どうもこんにちは!大地優香です
今回は文化祭の運営のルールメイキングを行った経験からルールメイキングに必要なことを考えていきたいと思います!!🤔
※私に関して※
あなただれ!って人は
↓このプロフィールものぞいてみてください!
文化祭のルールメイキング
↓実際に行ったルールメイキングの内容は別で記載しています👍
ルールメイキングを再考する
早速ですが、ルールメイキングとはなんでしょう?
私が思うに、
ルールメイキングは学校を生徒がより過ごしやすいものに変えていくための手段です
しかし、この手段は、校則を変えたいという思いがあればつかえるものとはなっていません
私の体感ではルールメイキングが成功している学校は生徒と教員の間の風通しがよく、生徒に対する教員方の造詣が深い学校が目立つような気がしています
しかし、本当にルールメイキングを必要としているのは、
伝統や世間の目を気にして変革を恐れ、理不尽を強いる学校に在籍する生徒
なのではないのでしょうか🤔
今回私はそんな生徒が
よりルールメイキングを現実のものにするためにも
ルールメイキングには何が必要なのかを考えていきたいとおもいます!
ルールメイキングに必要なこと
私が考えるに、ルールメイキングで一番重要なことは
変える事のハードルを下げる事
だと考えています。
私達も変えた際にデメリットが多いものに関しては変えることに慎重になるように、教員もルールを
変える事のハードルが高いと変えられなくなってしまいます!
そこで、ルールメイキングをイノベーションと捉え、
エベレット・ロジャーズのイノベーター理論を用いて、ルールメイキングを行うために
どのようにハードルを下げるべきなのか
を考えていきたいと思います
5つのポイント
↓イノベーター理論に基づいた、
ルールメイキングに必要な5つのポイントです!
これらのポイントを改善していくことで、
ルールメイキングのハードルが下がること
間違いなしですദ്ദി˶ー̀֊ー́ )

①相対的優位性
既存の校則より新しいものがより優れているか
ex)既存の校則:頭髪の染色を認めない
新しい校則:頭髪に染色も認める
→生徒からすれば選択肢の幅が広がっている
②両立可能性
学校がどのような価値観を持っており、その価値観に相反さないか
ex)学校の考え:校則を変えた際のPTAからの目が気になる
校則改正法:新校則に関してPTAに合意をはかる
→学校が校則改正するハードルを下げている
③複雑性
ルールが複雑でないか
ex)既存の校則:カーディガンは黒と紺のみとし、
ストライプ柄のような柄物やワンポイントはなしとし、
無地のもののみを認める
新しい校則:カーディガンの着用を認める
→新しいほうが複雑ではなく、認知しやすい
④試行可能性
試しに経験できるか
ex)新校則の試行期間を設ける
→生徒も教員も体験することができる
⑤観察可能性
校則改正を見ることができる
ex)他校の校則改正事例をあつめて、教員に情報提供を行う
→多くの事例を見ることで、改正の確実性が生まれる
最後に
最後まで読んでくださりありがとうございました!!😆🫰
きっとルールメイキングを行おうとしている生徒の中には、賛同を得られず、1人で抱え込んでルールを変えようとしている人もいるかもしれません
その力、声は大切です
しかし、1人で変えたルールは
その1人のためのルールです
もはややっていることは独裁と変わりありません
本当に何かを変えようとするのであれば、
一体誰のための、何を目的としたルールメイキングなのか、そこを忘れることなく、ぶれることなく持ち続け、なおかつ上記5つのポイントおさえ、
単一の思想のみではなく多様な価値観を持つ人と
ルールや校則に関して合意形成をはかる
そうすることで、本当の意味で
先生も生徒も学校に関係する全ての人が生活を
営みやすい学校が生まれるのではないでしょうか!
この他にも生徒会に関して、マガジンに投稿しているので見てみてください!👍
↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
