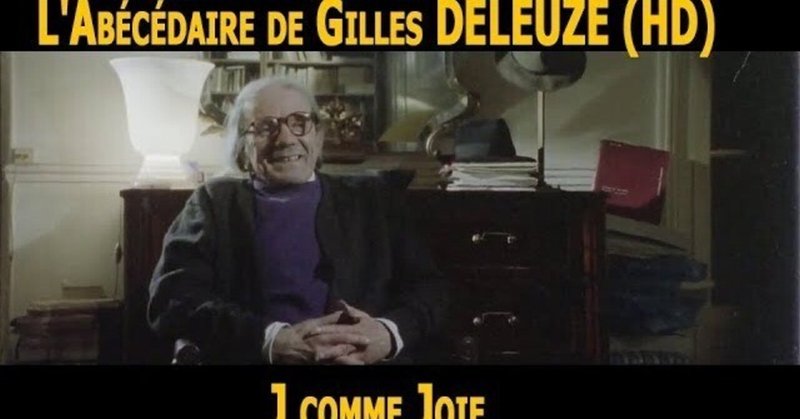
絶滅にふさわしく、ドゥルーズ
ドゥルーズは『意味の論理学』で「出来事の倫理」を語ったがその後この発想を深化させることはなかった。フーコーが『アンチ・オイディプス』を「倫理の書」と評した読み方が今でも支配的であり、ドゥルーズは奇妙なことに倫理的な哲学者だという風にみられている。しかし彼は生の形式にはほとんど関心を示さず生に生じたことに関心を示した出来事の哲学者であった。彼が信じる道徳の意味はひとつしかなく、それは「出来事にふさわしくあること」の道徳である。しかしこの道徳も、そこに「裁き jugement」の視点を導入すると破綻してしまう。誰も、誰が出来事にふさわしい生き方をしており、していないかということを判断(jugement)できないのである。
ドゥルーズはある講義で「泣き言をいうひとの周囲にとどまるのが難しいのはなぜでしょうか」と問い、「彼らは、彼らに生じることにあたいしないのです」と述べたあとで、すぐに自分の考えを撤回した。彼は、「大いなる不平家」、「苦情の天才」として、ヨブの存在を思い出したのである。ドゥルーズからしてみると、ヨブやエレミヤのような預言者は彼らの身に生じた途方もない出来事にふさわしい表現をもっていた。出来事にふさわしいのは、彼らの生の形式ではなく、彼らの表現の方であると、確かに「泣き言」には出来事にふさわしいアスペクトが──それを表現する者の生の形式を超えて──あると、ドゥルーズは気づいたのかもしれない。ドゥルーズは晩年のインタビューで、「私がもし哲学者ではなく、女として生まれたとしたら、泣き女になりたかった」といっているほどだ。ドゥルーズにとって存在するのは出来事と表現だけであり、「生の形式」という美的観点は彼には無縁だった。
フーコーはドゥルーズを生き方と実践の哲学者として読むことを推奨し、「いつの日か、世紀はドゥルーズのものとなるだろう」と予言したが、実際にそうなったと皮肉な見方をすることもできる。われわれは今や自分(たち)の生のことしか気にかけず、生に生じることの広範なネットワークに無感覚で、コカ・コーラ社が生産する無限の廃棄物には寛容だが、目の前でペットボトルを捨てるひとをみかけると怒りをおぼえるのだ。コロナ禍に日本社会が覆い尽くされたとき最初に目にしたのも、すべてを道徳化しすべてを個人の選択の問題としようとする異様な努力だった。われわれは、システムに何かを要求するための空間を知らないので、その要求を自分たちに返してしまうのである。
アガンベンは、ドゥルーズの死の数日後に発表された文章のなかで、「苦悶から始まった今世紀の偉大な哲学が喜びで終わる」と評した。ドゥルーズの哲学のなかでもっとも記憶にあたいする部分が(残酷や狂気や愚劣ではなく)喜びについて述べている箇所だというのである。私は、(これほどまでに腐敗し破壊的なものとなった世界のなかで)喜びを生の形式と結びつけるいっさいの思想に心底うんざりしている。そうした批評家はコロナ禍のなかで、剥き出しの生を絶えず生産するシステムを変えようとするのではなく、自分(たち)の生の形式への関心という美的観点からしか事柄をとらえられないということを露呈したのだ。剥き出しの生を生産する「主権権力」という(それ自身問題含みの)アガンベンの考察も、「ホモ・サケルになるな」という実存的メッセージへと驚くべき安易さで翻訳されてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
