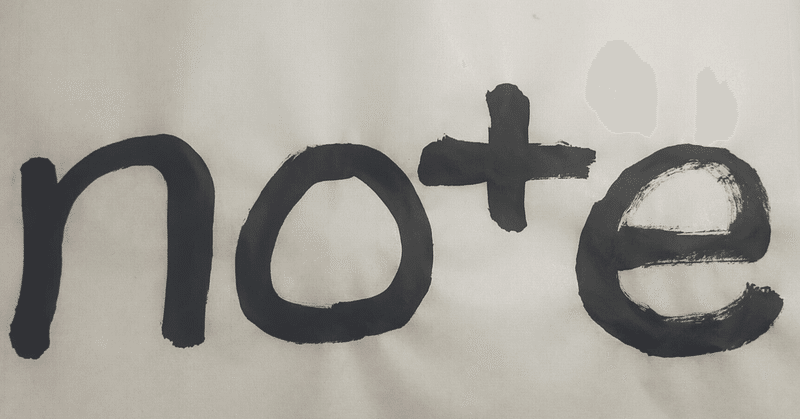
太字がもたらすデジタルとアナログでの効果の違い
太字(ふとじ)は、書式のひとつであり、文字を構成する線(ストローク)の幅を通常の書式より太くした書体のことを示す。ボールドとも呼ばれる。一般には文字の強調に使用されるほか、数学においては特別な意味を持つ。英語ではBoldと呼び、さらに太い太字をBlackと区別することがある。
書籍、つまりアナログでの読書で、太字がわずらわしく感じることがある。
なんというか、音楽を聴いていて、特定の箇所でいきなり音量ボリュームがあがる、みたいな。強調表現としては強引じゃない? という違和感。
というのも、読書になれてくると、文章のリズムの中で、そろそろハイライト、いちばんの盛り上がりの場が来るぞー、と事前の予感がある。
そういう箇所には、接続詞として「「つまり」「すなわち」「要するに」「言い換えると」「換言すれば」「煎じ詰めれば」「大事なことは」といった言葉が頭に添えられている。
なので、わざわざ太字で強調されてしまうと、突起が出っ張りすぎて、読む視線にひっかかりすぎる、という感覚がする。
もちろん、見出しや小見出しはいい。目次の時点で了解している。
どうも太字による読者の誘導という働きかけには、老婆心を感じてしまう。
悪意がないことは承知なのだけど、甘やかされているような居心地の悪さ。
よって、あくまでアナログの書籍では、太字が多発しないプレーンな感じが好ましいと思っている。
一方、さいきん感じたのは、noteやブログなどのデジタル上での文章の場合は、適度に太字があるほうが読みやすい。
太字以外の、ラインマーカーを引く表現も同じで、そんな違和感はない。
デジタル上だと、どうしても文字を負う視線が滑りやすい。
テキストの質感がつるんとしている。
適度な太字の強調は、手がかりや足がかりになる突起になる。
ロッククライミングで、手がかりとなる岩の出っ張りのことをホールド、というらしい。これと同じ役割を果たしてくれる気がする。
……というようなことを考えていて思い至ったのは、さいきんアナログの書籍で太字があるのは、それがkindle本(電子書籍)としても販売されている本だからかもしれない。
アナログとデジタル、どちらで読まれることを想定して作っていると考えれば、合点がいく。
そうなると、太字が多用されている本は、kindle本(電子書籍)で購入してみるのもいいのかもしれない。紙の書籍よりも安いだろう。
さして重要ではない事柄については、相手や世間に合わせるタイプである。
最後まで読んでいただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。 いただきましたサポートは、書籍や芸術などのインプットと自己研鑽に充てて、脳内でより善い創発が生み出されるために大切に使わせていただきます。
