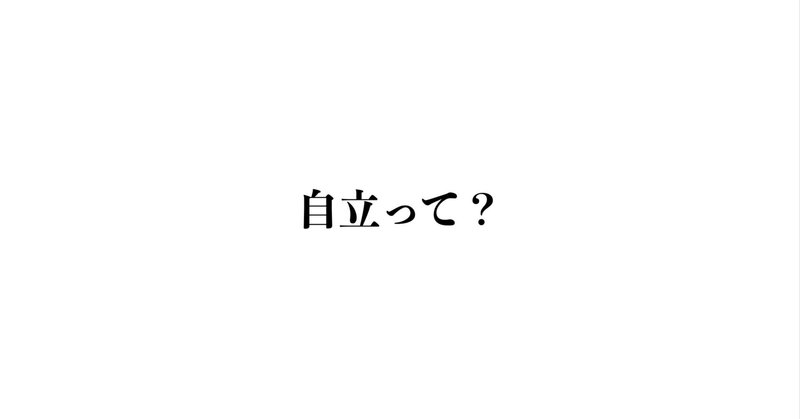
自立とコミュニティ
News Picksさんの番組でWeekly Ochiaiという、コンピュータサイエンティストの落合陽一さんが、毎回様々な分野の専門家の方と対談するというものがあります。
この番組が面白くてかなり視聴しているのですが、今回は当事者研究の第一人者である熊谷晋一郎さんがゲストでした。彼は脳性麻痺により、手足に障がいを抱えております。
そんな彼が語る自立の定義が非常に興味深い。
どんな定義かというと、
「自立とは依存先の数が多い状態のこと」
一般的には、自立とは独力で生き抜く力を持っていることと思われがちですがそれの逆をいきます。
障がい者として常に自立ということと向き合っている方の言葉だけにしみました。
では、これはどういうことなのか?ということを説明します。
そもそも、人間は誰しも誰かの助けを受けて生きています。発電所で誰かが頑張っているから電気を使えるし、電車は運転手さんが運転してくれるから進むことができます。
たまに自給自足の生活をしている方もいますが、それは森や海といった自然に助けてもらっているし、そもそも現代社会の上に成り立つような生活様式を取っていることが多いです。(ガス、電気、水道などインフラを全く使わない、そもそもそこにたどり着くまで歩いていったなんて人も少ないでしょう)
そういう具合に、皆それぞれ何かしらに頼る、つまり依存することによって生きています。
よって、活用できるもの(依存先)がある一定程度あると、健康で文化的な最低限度の生活を営める、つまり自立しているとなるわけです。
面白いですね。助け合っているという当たり前の感覚が熊谷さんは強いのでしょう。
【自分が思ったこと】
ここまでの話だと、依存先は何か功利的なものと感じますが、私は精神的安心感を得るための依存先も持っている方がいいと思いました。
わかりやすい例でいうと、会社では出来ないやつと思われないために中々自分の弱みを見せることはできないが、家族の前では安心して自分をさらけ出せるといったことです。
もちろん、家族でなくても友人や隣近所の関係などでも良いのですが、こういった依存先を複数もっておけば、いざあるコミュニティで精神的につらくなったとしても、別のコミュニティで安心感を得られる、もしくはつらいコミュニティから逃げることができます。
最近はオンラインコミュニティも増えてきて、多くのコミュニティに所属している人は増えてきましたが、安心して自分の心をさらけ出せるようなコミュニティを持つ人はそれほど多くないのではないかと思っています。
理由は、コミュニティを道具として利用する考えとそもそも安心できるコミュニティをつくることが難しいことだと考えます。
自分もオンラインコミュニティに所属しているのですが、自分にとってそれはどういう場なのか再考したいと思いました。
他にも学びの深い対談でしたが、一番印象に残ったことを記します。
【まとめ】
自立とは依存先を一定数確保している状態のことといえる。そのとき、精神衛生上多くのコミュニティに所属していることが重要なのではないだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
