
写真のように
第1回 野村浩「メランディ」に見る「小さな父」とその可能性
中目黒のギャラリーPOETIC SCAPEで開催されていた、野村浩の新作個展「メランディ」がさる4月3日をもって幕を閉じた。新型コロナウイルスの流行とそれにともなう世界規模の混乱によって、会期短縮を余儀なくされたのはとても残念だが、それでも初日と最終日と二回見ることができたのは幸運だった。また、コロナ禍という特異点がなければ得られなかった気付きもあった。ここでは、野村浩の新作「メランディ」について、妄想を交えて膨らませながら展評としてまとめてみたい。
www.poetic-scape.com/#exhibition
擬態とアイロニー
今回の作品は絵画、ペイントである。東京藝術大学油画科卒の野村浩本来のフィールドで、イタリアの現代絵画家、ジョルジュ・モランディがテーマであるらしい。らしいとするのは、筆者はモランディという作家を知らないからだが、誤解を恐れずに言えばここではモランディを知る・知らないはあまり問題ではない。もちろんWikipediaやWebの「美術手帖」の記事等々を確認したが、「ノムさん、この人から影響を受けたのか−、初めて知った」程度の認識に留まる。むしろ、モランディの画家としての人生を俯瞰しながら、野村作品と対比させて深掘りしながら論ずる作業は、美術史に詳しい方々に任せたい。ここでは、主に写真とサブカルチャー的な視点から新作を語らせていただく。
野村浩は絵画、写真、デザイン等さまざまな手法を用いるが、最も特徴的なのは「擬態」を駆使して自作に外部の力を取り込む点にある。擬態とは生物学用語で他者に姿や気配を似せてカモフラージュする生物の特殊能力を指すが、野村の場合は美術やサブカル由来の人物、作風をアイロニカルに自作へ導入する技術を指す。これまで藤子・F・不二雄由来の擬態写真作品「ヱキスドラ」、ゴッホを由来とする「inbisible ink」、チャールズ・M・シュルツ「ピーナッツ」シリーズのコミックに擬態した「CAMERAer」などを発表しているが、擬態を駆使するときに模倣ではなく原典をアイロニーとして引用するところが美術家らしいと言える。この手法は、原典への敬意を明らかにしつつ鑑賞の敷居を下げ、さらに批評性を獲得するといった効果を生み出すという特徴がある。
前面化する「小さな父」
「メランディ」として発表されたペイント作品は長辺が10数cmとどれも小ぶりで、野村の作品集『eyes』、『EYES WATER COLORS』、『CAMERAer -カメラになった人々』に登場する野村作品ではおなじみの一対の白黒目玉が静物の中に描かれる(fig.1)。色彩はベージュとグレーと白と黒。モランディもサイズの小さな静物画をだいたい同じ色彩で描いているので、率直に言えば野村の新作は擬態というよりは、タッチを含めてジョルジュ・モランディそのままという印象で、いつもの擬態化とは異なるように見えた。模倣というほどではないが、いつものアイロニー成分が色彩同様薄く感じられた。野村は周到な作家で、擬態に際し細心の気遣いを施す彼がまさか単純な模倣などしようはずはない。これは、野村が意図的に仕掛けた擬態の新バージョン、彼の新しい表現の回路ではないかと疑った。

fig.1 野村浩「Merandi / Like a Still Life with Four Boxes and Other Objects」
作品からアイロニーは後退したが、批評性そのものが弱まった兆候は見られない。目玉に込められた写真やカメラを連想する「見る」というメタファーは変わらずあるから、擬態の意図が変質・転向したのではなくアップデートされたと考えるべきだ。では、野村の擬態はどこがアップデートされたのか。それは、作品の前面に見え隠れしながら宿っていた。もちろん、目には見える。が、最前面にあるがゆえにあやうく見落とすところだった。筆者が発見した野村の新しい表現の回路、アップデートされた最新の擬態は「小さな父」化したジョルジュ・モランディである。正確に言えば、「小さな父」というコンセプトの前面化である。
「小さな父」とは何か。批評家の宇野常寛が評論集『リトル・ピープルの時代』(*1)で提唱したリトル・ピープル=小さな父を想起する方もおられるだろう。実際、筆者も同書を読み、宇野の主張に深く同意した一人だが、ここで野村に対して使う「小さな父」は宇野が定義したリトル・ピープルよりももっと限定的である。ただ、宇野の著書が本稿の出発点であることは確かで、ここで登場する「小さな父」は、リトル・ピープルの解釈の一つと捉えていただけると幸いである。
「小さな父」のプロトタイプ「すだ式」
予兆はあった。2019年、野村は作品集『CAMERAer -カメラになった人々』(以下、カメラー)と同関連展示で写真の会賞(*2)を受賞し、新宿御苑の写真ギャラリー・プレイスMで受賞展を開催することになった。単独受賞だったが、顕彰者たちの意向で特別賞を受賞した須田一政の作品「日常の断片」(*3)と同じスペースで展示することが提案された。須田は故人であったため、野村は自作と須田の作品をミックスした展示をプランニングするよう要請されたのであった。写真に限らず通常作品展はたとえグループ展であったとしても、複数の作家の作品を混ぜ合わせて展示することはあり得ないのだが、受賞作の「カメラー」が広義に写真をテーマとした批評作品という側面を持ち、デザイナーでもある野村ならば須田の作品を使って自作の展示もうまくまとめられるであろうという楽観的な判断のもと、顕彰者たちは野村にキュレーションを委ねたのだった。
野村は、苦心をしつつ須田の作品をキュレーションするなかで、コミック形態の小冊子『Suddallei -すだ式』(以下、すだ式)を制作した。会場で無料配布されたこの12ページの小冊子は、題名から想像がつくようにつげ義春「ねじ式」(*5)のパロディである。須田の遺族より許諾を得て実現したものだが、ここに野村の新しい擬態の予兆があった。
「すだ式」(fig.2)は、黄泉の世界に行った須田が身体がカメラ化した「カメラー」(*4)となって現世に戻り、野村と一緒に写真の会賞受賞展の会場に向かうという、「ねじ式」を下敷きにしたシュールな筋書きだ。注目したいのは、野村が擬態したのは須田ではなく、タッチを含めて「ねじ式」であることだ。須田は、身体を生前愛用した二眼カメラのローライフレックスに描かれるが、絵のタッチは生前の須田がこよなく愛したつげ義春の「ねじ式」で、結果として須田は「カメラー」的世界と「ねじ式」世界、二重の世界観に取り込まれる。また、須田に与えられた二眼カメラの身体と「ねじ式」擬態タッチは、野村の敬愛の顕れでもある。「それは単なる須田のキャラ化」と指摘する向きもあるだろうが、矮小化・軽薄化という意味も持つキャラ化という言葉は、野村に敬愛の意志があるがゆえに否定したい。ただ、「カメラー」化した須田は野村の操作が加えられるなかで、野村の作品化(≒キャラ化)しているのは事実だが。表層的な意味において、野村による敬愛とアイロニーを与えられた「すだ式」における須田一政を、ここでは「小さな父」のプロトタイプと考えたい。
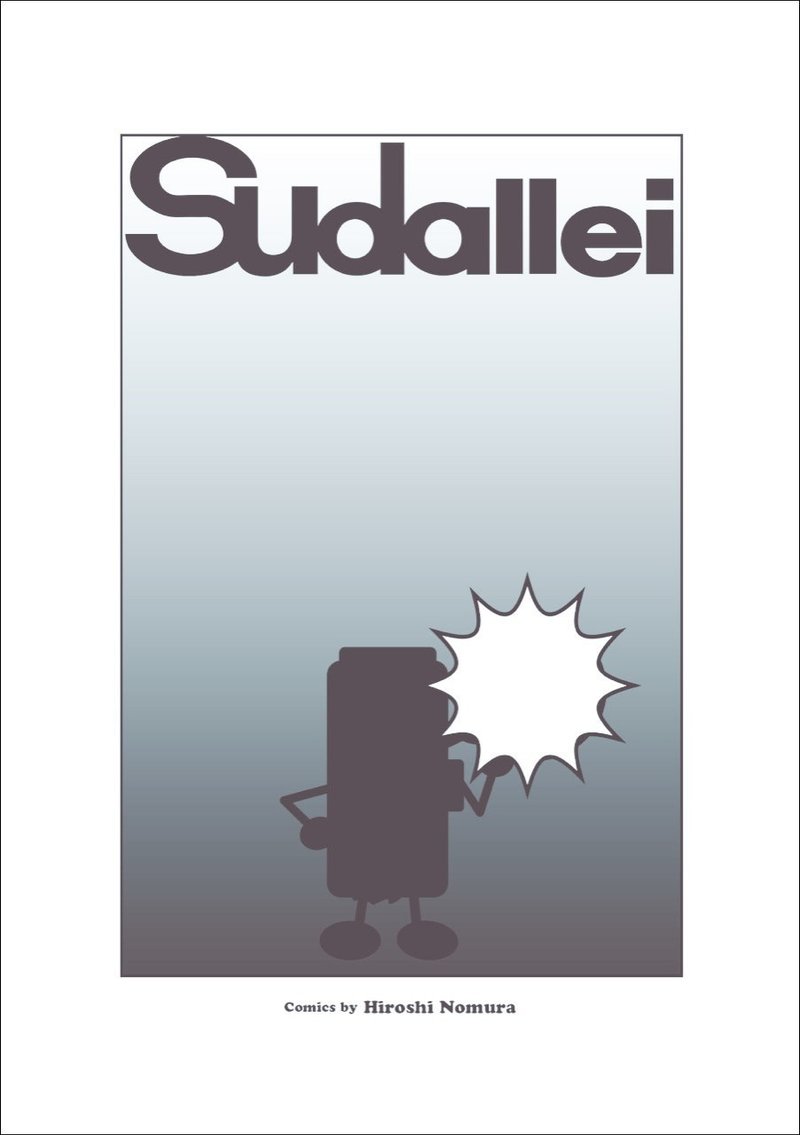
fig.2 野村浩『Suddallei/すだ式』より
擬態とイタコ漫画
「すだ式」で野村による敬愛と擬態タッチの二重に包み込まれることで、須田は別の存在に生まれ変わっている。ただ、それは「メランディ」に見られた「小さな父」化とは異なる。「すだ式」をプロトタイプとする理由の一つは、漫画だからだ。漫画の世界には、イタコ漫画家という存在がある。
田中圭一(*6)に代表される彼らは、漫画界の巨匠である手塚治虫や松本零士、高橋留美子、アニメ界の宮崎駿やサンライズのタッチ・絵柄・演出のエッセンスを汲み取り、特にギャグマンガ家でもある田中は、その才で絶妙な下ネタと風刺を組み込んだ二次創作として展開することでネット等で親しまれている。広義では、同人誌に代表される二次元作品の二次創作はほぼこの範疇に含まれるだろう。動機と目的は異なるが、「すだ式」も「ねじ式」に擬態したゆえにイタコ漫画の亜種と見られる可能性はある。
ただ、野村は確実にイタコ漫画を知っていて、研究を重ねていたと思われる(*7)。なので、「すだ式」を制作する課程に於いて、さらにその前の「カメラー」の制作時点ですでに、イタコ漫画と一線を画すよう配慮していたに違いない。イタコ漫画は普通、オリジナルのタッチと作風を100%模倣し漫画ネタとして成立させるが、「すだ式」は「ねじ式」風(原作者のつげ義春風ではないところに注目)のタッチに近づけつつも、100%野村のタッチで描かれたコマのほうが多いことからも(fig.3)、漫画ではなく自分の作品として成立させようとする意志が垣間見える。野村からすれば、あくまでも「擬態という技法」であるわけだ。野村は、サブカル由来のイタコ漫画とギリギリのところで戦った。そして、その戦いは新たな擬態の方法論であるところの「小さな父」を生み出すに至ったと推察される。

fig.3 野村浩『Suddallei/すだ式』より
再生・更新・拡張する「小さな父」
「すだ式」を、「小さな父」のプロトタイプと判断するもう一つの理由は、野村は須田一政に擬態していないことだ。須田はカメラー化しているが、それは擬態化した「ねじ式」と「カメラー化」の二重の世界観の中で行われている。当たり前だが須田は写真家で、写真の模倣は絵と違って難しい。野村は2017年にPOETIC SCAPEで発表した作品「Doppelopment」「もう一人の娘には、手と足の仕草に特徴がある。」で、牛腸茂雄あるいはダイアン・アーバスの双子の作品(*7)によく似た写真作品(fig.4)を発表しているが、ここでは擬態を用いていない。写真はまったく同一の時空と座標でシャッターを切らない限り、基本的に同じものを造ることはできないからだ。一方で、複製・模造は可能であるという写真固有のパラドックスも存在するが、ひとまずその議論は置いておく。

fig.4 野村浩「Doppelopment #014 」
「すだ式」を経て、「メランディ」では一歩進んだ形で擬態が使用された。「すだ式」のように一旦「ねじ式」を経由するといった手順を踏まず、モランディの作風と色彩をそのままトレースしている。モランディがペインターであるがゆえにストレートな表現を行えばよいのはもちろん承知だが、そのままタッチと色彩をトレースするだけでは単なる模倣にとどまってしまう。自作に引き寄せられないうえに、野村作品固有のアイロニーも発現しない(結果としてアイロニーは薄まってしまうのだが…)。

fig.5野村浩「Merandi / Like a Still Life with Snoopy and Black Block」
「小さな父」の発現とその効果を見るのにちょうどよい事例がfig.5だ。作品には目玉にピーナッツシリーズの○ヌーピー犬と思われるキャラクターが描かれている。これはモランディ作品を野村風にアレンジしたあるいは野村の作風に引き寄せた絵画と見れるが、再生されアップデートされた、あるいは拡張されたモランディの新作と見ることもできるだろう。モランディは21世紀の現在を生きていないが、いまを生きる野村はモランディに敬意を払いつつ擬態して新作が描ける。「もしモランディが20世紀後半を生きたならきっと○ヌーピーを描いただろう」とタラ・レバ的な夢想に浸るのもよいが、ここは「俺のモランディ」という前向きな発想、あるいは二次創作的な発想に意識を振り替えたい。
そして、この行為は擬態によって発動され、「すだ式」と同じく敬愛の方向に駆使することで、「小さな父」になったモランディがわれわれの前に召還される。同作に於いてアイロニーの発現が薄く感じられる理由は、野村の敬意がそれを押さえ込んでいるからと考えられる。野村の「メランディ」によってジョルジュ・モランディは「小さな父」となった。そして「小さな父」とは、擬態の依り代となった対象を再生・更新・拡張する、野村が生み出した新しい表現の技法である、と筆者は分析する。
二次創作との峻別
野村が使った擬態を経由して依り代となる対象(主に作家など)を召還する作業を、あらためて「小さな父」化と呼びたい。野村の手法は明らかにモランディの二次創作ではないかという指摘もあるだろう。敬意を込めた表現こそが、二次創作の真髄と考える面もある。だが、野村の手法を二次創作であるとするのは、彼の手法があまりに限定的なうえに固有で、表現としては純粋でネタ談義に留まらない深さと熱量がある。さらに野村が使う“擬態”は彼独特の技法だ。少なくとも野村の擬態は、技術的にも経験値的にも思想的な背景も含めて誰もが真似できる技術ではない。二次創作に用いられる技法の範疇に含まれるという指摘があるかもしれないが、あまりに汎用性がない。また、二次創作は自分と他者を楽しませることを目的とするのが常だが、野村は誰かを楽しませるためにこの創作を行っているわけではない。すべては自己表現のためだけに行われているのであって、目的が違う。卓越した擬態術が生み出す「小さな父」たちは、二次創作とは一線を画す手法である、とひとまずここでは結論づけておきたい。
私たちが目指す「小さな父」
ここまで野村浩の新作「メランディ」について、妄想を交え考えを巡らせてきた。野村作品の「擬態」については、筆者はすでに写真の会の会報85号(*8)において論じたが、ここでは擬態から派生した新しい表現の回路としての「小さな父」を見出すことができたのはラッキーだった。また、その課程でイタコ漫画、二次創作、同人誌などサブカルに由来する表現を経由・参照しながら論を進めたが、写真や美術など表現をめぐる言説に接するなかで、いま現在においてサブカルほど社会に隣接している表現はないと確信できたのも収穫だったと言えよう。
折しも現在(2020年5月1日)、世界では新型コロナウイルスが猛威を振るっている。感染者は全世界で300万人を越え、死者は20万人を超えた。科学万能の21世紀にペストやスペイン風邪に迫るパンデミックが起こるとは、誰も予想しなかった現実がいま目の前で進行している。人類は危機的状況に置かれ、特にウイルスの標的は経済そのものではないかと思えるほど、経済の停滞は痛ましい限りだ。
このコロナ禍という特異点で、「小さな父」となったジョルジュ・モランディについていま一度考えてみる。過去を遡り生前のモランディの功績を確認するのも必要だが、この先の「小さな父」たちのあり方について想像を働かせてみたい。そのためには論考の出発点となった宇野常寛の著書『リトル・ピープルの時代』をもう一度引いてみよう。宇野は村上春樹の作品を事例に戦後日本の父性をめぐる考察を展開したうえで、小さな父=リトル・ピープルの概念を以下のように表現している。
私たちは誰もが、老いも若きも男も女も、ただそこに存在しているだけで決定者、すなわち小さな「父」として不可避に「機能してしまう」。貨幣と情報を通じて自動的に世界にコミットしてしまうのだ。リトル・ピープルの時代を生きる私たちは、生まれ落ちたその瞬間から小さな「父」なのだ。
認めると認めざるとにかかわらず、私たちはすでに「小さな父」だという。『リトル・ピープルの時代』が出版されたのは、東日本大震災が起こった2011年。あれから10年経つが、いまの世界にリトル・ピープルを自覚している人はどれくらい存在するのだろうか。見渡せば、老いも若きも男も女もビッグ・ブラザー(=国民国家における大きな物語)の時代への回帰を指向する者と彼らを支持する者たちに溢れている。つい最近まで3度目の東京五輪開催にはしゃぎ回ったこの国の大人たち、英国のBREXIT、米国のトランプ支持者などなどリトル・ピープルの自覚どころか、世界は全力で真逆の方向に疾走していた。しかし、コロナウイルスはそれを許さない。回帰主義者たちの動きは間もなく(というかすでに)停滞を余儀なくされるだろう。
野村浩がジョルジュ・モランディに擬態して表現した「小さな父」化手法は、すでに失われた対象であっても再生・更新・拡張が可能であることを証明した。そこから持ち帰れるものがあるとすれば何か。それは、この日常において「小さな父」たちは何を為すべきかという問いでもある。野村の手法を振り返れば、己の得意な技術を怠りなく磨き、先行者への敬愛を忘れず、創作を継続する、となるだろう。3番目はとくに表現者でなくても万人に通用すると思われる。農夫は畑を耕し続け、作家は書き続け、ランナーは走り続ける。日常を、時代を生き継ぐために、私たちは正しく「小さな父」になる方法を模索するべきなのだ。(了)
*1 『リトル・ピープルの時代』2011年、幻冬舎刊。筆者の宇野常寛は1978年生まれの批評家。近代の国民国家における大きな物語(=ビッグ・ブラザー)がもはや成立し得ないフラット化された3.11以降の時代をリトル・ピープルの時代と定義した。
*2 有志団体「写真の会」が主催する写真作品賞。1989年に編集者・写真評論家の故・西井一夫が設立。野村浩は、2019年に通算31回を迎えた同賞を受賞、須田一政『日常の断片』が特別賞を受賞した。
*3 写真家・須田一政(1940-2019年)が青幻社から刊行した最後の写真集。1983年から84年にかけて『日本カメラ』誌に発表された同名作品に、事件現場の風景を撮った「SPOT」、日常の光景を撮ったポラロイドを作品を加えたカラー作品集。装幀は鈴木一誌。
*4 野村浩の作品集『CAMERAer -カメラになった人々』(私家版、2019年刊)において、カメラと写真に関するメタファーとして登場するキャラクター。モデルは著名な写真家、写真機、写真技術、写真的現象まで写真と写真術に関するありとあらゆる事物で、すべて野村のアレンジで「カメラー」化されて登場する。須田一政とローライフレックスが一体化した「スダーライ」も「カメラー」の仲間である。
*5 漫画家・つげ義春(1937年-)の代表作。つげが見た夢をモチーフに描かれた短編で、シュールな作風と写真を基に描かれた風景を下敷きにした細密な背景など、漫画における前衛を拓いたとされる作品。漫画をはじめ、のちの表現に与えた影響も大きい。余談だが、海外の評価も高いつげは2020年、フランスで開催されるバンド・デシネの祭典、第47回アングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受賞した。
*6 1986年に「ドクター秩父山」で漫画家デビュー。玩具会社、ゲーム制作会社の営業として勤務する傍ら、漫画家としても活動するが、手塚治虫の絵柄とタッチを習得後はイタコ漫画家として活動中。手塚以外にも一世風靡した漫画家やアニメ作家、アニメスタジオ等のタッチと作風を習得し独自の二次創作を精力的に発表し続けている。著書は『神罰』(2002年、イーストプレス)、『うつヌケ〜うつトンネルを抜けた人たち〜』(2017年、KADOKAWA)ほか多数。
*7 筆者はしばしば野村と田中圭一について会話したことがある。
*8 牛腸茂雄(1946-1983年)の写真集『SELF AND OTHERS』(白亜館、1977年)収録の双子の少女の作品、ダイアン・アーバス(1923-1971年)の作品、「一卵性双生児」( Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967)を指す。
*9 写真の会『会報85号』 収録の第31回写真の会賞選評、拙筆「写真はサブカルチャーを貫けるか?」を指す。
参考・引用文献
宇野常寛『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎、2011年)
須田一政『日常の断片』(青幻社、2018年)
野村浩『eyes』(赤々舎、2006年)
野村浩『Doppelopment』(私家版、2017年)
野村浩『CAMERAer -カメラになった人々』(私家版、2018年)
野村浩『Suddallei -すだ式』(フリーペーパー、2019年)
つげ義春『ねじ式』(青林堂、1968年)
『写真の会 会報85号』(写真の会、2019年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
