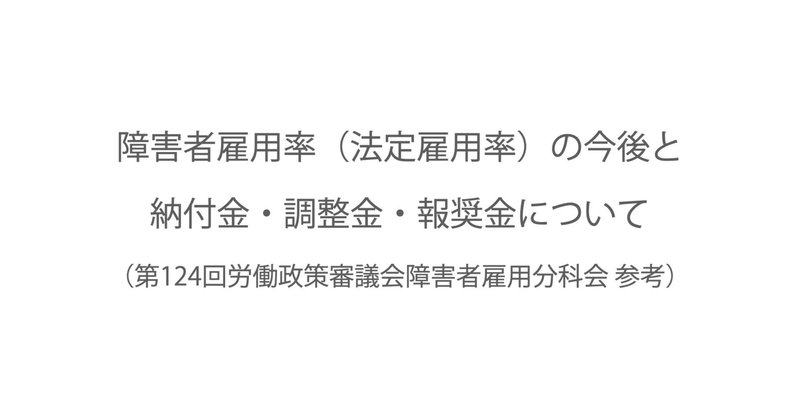
法定雇用率の今後と、納付金・調整金・報奨金について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」及び法に基づく「障害者雇用対策基本方針」改正の議論が大詰めとなってきています。概要が明らかになってきていますので、中身を抜粋して説明したいと思います。
なお、本資料は以下の
厚生労働省>(労働政策審議会(障害者雇用分科会)>第124回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)より抜粋しています。
今後の法定雇用率について

メディアでも報道されているように、過去最大の雇用率の引き上げと言われています。平成30年度に精神障害者が実雇用率に算定されたことにより、法定雇用率は2.4%となっていましたが、激変緩和措置のため2.3%としていました。この5年の間に、精神障害者の雇用者数も増えたことで、法定雇用率がUPしたのでしょう。
企業や官公庁は障害者活躍推進計画を立てて、障害者雇用促進のためのロードマップを作成しなければなりません。今回の雇用率の引き上げ後に、どのようなことが起こるのか引き続き追っかけていきたいと思います。
納付金・調整金・報奨金について

納付金・報奨金は据え置きで、調整金の金額はUPすることになりそうです。
(納付金制度について詳しく知りたい方は、以下のnoteが参考になります)
一方、調整金・報奨金ともに一定数を超える場合はその支給単価を引き下げる方針となっています。




財源確保のために、納付金や調整金・報奨金についての議論はされていましたが、納付金を引き上げるということではなく、調整金や報奨金を一定数以上雇用すると減額の方針で内容が固まりそうです。

その他
納付金や調整金、報奨金の話になると障害者雇用を「数」として捉えてしまうことが危惧されます。障害者雇用のあり方については今一度考えていく必要があると思っています。
また、新たな助成金制度が設けられる予定ですが、障害者雇用を促進するための支援員やコンサルテーションのできる有識者が少ないことも気になっています。
制度が空回りすることなく、有益に利用されるような仕組みであって欲しいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
