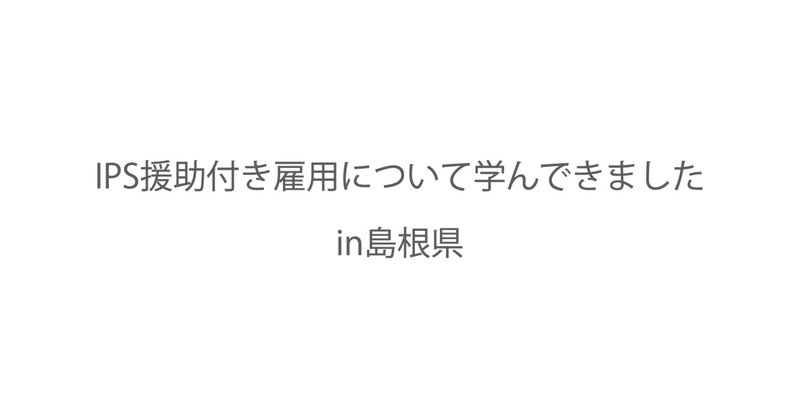
IPS援助付き雇用について学んできました in島根県
IPS援助付き雇用について学んできました。

IPS援助付き雇用への出会い
私はこれまで、就労移行支援施設で働いてたこともありトレーニングを行いいわゆる「職業準備性」を整えていきながら、就労にステップアップをすることが就労支援の基本だと考えていました。
しかし、障害者が訓練を行い就労をするということは、「障害者本人が就労のために社会に合わせることが必要である」と感じ、世の中は「社会モデル」を推進しているはずなのに、就労という文脈になるとどうして「個人モデル」が優位になってしまうのだろうと疑問に思っていました。
また、週5日勤務を目指すための訓練を行うということで、通所を促すことや、就労支援スタッフとしてハローワークの障害者雇用求人に依存し、良い求人は出ないかと待機期間があること、そして、「本人のこういった仕事をやってみたい」という思いに本当に寄り添えているのか、疑問に思う時期がありました。
そのようなもどかしさを抱えているときに、IPSという就労支援プログラムに出会いました。
IPSは個人を尊重し、就労支援員が積極的に職場開拓に動きまくるのが特徴的で「これだ!」と思いました。
その後、できる限り相手のニーズを聞くことに徹し、職場開拓を精力的に行うようになります。
友人のツテを使って、ケーキ屋さんの実習を調整したり、SNSを使って実習先の開拓をしたり、求人誌をめくりひたすら電話をし、実習や雇用に向けて動くようになりました。
現在は退職し、別の仕事をしていますが、IPSをきちんと学びたいと思ったので、IPSラーニングツアーに参加してきました!
IPS援助付き雇用ラーニングツアー
研修場所は島根県、浜田町。参加者は精神科Dr.から、私のような精神保健福祉士までIPSに興味のある多職種の方が参加し、病院見学〜IPSを利用する当事者との座談会〜企業の見学などを行い、とても充実したプログラムでした。
やっぱりIPSいいなぁと思ったことは、Train placeモデルから、Place trainモデルという、従来の就労支援のあり方を覆す取り組みを推進しているところです。
Train placeモデル:トレーングを行ったのち、就職をする。
Place trainモデル:希望者はいるでも支援を提供し、企業に就職して、最低賃金で給料を得られる。働きながら訓練する。
そして、きちんとIPSはエビデンスに基づく実践であり、7つの原則が体系化されていることです。
①除外基準なし
②就労と精神保健サービスとの統合
③一般就労
④保障計画
⑤迅速な職探し
⑥継続的な支援
⑦クライアントの好みの尊重
※⑧体系的な職場開拓
※IPSの原則は定期的に見直しされており、現在は⑧も追加されている。
詳しくはこちらの書籍でIPSを学ぶことができます。
ただ、IPSは構造化されたプログラムであり、それを日本で導入するにはなかなかハードルが高く、個別支援に特化していることもあり、事業運営(人件費など)にも支障がきたすことも考えられます。
それでも、今回研修を主催してくださった、西川病院の院長の林先生は「お金じゃないんだと」何度もおっしゃっていたことが印象的でした。
あと、日本で活動している団体のHPもあります。
感想
島根県。遠かったけれども行って本当に良かった。関心事が同じ方々(それも、バラバラの専門職)と一緒に研修に参加をすることはとても刺激になりましたし、仲間がいるような感じがして勇気をもらいました。
なにより、最高なロケーションと、美味しい食事、みんなで温泉入ったりと、良い思い出にもなりました。
最高に楽しかったです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
