
『サード・サマー・オブ・ラブ』BLM(ブラック・ライブズ・マター運動)の失敗はなにを意味しているのか?
極めてショッキングなニュースが流れてきた。
イスラエルのミュージシャン絡み、ユダヤ音楽絡みの原稿依頼があって、どう書こうかと考えていたら、それどころじゃない恐ろしい話題が。
— kentarotakahashi (@kentarotakahash) December 2, 2023
レイシズム丸出しで、ジェノサイドを欲する血塗られたヒップホップ・チューン。しかも、イスラエル軍に英国の女性アーティストを殺せと求めている。 pic.twitter.com/fNLTymggUo
イスラエルのシンガーがラップに載せてパレスチナ人へのジェノサイドを煽るといった内容の曲がイスラエルでは大人気だという。一応筆者も聴いてみたが、格好いいトラックに言葉は知らないが格好いいフローが載っており、文脈を知らなければお気に入りにしてしまいそうだ。アドリブ的なshoot!がいい味を出している。共有して再生数にさらに貢献してしまうのは癪なのでリンクは載せないが、興味のある方は調べて聴いてみると良いかもしれない。
要は、普通にいい曲なのだ。であるのに、少なくともここで歌われている内容は、「イマジン」や「オールユーニードイズラブ」、「ワンラブ」、「オールライト」などの、英米で積み上げられてきた"はず"のポップスの歴史からは明らかに逸脱しているように見える。さらに、イスラエルは(第一世界以外への差別的な物言いになってしまうが)一応は高い国民所得を持つ「西側先進国」の一員であることから、なおさら衝撃的である。ここで元ツイートの高橋健太郎氏の言うような「ポップスはそもそも殺人者の音楽だ」という見方に筆者は賛同しない。芸術とは本来価値中立的であり、それが時代によってどういう意味を持つかのほうが重要だからだ。つまり、ロックやヒップホップなど、戦後の平和のなかで築き上げられてきた「カウンター」カルチャーが、洗練されたプロパガンダの道具と堕してしまった現実のほうに、筆者は注目する。
アメリカン・ポップスの黄昏
筆者個人の歴史観として、ポップスの歴史は大きく3つのターニングポイントがあると考える。
1960年代中盤の、ビートルズを筆頭としたさまざまなグループが文字通り音楽に革命を起こした時代。
1990年前後の、ロックが覇権を失い、ヒップホップやR&Bが後釜に収まるようになった時代。
2020年以降の、サブスクサービスの伸長とBTS以降の「コリアン・インヴェイジョン」によって突入した新時代。
大体これくらいの時期に音楽界には地殻変動が起こり、カルチャーの変化が起こった。そして、筆者がこれから論じたいと考える「サマー・オブ・ラブ」はそれぞれこの時期と重なる。一度目の無印「愛の夏」は1967年7月に起こったと言われる。二度目の「セカンド・サマー・オブ・ラブ」は1980年代後半に起きた。そして筆者は「サード・サマー・オブ・ラブ」を2020年のBLM運動と定義する。
ここで、まず一度目の「サマー・オブ・ラブ」について簡単な説明をしよう。1967年のカリフォルニアにはすべてがあった。そこにはLSDがあり、サージェントペパーズがあり、コミューンがあった。「愛の夏」という安直すぎる表現は、安直すぎるが故にすべてを表していた。名だたる芸術家たちと彼らに教導された若者たちはあらゆる面での伝統を破壊して回った。それは明らかに「革命」の灯であり、1920年代のソビエト連邦が挫折した『人民に奉仕する芸術』のある種の姿だった……と、歴史書は言う。
いくぶんの誇張は含まれているが、1960年代後半の西側諸国民が岐路に立たされていたのは、振り返れば明らかだ。この時代における最大の特徴は、「ドラスティックな革命が起き"なかった"」ことにある。この時代、政治的な変化は特に起こっていない。唯一フランスではドゴール政権は倒れたが、その後共産主義革命が起きたわけではない。プラハの春はソ連に速攻で鎮圧されたし、日本やアメリカでは、佐藤栄作-田中角栄ラインや、ジョンソン-ニクソンラインによって保守的な政治が続いていた。しかし、ビートルズたちはこの戦いに「勝利」したと言える。68年革命およびその「前史」としての「サマー・オブ・ラブ」は、政治的な変化ではなくむしろ———もっと根源的な———人々の意識を根底から変革したのだ。経済成長によって都市的なライフスタイルが西側諸国の田舎まで浸透し、フリーセックス(現代的な恋愛の直接的な源流)やドラッグが広まり、ロックに代表されるようなカウンターカルチャーがメディアで大っぴらに流れるようになった。現代的な生活の直接的な起源がこの時代にある。
二度目のサマー・オブ・ラブは、レイヴカルチャーの興隆をもたらした。現代のクラブミュージックはここに直接的な起源があると言っても過言ではない。80年代後半のイギリスで盛り上がったこのムーブメントは、後のロックの没落を予期していた。ヒップホップの登場やヘヴィメタルの行き詰まり感など、それまでカウンターカルチャーの主役だったロック音楽は終わりの兆候を示し始めていた。二度目の愛の夏もその一つである。結局その後ロックは、カートコバーンという自己破壊的なスターによって再起不能な状態に陥り、ヒップホップとクラブの時代が始まるのだ。そしてその兆候の一つにこの「夏」があると言える。
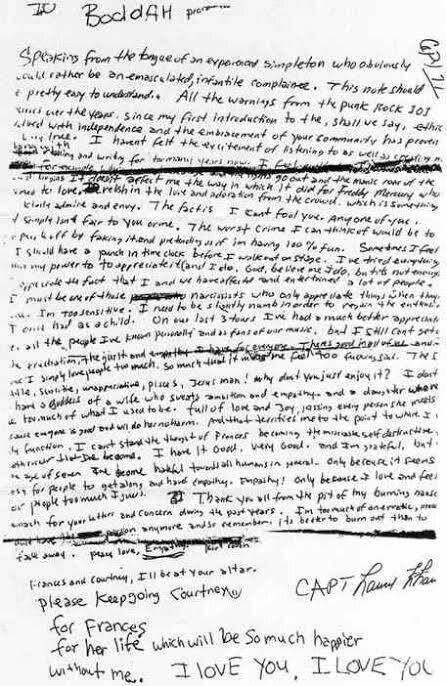
翻って、三度目の「夏」はどうであったろうか。筆者はこの年こそがカウンターカルチャーそのものにとって大きな転機だったのだと考える。おそらく2020年以前ならば、イスラエルの虐殺ソングが日の目を見ることはなかったのではないか?例えばイラク戦争が起きたときに世界で流行っていた曲は、ブラックアイドピースの”Where Is The Love”であり、SMAPの『世界に一つだけの花』であり、ジョンレノンの"Imagine"だった。無論パレスチナに恨み骨髄のイスラエルと、お気楽な平和を享受する日本国民の意識の間には相当な隔たりがあるのは事実かもしれない。しかし、実際ウクライナ戦争やガザ侵攻のあと、平和を願うプロテストソングは世界のどこでもヒットしていない。これは明らかにポップカルチャーの変質を表している。そして、その転機を端的に表したのがサード・サマー・オブ・ラブ=Black Lives Matter運動の失敗なのだと考える。
政治社会的に2020年は今に至る混乱の幕開けとして記録されるだろう。コロナ禍は社会の脆弱性を露呈させ、国際政治的にはその後さまざまな地域で一国行動主義が顕著になった。そして、何よりも超大国アメリカの覇権は明らかに相対化された。アメリカの力が落ちたわけではない。未だにアメリカはビッグテックや巨大な海軍を擁し、最強国家だ。しかし、BLMと議会襲撃事件によってアメリカを「スーパーパワー(超大国)」ではなく「グレートパワー(列強国)」とする相対化された見方が導入されたのだ。これ以降(特に議会襲撃事件や今年のガザ侵攻以降)、アメリカは「クーデター未遂が起こるレベルで国内は不安定で、中国やロシアにも押され気味のくせに正義面してる巨大な未開国家」として、一部の国からは明確に「舐められ」始めている。
音楽においてもこの年は新時代の幕開けを象徴するものとなった。2020年はBTSが始めてビルボードで一位を獲得するという、明らかな大事件があった年だ。しかしBTSの成功は、単なるアイドルグループの成功という以上に重大な意味を孕んでいる。BTSは、「アジアン」でありながらある種のセックスシンボルとして欧米を席巻した最初の存在となったのだ。これまで戦後70年間、アメリカの覇権のもとフィーチャーされてきたセックスシンボルは、格好の良い白人男性だったり、あるいはロックが没落してからはNBA選手やラッパーのような黒人男性だった。彼らはアメリカという国の人種プールの主要なところを占める属性であり、白人であれ黒人であれ「アメリカ」という覇権を背景にした存在であることは確かだ。BTSは、それら二つのどちらでもない。人種プールとしてはアメリカの中で最も小さな影響しか持たないアジアンで、アメリカ人でもない。アメリカは、おそらく覇権を握って以降始めてアメリカ人でもなく白人でもないアイドルに熱狂するようになったのだ。これは「アメリカ」が文化においても中心とは言い難くなったことを表しているのではないか?
20世紀のポップスはブルースや黒人労働歌、カントリーミュージックなどアメリカのルーツミュージックを直接の起源として誕生した。大衆文化の中心がロックおよびヒップホップであり、そうした文化は「パクス・アメリカーナ(アメリカによる平和)」のもとあった。イマジンなどの「お花畑」的な名曲の数々は、今やオリンピックで歌われるほどの「名曲」だ。こうしたプロテストソングはアメリカ「政府」の攻撃を食らっていたが、それら名曲の最大の後援者はアメリカが作り出した平和だったというパラドックスがある。いずれにしても、アメリカ人やイギリス人が作り出した名曲の数々は時代の中心として機能していた。日本や韓国などの「周辺」が、どのように英米の文化を取り入れるかを四苦八苦していた(日本語ロック論争など)ことからも、それは明らかだろう。
そしてその状況は2020年を境に明らかに変わった。今やアメリカの音楽はラテンミュージックとラップミュージックに占拠されるようになり、人口動態の変化がもろにメインストリームの変化に現れるという、ある種興醒めな状況が現出している。2010年代あれだけ出現したブルーノマーズやテイラースウィフトのようなメガ・スターの代わりに出てきたのは、ビリーアイリッシュを除けば陰鬱なラッパーばかりだ。右翼的なプロテストカントリーソングや、あろうことかK-POP、J-POPまでがチャートに現れるようになり、かつてアメリカが中心になって回っていた世界の音楽の図式は完全に崩壊した。
要は、すでにアメリカの音楽は世界の中心ではなく、そもそも音楽自体もカルチャーの震源地ではなくなったのだ。これには様々な理由がある。例えばSpotifyの影響でシーンが細分化され、中心を持たない様々な国での流行がインスタントな広まりを見せるようになったこと。アメリカの人口構成がもろに変化したことも相まって、ラテンの影響が可視化されたこと。アメリカの分断の加速による大衆文化の縮小。そもそもSpotifyによって音楽が「稼げる」ものではなくなったこと。色々ある。ただ、アメリカの音楽も、音楽そのものも世界を変える訴求力を持ち得ない時代が始まった。それは、AIの登場により「複製可能性」が臨界に達したことも重なって、これからも加速していくだろう。
ビートルズの新曲は「ビートルズサーガの終焉」や「ファンへの気の利いた最後の贈り物」以上に、音楽史に残る重大な意味合いがあるかもしれません。…
— みの (@lucaspoulshock) November 2, 2023
ここで筆者は改めて、ここまで述べた「音楽」の限界と終わりをある種象徴する出来事になったのが2020年のBLMだと主張したい。BLMのアンセムとなったのはケンドリックラマーの”Alright”だった。黒人コミュニティに大して希望と啓蒙を歌うこの曲は、発表から10年も経たないうちに歴史的名曲としての地位を確立した。かつての公民権運動で”A Change Is Gonna Come”があったように、ベトナム反戦運動で” What’s Going On?”、ジミヘンの星条旗があったように、その後の戦争で”Imagine”が常に鳴っていたときのように、今回の抵抗運動でも中心となるアンセムがあった。
「惨めな」シアトル・コミューン
筆者はBLMをさきに「失敗」と記したが、BLMの意義と方法論を否定しているわけではないことをここで断っておく。そもそも政治運動には血腥く破壊的なにおいが付き物であることは事実だ。今回、建国の歴史にまで遡及してリンカーン像やワシントン像が燃やされたのは非常に衝撃的だったが、それを除けば今回の暴動が60年代の公民権運動と比較してそれほど過激だったわけではない。さらに、60年代の社会運動は、ものごとの顛末だけをあげつらえば、基本的に「全て」失敗している。先ほど筆者はドラスティックな革命は「起きなかった」と記述したが、それは厳密には間違っている。正確には「起こせなかった」のだ。60年代の思想的リーダーだった毛沢東の起こした文化大革命はその後内部でおぞましい虐殺が進行していたことが白日のもとに晒されたし、東側のプラハの春も速攻で鎮圧されてしまった。要は、今昔で起きていることに大して違いは無いのだ。それでも筆者は68年を成功、2020年を失敗と主張する。
2020年の失敗を構成するのは以下の2つでほとんど説明がつく。
中間層の没落により社会に「上潮」な雰囲気が消えたこと
インターネットによって「失敗」の状況が可視化され、憎悪がさらに増幅されたこと
無印「愛の夏」の原動力は何度も言及したように中間層の成長であり、それに対して3年前の惨劇は中間層の没落が原動力だった。さらに人種間対立や階級間対立が深まったことで分断=「大きな物語の消滅」が起きて、インターネットがそれを煽ったことも大きな理由だ。そして筆者はここが何より見落とされがちだと考えるが、SNSは官制的な「真実」が通用せず、インスタントな刺激を駆動するアルゴリズムに従って悲惨な光景が流れてくる。それはBLMにおいて良性の影響も悪性の影響ももたらした。ジョージフロイド氏の衝撃的な殺害動画がインスタントに拡散され、それが民衆のフラッシュな怒りを喚起したのは、良性の影響といっても良いかもしれない。しかし、怒りに駆られた人々が暴動や破壊を起こせば、第三世界の如くセンセーショナルな風景がやはりインスタントに拡散され、ただの「暴動」としてのBLMの現実を「暴いて」しまう。全ての政治運動は闘争としての血腥さを孕んでいるのに、SNSはその血腥い要素をことさら強調することで、更なる分断をもたらしてしまうのだ。官制的な真実の切り取りが効かなくなったことで、言論空間は完全なカオスに陥った。トランプ以前の私たちの平和は、「マスゴミ」による「言論統制」によって成り立っていたような気さえしてくる。
上記のクリティカルな例として、2020年のシアトル・コミューンをあげよう。実は、60年代の変動期にはコミューンが各地で現れた。ドゴール退陣を要求するフランスの大学生が路上のいたるところに作ったコミューン、サンフランシスコのヒッピーコミューン、ウッドストックやワイト島のフェスティバルもコミューンの一種と言って良いかもしれない。
この中でいちおう成功を収めたのはウッドストックくらいだろう。フランスのコミューンは最終的に住民の総スカンを食らい、翌月の選挙ではドゴール派が大勝した。ワイト島フェスティバルでは暴動が起き、この暴動や前年のオルタモント・フェスティバルでの殺人事件を起点に、急速にヒッピームーブメントが萎んでいくこととなる。サンフランシスコのヒッピーたちも、漏れ伝わってくる外からの実像で見れば成功だったのかもしれないが、訪問したジョージハリスンがドン引きしてLSD断ちをするくらいには荒廃した状況が広がっていたようだ。

それが許されていたのはやはり「上潮」の経済とインターネットの不在によるものだろう。当時の彼らの少し間抜けで破壊的な実相は覆い隠され、栄光の歴史として今では語られている。翻って、2020年にはシアトルでコミューンが出来た。当時高まっていた警察への批判を受けて、警察権力の通用しない楽園を作ろうとしたようだ。自治区の宣言当初、民主党のダーカン市長もこの存在を「近所のパーティのような雰囲気だ」と肯定的にとらえ、市の予算を配分する交渉も始まっていたらしい。余りにもお気楽な話である。トランプの攻撃もレッテル貼りと考えられ、リベラルを中心に歓迎の雰囲気が広がっていたのだ。
その高邁な理想はできた瞬間からかなり怪しくなってくる。組織の内部での対立や暴力が蔓延し、KKKなどとの抗争が起こり、一ヶ月もしないうちに市は強制排除した。語るまでもなくどうしようもなく「惨めな」失敗の光景だった。ただこれがもし60年代に起こっていたら、いまの筆者のような語り口だっただろうか?彼らは別にあさま山荘事件のように人質を取って殺しを行ったわけでは無い。ただ内部の治安が悪かっただけで、上で見た60年代の抗議運動とあまり違いは無いのだ。それでも60年代の運動は今でもヒロイックに語られ、2020年の運動は明らかに「ダサい」結末となってしまったのだ。起こっていることは変わらないのに、社会状況とインターネットがBLMを失敗に追いやってしまった。キング牧師が実現した国民統合の世界は遠のき、欧米先進国は人種階級間闘争の渦に放り込まれることになる。
そして、こうした暴力の渦が行き着いた一つの象徴として議会襲撃事件があった。この一連の事件は、先ほども述べたようにアメリカの文化覇権に致命的な影響をもたらした。メッセージはより内向きに、モンロー主義的な自閉をし始めている。ケンドリックラマーは今でも巨大な影響力を持つ現代のジョンレノンというべき存在だが、その力のベクトルは共産主義的で夢想家的(ドリーマー)な方向には向かわない。クソみたいな現実(マッドシティー)で育った男が、出自の黒人コミュニティのためにalright!と、メッセージを発するのみだ。その純度とクオリティが普遍性を持って「しまう」から人気なだけで、彼のメッセージ自体に普遍性があるわけでは無いのだ。彼の存在は、大きな物語が完全に崩壊し、小さな分断が覆う世界を象徴している。
夢は終わった
今後この状況はさらに加速していくだろう。ケンドリックラマーの人気も、ラテンやK-POP、J-POPの躍進も、イスラエルでの虐殺ソングのブレイクも、そしてBLMの失敗も、全ては一つの線で結ばれていると、筆者は考える。それは、世界の全てが「夢」を見られたイマジン的な時代の終わりであり、冷戦のような主義の時代の終わりであり、破片のように散らばった小さな物語たちが対立を先鋭化させていく時代だ。そしてAIの発達とサブスクビジネスはポップスという夢を終わらせていくのだろう。サード・サマー・オブ・ラブはもう来ない。何故ならオピオイドまみれの"それ"はもう来たあとで、それが残したのは愛ではなく憎悪だったからだ。「戦後」という夢は終わり、私たちは次の時代を見通せないままでいる。
Yesterday
I was the dream weaver, but now I’m reborn
I was the Walrus, but now I’m John
And so dear friends, you’ll just have to carry on
The dream is over
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
