油井正一「ジャズの歴史物語」と村井康司「あなたの聴き方を変えるジャズ史」を読んで。
油井正一「ジャズの歴史物語」(1972年)が電子書籍で出ているのを知り、久しぶりに再読してジャズ知識欲?が高まって、村井康司「あなたの聴き方を変えるジャズ史」(2017年)も勢いで通読。村井さんのは出てすぐ買ってたけど、積ん読になってたもの。分厚い本なんでつい放置しててすいません! 今さらですがこの両書を読み比べた感想など書いてみたいと思います。

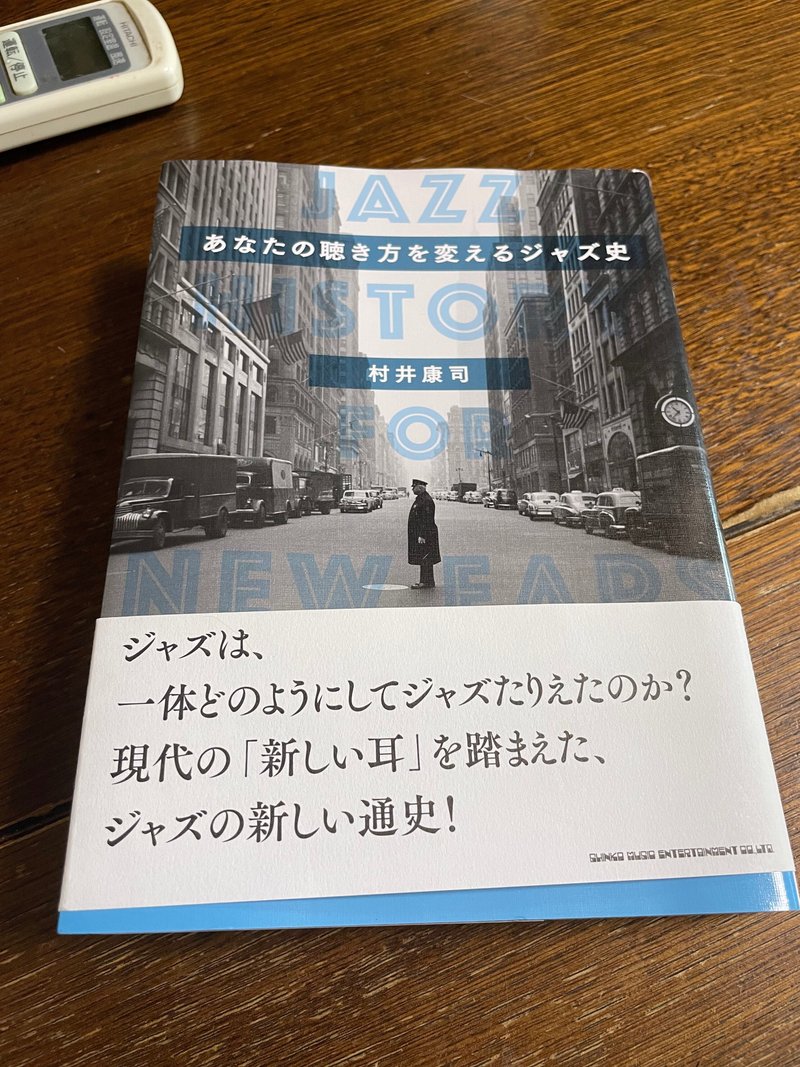
「ジャズの歴史物語」は1972年の出版で、私も出てからわりとすぐ買った記憶がある(手元にある現物を確認したら1973年の第二版だった)。一読してこれはすごい本だと思い、それでジャズのことをなにもかもわかった気になったものだった。まだ高校生でロックのことさえ何もわかってなかった時期なのに。でも「油井史観」によって私のジャズ観が出来上がったのは確か。ロックやポップ・ミュージックが専門でジャズは門外漢の私ですが、今でもこの本の影響は大きいと思っています。

「ジャズの歴史物語」は当然ながら1972年以降のジャズの動向については触れられていない。マイルスの「ビッチェズ・ブルー」が出て、ジャズが大きく変わりそうな予感はあるもののまだその影響は顕在化していない時期。なのでそれ以降、現在(2017年)に至る動きについてしっかり語って歴史の中に位置づけている「あなたの聴き方を変えるジャズ史」は、時差45年(!)を埋めるという目的だけでも、十分に一読の価値がある。
でも私が痛感したのは、半世紀前の油井さんの本の、今でも十分通じる「現代性」だ。そこで語られているジャズを巡るさまざまな言説や視点、歴史の捉え方、アーティスト評価の妥当性は、今でもほとんど古びていない。これは全くの憶測だけど、村井さんの本は「ジャズの歴史物語」を踏まえながら、そこに足りないものを加えたり、ちょっと疑問なところや不要なところは省いたり修正したり、さらに現代のジャズを知る者からの視点を新たに加えることで成り立っている気がした。つまり「油井史観」そのものはもはやジャズの歴史を語る際の「王道」として揺るがぬものがあり、今ジャズの歴史を語るのであれば「油井史観」を大前提、下敷きとしてそれを発展させるのが妥当、という立場から書かれたのが村井さんの「あなたの聴き方を変えるジャズ史」なのではないかと。その付け加えられた、あるいは強化された視点は、中村とうようの「ブラック・ミュージックとしてのジャズ」あるいは「大衆音楽としてのジャズ」という史観にヒントを得ているようだ。
で、その油井さんの本にない1972年以降「その後45年」のジャズの歴史なんだけど、1918年生まれの油井さんにとってジャズの歴史はほぼその始まりからリアルタイムで経験してきたものだったのに対して、1958年生まれの村井さんにとってリアルタイムで体験した現代進行形のジャズは、まさにその1972年以降なのである。なので「あなたの聴き方を変えるジャズ史」の1972年以降の稿は、その実体験や同時代的実感を踏まえたイキイキした筆致になるかと思えば、「フュージョンブーム以降のジャズの歴史については、それ以前の話よりとっ散らかっちゃう」(本書より)のだった。その理由を村井さんは相倉久人さんの文を引用しつつ、70〜80年代以降のジャズのあり方が、「変化」から「差異」へ、過去のカーカイブやデータベースへのアクセスへと変容してきたことにあるのでは、とする。
つまり1972年までのジャズは常に新しい形式・様式へと「進化」「成長」してきたしそれを志向していたけど、70〜80年代以降のジャズはリサイクル、つまり過去の音楽遺産の引用と再構成・再解釈、言い換えると「DJ的視点」が主流になってきた、ということ。ここから先は私の見方だけど、1970年代以降のジャズはすでに「進化」が止まり成熟して完成され、かつてのモダン・ジャズやフリー・ジャズのような画期的・革命的な新様式を生み出す力は既になくなってしまったのではないか(ただし村井さんは初期のフュージョンは「画期的な新しい音楽だった」という立場なので、村井さん視点では「80年代以降」ということになる。私はその立場ではないので「70年代以降」)。その事情はロックも全く同じ。つまりジャズもロックも不断に進化し脱皮していく「成長途上の音楽」では、既にない。定方向的な進化史観では捉えられなくなってる。だから70年代以降のジャズは「歴史」として語りづらくなっている。相倉久人さんはそのへんのことを著書「新書で入門ジャズの歴史」で「ポストモダン」というキーワードを使って解説している。
で、私はどうなのかといえば「成長途上の音楽」が好きなんですね。言い方を変えると、形式・様式が定まっていない、未完成の音楽。いつでどこでどう変わっていくか、成長するかわからない未知の可能性に満ちた音楽。私が常々「かつてのパンクやテクノのような、手前の音楽観、後生大事に抱えた価値観を粉々に打ち砕くような”革命”を待ち望んでいる」と書いているのはそういうこと。もちろん過去のアーカイブへのアクセス、過去への新しい視点からでも新鮮で面白い音楽が出来ることはわかっているし、日々それを楽しんでもいる。でもそれまで聞いていた音楽がすべてガラクタになってしまうような「ガラガラポン」の「革命」を待ち望む気持ちが、やっぱり一番強い。でも今のロックやジャズにそれを望むのは難しそうで、もしそんなものが出現してもそれはロックともジャズとも呼ばれないかもしれない。そんなことを思った。もしかしたらそれが今のR&Bやヒップホップ、ベースミュージックなのかもしれない。
今からジャズの歴史を学びたいなら「あなたの聴き方を変えるジャズ史」だけど、「ジャズの歴史物語」はお勉強になるだけでなく、単純に読み物として抜群に面白い。油井さんは雑誌連載が始まる時「エピソード多めのジャズ史」を求められたらしいけど、そのエピソードを書く筆致のリアリティというか臨場感がすごいのである。まるでその場にいたかのようにパーカーやエリントンやマイルスのエピソードをイキイキと語るその筆致はまさに名人芸。それを読むだけでも価値がある。また、とにかくジャズがさまざまな視点から語られ、初めて読んだ時はわからなかったり読み飛ばしてたり咀嚼できなかった部分が、年月をおいて再読すると理解できたりスッと頭に入ってきたり納得できたりする。そういう発見が多い本でもある。きっと「あなたの聴き方を変えるジャズ史」も、今後再読を重ねればそんな本になっていくのだろう。なお村井さんは「もう少しコンパクトで、『あなたの聴き方を変えるジャズ史』とは違った視点からのジャズ史の本」を執筆中だそうで、そちらも楽しみだ。
で、今はいい時代だなーと思うのは、本を読みながら「このアーティストちょっと気になるな」と思ったら、サブスクやYouTubeですぐ確認できること。油井さんの本を初めて読んだ時は、ただ文献上の知識を得るだけで実際の音に触れるのは難しかった。便利な世の中になったもんです。
よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。
