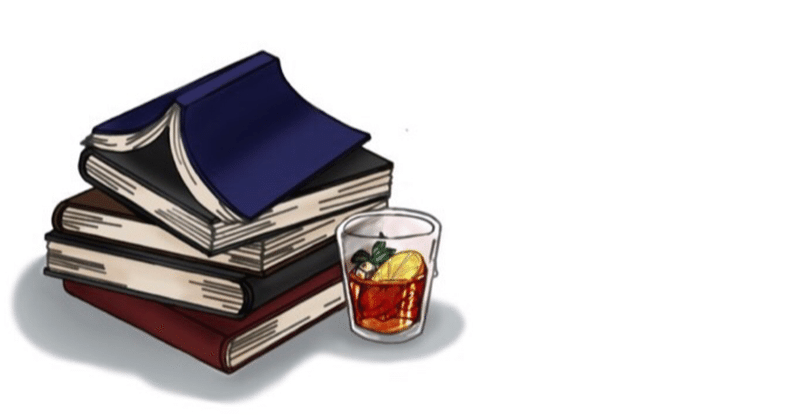
感想のようなもの Unnamed Memory
去る4月17日、『Unnamed Memory』(古宮九時)の完結巻となる第6巻が発売された。結末を知っていた私でも楽しめたし感動した。それは書籍から入った方でも同様だと思う。
発売から3週間。少し早いような気もするが、ネタバレ込みで本編の感想を書きたい。今回は書籍版(と特典SS)のみの内容でWEB上の後日談についてはできるだけ語らないようにする。できるだけ多くの方と感想を共有したいのだ。
私がこの作品に出合ったのは4年前。初出は13年前なので古参でも何でもない。本編は「小説家になろう」で読了した。それ以前に『Rotted-S』『Babel』は読んでいたので『Unnamed Memory』に対する期待は高かった。
ちなみに『Babel』に関しては書籍化している。
そして『Unnamed Memory』は、その期待を優に超えてきた。
硬派で美しい文に対照して繰り広げられるオスカーとティナーシャの軽快な会話。隅々まで張り巡らされた伏線とどんでん返し。ハッピーエンドともバッドエンドとも言えない稀有なる結末に感情を揺さぶられた。
なんというか全体としての感想を述べようとするとどうしても抽象的でつまらなくなってしまうので、少しではあるが視点を限定して深堀してみたいと思う。それに伴って考察のようになってしまったので、苦手な方には受け付けられないかもしれない。
また、明らかな読み間違いは勿論のこと、人によって解釈が分かれるような意見でも指摘していただけると嬉しい。
オスカーとティナーシャ
この文章の8割はこの二人に関することである。
この二人は王という立場故に自分の事は棚に上げて国や民を優先することが多い。これは特に二幕で顕著になるのだが一幕にもそれを示す記述は多い。
以下はオスカーの心情描写である。
だが、どれほど忌々しく気分の悪いことがあろうとも、それらを含めた全てが自分の負うべき重さだ。誰とも分かち合うことはできないし、誰に押しつけるつもりもない。自分はそういう一生を送るのだと、すでに覚悟はできている。 (一巻117ページ)
おそらくオスカーの立場と孤独をはっきりと表現した最初の文ではないかと思う。王族としての責務と覚悟は一幕二幕共に変わらない。というかオスカー自体一幕二幕共にあまり変わらない。ティナーシャの変化が大きい分目立たないだけかもしれないが……。
そしてやはり、一生で一度の私情による我儘がティナーシャへの求婚なのだ。
ヴァルトを通してではあるが「いつかの君と」でティナーシャが死んだとき私人としてのオスカーも死んでしまったのだと書かれている。そして、過去に戻る力があってもは自分だけのためには使えないだろうと言うのだ。おそらくエルテリアがあってもティナーシャを助けるために使うことはないのだだろう。それは私情の我儘にすぎないのだから。
このような面はオスカーの強さの一部でもある。迷わず過去に囚われない(囚われてる素振りを見せない)。そんな彼が迷った姿を露わにしたのは一幕でティナーシャがクスクルへと行ってしまった時だ。
「じゃあ、あいつは俺の事をどう思っていると思う?」(二巻71ページ)
なんともオスカーらしくない台詞である。それに対してルクレツィアが分かり切ったことを聞かないでほしいと一蹴したことにより介入を決める。
また、二幕でもティナーシャがマグダルシアとの戦争へ単身行ってしまった時も迷いを見せる。
――なのに今、自分が私情で彼女の選択を侵してもいいのだろうか。(六巻209ページ)
ここでオスカーを諭すのはヴァルトなのだがその言葉が秀逸だ。少し長くなってしまうが引用しよう。
「今更何を言ってるんですか。今回は苦労せずに彼女の心が手に入ったからといって、怠けないでください。貴方は毎回彼女を口説き落とすのにかなり大変な思いをしてましたよ。最初から愛されている方が珍しんです。ちゃんと動いてください」
~中略~
「あれが彼女の本当の姿です。でも同じくらい貴方といる時の彼女も本当なんですよ。貴方にとって彼女は無二の女性ではありませんが、彼女にとっては貴方しかいないんです。彼女を救うのはいつだって貴方なんですよ。なのに手を離すんですか?」(六巻209-210ページ)
この台詞で敵でありながらもヴァルトの事を好きになった読者は多いのではないか。私はそうだ。
この場面で改変の記憶を持っているのはヴァルト、そして読者のみである。3巻で無事にゴールインし幸せを見届けた我々にとって、一幕ラストの改変は衝撃的なものであったはずだ。
そして、一幕を読んだ我々はティナーシャが自分一人で無茶をする時、そばに行って助けるのはオスカーであると分かっている。ヴァルトの言葉は読者が持つ「オスカーはよいけ」という気持ちをうまく代弁しているのだ。好きにならないはずがない。
ヴァルトに関しては後述するのでいったん置いておくとして、オスカーが迷いを見せるのはいつだって私情でティナーシャに接する時なのだ。それ以外、特に王の立場でのオスカーは一切迷いを見せない。それはティナーシャに対してもだ。「いつかの君と」ではティナーシャを殺す決断をもしている。それが「私」としての彼を失うことと同義であろうともだ。
ちなみに本編後はそのせいでとある事が起こり結構大変なことになるのだがそれはまた別の機会に……。ともかく、これがオスカーという人物である。
対してティナーシャは一幕、二幕ともに過去へと囚われている。そして(これはオスカーも同じであるが)周りに助けを求めない。
一幕のティナーシャに関してはずっとボッチ生活を送っていたためか序盤からそれが顕著に表れ、そこにクスクル問題も加わり半年で過去との清算を果たし人に頼ることを知る。
それに対し二幕のティナーシャはオスカーの前では幼く振る舞っているためか、あまり孤独な面は表に出さない。そして一幕のようなイベントがないので結局終盤になってやっと助けを求めるのだ。
「貴方は何でもできますし、自分でやろうという姿勢は評価できます。でも王になるというなら、もう少し周りを使うことを覚えなさい」(一巻149-150ページ)
一幕序盤のこの台詞はティナーシャ自身にも大いに当てはまる。まさにブーメラン。特に二幕のティナーシャは王としてなんでも自分で抱えてしまうが、その姿はオスカーに通ずるところがある。
そして、その凍った心を溶かすのは彼女の唯一の王と決まっているのだ。
背中合わせの記憶
繰り返しになるが、おそらくこの章で多くの読者は衝撃を受けたのではないだろうか。そしてタイトルである『Unnamed Memory』の意味を考えたのではないかと思う。
ここまできて今まで積み上げてきた全てが崩れてしまった。ようやくティナーシャが自分の気持ちに自覚を持ちオスカーと結婚を果たしたのにも関わらず、何もかもが無に帰ってしまった。これは作者に人の心がないと言われても仕方がない。
それはさておき、ここでオスカーは二幕のティナーシャに多大な影響を与えている。
オスカーに対する執着やエルテリアによって自分は助かったのだという想い、それこそ二幕のティアーシャの半分はこの章によって形作られたと言っても過言ではないだろう。
この物語は全編通して印象的な台詞や文章が多くどれも素晴らしいと思うのだが、なかでも下記の台詞は群を抜いている。オスカーが「背中合わせの記憶」でティナーシャへと言った言葉だ。
「歴史が変わっても、書き換えられても、俺がお前に出会って共に過ごしたという事実は消えない」
~中略~
「お前が忘れても、俺が忘れても、俺たちが出会わなかったとしても――お前を愛している」(3巻 390ページ)
この台詞自体とても素晴らしいので感動した人も多いだろうが、この台詞の本当の素晴らしさは最終巻で下の台詞と対面した時に分かることになる。
「オスカー……歴史が変わっても、全てが元に戻っても。どこにも誰にも記憶が残らず、たとえ私が生まれなくても……愛しています。貴方が私の、最初で最後のただ一人です」(6巻 400ページ)
この言葉は明らかに「背中合わせの記憶」で発したオスカーの台詞に対応している。まさに400年越しの伏線回収だ。こういう事をするから「運命の代償」は何度読んでも泣いてしまう。今もこれを書くために読んで泣いている。
そしてティナーシャはこう続ける。
「だからどうか待っていてください。必ず私は貴方の前に現れる。時を越える。そうしたら私たち、もう一度恋をしましょう」(6巻 401ページ)
端的に言ってこの言葉は『Unnamed Memory』という作品を体現していると思う。
歴史が何度変わろうとも、生まれた年が4世紀違っても彼らは出会い、恋をする。これを何千年と繰り返す。この壮大で美しい御伽噺がこの台詞に詰め込まれていると思うのだ。
同じような台詞は「物語の行方」にもある。こちらの方がよりこの作品を、二人の運命を表しているかもしれない。ちなみに一巻のアイテア祝祭は187回目。「物語の行方」の祝祭は342回目なので、彼が塔で魔女と契約してから155年後の話だ。
ここに至るまで紆余曲折あるのだがそれは制作が決定した続編に期待するとして、155年という月日である。ラザルやシルヴィア、パミラやレナートなど二人の知り合いはもう殆どがいない。そして今後何千年と彼らは死んでは生まれ、出会い続ける。
そういう果てしなさをこの台詞がうまく表現している、と思う。
「背中合わせの記憶」で発したオスカーの想いは、奇しくも何千年と二人の中に残り続けるのだ。
トラヴィスとオーレリア、ヴァルトとミラリス
他にも書きたいことは色々とあるのだが、最後にこの二組について述べよう。
この物語には印象的なペア(カップル)が多数出てくるが、その中でもトラヴィスとオーレリア、ヴァルトとミラリスは外せない。
トラヴィスオーレリアについては、特に「永遠の半分」での二人は微笑ましい反面、悠久を生きるトラヴィスの悲しさというか苦しさというか、なんとも形容しがたい感情が呼び起こされる。永遠に生きるとはどういう事か、オスカーとティナーシャの運命が決まるより一歩早く、読者はそれを意識するのである。
またトラヴィスとオーレリアの挿絵は出てきた途端笑ってしまうほど彼らをうまく描いていた。あの絵が一番好きかもしれない。
ヴァルトとミラリスは、私は第二の主人公ペアだと勝手に思っている。最終巻の「いつかの君と」についてはWEB版本編にはなく、書籍で追加された章であるが、ここでヴァルトへの愛が増幅された。
「いつかの君と」についてはティナーシャの
「どうして? 貴方がその剣の持ち主で、私が魔女である限り、いつか貴方は本当に私を殺さなければならないかもしれませんよ」(一巻264ぺージ)
という台詞が現実になってしまったという点でも印象深い話ではある。
最後、自分のためだけに過去を変えることはできないと答えたオスカーに対して、ミラリスを生き返らせるためにエルテリアを使ったヴァルト。この対照さがたまらない。
オスカーに心からの礼を持って一礼したヴァルト。
彼はオスカーを苦手と言っていたが、その裏には尊敬の念があったのではないかと思う。
最終的にヴァルトは消えてしまったが、ミラリスは六巻特典「忘れられた食卓」において幸せな生活を送っていることが描かれている。それだけでもヴァルトの意思が報われたのだと思う反面、彼らが一緒になれなかったことへの虚しさに苛まれるのである。
終わりに
拙い文章に加え常体で統一しているので高圧的な印象を与えてしまったら申し訳ない。深堀とか言いつつも結構薄っぺらいことしか書けてないような気もする。
『Unnamed Memory』はここで語ったこと以外にもたくさんの読み所がある。何回読んでも面白いし伏線等が多いためか結構新たな発見があったりするのも魅力の一つだ。
発売日は未定だが続編の制作も決定しているのでそちらも楽しみである。古宮九時先生のツイッター曰くBabelまでの間が飛び石的に埋まるらしい。今回の書籍化では加筆が多くアップデートを感じられたので続編もどのようになるか楽しみである。
ちなみにトラヴィスとオーレリアの絵が一番好きと言ったが、一巻目次のルクレツィア、四巻目次のミラ、五巻の表紙、五巻の冒頭のカラーもめちゃめちゃ好き。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
