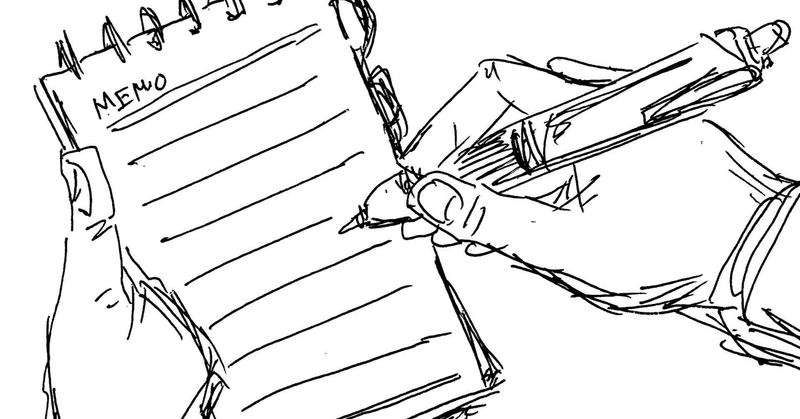
漁夫の利の専横と小競り合いー『何が記者を殺すのか』より
先月観てきた『教育と愛国』のドキュメンタリーを制作された、MBSディレクターの斉加氏による著書『何が記者を殺すのかー大阪発ドキュメンタリーの現場から』を読んだ。購入して一週間、沖縄基地問題から『教育と愛国』のテーマである教育現場まで、壮絶な現実の側面があることに次々衝撃を受けながらページをめくる手が止まらなかった。
参考:『教育と愛国』ドキュメンタリーの感想
https://note.com/onthefirstday_c/n/nb2ba78f30107
著者が取材してきた対象やテーマは様々だが、一貫して感じたのは「我々の小さい利益をめぐっての小競り合いが政権側の専横を赦しているのではないか」ということだ。「おわりに」にもあるように、報道機関だと新聞記者同士の特ダネ争いだったり、企業だと自社の利益を上げたいがために結果政権に阿るようになったりと(例えば直近明らかになった、桜をみる会でのサントリーの酒類無償提供)、持つ側がますます好き勝手にできてしまう状況を作り出してしまっている。日本人/社会特有の、共通のモラルや公的なために動くことの意識が薄い特徴が見られて個人的にはすごく残念な気持ちだ。
己の利害、関係者からの評価に囚われて自分の行動がどのような影響を社会に及ぼすのかが見えていない、お互いが小さい世界で小競り合いしているのをいいことに、政権側は憲法改正や重要な法案をこっそり都合のいいように改正しようとしている。漁夫の利とはこのことではないか。
政権批判、政治家批判は国民の権利であるはずなのに、同じ一般市民から「批判するのは違う、自分が悪いんだろ」とかえって非難される。なぜ公権力をかばうのか?
本の中で描かれている出来事には、公的なモラル観の欠如のほかに、過剰な自助の意識・美化があると思う。
人に頼るのは悪い、自分が悪いんだから自分で良くなるよう努力しろ、批判よりもまずは提案しろ等々。ネガティブなところばっかり挙げてないで、自分たちで周りを良くしていこうという行き過ぎたミニマリスト思考。~してないから、できないから非難する資格はないとか。同じ土俵で比べるスケールが違いすぎるのになんで単純化してしまうんだろうか。もう自助では限界だと、SOSサインを堂々と出していくことが、私たちにとって少しでも生きやすい社会に一歩前進だと痛感した。批判がないとよい提案は生まれないのだから。
いろいろなゲストとの対談を見ていて終始穏やかな著者だが、粘り強く今の社会への問題点を浮き彫りにする芯の強さに圧倒され、励まされた。ぜひまだの方は読んでみてほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
