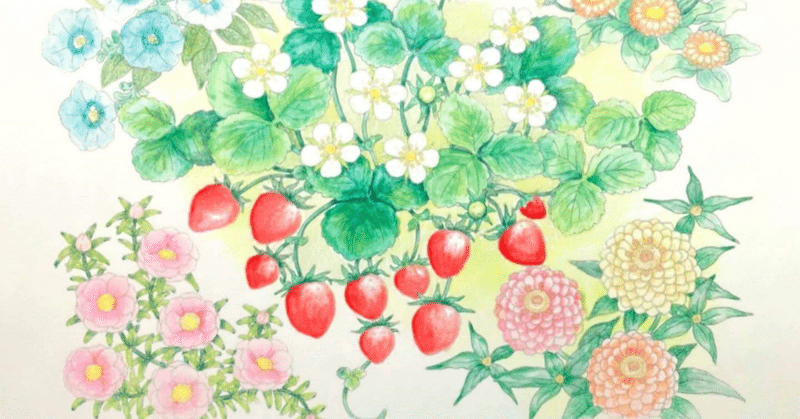
萩尾望都の『ストロベリーフィールズ』に書かれた初期エッセイ
1976年に新書館から『ストロベリーフィールズ』という萩尾さんのイラストや詩や物語や対談やエッセイをまとめた本が出ているのですが、ここに出てくるエッセイは後の大泉本(『一度きりの大泉の話』)の片鱗が伺えてなかなか興味深いです
大泉本では竹宮さんが攻撃対象でしたが、『ストロベリーフィールズ』は萩尾さんの言うところの「ド・マニア」が主な対象となります。以下紹介していきたいと思います
「表現のことⅠ どうして言葉ってすれ違ってしまうの?」より抜粋
ある日私はさる大学のまんが部のめんめんと会合した結果、その会話にぐったりつかれて帰ってきた。私は小半時考えた末、やはり変だと思って友人に聞いた。
「これまでにも、まんがマニアの大学生と話すたびに、疑問に思ってたことなのだけれど」
「うん」
「何だか、常識に欠けるというか、会話が成り立たないのよ、連中と。そもそも表現の基礎構文が異なるの。いったい、その年でまんが読んでる大学生がばかなのか。ばかだから、まんがを読むのか」
大学生との会話の詳細が書かれてないので、いきなり「ばか」と言われても何がなんだか?と思うのですよ。しかも「表現の基礎構文」って聞いたことないし、何が言いたいのか意味がつかめないのでネットで検索しちゃいました。どうやら萩尾さんの造語のようですが、何の説明もなく造語を持ち出してくる人とは確かに会話が成り立たないだろうなと
以下、その後の友人(城さんと思しき人)との会話です
「でも。大学生って、頭いいはずよ」
「きみんちの弟、大学生でしょ」
「あ、そうだった」
「どこ」
「Q大」
「すごい。頭いいでしょ」
「いや、あいつとの対話は意志(ママ)の疎通に欠ける。第一、プリーズと発音できない。リンガフォン使って授業うけたくせ、ピーズなんていいよる。それに要所ついて、あげ足とった質問すると答えきれない、理工をとってるくせに、宇宙船の軌道計算を、私に解るように説明できない」
「そんな、あなた」
「ううん、Q大であの程度か」
私は、自分が大学へ行ってないので、大学へ行った人はみんな頭がいいと思ってしまうのだ。だって高卒より数年余分に勉強するんだもの。良くならずして何としょう。
これはひょっとして萩尾さん流の高等なギャグか何かなんでしょうか?
プリーズの発音が頭の良し悪しにどう関係するのかもわからないし、意思の疎通に欠けることも、宇宙船の軌道計算が理解できないことも、弟さんではなく、実は萩尾さん側に原因があるのではないか?という疑問は一切浮かばないのでしょうか?
以下、続きます
さて、TVの“クイズ・グランプリ”を友人どもと見て、みなで解答してゆくと、毎回、百点そこそこの私に比し、二、三百点とる友人がいた。
「すごい、記憶力いいのね。辞書みたい」
「学校では委員長やってたわ」
ところがこの方、記憶力は良いのに、表現構成と創造力に、はなはだ欠ける。手近な例では、右から聞いた人の話を、左の人に伝えることができない。人がAといったのに、Bと解釈したりする。この方、私が会った、まんがマニアの大学生と、いくぶん似てるとこがある。基礎思考に、ぽっかり穴があいてるような。
「右から聞いた人の話を、左の人に伝えることができない」「人がAといったのに、Bと解釈する」というのは、「表現構成と創造力」の問題なのでしょうか?全く関係ないのでは?
「基礎思考にぽっかり穴」というのも何を言っているのか?「基礎思考」って言葉も聞いたこともないので検索して調べましたが、どうやらこれも萩尾さんの造語のようです
こんな調子では、萩尾さんがAと言ったつもりでもBと解釈する人がいるのは当然のように思えてしまうのですが……
さらに続きます
「昔は頭のいい人、本当に学問やりたい人がいってたけど。今はね、誰でもいくじゃない。大学生だからってスペシャリストではないのよ。広中教授みたいなスペシャルは、一割ぐらいよ、きっと」
そうかなあ。そうだろうな。
ああ、彼らはいうのだ。私が、「これではお話のテーマがふたつもみっつもに、分かれてしまうでしょう」と評した作品に対し、熱っぽく大まじめで、
「ひとつの作品に、テーマはいくつあってもよいと思います」
――国語教育はどうなってるんだ。国語教育は。
いきなり、話が作品のテーマに飛ぶのも理解しがたいし、テーマは複数あってはいけないのでしょうか?そんなこと国語教育で習った記憶はないんですが……それより、萩尾さんのこのエッセイのテーマがわからない。「表現のこと」というタイトルだったはずだけど、どこが「表現」の話なんだかわからない
しかし、エッセイは「表現のことⅡ」に続きます
「表現のことⅡ なぜかしら、このごろすこうし憂鬱です」より抜粋
ある日私が描いた、吸入器を見て、マニアのひとりが、「私もぜん息で病院で吸入器を使ったことがあったけど、こんな形じゃなかったわ」と言った。
「あらそうなの、私、写真見て描いたの」
「私のは、こんなのじゃなかったわ、吸入器って、こうじゃないわよ」
彼女は主張し、私は写真を見せた。おじいさんが、吸入器を使ってる姿が写っている。彼女はだまった。私は「きっと、いろんな形の吸入器があるのね」と言った。「そうね」と、彼女は答えた。
こんなエピソードは日常茶飯事だと思うし、まして相手の女性は最終的に「そうね」と理解してくれたのだから、ことさら取り上げるような話でもないと思うのですが
ある日私がまんがに使った名前を見て、マニアのひとりが手紙をくれた。
「ドイツが舞台だというのに、“シューベル”という、フランス名を出している。私はドイツ語を勉強しているので、すぐわかりました。読んでいて興がそがれて、不愉快な思いをしました。ちゃんと、ドイツ名だけを使って下さい」と書いてあった。
へー、シューベルってフランス名だったの、と私は思った。シューヴァルという、推理作家がスウェーデンにいるのは知ってるが、私のこのシューベルは、かの作曲家シューベルトの最後の一字を取っただけという創作名にすぎない。理由?そっちの名の響きの方が好きだから。
おそらく「11月のギムナジウム」に出てくる、トーマ・シューベルのことを言っているのでしょう。このマニアの方も「不愉快」とまで言っちゃうのは言い過ぎかと思いますが、シューベルトから「ト」の字を取ってシューベルにしちゃえという萩尾さんの発想がなんかもうついていけません、一応、実在の西ドイツという国を舞台にしているのだから、「響きが好きだから」という理由で名前を創作しないで、ちょっと調べてから作るのが相手国への礼儀ではないかと思うのです
そして、この件についての言い訳が延々と続きます
しかし、ドイツが舞台の話だからドイツ名だけにしろとはこれまたなぜに。
では戦後、一千万を超す、ポーランドやユーゴの引き揚げ者を吸収したという西ドイツ社会で、ポーランド名やユーゴ名をもつ者はどこへやろう。フランスのザール、アルザスの地方は、たびたびドイツ領となったり、またフランスへ返されたりしている、良質の石炭のとれる地域だが、そこの人名と人種の混合を、どう分けよう。
また、英国人やスペイン人と結婚して、ドイツでくらす若奥さんの、ダンナの国の姓名を、どう排除したもんか。ヨーロッパのそもそもの、語源の基のラテン語の、各国における多くの共通性を、一体いかにしたものか。
「百億の昼と千億の夜」を連載すると決まった頃、岡田斗司夫氏が萩尾さんに漫画化にあたっての注意点を書いて手紙で送ったら、萩尾さんから便箋14枚にわたる反論の手紙が送られてきたという有名なエピソードを思い出してしまったほどの反論っぷり
でも、萩尾さんはいろいろわかった上でシューベルってつけたわけじゃないんですよ?シューベルトから「ト」を取っただけなんですよ?フランスに詳しい人だったら、トーマ・シューベルはフランスから先祖が移り住んだのだろうか?それは物語的に何か意味があってのことか?なんて余計なこと考えちゃう人もいると思うんですよ、ここまで言い訳を連ねるならそんな読者の心理を考えてみても良かったのではないでしょうか
以後、デッサンの狂いを指摘したマニアの話、ちばてつやにはアシスタントがいないはずと強硬に主張したマニアの話の後で
いったい、若い人たちに何が起こっているのか、みんな、表現に窮している。自分の知りうる狭い真実にしがみついている。何が自信を失わせているのか。
と続くのですが、また「表現」、いったいどこが「表現に窮している話」なんでしょうか?萩尾さんは「表現」という言葉に萩尾さん独自の意味を追加してるのか?と思えてきます。それに若い人たちが自信を失っているどころか、自信満々な点が問題なのではないでしょうか?
そして結論が
なぜかしら?
なぜかしら、なぜかしら。考えていると、受験地獄といわれる今の学校教育にぶつかってしまう。若者たちと密接につながっている学校。学生である若い人たちは、今学校で、何を教わっているのかと。人間の本分と価値が、テストの成績によって決められ、受験のための勉強を勉強しているのなら、若い世代の熱量が、それで消化できるのかと。
1976年と言えば、「トーマの心臓」も「ポーの一族」も描き終えたばかりで、萩尾さんの評価は頂点に達していた頃かと思いますが(まあ、「花と光の中」を描いたのも1976年ですが)、こんなエッセイを読んでしまったファンの中にはそっと萩尾さんから離れてしまった人も少なくなかったのではないかと
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
