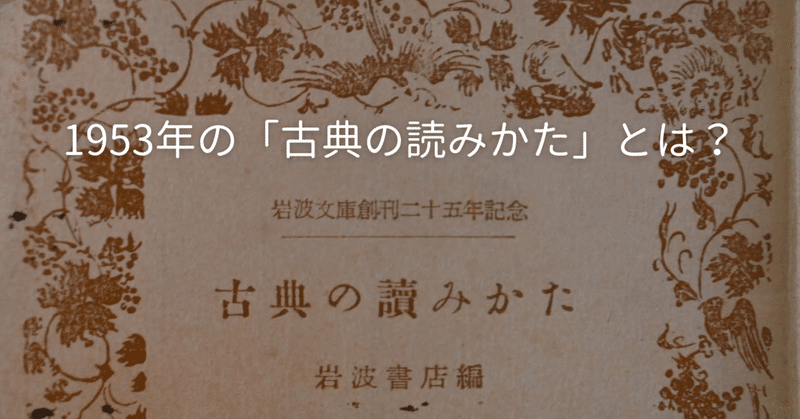
1953年の「古典の読みかた」
小冊子「古典の讀みかた」(非売品)は岩波書店が岩波文庫創刊二十五周年を記念して1953年に発行したもの。小泉信三や清水幾太郎など計7名の知識人によるエッセー集である。
備忘録として、各人のエッセーの概要をまとめることにしたが、その前に各エッセーの冒頭を比較する。これだけで、各人の文体の特徴や、エッセーの内容の密度、あるいは思想の片鱗といったものまでが伺われると思う。(なお、小冊子は旧漢字・旧仮名遣いだが、引用する際は現代表記に直している。)
エッセー冒頭の比較
早速各々のエッセーの冒頭部分を引用してみたい。こうして比較してみると、各人の読者を引き込む筆力というのが、たったの数文で表れるのがよく分かる。
小泉信三「古典の読み方」
古典を読めとはよく人もいうし、私もたびたびいったが、その古典とはどんなものか。まず古典と相対するものは、新刊書であろう。…
小泉は古典とは何か、という問いから書き起こしている。この点は良い。しかし、すぐには結論を示さず、わき道を延々たどってようやく結論に至るというのがどうもこの人のクセらしい。
清水幾太郎「古典」
誰でも同じことであろうが、私は古典について二通りの記憶を持っている。
第一は、ひどく退屈してしまった場合である。…
7名の中で清水の文章に最も引き込まれた。まず「2通りの記憶がある」と宣言し、「第一に…」ともってくる。これだけで読み手としては読みやすい。しかも、第一の記憶として、「ひどく退屈した」ということを挙げる。こうもあけすけに言ってのけることで、たちまち読者は続きが気になることだろう。
大内兵衛「古典と岩波文庫」
古典はいかによむべきかと聞かれたが、私にはかんたんに答えられない。「人見て法とけ」ということばがある通り、質問者の求むるところが何であるかによって答えが異なるのは当然である。…
質問者によって答えが異なる、というなら、ある程度質問者の関心を類型化してそれぞれに答えるのが筋だろう。しかし、大内はこの後で自らの読書体験を長々と記している。要するに、問われたことについて答えていないのだ。テストなら0点の作文だと思う。
高木市之助「国文学の読み方」
私がここで国文学というのは、仮に文庫の分類の名称に随ったまでで、文庫が国文学という名称で分類したのも仮に世間の慣用に随ったまでで、少し皮肉に言えば、それは国文学のはらまきに黄色が選ばれた偶然とたいしてちがってはいないであろう。…
このようなウダウダした一文から始められると、もう、読む気が失せにけり。
桑原武夫「日本で読む西洋文学」
岩波文庫が発足してから、今年で二十五年になる。…岩波文庫が多難の四分の一世紀をちゃんと生きたという事実に、まず敬意を表したい。…
岩波書店に寄稿をお願いされたのでとりあえず敬意のごあいさつ、といったところか。つきあいを大切にされる方なのかもしれないが、読者としてはどうでもいい。
吉川幸次郎「中国の古典」
クラシックという意味で、古典の二字を使うことは、中国の言葉として生まれたもののように、予想されるかもしれない。しかしこの予想は、あたらない。…
「古典」という言葉は中国由来でないらしい。こうした一般通念と反する事実から導入してもらえると、興味が湧く。
河盛好蔵「現代文学の古典」
現代文学の古典という表題を掲げているが、ここにいう古典とは厳密な意味での古典ではなく、現代文学の古典的名作というぐらいの意味であることをまず断っておきたい。…さし当たって、明治文学の名作がその対象になるであろう。…
こんな断り書きから始めなけらばならないなら、表題を「明治文学の名作」とでもすればよかったのに。
小泉信三「古典の読み方」
小泉信三(こいずみしんぞう、1888-1966)は経済学者、教育家。岩波新書からは『読書論』(1950)が出ている。
小泉の考える古典とは次のようなものだ:
古典とは、世に出てから或る年月を経て、自からにしてその声価が定まり、後代の人の思想がそれによって支配されている著書だということになる。
小泉によれば、古典は「読者を、精神的又は思想的に高く若しくは大きくする」。しかし、そんな利益があるにもかかわらず、「人は意外に古典を読まない」と書いている(もはや古典を読む方が意外なのだが)。
人が古典を読まない理由について、小泉は次の論を張る。いわく、
古典とは何らかの意味で独創的
→その独創性は著者の強い個性から発する
→強い個性の持ち主は自分の言うことを読者がどうとるかについて往々にして無頓着
→読者は古典に取りつきにくい厳しさを感じる
これでは古典の著者は読者のことを考えていないという文句と変わらないのではなかろうか。未来の古典を書こうとする者は、読者に無頓着で構わないと言っているようなものだ。
さて、いろいろと書いた後で、結局著者が言いたいことは、「古典的大著など、そんなに大して恐れることはない、恐れずに読めば存外分かるものだ」ということと、「本を読んで、それから出発して自分で物を考えること」だという。何のことはない、著者のメッセージは教育家として実にまっとうで模範的であると言えるだろう。このありがたいお説教を読んだら、次は毒舌家のお出ましである。
清水幾太郎「古典」
清水幾太郎(しみずいくたろう、1907-1988)は社会学者。岩波新書の『論文の書き方』(1959)は代表的ロングセラー。読書論である『本はどう読むか』(1972)は講談社現代新書から出ている。
清水は、古典を読んでひどく退屈した経験と夢中になった経験を挙げ、次のように述べる。
肝心なのは、読む私の方の心構え、読むときの私の態度であるように思う。即ち、これは古典だから一度は読んでおこうという程度の気持ちで読み始めた時は、必ず結果がよくない。(中略)ところが、これに反して、流石は古典、などと頷いたりする場合は、漫然と読み始めたのではなく、こちらが特定の問題を追っている時である。結局は、現代社会の中に露出している諸問題と関係があるのだが、そういう問題を追っている時、いや、問題に追いかけられている時は精神的にガツガツしているし、精神の牙――というものがあれば――が鋭くなっている。錆ついた歴史の殻を噛み破って、その内容に学ぶことができるのだ。
これは確かにその通りだ。「本には個人的な旬がある」と何かで読んだが、旬の本は古典だろうと夢中で面白く読めるものだ。
続いて、清水は特に西洋古典は漫然と読まれやすいと述べ、その事情を二つ挙げる。一つは、「西洋思想に対する非常な尊敬の態度」であり、もう一つは「永遠の問題に対する愛好或は尊敬」である。しかし、清水はいずれの事情にも否定的だ。前者については、西洋古典は西洋の自然的・文化的条件と密接な関係にあり、そうした条件を共有しない日本人が古典を漫然と読んでも血肉にならないという。また、永遠の一般的問題については、日々の、時代の問題を追及した後に図らずも遭遇するものであるとし、具体的・日常的な問題から出発するのでなくては永遠の問題など存在しないと断ずる。
さらに、清水は「批評家を代表とするインテリ全体」に批判の目を向ける。清水によれば、批評家らは現代作品の内容と現代の問題については沈黙し、もっぱら作品の技術的側面を批評して冷たい評価を下しているという。その反面、彼らは古典には大きな問題が潜んでおり、永遠の問題を扱っているとして尊重する。これを「無条件降伏」と形容するのは、彼らが古典の「殻」と格闘する前に礼讃しているからだ:
だが、私自身の経験から言えば、賞賛し推薦する人たちが、本当に興味を持って古典を通読しているとは信じられない。時代や伝統の差のために、多くの古典は堅い殻に包まれている。これを噛み破るのには、生きた問題に心をつかまれた人間の、あのガツガツした精神の食欲、鋭くなった精神の牙、そういうものが要る。この条件はそう簡単に生まれるものではないし、就中、権威の前に叩頭するような態度とは絶対に相容れない。
一方、「古典の世界に生きていて、古典の刊行の時は校訂を試み、解説を書く」専門家についても、「現代社会の問題との縁はプツンと切れている」と手厳しい。
最後に、清水は現代社会における古典受容のあるべき姿について論じる。
清水によれば、そもそも書物とは、「自分自身の経験を処理し、自分自身の問題を解決するための道具」でしかない。そこで古典を道具として用いようとする場合に考慮すべきことは、古典が書かれた当時の社会事情と現代の事情は相当に異なっているということだ。貴族・精神的貴族に独占されていた古典は、廉価で大衆の手に入るようになった。それはつまり、現代文明に生きる人々の問題意識と古典とのつながりは時の経過とともに細っていくということでもある。また、新聞やテレビによるマス・コミュニケーションの発達は、大衆を受け身にさせ、「精神の牙」をなまらせる。
こうした事情から、古典を現代社会で活かすためには、まず古典と大衆との間を取り持つインテリや解説者は「現代文明の諸問題に対するセンスによって古典の上に新しい光を加えるだけの度胸が要る」。また、読者にしても、問題意識をもって古典に取り組まなければならない。清水は読者に対して、古典を理解し、忘れないためにも、自らの思想と古典の思想との「噛み合い」を文章に表現することを勧めて筆を擱いている。
大内兵衛「古典と岩波文庫」
大内兵衛(おおうちひょうえ、1888-1980)は経済学者。岩波新書からは『マルクス・エンゲルス小伝』が出ている。
大内は自らの読書遍歴、現在(執筆当時)の読書習慣について長々と記している。ついで、大内は社会科学の領域ではマルクス・エンゲルスの著作だけを「第一級の古典として尊重している」と書いている。
また、「資本論」のような第一級品に比べれば、ミルやマルサスやリカードウやマーシャルやケインズといったイギリス経済学の古典は第二級品だという。その理由は、「粗朴で、偏執が多く、未熟で、まがぬけている」からだそうだ。
大内は最後のほうでこう記している:「世界には偉い人物がいたことは間違いなく、その偉い人間の偉さは底が知れない。そういう偉い人間の書きのこしたものがすなわち古典だ」と。何をもって大内が「偉い」とするのかは示されていない。何をもってマルクス・エンゲルスの著作を「第一級」と評するのかも記されていない。悪しき権威主義の権化とも言うべきだろうか。清水幾太郎が直前のエッセーで批判した「インテリ」のお手本を示してくれているのだろう。
高木市之助「国文学の読み方」
高木市之助(たかぎいちのすけ、1888-1974)は国文学者。
高木は国文学を「非現代文学」かつ「非外国文学」として定義し、それらが民衆に読まれていないことを嘆く。
次いで「現代文学は横のつながりで読め、古典は縦のつながりで読め」のモットーを示し、古典文学の縦のつながりの事例を挙げる。事例として万葉集の柿本人麻呂と山部赤人の関係、源氏物語の「もののあはれ」について書かれている。詳細は割愛。
また、「古典文学は民族の一つのありか(在処)であり、その故に民衆が古典文学の中に彼らの発祥した胡園としてそうした民族又は民族的なものを求めることはそれ自身一つの読み方でなくてはならない」という。例として歌謡集の一系列(記紀歌謡集――神楽歌催馬楽――梁塵秘抄――閑吟集)と説話の系列(古事記、日本書紀、風土記、今昔、宇治拾遺、十訓抄、古今著聞集、沙石集)を挙げる。詳細は割愛。
最後に「ことばの問題」が唐突に取り上げられる。文学における言葉の役割は大きいが、「ことばさえ分れば古典文学は分るというような見解は正しくはない」という。「古典文学を真に古典文学として読む為に必要なもっと高次の条件は、何よりもこうした天才の創造力とじかに対決し得る謂わば人間的総力を具えることでなくてはならない」という。その人間的総力とやらが何であり、どのように具えられるのかは書かれていない。
専門家にしか書けないが、だからといって学問上の価値もなく、読み物として面白いわけでもない、救いがたいエッセーと思う。
桑原武夫「日本でよむ西洋文学」
桑原武夫(くわばらたけお、1904-1988)はフランス文学者、文芸批評家。岩波新書の『文学入門』(1950)はロングセラー。
桑原はまず、岩波文庫の登場により西洋文学の翻訳が容易に手に入るようになったことが社会にどんな影響を与えたかを推測する。ただし、自分は岩波文庫の生産者の側で消費者の側でなかったので、文庫本の登場により青少年が西洋文学にどう接し、どんな影響を受けたか実感を伴った推測はできないと断っている。
第一の影響として、「日本の国民、といっても実際は知的に見て国民の中流以上の人々、つまりインテリに幸福を与えたということ」を挙げる。
第二に、「西洋文学の日本での流行は、間接的に日本人の文学観を変えつつある」という。しかし、桑原はその文学観の詳細について、「西洋化された」ということ以外書いていない。
第三に、「戦時中次第に弾圧を受けたにもせよ、西洋文学の反訳が極端な排外思想と超国家主義に圧倒されようとする人々に対して、ささやかながら心の抵抗の拠点を提供しつづけた」という。
第四に「岩波文庫が西洋の文学の古典について、大よその枠を示すことによって、西洋文学のほぼ基準的な輪郭を与えた、正確にいえば与えようとした、という功績がある」という。
続いて、桑原は日本の西洋文化の受容のあり方に反省を加える。
一つの文化民族において、その国で生産されたものよりも他の国で生産されたもの、それについての本、あるいは外国で生産された文学の反訳の方が多く好まれ、売行きがよいということは、決して健全な現象ではない。
このような西洋文化一辺倒の生じた事情として、桑原は2つの観点から論じている。一つ目は歴史的に観点であり、「明治以後、後進国日本は駆け足で西洋諸国に追いつく以外に生きる道はなかった」のであり、西洋文化の流行もその大きな流れの一つの表われだ、というのである。二つ目は文化的な観点であり、「日本には大昔から、外国の優れたものに対しては、きわめて公平無私にこれを摂取するという伝統的態度がある」ことと「西洋文学とくに近代文学の優秀性と豊富さ」とがかみ合った、というわけである。
以上のように西洋文化の流行の事情を顧みた後、桑原は次のように総括する。
西洋文学に溢れたヒューマニズムをはじめ、先に述べたさまざまの美点、それは否定すべくもないが、それに養われた心を持って日本の現実に歩み戻す、いや日本の土地をしっかと歩み進むことの必要を常に忘れてはなるまい。(中略)改むべき日本の現実とは社会生活のみではなく、文学をも含むのであって、日本によき文学を生み出す努力をおこたって、ただ西洋文学の過度の流行をののしり、これを排斥せんとするのは褊狭なナショナリズムであって文化の低下ということに他ならない。
桑原の文は論理が明快でないが、結局西洋文学の価値は揺るがないのであるから、西洋文学は西洋文学として理解しなければならない。その際に、「西洋を文学以外の手段、たとえば社会科学、自然科学、歴史などの眼をもって捉えようとする努力が大切」であり、西洋映画の鑑賞も一つの手段だという。
続いて桑原は何を読むべきかの問題に移る。桑原自身の新書『文学入門』の付録「近代文学五十選」を薦めたいが、「自己のインタレストをひくものを選ぶべき」で、「インタレストのもてない文学は名作でも強いて読むな」と書いている。
ここで、桑原の「インタレスト」には2つの方向性がある。一つは現実の社会的政治的問題に関するインタレストを持って読む「問題意識派」であり、もう一つは作品から得られる感覚や感動にインタレストがあるが知的・学問的にはインタレストのない「素朴派」である。桑原は問題意識派としての読み方に限定することは窮屈だとし、「文学の楽しみは、あくまで作品そのものにあるという鉄則」を楯に素朴派を擁護している。
最後に桑原は3点話を付け加える。一つは「反訳を読んで感動したような大作を、そのせめて一部でも原語で読む努力、並びに楽しみをもたれるように勧めたい」ということ。2つ目は日本ではフランス文学とロシア文学とが圧倒的支持を得ているが、良識と経験主義をふまえた英米文学はもっと愛好されてよいということ(ドイツ(系)文学はどこに行ったのだろう?)。最後に「熱心に本を読むと同時に、一方で本なしで生き得るという自信を養わなければ、本を読むことは意味をなさない」として、「読書にあまりあせるのもおかしい」と書いている。
桑原のエセーは全体を貫くテーマというものがなく、思い付きのまま雑多な内容が陳列されている印象を受けた。
吉川幸次郎「中国の古典」
吉川幸次郎(よしかわこうじろう、1904-1980)は中国文学者。三好達治との共著『新唐詩選』(1952)は岩波新書を代表するロングセラーの一つ。
吉川は「古典」という言葉は元来中国にはないが、古典を尊重する文化は2千年以上に渡って大変強力だったという。
中国では漢の時代から、孔子の編纂とされる「五経」が役人の必読書となった。しかし11,12世紀から役人が一般市民層からも出るようになると、宋の新儒学の大成者・朱熹により選択された「四書」が優勢となる。そして、これらの古典の根本思想は寛容な人間肯定の思想だったと吉川は書いている。そしてそのことが、四書五経以外の書物を知悉することを促したのだという。
四書五経以外に尊重されたものとして、歴史の書、文学の書があった。歴史の書の代表として、史記や資治通鑑が挙げられ、文学の書としては楚辞や文選、唐詩、唐宋八家文が挙げられる。
こうした書物がかつての中国や明治維新までの日本の人々の生活を窮屈にした一面はあるが、それは書物そのものの罪ではなく、「それらの書物にのみ生活の基礎を求めるという生活態度の罪」だという。現在では、これらの書物は「古典」としてその価値を新しく捉え直すことができると訴える。
吉川によれば、古典とは、狭義には「古代人のみがもち得る、するどい直観、洞察をそなえ、現代のわれわれにも助言を与え得る書物」のことである。また、古典はよい文章で書かれていることが必須の条件であるという。そして論語をはじめとした中国古典はこうした条件を備えているという。
最後になって吉川の文はいやに羅列的になる:
中国古典はその寛容な人間肯定の思想のゆえに「ヘブライ的なもの、ギリシア的なものが、別の方向にむかって生む偏向を、中和する」;
水滸伝、三国志、西遊記、金瓶梅、紅楼夢といった小説の系列は、「多くの人類の知慧、乃至は人生への慰めが、ひそんでいる」;
「民国以後の中国近代文学は、魯迅を新しい古典として、進行しつつある」;
中国古典を読むことで西洋文学はよりよく理解でき、逆もしかり;
中国古典として時間のない人のために最小の書目を挙げるなら「論語」と「杜甫の詩」。
河盛好蔵「現代文学の古典」
河盛好蔵(かわもりよしぞう、1902-2000)はフランス文学者、評論家。『人ととつき合う法』(1958)は "昭和30年代のベストセラー" として近年復刊された。
河盛は「一般に古典と呼ばれるものは、作者から独立して、作品だけで独り歩きをしているものである」としつつ、「現代文学の場合にあっては、純粋に作品ばかりを取り上げるよりは、作家との連関に於いてそれを理解すべきこと、個々の作品よりも、それを書いた作家が、いかに人間として、文学者として生きたかをその作品を通じて研究する方が興味もあり、得るところも多いのではあるまいか」と書いている。そうして河盛はまず夏目漱石と森鴎外を取り上げ、続いて自然主義文学とその三大家――島崎藤村、徳田秋声、正宗白鳥――について述べ、その他雑多な話を羅列する。
最後にまとめとして、河盛は次のように書いている。
いかに古典を読むべきかというよりも、いかにわれわれは正しく生きることを志すべきかということの方が先決問題になる。すぐれた文学、長い生命を持つ文学は、すべて正しく生きようとして苦闘した文学者の手になるものである。等しく正しく生きようとする作家と読者との魂の出会いが読者の真の悦びなのである。現代文学を正しく読む読み方も、この魂の出会いを見出す以外にはない。
すぐれた文学の書き手は正しく生きようとする人物でなければならないという、およそ現代で賛同者のいなさそうな主張である。非常に偏狭な文学観が露呈されているが、これも当時の時代精神というものだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
