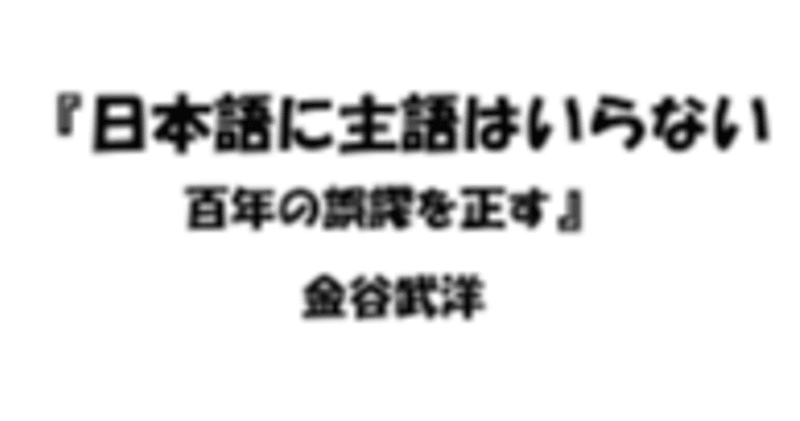
◆読書日記.《金谷武洋『日本語に主語はいらない 百年の誤謬を正す』》
※本稿は某SNSに2020年1月22日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
金谷武洋『日本語に主語はいらない 百年の誤謬を正す』読了。
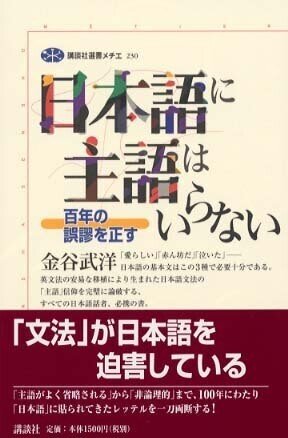
先日読んだ三上章『象は鼻が長い』で三上が展開していた「主語廃止論」を受け継ぎ、モントリオール大学にてカナダ人に日本語を教える言語学者の立場として、日本語教育に主語廃止論を導入すべきだと主張する新たなる日本語教育の主語廃止論。
現在の日本語教育が英文法を日本語に当てはめたものを基礎としているのは、明治政府下の時の文部省の意向によって大槻文彦の学説を元にしたためだった。
明治政府の文部大臣は森有礼である。この人は「日本の母国語を英語にしよう」と目論んでいた人物だ。明治以降の日本語文法教育には、彼の意志が或る程度反映されているのである。
本書で金谷氏が紹介しているが、その森有礼の三男の森有正は自分の著書で一冊丸々かけて日本語の非論理性や文法構造の未熟さについて論じたそうだ。
こういった「日本語が劣っているので、英語の文法に合わせよう」と考える「悪しき英語中心主義」を、著者は「英語セントリック」と呼んで批判している。
そういった英語文法を基礎にした「英語セントリック」的な日本語教育は、明治期から21世紀の現在に渡る優に100年以上も主流となってきた。
本書の副題「百年の誤謬を正す」というのは、明治政府が大本となる「英語文法に即した日本語文法理解」=「悪しき英語中心主義」を批判するということを意味しているのだ。
そのために著者は「日本語に人称代名詞という品詞はいらない」や「日本語に主語という概念はいらない」、「日本語の自/他動詞の誤解」等、日本語教育と真っ向から対立する日本語文法の新しい考え方を提示することでその誤りを指摘しているのである。
このように、現在の日本語教育の現場を真っ向から批判する本書を書こうと思った著者の動機はシンプルだ。
「外人向けの日本語教育方法として、現文法教育がからっきし役に立たない」という現場からの怒りである。
この「現在の日本語教育の教科書で外国人に日本語を教えると、いかにもガイジンさん英語といった感じのぎこちない日本語になってしまう」という問題は、これは金谷氏がモントリオール大学でカナダ人たちに日本語を教えている現場で、以前から憤っていたことだったのだという。
著者の主張によれば、どの日本語教科書を見ても、この「英文法に無理やり合わせた日本語文法教育」ばかりだったのだという。
本書を書いたのは、そういう日本語教育の現場からの切実な要請があったからなのだ。
そして著者が、外国人に日本語を教える際に最適な言語論だと初めて納得したのが三上章の『象は鼻が長い』であった。
三上章は世界的にも評価されている言語学者だったが、1971年に急逝されているのだそうだ。
その後、三上の亡くなった後の70年代に久野暲や柴谷方良等のチョムスキー学派が主語擁護論を展開し、三上章の主語廃止論を批判した。
本書の金谷の理論はこのチョムスキー学派への再反論でもある。
金谷の主張するチョムスキー学派への反論は、チョムスキー学派の理論は「教育現場でほぼ役に立たない」という事なのだそうだ。
チョムスキー学派はその理論が高度に専門化されてしまって、全く一般人が理解できないいわゆる「象牙の塔」化してしまっているという。権威主義化しているのである。
また、チョムスキー学派の普遍文法についても基本的には英語文法を中心にして他国語へアプローチする方法論がとられているがために「英文法に無理やり合わせた日本語文法」の考え方をそのまま肯定させてしまっている点にもあるのだという。
これらの英語文法へ偏った日本語文法理解を覆すために、著者は主語廃止論を展開する。
「主語廃止論」というのは、例えば「AはBである」という文章の「主語」とされている「Aは」という「主語にあたる言葉」を「失くそう」という意味の「廃止論」ではない。「われわれが"主語"だと思って使っている言葉は、所謂『主語』と呼ばれる機能とは別のものではないのか?」という疑問から、「主語―述語」という英語から流用した日本語文法の考え方そのものを廃止しようという「廃止論」なのである。
基本線は、三上文法を踏まえ、独自に日本語の文法を自立させる事にある。
三上文法や佐久間文法の弱点は「日本語の自/他動詞の誤解」を正しきれていない点にあるという。
それを補って新たに「外国人が"ちゃんとした日本語感覚を掴める"日本語文法」を展開するのが本書の内容となる。
余談となるが、本書の最後に著者がカナダ在住の視点からアメリカの「一国覇権主義」「No.1イズム」が、ある種「悪しき英語中心主義」の背景に潜んでいると指摘している。
ふいに立ち寄った言語学の世界だったが、この分野の世界でさえもアメリカ中心主義への批判に再会したというのは何か意味がありそうではある。
(再掲時注:本稿を書いた時期というのは、直前にチョムスキー『覇権か、生存か』と豊浦志朗『叛アメリカ史』を読んだ直後であった)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
