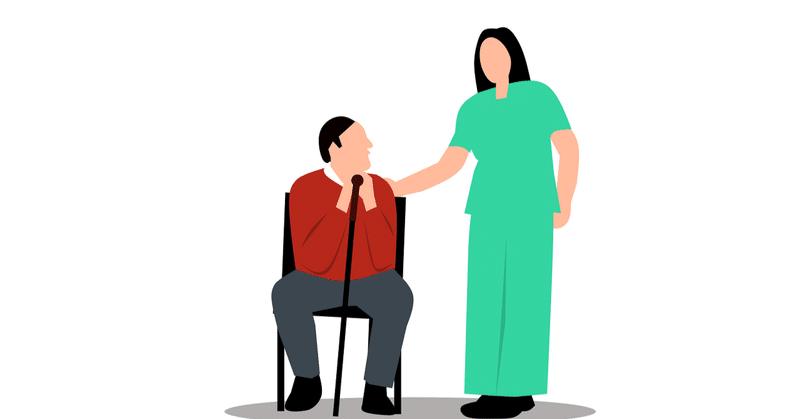
障害・福祉の処遇改善特定加算について【第一回】
今回は処遇改善特定加算について説明していきます
通常の処遇改善加算に上乗せで計上できる加算となります
処遇改善加算と同時に計算するので、より複雑になります
頑張って理解していきましょう!
制度の目的
特定加算の目的は
賃金改善をする配分を適正にすること
経験・技能のある人材の賃金をUPすること
ベテラン職員の賃金を日本の平均賃金以上にすること
にあります
賃金改善するのに、より細かなルールが求められるので、
導入の際のシミュレーションは綿密に行う必要があります
グルーピング

賃金改善をするためには、後で説明する配分ルールを守らなければなりません
配分ルールを適用するために、従業員を次のグループに分けます
A 経験・技能のある障害福祉人材
B 他の障害福祉人材
C その他の職種
Aは、原則、事業所での勤続年数10年以上の職員で、
福祉・介護職員のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
心理指導担当職員(公認心理師含む)
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
サービス提供責任者
の人が対象になります
Bは、経験・技能のある障害福祉人材に該当しない
福祉・介護職員、
心理 指導担当職員(公認心理師含む)、
サービス管理責任者、
児童発達支援管理責任者、
サービス提供責任者
とされています
Cは、AにもBにも該当しないその他の職員です
とはいうものの、グループ分けのルールは結構例外が認められていますので、
細かいルールを確認したい方は職員分類の変更特例を確認してみてください
配分ルール

ルール1
Aのうち1人以上は、
月額8万円以上の賃金改善
OR
改善後440万円以上となること ※1
ルール2
Aの賃金改善がBの賃金改善より大きいこと ※2
ルール3
Bの賃金改善がCの賃金改善の2倍以上であること ※2
ルール4
Cの改善後の賃金が440万円以上にならないこと
※1 ルール1は、以下の場合には満たさなくても問題ないとされています
小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
直ちに一人の賃金を引き上げることが難しい場合
規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
特定加算の要件
加算の要件は、ⅠとⅡで異なります
Ⅰの方がⅡより加算額が大きくなります
特定加算Ⅰ
配当等要件
処遇改善加算要件
職場環境要件
見える化要件
特定加算Ⅱ
処遇改善加算要件
職場環境要件
見える化要件
ⅠとⅡの違いは、配置等要件を満たしているかどうかです
それぞれの要件の具体的な内容は割愛します
処遇改善加算への影響
処遇改善加算の賃金改善額を判定するときに、全体の賃金改善から特定加算による改善を除く必要があります
実績報告のとき、特定加算分を控除した際に、試算どおりに行かなくなる場合もあるので十分注意しましょう
もしも、実績報告書を作成している段階で賃金改善が少なかった場合には、都道府県の担当者に相談し、速やかに不足の賃金改善分を支払うことで問題ないケースがあります
まとめ
今回は、要件など基本的な項目を説明しました
次回は、具体例を用いて説明します!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
