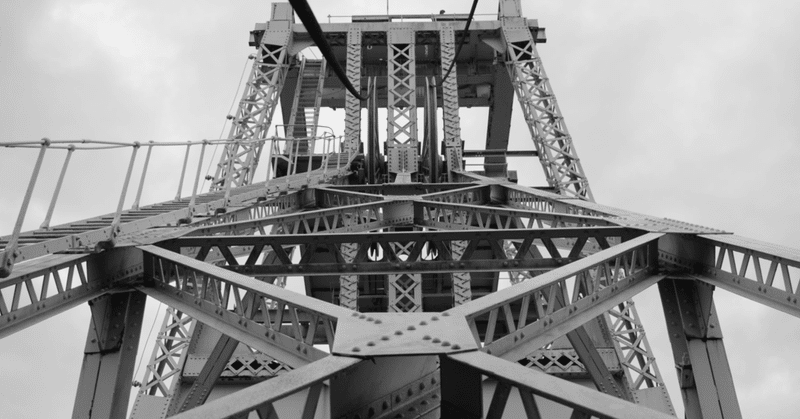
日本のエネルギー資源について考える〜第1次エネルギーの枯渇資源エネルギーについて知る〜
0.アイスブレイキング
みなさんはいかがお過ごしですか?
私は2023年の3月初旬を暖かい日と寒い日の区別をつけきれず、外出して今日失敗だったな、などと感じながら過ごしています。笑
今回もお時間をいただいてありがとうございます。
今回は、まず最近出会った素敵な人の話をさせてください。
というのも、私の周りには素敵な人がたくさんいます。みなさんにもぜひ紹介していきたいと考えていますので!ぜひ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回出会った人を仮にAさんと名付けさせてください。
Aさんと私との関係性は、同じバイト先であるということ。(Aさんは先輩)
私が本当に最近バイトに入ったという関係もあり、Aさんとは全く初めての対面でした。
某カフェが舞台なのですが、私は本当に初期の研修中。
研修を受けていると(タブレットでの学習中)Aさんは「楽しい?笑」と。
それに脳無しに「楽しいです」と答えると「絶対嘘だろ」と肩に力が入る私を和ませてくださり。
そのついでに「水飲まない?」と真摯な気遣い。
それにも私は、「大丈夫です!」と、人の気遣いもそっちのけな返答を…。
その後研修を進めていると、他の方が「Aさんから」とお水を持ってきてくださって。どれほど気の回る人なんだ、と私はすごく心を打たれました。
本当に素敵な人だ、と感じたので帰りに感謝を伝え、従業員間のチャットでも感謝を伝えると、「わざわざ連絡くれるなんて神すぎる。なんでも相談乗るから頼ってね。」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
返答まで素敵なAさんのような、そんな人への気遣いを身につけたいと感じる出会いでした。
と、そんな出会いもありつつ前回の内容から発展して今回は各第1次エネルギーについて日本の現状と共に、特徴を知り、考える材料にしていけたらなと考えています!
それでは今回もお付き合いください!
1.エネルギーについて(復習)
エネルギーについて
前回のおさらいとして、枯渇エネルギーについて紹介します。
まず、エネルギーには複数の種類がありました。
第1次エネルギー、第2次エネルギー、最終エネルギー消費の三つですね。
第1次はエネルギーの源となる自然のもの。
第2次はそれらを消費できる形に変えたもの。
そして、最終的にどれだけエネルギーを消費したのか。
これらのうち、第1次はさらに2つに分けることができました。
〇枯渇エネルギー
〇自然エネルギー
この2つの違いを以下の3つの特徴をもとに紹介しました。
①永続性
②普遍性
③クリーンさ
それでは、それぞれの構成資源を一つ一つ見ていきましょう!
2.枯渇資源(枯渇エネルギー)
枯渇エネルギーについて
さっそく、枯渇エネルギーの構成資源を見ていきましょう!
・石炭
・石油
・液化天然ガス(LNG)
・ウラン(原子力)
こう言ったものが主なものになります!
これらは、「化石燃料」と表現されることもあります。
それぞれ、なくなる年数まで予測されちゃってるんです。
石油 →50年
石炭 →134年
天然ガス→53年
現時点で見つかっている量から推測すると、こんな期間でなくなるそうな、。
だけど!なくなるのが怖い、というのではなく、なくなるまで使うとさらに環境被害が増進する方が怖いということ!
そんな側面を持った枯渇エネルギーについてそれぞれの輸入先などを見ていきましょう!
石炭
まずは、過去、日本が採炭で栄えたことも記憶にある「石炭」について✨
私の地元もかつては採炭で栄え、「炭坑節」たるものがありました。
月が〜出た出た〜月が〜出た〜♪
と。笑
そんな石炭ですが、驚くことが一つあります。
それは、、、
99.7%が輸入であるということ!!(2020年度)
なぜ石炭が国内産から外国産へ移行されていったのでしょうか。
資源エネルギー庁の作成した「2022年度エネルギー白書」によれば、
1960年代に石油へ転換したこと、1980年代以降に外国産の石炭が安価で輸入できるようになったこと、などがあるそうです。
2018年には100万トンを割った石炭(これがどれほどのものかは後ほどあげる表をご覧いただきたいです!)は2020年には75万トンにまで減少したそうです…。

この驚きが伝わるでしょうか…。
1965年ごろは5000万トンほども国内生産していた資源がわずか数十年の間に足元すら見えないほどに縮小していると。
しかし!それだけじゃないですよね。現在の輸入量というか、総供給量というか、これらが驚くほど増加しているのです!
それでは、輸入先についてはどうなっているのでしょうか。

輸入先はオーストラリアがほぼ大半を占めていること。
石炭は世界各地に埋蔵量が多く、先進国にも供給余力があるということ。また、量が多いために供給の安定性が高いということも一つの特徴です。
世界の埋蔵量はアメリカが1位(31.9%)であり、中国が2位(17.8%)。
ついでインド(12.2%)、ロシア(10.0%)、オーストラリア(8.9%)。
それに対して、生産量は中国が1位(54.4%)であり、世界の大半を生産しているということがまた一つ驚きですね。
ちなみに、輸出はインドネシアやオーストラリア、輸入は中国や日本が多いそうです。
最後に、分布としては古期造山帯に多いそうです。(古期造山帯を調べると、カレドニア山系、ヘルシニア山系などがあって、土地や写真を調べるとさらにワクワクが生まれるのでぜひ!)
石油
続いて石油です。
実は、石油、世界の第1次エネルギーの消費の32%を占めている最も重要なエネルギーでもあるそうですよ!
そんな石油ですが、埋蔵量の48%ほどが政情の不安定な中東に集まっているそうで…。
そんな石油は、もろに第4次中東戦争などの影響である石油危機を日本へ浴びせました。
しかし、価格の下落などに伴い、1980年代から増加傾向に向かったのです。

見ての通り、中東!中東!中東!ですね。笑
石油は中等様様のご様子です。
実に80%以上も中東という。。。
ちなみに原油自給率は1970年から2020年までいずれの年も0.5%未満とのこと。(驚くべし)
天然ガス(LNG)
LNGと聞いてアレルギー反応が出た多くの方!
自分もです笑
でも恐れることはない!導入プロセスを聞けばすんなり入ってくるはずです!
まず、日本は1969年以前、国内天然ガスのみを使用していました。そのため、第1次エネルギーに占める割合は1.1%に満たない状況。
しかし、転機となる1969年が訪れます。
アメリカ(アラスカ)からの輸入です。天然ガスが液化できた(LNG)ことでそのことが可能となりました。そして日本は輸入に成功したのです。
そして、着々と日本の供給量が増加していき、2014年には24.5%、2020年は23.8%と、日本では第3位を誇るエネルギー資源となりました!
どうですか?LNG(=液化天然ガス)がアレルゲンとなることが防げたのではないでしょうか。笑
ちなみに輸入率は97.9%であるそうな。

それにしても石炭と同様、オーストラリアへの依存率が驚くほどすごいですよね。笑
それもそうと、なぜ、天然ガスを液化してまでも輸入する必要があったのでしょうか。
それは、天然ガスが他の化石燃料よりもCO2の排出量が少ないこと、そして、原油よりも開発余地が大きいことなどが挙げられます。
埋蔵量はロシアや中東、アメリカなんかに多いそうです!
CO2の排出量削減について
そう、CO2の排出量については最終到着地点。
CO2の排出を減らすとはよく耳にしたものであると思います。
しかしそれらはどこからきているかご存知ですか?
気候変動について、温室効果ガスの安定など1990年ごろ敏感になりだす頃でした。
そして、1995年、いわゆるCOP1というものがドイツのベルリンで開催されることとなるのです。
COP1=第1回 国連気候変動枠組条約締約穀会議
ここで気候変動について話されることになり、のちの京都議定書につながります。COP3がその会議です。第3回であり、1997年に京都で開かれた会議となりました。
京都議定書は、地球温暖化を防止しよう!というもので、温室効果ガスの削減を目的とした協定です。初の国際協定だとか!
パリ協定が2016年に新たな枠組みとして誕生したりと。(詳しいことはまた後日!)
と、まぁ各国、環境問題への対策を取らざるを得なくなったということですね!
3.次回について
今回は、枯渇エネルギーについてそれぞれ説明しましたが、次回は自然エネルギーについて述べます!
その後、各国の状況から、日本にはどう言ったエネルギーが適しているのかを考えていきたいと思います!
延ばし延ばしでまとまった情報にできず💦
今後もお願いします🙆♂️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
