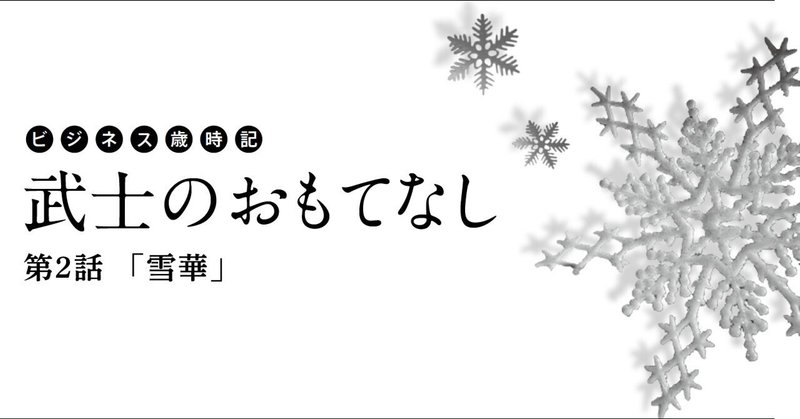
ビジネス歳時記 武士のおもてなし 第2話「雪華」
雪の殿さまが流行させた、江戸の雪華模様
「新しき年のはじめに豊の年 しるすとならし雪の降れるは」(葛井諸會)新年の始まりの1月は、大寒近く冬将軍が居座る寒い月。冒頭の短歌は、降り積もる新雪に、縁起のよい、その年の豊作を予測して詠んだもの。春には溶けて大地を潤す雪は、“豊年のしるし”とされていたのです。雪国では脅威となる雪の力も知られていましたが、日本人の自然観には「雪月花」といわれるように、雪を愛でる美学がありました。
下総国古河( 茨城県古河市)藩主の土井利位(※)も雪に魅了された一人。幕府の重職を務める一方で、雪の結晶を研究し続けて図鑑を出版しました。今回は、その観察図の雪華模様が、江戸っ子たちを魅了する流行をもたらしたという、“雪の殿さま”のお話です。
寛政元年(1789)、三河国(愛知県)の刈谷藩に生まれた土井利位は、25歳の時に本家の古河藩主の跡継ぎとして迎えられ、34歳で新藩主に。そして、利位の一番の理解者となる蘭学者の鷹見泉石(※)が家老となり、江戸幕府の重要な大坂城代、京都所司代などの役職を務める日々が始まりました。利位の雪の観察活動は20代から20年以上も続き、政治と研究活動との二足のわらじを履いていました。最初は黒い布や漆器に採取した雪を虫眼鏡で観察していましたが、オランダから当時は珍しい顕微鏡を購入し、本格的な研究活動を始めます。
利位に雪の観察を積極的に勧めたのは鷹見とも言われています。4歳年上の鷹見は、仕事上での有能な補佐を務めると同時に、私的な部分では時には兄のような気持ちで接していたようです。利位が研究の参考としたのは、オランダの教育者が天文学などをQ&A方式の図入りで書いた書籍『格致問答』(※)ですが、その訳出などでも鷹見が協力したことが推測されます。
江戸時代の気温は現在より5度くらい低かったといわれていますが、それでも雪国ではない大坂、京都では雪の観測には限りがありました。また、こうして顕微鏡下で確認できた雪の結晶の記録手段は、凍える手をさすりながらスケッチせざるを得ない状況でした。
天保3年( 1832)、利位44歳の年に、20年に及ぶ研究成果『雪華図説』(※)として刊行され、鷹見も推薦文を寄せました。そして、利位は手紙に自ら雪華と名付けた雪の結晶模様を描いたり、古河藩の調度品や道具類の意匠に使っています。なかでも「雪華文蒔絵印籠」は、江戸を代表する蒔絵師の原羊遊斎に制作を依頼し、長年苦労をともにしてきた鷹見に贈っています。また、当時財政難に陥っていた古河藩の資金調達などの交渉や贈答品としても活用されました。
この雪華模様は利位の役職から「大炊模様」(※)とも呼ばれ、浮世絵に描かれたり小袖の文様として大流行し、江戸時代のファッションにも一役買い、庶民の間に普及しました。江戸時代の小袖の文様は多彩でしたが、この雪華模様のように武士による学術・研究活動から生まれたものは、珍しいことだったといえるでしょう。
【監修】
企画・構成 和文化ラボ
東京のグラフィックデザインオフィス 株式会社オーバル
https://oval-design.co.jp/
※土井利位[1789-1848]
三河刈谷藩主土井利徳の4男に生まれ、本家の古河藩主土井利厚の養子となる。文政5年(1822)11代藩主となり大炊頭の任命を受ける。1835年、大坂城代となり、1837年飢饉をきっかけに起きた大塩平八郎の乱を治めたことから同年京都所司代、翌年、西の丸老中に就任。1844年に引退した。
※鷹見泉石 [1785-1858]
江戸後期の武士。蘭学者。下総古河藩士で家老として、藩主土井利位が大坂城代在任中に起きた大塩平八郎の乱での鎮圧を指揮。オランダ人や渡辺崋山らの蘭学者との交流もあり、藩主の『雪華図説』にも協力し、ペリー来航時には開国通商を提言した。
※『格致問答』
オランダのヨハネス・ボイス( 1 7 6 4 -1838)の著作で、教師1人と児童2人の問答形式による、大衆向けの物理学・天文学入門書。単純な雪の結晶図なども描かれている。
※『雪華図説』
天保3年(1832)に出版された木版刷りの小冊子。8年後には『続雪華図説』も出され、全部で183種類の雪の結晶図が収められている。現在、国立国会図書館デジタルコレクションに『雪華図説』が登録されており、閲覧できる。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2536975
※「大炊模様」
大炊とは、大炊寮ともいう。宮内省に属し、諸国から集めた米や雑穀を収納し、諸官庁に分配する役所。土井利位は大炊頭として、全体を束ねる役職にいた。
参考資料 『江戸大名の好奇心』(中江克己著 第三文明社)
『雪花譜 自然の造形美と不可思議の世界』(高橋喜平 他著 講談社カル チャーブックス)
『花鳥風月の日本史』(高橋千劔破著 黙出版)
『江戸時代の生活便利帖 現代語訳・民家日用廣益秘事大全』(内藤久男著 幻冬舎)
『日本ビジュアル生活史 江戸のきものと衣生活』(丸山伸彦著 小学館)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
