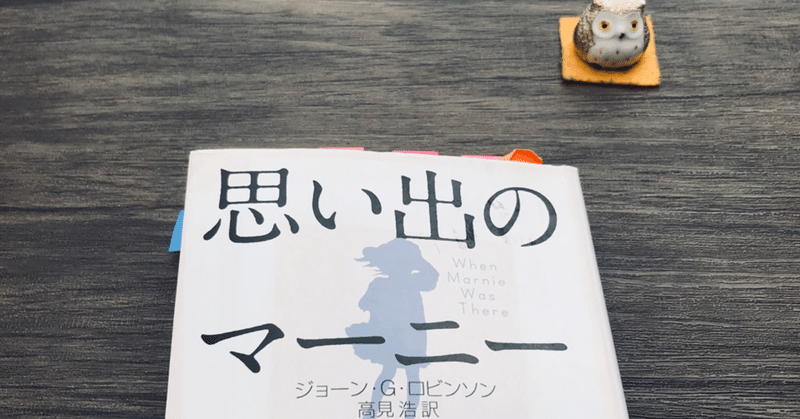
【読書】 思い出のマーニー ジョーン・G・ロビンソン
パーティーや映画、お茶に招かれたりすることが素晴らしいのは、あくまでも自分以外の連中ーはみな「内側」の人間、何か目に見えない魔法の輪の内側にいる人間なのだから。その点、アンナ自身は「外側」にいる人間だから、そういうことはすべて自分とは無関係なのだった。
イギリス児童文学の金字塔にして、ジブリでの映画化がされた「思い出のマーニー」。絶対に原作を先に読んでから、映画を見る!と変なこだわりがあるぼくは、上映の2014年から6年経った今。ようやく手に取り、読み終えました。6年も寝かせていたのに、1日と経たないうちに読み切ってしまい、すぐに二度目を読み始めしまうほど、ぼくにとって忘れられない1冊になったのです。
文章からは、ありありと、アンナやマーニーの顔が浮かんでくるし、会話からは二人の性格や表情までもが浮き上がってくるほど、印象的な作品です。感じたことや、思ったことを通して、『思い出のマーニー』の世界観を少しでも切り抜いてゆきたいと思います。
あらすじ
ロンドンの街でプレストン夫人と暮らしている、小学生のアンナはぜんそくをこじらせて学校を休んでいた。
アンナには友達がいなかった。楽しそうに友達を作る同級生たちは「内側の人間」、自分は彼らとはまったく関係のない「外側の人間」だと心を閉ざし、日々つまらなそうな顔をして過ごしていたのだ。頭は良かったが、「頑張ろうともしない」アンナを夫人は心配していた。
夏休みを6週間後に控えたある日、アンナは療養のため、イギリスの田舎(避暑地)リトル・オヴァーンのペグおばさんの下へ向かった。好きなだけ孤独を楽しめる環境に喜ぶアンナだったが、プレストン夫人のハガキや、避暑地あでの少ない人間関係はアンナにストレスを与え続けていた。
海岸へと足を運んだアンナは誰かに見られている気がして周囲を見渡すと、湿地の向こうも館に金髪の女の子を見つける。
数日後の夜、海岸でボートを見つけたアンナが興味本位で乗り込むと、ボートは独りでに動き出しアンナを湿地の館へと運んだ。金髪の少女に出会ったアンナは彼女と打ち解け合っていった。
金髪の少女は「マーニー」といった。村の子と遊んではいけないらしいマーニーは、アンナと秘密のお友達になる。二人は秘密を共有してゆく。
アンナは自分が孤児として夫人に引き取られたこと。夫人は支援金のために私を育てているのかもしれないということ。父も母もおばあちゃんも私を置いてけぼりにして死んでしまった事。マーニーは使用人に世話をしてもらっていること。使用人に意地悪をされ、お金持ちだけど、孤独な生活をしているのだということを話し合った。
永遠の友達となった二人に暗い影が差す。マーニーはいとこのエドワードと過ごすようになって二人の時間が少なくなった。エドワードに「怖いものから逃げてはいけない」と言われたマーニーは使用人の意地悪によって閉じ込められたことのある風車小屋にむかっていき、降りられなくなってしまった。きずかずに風車小屋へ向かったアンナは降りられなくなってしまったマーニーを助けようと奮闘するも、怖がって動けなくなったマーニーと眠りこけてしまう。
人の声で目を覚ますと、エドワードがマーニーを助けて降りて行ってしまう所だった。置いてけぼりにされたアンナはマーニーを憎み、友達をやめることにする。
数日後、海岸へ向かったアンナに館のマーニーが謝罪と別れを告げる。許してさよならをいったアンナはそれっきり、マーニーとは会えあくなってしまった。
マーニーが館から消えてから数日後、新たな湿地の館の子どもたちと友達になったアンナ。館のマーニーの部屋に住んでいる女の子は「マーニー」のことを知っていたのだ。
女の子はマーニーの日記をもっていた。数日後、50年前にマーニーと友達だったというおばさんが館へ現れ、マーニーとの話をしていくうちに、マーニーとはアンナのおばあさんだったことが判明する。
外側だったアンナは、マーニーとの不思議な出会いと友情によって「内側」をてに入れた。これは二人の少女の不思議な友情の物語である。
内側と外側(アンナの孤独)
パーティーや映画、お茶に招かれたりすることが素晴らしいのは、あくまでも自分以外の連中ーはみな「内側」の人間、何か目に見えない魔法の輪の内側にいる人間なのだから。その点、アンナ自身は「外側」にいる人間だから、そういうことはすべて自分とは無関係なのだった。
内側と外側の人間。小学生の女の子の目に映る人間模様は、きっと幼い頃、誰もが感じる思いなのではないでしょうか。大人になって内側と外側のラインがはっきりと分別できるようになっていく。世界は年を重ねるにつれて、どんどん広がってゆくけど、自身の世界は狭くなってゆくのではないかと感じます。
子ども時代で一番大切なこと。それは目の前の人が自分に関心や興味を持っているかではないでしょうか。ぼくじしんも、友達の中がいい人には順位があるのだと思っていて、遊ぶときなど、○○ちゃん(くん)と○○が仲が良くて、その次の人数合わせや取り巻きが何人か一緒にいる。といった思いが強く、失望したり、悲しんだりしました。それこそ、彼らにとって、ぼくは内側の人間なんだという風に。
自分はあなたが好きです、と、そんなにあからさまな調子でなくプレストン夫人んい伝えるには、どうしたらいいだろう。
気持ちを表現して、相手に伝えるのはなんて難しいんだろう。「すき」も「きらい」も素直に言えなかった(今も)ぼくにとってアンナに共感した文章です。
誰かの優しさを素直に受け取ることのできないもどかしさ。恥じらいや気遣いでいっぱいになってしまう。アンナにとってプレストン夫人は里親であって、ただでさえ、大人との関係は、子供にとって死活問題なのにこんな気苦労を続けている。そんな描写からアンナがいつも「つまらない顔」をしている背景も浮かんできます。
自分が馴染みやすい人間ではないことに気づいたらーきっと自分に対する興味を失ってしまうだろう。
内側の人間はとても幸せそうで、どこか完成された空気を漂わせていると感じます。とっても幸せそうな人たちのいる場所に入る外側の人間にとっては、自分は異物なのではないか。入り込む余地はないのでは?と不安に駆られるのも無理はないと思うのです。
もし、仲良くしてもらったとしても、それは対等な関係なのではない。優しさもそこでは残酷すぎる機能をもっている。こどもの世界では、これら人間関係がいい意味でも、悪い意味でも純粋に日々繰り返されてる。こどもの頃に駆られた不安や苦しみがいっぺんにわきあがってくるような場面です。だからこそ、かつてこどもだった人も、いまこどもを生きる人にとってもささる場面なのではないでしょうか。
よきものからいちばんかけ離れているのは自分だった。
いい子にはなれない。アンナの悲痛なさけびに胸を打たれました。ありのままの自分がどう受け取られるかを子供は無意識に学習していくのかもしれません。顔色を伺うのも、ちぐはぐな行動をとるのも単に「こどもだから」という理由ではないと思います。
ああ、もし、ときどき何の理由もなく、あるいはたいした理由もなく、好きなだけ自分が泣いても黙って見ていてくれる人がいたら、どんなにいいだろう。でも、この世には、そんなことをさせてはならないという暗黙の了解があるらしい。
自分をさらけ出せることは、きっと強い人のできることのように思います。たいていの人はなにかを我慢したり、隠している。弱みを見せるには理由が必要で、場所も限られている。
例えば職場で、「もうほんとうにつらいんです」といって、 仕事面での配慮だけでなく、その人の気持ちまで考えた上で対処してくれることはあるでしょうか。学校で言ったら「保健室」のような場所。ただ、そこにいることを肯定されるような場所はどこにあるんだろう?と探してみました。
家は本当に、ありのままを肯定される場所でしょうか。家族や友人や恋人はそうでしょうか。そんな場所本当にあるのかなと、小さい頃からの疑問が本書で再びよみがえったのです。そして、小さな頃の疑問にたいして、何一つ明確な答えを持っていない自分にやれやれと感じるのです。
自分は誰からも見張られていないし、だれにも心配をかけていないと思うと、心からほっとした……
「ほっておいてほしい」そう感じたことが、こどもの頃からありました。世の中には期待や同情、憐れみなども美しいものが、総出を降って人にのしかかってくくる。それがない無関心の世の中はもっと悲しく寒々しい。
そんな都合のいい世の中などあるわけがないと、心では理解しつつも、考えてしまうのです。夏目漱石の『草枕』で「ただの人が作った世の中が住みにくいからとて、超す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう」とというように、世の中は住みにくいんだと思うのです。
マーニーと友情
「あなた、本物の人間?」-「そうよあなたは?」二人は笑い声をあげ、お互いの体にさわって確かめ合った。
金髪の少女マーニーがどんどんアンナにとって現実になってゆく場面です。小さな女の子の無邪気な好奇心と会話。ここで、アンナが心を打ち解けていくのにホッとしました。本物の人間かどうかさわって確かめるなんて、大人には決してできないだろうなぁとちょっと愉快な気持ちで読めます。
秘密の友だちを持つこと。自分以外の誰も知らない友達を持つこと。それは本物の人間なのだけれど、でも、どこかしらちがうような
ぼくは「友達の多い人」を羨ましいと思うと同時に、それは嫌だなぁと思うのです。友達が多ければ、休日に予定が合わなかったり、忙しくて連絡したいときに連絡できないなんてことがなくなることはいいなぁと思います。
でもまさに「秘密の友達」はそう多く作れないのだと思います。それに、友達というモノが欲しいのではなく、お互いのことだけで十分完結するような友達……。カラオケやゲームセンター、お酒や余計なモノがなければ成り立たない人間関係を友達とは言いたくない。マーニーとアンナはそんな、余計なモノの一切を抜きにした、掛値のない友達になれたぼだと思います。なにより「秘密の友達」という言葉の響きにはなんともいえない魅力を感じるのです。
「お互いにぺちゃぺちゃしゃべったり、くだらないことをいろいろ訊いたり、言い争ったり、最後には喧嘩までして、せっかくの二人の仲をだめにしちゃうーそんなことにはならないようにしましょうよ。いまのふたりのままでいいじゃない」
なんて素敵な子なんだろう…。多くの読者が感じたように、ぼくも読めば読むほどマーニーのファンになってしまいました。「いまのふたりのままでいいじゃない」この名言がアンナの心を救ってくれるのです。アンナの求めた「ただ黙って見守ってくれる人」とはまさにマーニーのことだったんだと感じました。
その後、二人は「一晩に一つしあ約束しないって約束するの。」(アンナの提案で3っつになる)という会話をします。こんなに美しい友情の育み方のできる二人が羨ましくてなりません。この辺りから、本書のテーマは「友情」なのだろうなぁと漠然と思い始めますが、それだけでは終わらないのが、名作たる所以なのかもしれません…。
「心配しないで。あたし、必ずあなたに会うからーいつか、どこかで。正確な場所と時間は言えないけれど。でも、あたしのこと、探し続けてーおねがいー」
マーニーはいつもアンナが会いたくて会いたくて一心不乱に海岸を探しているとひょぃと現れるのです。そうして、アンナが他のことを考えこんで、意識の中からマーニーがいなくなると、現実のマーニーまで消えてしまう。マーニーは「思い出」の象徴のような子供なのです。
「気持ち」って残酷なんだなぁと思います。相手を悲しませないために、言葉ならいくらでもいいよがある。だから「言葉は優しい」んです。半面、気持ちには噓が通用しません。嫌だなぁと感じたり、興味や関心が薄れてゆくのは歯止めがかけられない。読みながら「マーニー」は思い出であるからこそ、儚く脆い存在なのだなぁとしみじみ感じました。
エドワードが与えられないものを、あたしはマーニーに与えることができる
マーニーのいとこ、エドワードの出現で、アンナとマーニーの時間が少なくなっていってしまいます。興味や関心の薄れ。アンナが最も恐れていたことが現実になってしまいます。ただ、アンナは「与えられる」という確信を持つことができるようになりました。
それはマーニーからの「優しさ」を与えられたきたからで、人は持っていないものは与えることふができないといったことを感じます。「与えあう」ことが友情なんだと思うと、アンナにとって悲しいシーンでも、どこか心の癒される思いになるのです。
思い出のマーニー(まとめ)
湿地の館へ新たな家族が入居者することで、アンナはマーニーと永遠の別れを迎えます。最後の100ページあまり、マーニーが現れないのは読んでいるぼくにとっても相当悲しい事でした。
読み終えて思ったことは「友情」とは「思い出」なんだということです。肉体や人間関係にはどうして終わりがあります。でも、「思い出」は思い出すことができる。そして、思い出しているその時、相手はまさしく思い出す人のなかで現在進行形で生きているのだと思うのです。
アンナとマーニーの謎には触れませんでした。二人の友情に終わりはないからです。もちろん、終わりがあるからこそ美しいという考え方もあります。しかし『思い出のマーニー』を読み終えたいま。終わりがないものは確かにあり、それはなによりも美しいのではないかと考えを改めさせられつつあるのです。
貴重な時間をいただきありがとうございます。コメントが何よりの励みになります。いただいた時間に恥じぬよう、文章を綴っていきたいと思います。
