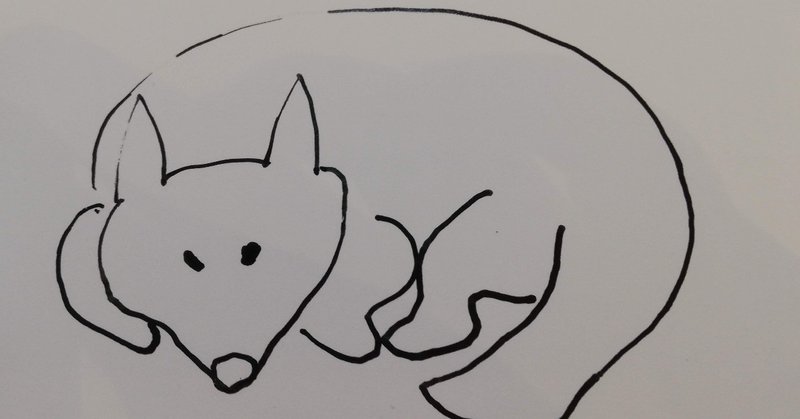
断片的なもののかわウル
かわいいウルフと出会い、ヴァージニア・ウルフという作家を知った。作り手の方々の一部が同じ大学で同時期に同じような意識や価値観や言葉を共有できていたときがあった好きな人達だったので、ひきこもってた私はなにかを直観し、迷わず注文した。およそ1世紀前の英国の女性作家のウルフさんと自分との接点が見つけられるのだろうかとドキドキしながら、この分厚くてかわいい本の中に入っていった。彼女が戦争の時代に生きて、時の空気を敏感に感じ取り作品に書き残しながら神経衰弱となってしまったこと、女性としての生きづらさをかかえていたことや男性のような権利や自由を望んでいたこと、彼女の『三ギニー』という著作にあるように女性の直接的・制度的差別が戦争と通底する暴力行為であることなど、現代の日本に生きる私にも共感と学びがあまりにも多かった。これをきっかけに関連する人文の本をたくさん学んでいるところだ。
〈かわいい〉というタイトルは、ウルフ自身のかわいさ、作品のかわいさ、小澤みゆきさんのかわいさ、漫画やイラストや装飾のかわいさ、作品解説で触れられる四つの魅力。それらももちろんそうだけど、他にもいろんなかわいさがある。寄稿者の大半がウルフ作品を初めて読んで文章を書いたそうで、オタクでギークなお兄さんやクールなデザイナー、ムーミン好きなソフトウェアエンジニア、SFをこよなく愛すブロックチェーン技術の研究者、ボリウッドが大好きな脳科学の研究者など、この企画がなければ接点のなかったような方々もウルフについて考えを巡らせ、物を書いているというのが衝撃的にかわいかった。また、カラー刷りの広告欄の絵面のかわいさがやばい。小澤さんがウルフが大好きで文芸が大好きなご自身と、コンピュータ・サイエンスやソフトウェア・エンジニアリングが大好きで大学と大学院で6年間学び研究したことが他に生きていない乖離状態を編み直されたのだと理解しているが、学問的なカテゴリにとどまらず、あらゆる遠くの人達をつなぐ地下茎のようなものになっているとわかって感動している。私もこのような意味のあるものをつくらねばと思った。ウルフの思いや表現に絡めて私が通ったSFC(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)について断片的に振り返りつつ、意識の流れについて考えてみる。2010年9月に学部に入ってから、アクシデントに見舞われたり休学ひきこもり期間などを断続的にやったりして2019年現在も籍を持っているが、かわいいウルフとの出会いやその前後に吸収した知見から当初の研究計画と変えて復学を目指し始めたので、それについても書いてみる。
女のくせに
お前女のくせに狂っててキモい。
女らしくなる方法がわかってないんだね。もっと服とか髪型とか化粧とか女らしくしたほうがいいぞ。
2011年春ごろの夜中、私は会ったこともないSFCの男子学生らにTwitterで絡まれ、Skype通話をかけられ言葉のパンチを食らったのだった。なぜ彼らは上からものを言ってくるのだろうか?と疑問であったが、謙虚に彼らの言葉と向き合い、いったん受け止めてみることにしたのだった────。
SFC政策コーカス
2010年秋にSFC環境情報学部に入学した最初の学期に「政策コーカス」というプロジェクトに参加した。政策コーカスは、総合政策学部の入学初学期のオリエンテーション授業である「総合政策学の創造」において、テーマに沿ってチームごとに政策を立案し模擬選挙を行う企画。かわいいウルフをつくった小澤みゆきさんも第一回政策コーカスの立候補者の大先輩。教授から受け身で授業をされるだけではなく、学生自らが問題発見問題解決をすべく先輩たちが始めた企画である。2010年秋学期のテーマは「SFCのカリキュラム」についてで、2014年に改定予定の新しいカリキュラムに意見が反映される可能性があるという実践的なもの。私は環境情報学部生なので「総合政策学の創造」は受講していなかったが、「環境情報学の創造」と「総合政策学の創造」がコラボレーションしていたため環境情報学部の学生も参加を促された。教育(数学教育)に問題意識を持ってSFCに入学したため、カリキュラム立案に携わることは良い経験となると考え、選挙に立候補する「リーダー」ではなくブレーンとしての参加を希望した。ところがそもそもリーダー候補の参加者がいなかったためリーダーに立候補した。9月生は4月生と比べ母数が少なく、チームのブレーンを集めるのはどのチームも苦戦した。私はとにかくSNSで参加者を呼びかけ、9月生の女子を3人、4月生の男子1人、商学部の男子1人、東京大学の男子1人をなんとか集めて模擬選挙に挑んだのだった。政策コーカスの会期中も、積極的にSNSを使った。政策コーカスには参加していない人も、「SFCカリキュラム」はSFCの学生や教職員皆に関わることであり、これまでの不満な点や良かった点などは卒業生にも意見を伺ったほうが良いこと、また他学部や他大学の意見も参考にしたいことから、ありとあらゆる人とオンライン、オフラインともコミュニケーションするためにも、SNSではすこし過激なことをいってみたり、ふざけたことも言いながら、パフォーマティヴに動きながら、距離を置いていそうな人も少しずつ政治に巻き込んでいった。また、図書館にある持ち出し禁止のSFCのカリキュラムの変遷に関する資料も調査した。どのような敬意で今までのSFCのカリキュラムが設計されてきたのか、カリキュラム委員の先生方にインタビューもして、狙いを理解していった。
ちなみに、政策コーカスの男性の先輩とグループワーク(グルワ)の授業について話していると、SFCのグルワの授業というのは、可愛い女の子がいるとすごくモチベーションが上がって頑張れるんだ、だからグルワというのは可愛い女の子がいることが一番重要なんだ、と力説していた。この方は一体何を言っているのだろうか、なぜこんな発言をできるのだろうかと疑問に思った。女性は所詮、男性が支配し決定しつくっていく仕事や社会のなかの装飾…?癒やし要素…?ウルフが生きていた時代と今と、たくさん変わったこともあるけど、何も変わっていないことがまだまだある。この世界にはまだ暴力的な構造がたくさんあるということを見えるようにしていかなくてはいけないな。
縛りと自由のジレンマ
1990年に始まったSFCのカリキュラムについて2010までに調べてわかったことは主に以下である。
①現代社会の複雑な問題に対して、細分化された専門領域の枠を超えて問題解決できる人材を育て排出する理念が置かれてきた
②SFCのカリキュラムはおよそ7年ごとに改変されてきた
③必修の縛りが厳しくなる代とゆるくなる代が交互にあった
④自由すぎると迷子になる学生が多いが、条件が多いとやりたいことをやりにくい人も増える
⑤一代前の01カリキュラムのように、ある程度分野を深める指標となるクラスター制やガイドラインを復活したほうが良いという意見
⑥SFCは1000人の秀才ではなく1人の天才を生み出す場所であるという教授の意見
⑦SFCでは設立当初リーダーという概念は不要とされたが、後にリーダーシップが学生の資質として求められるようになった
⑧現行07カリキュラムを決める際には必修に関して教授たちが決裂するほどのガチ討論バトルが繰り広げられ、総合政策学部の必修にはプログラミング言語と自然言語があるのに対し環境情報学部の必修にはプログラミング言語はあるが自然言語が外された
ゆるゆるに自由にすると大方の学生が迷子になり、必修や条件をきつくすると自由にやりたい学生が制限を受けてしまうというジレンマをいったりきたりしていた。一人の人間の中でもこういったことはある。自分を強制的に縛り付けてプッシュして何かを成し遂げることができるときもあれば、縛りすぎて窮屈になって制度疲労のようなものを感じて開放してみたり…。
ヴァージニア・ウルフの意識の流れのなかにも、そういった緩急の波のような旋律を感じる。そのいったりきたりぐるぐるしたりのジレンマをどう評価したりできるのか、人間も教育機関も作品も、その功罪や意味はすぐに端的に決めることはなかなかできず、後々時間が立ってからわかったり、時代とともに意味がかわったりするものであろうことを理解した。
自由にしすぎて自己責任論で放置して迷子の学生をたくさん出してしまうのは、大学としての責任を果たせていない、というかそもそも大学の意味がなくなってしまう。故に何かしら大学として意味のある制度にするには、入学時点の教育にもっと工夫をこらしたりセーフティネットの仕組みが設けられていたりすべきではないかと考えた。
自分自身を説明すること
私たちのチームが最終的に提案したカリキュラムの主軸は「(入学初学期に)自己分析WSをする」ということだった。カリキュラムがなるべく自由であることは、個人のやりたいことの実現可能性を高めて制限をしない良いこととする。しかし、何がしたいかわからず迷子の学生が増えてしまわないようにするためには、入学時に自己の内側と深く向き合い自分自身の不透明な部分や興味や問いを他者に説明できるようにすることが必要であると考えた。このために、他者と協同でワークショップ形式の作業を行うことが望ましいというのが私たちの提案であった。AO入試に本気で挑んで入学した人は入学前に自身のやりたいこととじっくり向き合って入学した時点で目標や目的が定まっていることがとても良いことだという意見が多かったので、一般入試の学生にもその期間を入学の最初の時点でやればいいという考えだ。また、多数の声が寄せられた「履修選抜でたくさんの授業で通過するのに受講権利を放棄する人がいることによる枠の無駄をなくす補欠の繰り上げをシステム化したい」という意見も、カリキュラム案に組み込んだ。これは2014年の改定を待たずに履修選抜のシステムに導入されていった。
選挙と民主主義
模擬選挙では最終的に3チームが立候補し、投開票日には私たちのチームのカリキュラムが投票数を多く得た。これには、SNSでずっと情報を発信し有権者と対話をしてパフォーマティヴに巻き込んでいたのが大きいと思われる。それから、モチベーションや本気度が最もよくわからず、人気が低そうに予想された泡沫候補に意外と票がたくさん入るというのは、実際の選挙でもよく起こる現象が再現されて学びがあった。
当時私は19歳で選挙権がなかった。政治のことは社会の授業やニュースや新聞で学んできたが、選挙という手段を採用している民主主義のコンセプトや政策コーカスの意図を当初掴めていなかった。民主主義の肝は選挙や多数決ではないこと、しかし現行の日本の制度では選挙の多数決によって選ばれた代表者が議会でルールやリソースの分配を話し合ってさらに多数決で決めるという方法が採用されているために、少数の意見も尊重するには憲法が大切なこと、選挙についての企てを知らないといけないとわかった。
模擬選挙を行う上でのルールや取り決めを判断する際に、担当の先生に個人メールで問い合わせたことをひどく叱られたのを覚えている。みんなにきかなくても勝手に他学部の学生とか他大学の学生を参加させたりしてしまったけど…。コミュニティ全体に関わる話題であるのにCcで共有しなかったこと、それからルールの判断について先生に判断を仰いだことがよくなかった。ルールは自分たち参加当事者みんなで話し合って確認し合って決めるべきことである。ルールを決めるためのルールもそう。当事者や主権者がある種のわがままを言い合ってみて意志を疎通して合意形成していくってことが民主主義だった。高校でもそういうことはよくやっていた。学生たちが学校内のルールやガイドをつくって自治していく。私も学校にいくつもの規則や規範をつくったり型を破ったりしてきた。
ウルフの生まれた時代には、女性には参政権がなかった。彼女の生まれる少し前からイギリスでは女性参政権の要求運動が行われていたが、第一次世界大戦末期の1918年にやっと30歳以上の戸主の女性に参政権が与えられ、1928年に男女平等(21歳以上)の普通選挙権が与えられることとなった。女性に男性と同じ基本的な権利である選挙権が保障されていないという抑圧的な状況。選挙権がないということはつまり今で言えば子供と同じ扱いである。男性が作ってきた社会構造の中で女性は未熟で保護すべき存在、自分の頭では物事を正しく判断することができない存在とみなしていたわけだ。この時代に権利獲得を目指し運動した人々がそれだけの恐怖の中で勇敢に闘って権利を勝ち取ったことか。
民主主義というやり方は歴史上未だにうまくいったことがないと言われている。古代ギリシャは奴隷に参政権を与えなかったことにより崩壊した。フランス革命の後の民主主義では女性に参政権や男性と同じ権利を与えず帝国主義的な性格を拡大させようとしたことで崩壊した。第二次世界大戦を防ぐことができず全ての世界の意味を失った反省を踏まえて、国連の世界人権宣言や各国の憲法において人が皆法のもとに平等であることや、個人の尊厳が最高価値であることが強調された。それでもこの社会には暴力が耐えず、個人の尊厳が日々どこかで蹂躙されている。全員が全員と直接的なロゴスによる対話ができないからこそ、選挙や議会制、官僚性による情報を捨象し共有しようとする制度がある。それらの制度も日々破壊され、不透明で暴力的な構造が拡大されてしまった。そんな状況でも人々は忙しなく目の前の仕事をこなし続けるという社会維持のための手段にこだわり、目的を逸しつつある。
ルールや前提を問うこと
ルールを話し合うことや当事者としてつくっていくことの重要性を肝に銘じ、その後の研究や仕事や生活でも前提を疑ったりルールや低いレイヤーのことから議論したりすることは心がけた。しかしルールを問うたり議論したりするというのは、常にいつでもできることじゃないのだと後々わかっていった。なぜなら、いちいちすべての世界の前提を疑うのはとてもエネルギーと時間と費用を要することでもあり、あまり疑問に思わないものは受け入れたり諦めたりしていないと時間が足りず、社会の時間に合わせて生活をまわしていくことが困難だからである。また、ルールを決めることを声の大きい人だけが無理やり推し進めて行けば秩序や倫理が崩れる可能性のある危険で暴力的なことでもあるから。なにか疑問に感じたときにそれを疑って投げかけたり議論したりしてみる、というスタイルでやっていく人は多いと思う。それにしても、できるときとできないときがある。
例えば数学の問題を解くとか、ものづくりをして問題を解決に挑む時には作業をしている手元のルールについて向き合って根本から疑ってみたり覆してみたりする。数学の問題は数式や計算機や定規やコンパスだけで解くのではなくて物と身体で物理的に解いてみたりした。建築設計というのが意図した形を建てるために図面に形状や寸法や手順を記したりコンピュータで計算して最適を求めたりするだけでなく、虫や鳥が自分より大きく複雑で合理的な巣を比較的単純な作業の繰り返しで作っていくのを、人間が紐を編んで服をつくるのと同じような感覚でつくれないか、そうして編み物のジャングルジム兼数学教育体験をつくってみたり。
手元や眼の前にあるルールについて夢中になって考えすぎていると、なんだか足元のルールを疑ったり、自分の両脇の当たり前を疑ったりするのはなかなか難しい。編み物の模型を編みながら歩いていたらコンビニの駐車場の車止めにつまずいて転んで模型が手に刺さってめっちゃ痛かった。そういうことっていろんなレイヤーで起こっているんだな。

ヴァージニア・ウルフは、女性が男性と同じ人権を持てていないことや男性中心的社会の差別や侮辱が暴力性や戦争につながる恐れを感じ、そうした社会制度や規範に対する自分の意見や表現を発信していた。彼女はペンで戦い続けた。第二次世界大戦は勃発し、世界のすべての意味は破壊されることとなってしまったが、彼女が書き残した作品や思想は残り、受け継がれ、再評価されたり翻訳されたりして、こうやって遠い時代の遠い国の人にも親しまれている。彼女は今も生きている。ペンは剣よりも強し…。

説教したがる男たち
私がTwitter上で政策コーカスのために大勢の人に絡んだり、また単に友達を増やしたいこともあり変な発言をたくさんしてたことについて、なんだこいつ気に食わないなと思う人がいたらしい。それが「女のくせに」と言ってきた男子学生である。出る杭を打たない、異端な人を歓迎するSFCときいていたが、そんな冷笑的な人もいるのだなと知った。
お前さー、虚勢張ってるんだろ、と言われたので、そうだよ虚勢張ってるよ、と答えてみた。
お、何今の、いいじゃん。お前意外と素直じゃん。
彼らは私を上から評価しているようだった。素直だからお前を認めてやろう、という謎の承認を頂いた(?)。自分をより積極的にアピールして見せることの何が悪いのだろう?多くの文化圏ではこれは批判されることではないのに…。
私は東京生まれHip Hop育ちで、都立国際高校での文化や中高6年ダンスをした体験から、日本の保守的な文化とは異なった、自分をポジティブにアピールして他者と関係を築いていくコミュニケーションスタイルには違和感を感じていなかった。
ところが大学に入るやいなや「もっと素直になりなさい」「もっと女子らしくしなさい」と男たちに説教されたのである。高校では男女比が2:8と女子が多く、権力を持っていた。満員電車の登下校以外は、女として男から抑圧を受けるということがあまりなかった。むしろ男子が抑圧されていてかわいそうだと思っていた。大学に入るといろいろな人と出会うのだな。彼らはどうやら女性にとって何がよいことなのか、女性よりもよく理解していると言いたいらしい…。
どうやらこれが〈マンスプレイニング〉なる仕草と言えそうなのだと知った。
(通常は女性に話しかけている時に)必要もないのに、横柄だったり、相手を見下していたりするようなそぶりでものごとを説明すること。とりわけ保護者ぶっていたり、男性優越主義的な態度を示していたりすると思われるような口ぶりの時に使う。
〈マンスプレイニング〉という言葉が広まるきっかけ、そして#MeToo運動の火付け役となった『説教したがる男たち』という本で著者レベッカ・ソルニットは、“説明しがたいものを受け入れること”と小見出しを添えヴァージニア・ウルフの言葉の纏う闇から、不確定であるということに向き合えることの重要性やその態度の希望について触れている。
「未来は暗い。思うにそれが未来にとっての最良の形なのだ」
このウルフの言葉からは、暗闇の中にいるような、暴力的な構造ついて声をあげたり行動をしていくことが、すぐにではなくとも後々に影響を及ぼす可能性があること。さらに、ものごとについて断定せず不確定である可能性を排除せずに、自らの主張の不確かさと向き合えることや自己批判の余地を持てることが、豊富な知識を堂々と主張する態度よりもとても大事なことなのだと説明している。まさにウルフの作品たちは亡くなった後の時代に力を発揮し、今の時代の私達にも力をくれている。痴漢やセクハラなど、性暴力に対して声をあげるのはとてもこわい。被害経験のない人からは想像もつかないだろう。女性の多くと男性の一部の人は経験しているけど、なかなか可視化されにくく、問題が改善されてこなかった。泣き寝入りしないことはかなりエネルギーと勇気がいる。きっと無駄じゃない。
堂々と自信を持って強い主張を打ち出していく男性ジェンダー的な態度が必ずしも正しいわけでもなければ、弱々しく謙虚に自信がなさそうにして主張する言葉が必ずしも間違っているわけじゃない。それなのに、こういったニュアンスにあまりにも簡単に、我々は日々惑わされているんだな。
『説教したがる男たち』では殺人犯の90%は男性というデータや、「男性らしさ」というジェンダーが孕む問題をにしている。ちなみに私は学部3年の頃、授業のある日の空きコマの時間に警察に呼び出されて事件の任意調査協力を要請されたことがある。警視庁が扱う振り込め詐欺グループの事件に関して、私の個人情報が犯人たちに悪用されていたと告げられた。中年の警部補とその相棒の若手の2人は私に容疑者たちの写真一覧のファイルがあるから、知り合いや心当たりのある者がいないか確認してほしいと言って見せてきた。ファイルの中の写真はほとんどが青背景の同じような写真、つまり警察が管理している運転免許証に使われている写真だった。100人以上は顔があった気がするが90%どころではなく95%くらいは男性だったと思う。もちろん心当たりなんてない。警部補たちは、慶應の卒業生がこのグループの幹部だからもしかしたら後輩である私も関わってる可能性があるかもと疑っていたらしい。いやそんなことするはずがないのだが被疑者になりかけたこととか恐らくその数日前から内偵されてたのかとか考えるとめちゃくちゃゾワッとする経験をした。その幹部らの写真もみたが、およそ40代くらいのいわゆる団塊ジュニア世代だった。慶應義塾大学を卒業して、その人はどうしてそんなことになったのだろうかと考えると辛くなった。自分の大学の人や卒業生が犯罪に関わるニュースは結構な頻度で見る…つらい。何が彼らをそうさせてしまったのだろう。
とにもかくにも当時、自分に説教したがる人の動機は何であるのか、よくきいてみることにした。
俺が正しく導いてあげるゼ
実は私が入学する半年前の4月に入学した「キチガイっぽいキャラ」の女の子Kがいたことが関係していた。私は入学したときからKの性格や仕草が根っこから常識を逸脱している感じで好きで、いつも好きだと言っていた。Kの言動を彼らが分析し、Kは勉強ばかりしてきて女性らしくする方法や恋愛などを知らないのだ、だからきっと男のように自己顕示的で周りと摩擦をおこしてしまうのだろう、俺達が正しく導いて幸せになれるようにしてあげなくちゃ。そんな、あくまでも善意の心で彼らはKに女子らしくする方法をいろいろと指南し、結果的にKはおしゃれの楽しさやおしとやかにする楽しさに生まれて初めて気づいたと言って彼らに感謝するようになったというエピソードが掘り起こされた。Kをプロデュースするプロジェクトの成功体験から、私のこともきっと同じパターンだろうと箍をくくって近づいてきたことがわかったのだった。ボーヴォワールの「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」を秒速5億センチメートルくらいで体験した気がした。
はっきり言って、なんでそんなレベルの低い話に私が巻き込まれるのかと内心思ってしまった。私はおしゃれに興味が無いわけじゃない。子供の頃から街に繰り出してファッションやカルチャーに親しんでいたし、ダンス部のステージではメイクも髪型もバチバチにやってた。大学っておしゃれ楽しみに来る場所じゃないでしょう…。SFC入学前に将来を考えるために見学しに行った海外の大学街ではパーカーにデニムパンツにビーサンの女の子がぞろぞろいたぞ…。なんのために大学きてるんだこの人達?意味不明だった。東京にいる私は恵まれてたからそれができたのだろうか、全国の多くの人々は、大学生にならないと広い文化に触れることができないためにこんなレベルの低いことを言ってくるのだろうか…?危うく地方出身者を差別する人になりそうなほどの衝撃や疑問があったが、差別をするのはよくないから、ちゃんと向き合おうと思った。
人を短絡的にばかにするのは良くないと思ってた私は、もしかしたらこの人達が言うことを受け入れてみることでなにか違った見え方が得られるのかも?と、自分の価値観を一度疑ってみた。私は真面目すぎるのでもっとふざけたり冗談をいったりしたほうが良いのかもしれない、アホっぽいけど受け入れてみるのもいいかと思い、2011年春学期に約1ヶ月間「Going女子女子キャンペーン」なるプロジェクトをやった。具体的にはパンプスを履いたり、おしとやかな言葉遣いをしたり、思いつくかぎり女子っぽいものを摂取したり。すぐにバカバカしくなって飽きた。パンプスなんて今や強制ヤメロという#KuToo運動も起こってるくらいだ。本当にバカバカしい。
なんで女というだけで舐められてこんな目に合わないといかんの?男は羨ましいなあと思うようになった。女性があびる抑圧を回避できるその既得権が羨ましくなった。かわいいウルフの冒頭に言及されるおかあさんといっしょの歌の歌詞
クジラになりたいラッコ
ラッコになりたいコアラ
コアラになりたいライオン
ライオンになりたい女の子
女の子になりたい男の子
いやほんとこれ。むろんこれ。なりたい。なりたい〜〜〜〜。
説教したがるパオたち
他者から説教されたりもっと不真面目になれよと言われ、今度は私が誰かに説教的になったりいじりだしたりするようになっていった。後輩とか男性とかに。なんだこれは。なんだかわからないけど、社会生活の中で嫌なことや理不尽を感じたりしながら、これは我慢すべきことなのか、これくらいはしょうがないことなのか、いろいろと考えながら、自分の中の価値観や概念のモデルがゆらゆら揺れながら再構築を繰り返していった。繰り返しながら、外から来た圧を同じ方向に打ち替えすのではなく、別の方向にはじき出したりしていた。説教の再生産…?自分が女性だから抑圧を受けているのなら男性もそれなりに要求に応じろよという気持ちが湧いてしまうのだ。だから男のくせにとか〇〇のくせにとか、抑圧の再生産を自分はしてしまっていた。けど、くるもの拒まずすぎると来るものが来すぎて窒息して死にそうになるし、人権のチューニングは本当にむずい。
他者を見下す気持ちとの葛藤
女子らしくなることを指南されて成功体験を得たK自身もまた、女子らしくしない私のことを攻撃し始めた。なんだこれは。プロデュースしたい男子に、バカバカしいので女子らしくするのを辞める旨と、Kのこと大好きだと言葉ではいいつつ心の底でどこか下にみてる自分がいるグロさに関する葛藤を伝えた。
同級生の人をどこか心の中で見下してしまう葛藤が子供の頃からあって、それを初めて同世代と共有することができたのは高校を卒業する時の同級生たちとだった。先生に反抗したりするのは普通だったが、気を抜くと同級生を自分より下等な存在と思ってしまいそうな自分をなんとか抑制させる働きが常に心の中にあった。人を自分の価値観で見下して尊重しないのは下品なことだと思っているのに、自分の興味のある幅広い話をシェアできる人が周りにあまりいない中学までの環境の苛立ち。苛立ったとしても馬鹿にしてたらよくないという気持ちとの葛藤。その気持ちに関しても、男子学生は褒めてきた。それからはしばらく、その男子とも悩みや知識を深く共有できる仲の友人になっていきその周りの友達ともつながっていけてよかった。〈女子力〉という呪縛はその後も私につきまとった。
強く見えるものに抗うこと
大学生活では、本当はサークルをやりたかったが学業との両立が難しく入るのを諦めてしまった。それでも何かしらの研究会以外の縦横のつながりを持ったほうが良いぞといろいろな人に言われ、先輩たちが研究の実践として茨城県の港町で地域活性化の研究プロジェクトを兼ねたアートイベントを行うSFCの学生の有志団体に入った。初回から3度目の開催を2011年の夏に控えていたが、3月11日に東日本大震災が起きてしまいイベントの開催地域も大きな被災を受けてしまった。それでも、それだからこそアートで地域の傷や疲弊を労り復興を盛り上げるためにイベントの企画を準備していった。そこで、イベント創始者の博士課程の男性と揉めてしまった。小さな頃から母に「弱い者いじめはだめ。強い者と戦いなさい」と言われその価値観が刷り込まれていた私は、上の人に反抗する精神がインストールされていた。保育園と小学校では女子をいじめる男子をボコボコにしたりしていた。暴力は良くないと学んだ後も、中学でも間違った言動をすると思う先生には反抗して闘っていた。そして大学でもやってしまった。震災復興のためにイベントを真剣にやりたい地元の方々と触れ合う中で、不真面目にやってるように見える博士課程の人が許せなくなった。そして口論をしたのだが、結局話し合って合意形成し治まってから思ったのは「最近の若者は〜って言って年下の者が未熟だと決めつける人もいるけど、自分は年上や大人に対する期待がでかい。自分より上の存在だから自分より多くの要求に対する責任を負って当然だと考える癖が強い」ということだった。経験は多いだろうけどこれは仕事でもないし同じ人間同士だしそこまで要求しても仕方ないし、できる範囲で協力してできることをやってこうと思うようになっていった。年上をバカだなと思う気持ちとか老害だのと言う気持ちって若者なら持つのが常みたいなところあるけど、なんか自分は、バカだなと言う気持ちを持った瞬間に自分も同じ穴の狢になるという感覚が強い気がする。既存の価値観を超えて上からマウンティングするとか拳を上げて対抗しようとするみたいな気持ちがあまりわかなくなってしまった。マウンティングというのがもうそもそもある種男性ジェンダー的だ。みんなそれぞれの指向性や知性というものがあるし…はぁ…つらいね…という平成の時代だった。でもこれじゃいけないのかもしれない。なんか、とにかくほぐして対話できるきっかけをいろんなところでつくりたいんじゃ…。
現代社会は、マイノリティに配慮しましょう、政治的に正しくない言葉は慎みましょうというポリティカルにコレクトでリベラルな規範が広まれば広まるほどバックラッシュ(反動)が起こってしまう。世界では極右的な政党が台頭してしまっている。ウルフの時代にもその後にも、資本主義が加速し自身の生存の危機に必死な人々が増える中でフェミニズムやマイノリティの人権運動が強まると反動から暴力的な社会へとさらに突き進む構造が繰り返されている。
ヴァージニア・ウルフはレズビアンであった。昨今はジェンダーやセクシャリティに関しての議論も混沌とする。「LGBTは生産性がない(から異性愛者と同等の権利を認めない)」と主張する杉田水脈議員はなぜそんなことを言ったのだろうか。同性愛や両性愛、トランスジェンダーの人たちはかつては病気や障害とされ、正され治療されるべきとまでされていた。その偏見がいかに人々を抑圧していたのか、そのような差別はやめようという意識がやっと最近は広まってきたところ。ところがその流れへの反動も起こる。。
日々忙しなく仕事に追われる中で、強そうに見える人が実は心の中でいつも泣いているかもしれないとか、過去に抑圧を受けて周りから大事にされない状況に曝されまくってきた過去があるのかもしれないとか、そういったことを対話する時間があまりにも少なくなって、その場その場で強者・弱者のジャッジがされたり責任が追求されている。そこからまた新たな抑圧は再生産される。障害や性別や病気や人種、年齢など、カテゴリーのラベルのある「見えやすい困難」と「見えにくい困難」の対立をどうやって解消できるか、ずっと考えている。
ポライトネス理論と認知科学
2010年秋に「認知科学ワークショップ」という授業で「ポライトネス理論」という言語学や認知言語学の概念を知った。人間のコミュニケーションには、「円滑な人間関係を確立・維持」するための尊重的な言動がポジティブ(外向き、他者への介入的)なものと、ネガティブ(内向き、自己制御的)なものがあり、文化圏によってどちらをより重視するかも変わってくるし日本文化はどちらかと言えばネガティブが多いとか日本語はこの二項では説明しきれないとか、とそういった内容の研究についての講義をとった。ある文化圏では尊重を表すためにとる態度が、他の文化圏では失礼な言動になったりする。何を意図しての行動なのかは深くコミュニケーションして確認しなければわからなかったりする。女のくせに虚勢張るなと言ってきた男子たちは、ポジティブポライトネスな言動を叩きたくなってしまうお年頃なのだな、と理解することができたので良かったが、その授業の受講態度があまりにも悪かった私は、担当の先生から呼び出されてしまった。
教授の部屋に入ると、ピリリとした空気の中、叱られ、問いかけられた。
あんた何がしたいのよ!馬鹿にすんのもいいかげんにしなさいよ!何したくて大学に入ったのよ?と問われたので、教育について考えたい、数学の新しい教育方法を考えたいですと答えた。
あらそうなの、じゃあうちの研究会に来たら良いじゃない。
ものすごく意外だった。授業態度が悪すぎて頭に来てるだろう学生に対しそんなことを言ってくれる器の大きな方がいるのかと驚いた。次の学期にはその認知科学の研究会に入った。
人が学ぶということ、すなわち外界を認知し学習するとはどういうことなのかを研究する研究会だった。学ぶことというのはある種偏見のような情報の変数を蓄積していくことでもある。偏った情報によって構築された概念モデルは、そのモデルによる限界を迎えると再構築される、一人の人間の頭の中でも、学問のような集合知的な総体でも、そのような仕組みの繰り返しによって知識が構築されていくということを理解した。
ギークとホモ・ソーシャル
1つ目の研究会から、ものづくりの研究会に移った。ギークで博識で柔軟でいい意味でクレイジーな先輩が多く、かっこよかった。ものづくりは手や体を動かして自分も学習しながら問題を解決していくプロセスでものすごく楽しかった。外部から訪問する人、美術系出身の女性の方、女子学生も他に2人いて、エンジニアリングとは違ったものづくりやデザインの価値観が共有されていて素敵だった。しかし、ギークな男性を中心としたホモ・ソーシャルなコミュニティ性があった。研究会メンバーで食事をするときには女子力とはなにかという議論がなされ「殺伐を和らげる力」という発言がされていた。私も女子力とはなんだろうと考えた。母には「マルチタスク能力」と言われたが、謎だった。女性はなぜマルチタスクが求められて当然なんだろう、男性はシングルタスクだけ集中してれば良いといった空気はなんなのだろう…。考慮すべきことが少なくて羨ましい、というかむしろ無性になりたい。男性は身体をはらむ可能性とか考えもしない。自分の身体だけで40代くらいまで身勝手にキャリアと自分のことだけ集中して生きれる。なんて自由なんだろうか…。
ひどいときには女性を品定めするような発言を公然とする男性の先輩もいて、うんざりした。研究能力も柔軟な発想ができることも尊敬して慕っている先輩たちだったが、性差別やセクハラな発言をするのをどうしたら良いのか困った。それをニコニコ受け流せない女子は排除されかねない空気があった。男たちが殺伐としすぎないように立ち回りをしていれば成長したねとか言われた。そこで私は、研究会に女性をたくさん勧誘する取り組みを行った。企みは功を奏し、女性は徐々に増えて空気が変わっていった…。
学生に女子が増えても、デザイン系、建築系、技術系の研究室の教員の男性率の高さはその後も異常な高さを維持し続けている(分野にかかわらず教員の男性率の高さは高くて異常な国だが)。ギーク、ハッカーたちはものつくってナンボ、技術で新しい価値つくってナンボといったゴリゴリした思想を根底に持ちながら、市場や競争的な価値観にどんどん加速的に飲み込まれてしまう嫌いがある。そうした中にあるバーチャルな不気味さからの民主化を目指すためにも、Fablabを広めるための研究室に入ったはずだった。Fablabはものづくりとラボの民主化によって物理的な連帯のネットワークを広げる運動がアメリカに始まり、所属研究室ではそれの実践に取り組んでいた。大学のラボの中にある先端技術を、そこだけにとどめてはいけないということで貧困のあるボストンのダウンタウンの地域に設置され民主主義を目指そうとしたのがFablab第一号だった。日本に運び込まれ、その文脈はいつしか「日本にはクリティカルな問題があまりないし、パーソナルなものをつくる自己実現とか、大企業がやってたようなビジネスをスタートアップでやりやすくなったとかの文脈しかなかったね」となってしまった…。日本の中にはクリティカルな問題は山のようにあるはずなのになぜか流されてしまった。

自分ひとりの部屋
研究会では、新規生は春に3Dプリンタやレーザーカッターなどデジタルファブリケーション技術のトレーニングコースを一学期間やる慣例があった。私は2012年春に他の受講生と協力したり先輩にわからないことを教えてもらったりしながら取り組んだ。一学期のトレーニングを終えての最終制作物には、自分が本当に欲しいものをつくろうという指針があった。その頃の私が一番欲しかったもの、それはまさに「自分ひとりの部屋」あるいは「自分の家」だった。
ウルフは、女性が小説を書こうと思うなら、お金と自分一人の部屋を持たねばならないと言う。小説に限らず創作的活動全般においてそうだろう。家にいても常に誰かの世話をさせられる女性ジェンダーの窮屈さ。他者との交信を一日のひとときでも遮断できるような個人の空間を持つのは、創作のためにも、また哲学的な時間を有し他者や外界を理解するためにも、人間の基本的人権としても重要である。
『かわいいウルフ』p.78-81、戸田恵一氏の『灯台と踊ろう、そしてあなたは灯台と踊る』内のコラムにて、ウルフの『灯台へ』とトーベ・ヤンソンの『ムーミンパパ海へいく』、また作者同士が比較されていて面白かった。作中のラムジー婦人やムーミンママが家の外への脱出を試みることや、ウルフとトーベが同じく自分ひとりの部屋としての書斎やアトリエを持つが、そこに友人を度々招き入れるなどの社交性や公共性を持っていたことが類似点に挙げられている。人間は人間を好きではないにもかかわらず公共性や社会をもつのか、あるいは人間が好きだからこそ自閉的な時間や空間を欲するのか。どちらもあり得るとして、その矛盾を包括できるようにする仕組みを、制度または設計により企てることの重要性を、ものづくりや環境デザインの実践を通して学んでいった。
ひとりの部屋を欲するようになったのは、その直前まで「かもめハウス」という大学の近くのたまり場でルームシェアをして楽しく暮らしていたが男子の後輩たちをたくさん入れたことで居づらくなって退出し、遠い実家と更に遠い祖母の家とSFCを行き来する生活からの脱出要請が自己の内側から湧いてたからだと思う。冷静に考えれば限界超えていたのだと思うが、介護疲れで余裕がない家族とコミュニケーションが破綻しており、相談や検討が十分にできないまま何をどう優先すべきかわからないまま根性で大学生活をやっていた。
実家でも満足な自分の部屋を持ったことがなかったこと、祖母の介護をしながらの通学があまりにもキツかったことで、研究室の中や隣くらいの位置に家が欲しかったこと、研究室が広く他の研究会の人も出入りするオープンな場での作業の集中力が上がらないことから、ひとりでひきこもれる「メディテーションルーム」のようなものがほしいと切に望むようになった。そんな時に、坂口恭平がモバイルハウスをつくろうと促す動画を観た。早口でこの人大丈夫かなと心配になる感じもあったが、人々は消費社会や製造業者に振り回されていないか、身の丈の生活で良いのではないか、現状に文句があるなら自分で国をくろう、家をDIYしよう、と言っていた。
2012年夏、自分ひとりの部屋もとい小屋をつくった。
井上涼のYADOKARIから名前をとったYADOKARIハウスという名前にした。まじであたまおかしくなってしまったね、と言われた。デジタルファブリケーションによるものづくりという課題を完全に無視したものをつくったから。けど、本当に正直に欲しいものが家や部屋で、その時持っている技術や時間や素材を組み合わせてつくれる限界がその小屋だった。秋に研究室を破門された時には、その小屋を「マイ研究室だ」と言って作業をしてた。研究室に戻れたが、祖母の介護の疲労、そして死が辛くて、その当たりからかなり鬱だった。その後家族も何度も入院して、また同い年の親族も亡くなり、自分自身も事故にあって2度救急搬送されたり医療ミスされたりいろんなことがあった。家族やいろんな人のケアをとにかくやっていた。で、とにかく女性生きづらさやべえなというのと、ジェンダー関係なく同世代死にたみに包まれた人多いなという感じだった。
〜〜〜断片的なpao記前半終わり。また今度。つづく〜〜〜
うつになって見えた下駄
鬱には度々なっているので、ウルフが神経衰弱という状態になってしまったことに関しては自分ごとのようによくわかる。「なんかしんどいよね〜。でもなんとかやっていきましょう」という社会生活を送りながらの抑うつのような状態を超えて鬱2.0になると、本当に身体が動かなくなる。選択肢の自由があるのにもかかわらず行動を変えずに文句を言ったりしている人を疑問に思っていたときがあったが、人間に自由意志がある保障など考えてみればなくて、意志とはある種の信仰なのだということもわかってきた。
自由意志で自分の身体をコントロールすることの当たり前さが、当たり前でなくなる。そうすると、自分以外のものをコントロールしたり確実性を担保するのは難しいが自分をコントロールしていけば世の中いろんなやり方で生きていけるだろう、という感覚も怪しくなっていく。現実の確からしさが薄くなっていき、何を信じて今まで生きてきたのかという素朴なことがどんどんわからなくなり、20年近くかけて認知と学習をして脳内に蓄積してきた概念モデルや確実性に関する変数のネットワーク構造がぼろぼろと崩れていく音がした。人間が世界を認識したり理解したり分析したり行動をしたりするには、身体に関する変数がものすごく大きいのだと改めて気づく。もともと軽度難読症(ディスレクシア)があって文字を読んで処理することに難があるが、まったく本も読めなくなりあらゆる刺激が無理になって、この自分の状態をどう問題解決すべきかという情報を入手することも難しくなった。人間が一人では生きていけないことも痛いほど理解した。
何もかもすべて自分の過去は辛いことしかなかったかのような気分になる。努力してもまたアクシデントにあったり他者に振り回されたら全て無意味になるのか。計画し工夫しても明日がある保障などどこにもないことに気づけば、なにもかも虚しくなってしまう。それでも、逆に確かに過去に楽しさを感じて生きていたという事実があったと思い出せると、おもしろいパラダイムシフトが起こっていった。今までになにかを信じて努力をすることができていたのは、自分のいた環境に一定水準以上の秩序があったからで、信じられる大人と出会えたり、感動できるものごとに触れることができたからだ。つまり、私はかなり恵まれている。虐待サバイバーであり中学でも高校でも大学でもつらい思いをして不可抗力を感じながら這い上がって努力をして高校受験に成功したり大学受験に成功したりコンペや学会で賞をとったりした、と思っていたことも、社会秩序や環境、運の要素がかなりあった。
もし東京に生まれてなかったら…。もし文化資本の水準の違う家庭に生まれていたら…。もし日本以外の国に生まれてたら…。自分の努力は自分という主体だけによってできたのではないね。
女は楽でいいね……????
大学進学以降、東京出身の女というだけで、人生イージーモードで良いねというルサンチマンの視線を度々感じた。直接言われたこともあった。ということは、男性、とくに地方出身の方の多くはまた別のなにかからかなりの抑圧を受けていたのだろう。立身出世せよ自立せよという要求があるのだろうか。だとしてもその抑圧のはけ口を女に向けるのはどうなのだろう…?抑圧を向けてきたものは既存の社会やそれを形成してきた男性社会ではないのだろうか。上の世代もまた抑圧を受けながらもなんとか生き残るために必死だったのだとすれば、抑圧を再生産しない人、つまりケアをする人がもっと評価されたり、他者にあまり干渉せずひっそりとひきこもって暮らしたりしている人が安全に尊重されて暮らせるようにしたほうが良いのではないのかな…。今の社会は市場の自由競争の原理が生活のあらゆるところに侵略し、人々は自分の市場価値を高めなくては生き残れないかのような価値観を内面化しがちになって息苦しくなっている。憲法に保障される個人の尊厳や基本的人権を意識しないと忘れそうになるほどだ。どんなジェンダーも楽じゃないかもしれないけど、少なくとも一般的に女のほうが楽ということがあるわけはない。日本の2018年のジェンダーギャップ指数は149カ国中110位である。どれだけ女性は生きづらいことか。どれだけ下駄を履かされている人が下駄を履かされていることに無自覚であることか。なんで100年経ってもまだウルフの言葉や考えを頼りにしなければいけないのだ。楽なわけあるか。楽な世の中にするぞコラ。
意識の流れと同一性をめぐる抑圧
ウルフの「意識の流れ」と呼ばれる表現の仕方を知って、意識や表現が常に定速であったり留まったりしておらず変則的であったり開いたり閉じたりする私のような人間が他にもいたのだな、私もこれでいいのだなとわかってとても安心した。一貫性を保つのでもなく、誰かにのりうつったり、冷静になってたかと思えばエモくなったり焦ったり。誰か違う人になりたいなと思ってその人の視点に入ることを妄想してみたり。
大学時代、頭が柔らかくて優秀で面白い人にたくさん出会った。けれども一喜一憂する不安定さを嫌う人が周りに多かった。安定したい、安定した人と付き合いたい、不安定をやめたい、メンヘラが嫌、自分を好きになって周りの言動に影響されずにいたい、周りに影響されるのは自分の軸がないからだ、こんな願望や価値観をもつことが当たり前のように私の観測範囲には充満していた。
かく言う私も不安定な人で、入学当初から泣きながら学校に通っていた。つらみをシェアできる友人を徐々に増やしていった。その友人の一部はかわいいウルフのつくり手の人たちでもある。
あるときとても優秀で博識でいつもいろいろな視座を与えてくれる友人が、不安定をやめたいな、と言っていた。そこで、不安定を受け入れれば安定するのではないかな、不安定をやめたいやめたいと思えば思うほど不安定になる気がした、と言ってみた。よほどのことじゃないと彼女を唸らせることはなかったのだけど、その時はなるほどと言ってくれたのを覚えている。
かわいいウルフの特集②『オルランド・ア・ラ・モード』では、ウルフの小説『オルランド』が後の人々の創造活動にあらゆる形で刺激を与え、それぞれのつくり手に解釈され、作品として再生産され映画や舞台に息づいてきたのがわかる。時代を超えジェンダーを超え違う自分として生きる妄想って、いつの人もするのかな。平成の時代にはコスプレによって違う自分になりたい人々、SNSやネットの仮想世界のアバターで違うペルソナを持ちたい人々、ハロウィンの渋谷で仮想したい人々、いろんな人が日常とは違う自分になりたがっているのをみてきた。
近代以降の社会は人が変わることに対して不寛容になった。国家や自治体によって籍を管理されたり、警察に免許証や指紋による個人を把握されたり、所属組織には番号によって管理されている。そういった権力の後ろ盾によって身分を証明することができても、人が変わることへの抑圧が大きく、不安定であることを嫌い安定した人格を求める。これがある意味で変身の欲求を掻き立てるのかもしれない。
平野啓一郎は『私とは何か 「個人」から「分人」へ』の中で、本当の自分が何かわからなくなって生きづらさを抱える現代の若者たちに分人主義のあり方を提唱した。
一人の人間は、複数の分人のネットワークであり、そこには「本当の自分」という中心はない。
家でのわたし、職場でのわたし、友だちといるときのわたし、恋人といるときのわたし、ひとりのわたし、ネットのわたし…。つまり、接する相手によって態度や性格が異なるのはあたりまえで「どれが本当の自分か?」と悩む必要はないよ、どれもこれも全部「自分」だよ、人間というのは人間関係のネットワークの基点に過ぎないのだから関係によって在り方はかわるのでアイデンティティの核を持とうと焦らなくても大丈夫だと説いた。東洋的な視点からアイデンティティの考え方を再考した「分人」は確かに人格としてのアイデンティティの定まらなさに対するコンプレックスや一貫性の呪縛から開放される言葉だ。けれども「分」という字の離散性に私は抵抗感を持つ。場面や人によって分かれた人格の乖離に苦しむ人々がこの世界にたくさんいるのではなかろうか。
市場競争的な社会において、建前の人格の市場価値を維持し続けるレールから外れることができないために人格を分け、裏側の人格の闇を扱いきれずに問題をおこしてしまったような構造を日々ニュースで見聞きする。中央省庁のエリート官僚が違法なことをしたり、まさかという人が陰でなにかをやっていたという話。
人間が一貫性を保たなくても良いのはそうだけど、デジタルな「分」よりも連続的で冗長な波のうつろいを許容する「変」が良いなと私は思う。結局は、人は不安定でも良いし変人で良いのだよ、ということ。そして個人の生きづらさや不安定が構造によって影響されひき起こされているのだとすれば、個人的なことは政治的なことなので行動していく必要がある。デジタルな指向性というのは、いくら究めようとしてもそこには無限のアナログの深淵が広がっており、連続的で不確実な世界を不確実なまま受け入れなければいけないことに挫折するときがいずれくるのだと思うけど、人はそれに気づくまでにはゲームに夢中になりすぎて忘れてしまったりする。
SFC
学部の頃にはガチギレする先生が結構いた記憶がある。熱く議論してる先生がいたのを目撃した記憶がある。課題やプロジェクトのルールを先生にきいてしまったこと、授業態度が悪かったこと、遅刻して適切に対応できなかったこと、道具を丁寧に扱えなかったこと、SNSに不適切なことを書き込んだこと、SNSの使い方が不適切なこと、SNSの使い方がバグっていること、もろもろ…。ブチギレのロゴス。学生と向き合っていたのだろうなと思う。
かわいいウルフに携わった方々はSFCに関わる人が多い。小澤さんがかわいいウルフをつくるきっかけになったという『Rhetorica』という批評誌プロジェクトのメンバーの多くもSFC関係の人たち。私は文盲で挙動がバグるけどやっと最近レトリカにキャッチアップできつつある。すごく偉いことをし続けている同世代がいて本当に素敵。私も頭とからだを使って頑張らねばと思った。昔はRhetoricaのことをどちらかと言えばゴリゴリな男たちのクールで鋭利な批評誌だと思っていた。最新刊Rhetorica4も重厚な装丁で敷居が高く感じていた。でも、かつてこうしたプロジェクトを展開してきた先人から知恵を継承しつつも、彼らよりもさらに敏感に時代を感じ取り投げ返しているのだと思った。巻頭言を読み、中も掘り進んでいけばRhetoricaはかっこよさの中にある種の〈かわいさ〉も備えているのだと思えた。それからRhetoricaもかわいいウルフも、大学という制度や場を離れても知性や文化の意味を紡ぎ続けているな、と私は感じてしまった。
DV被害者の気持ち
あの人すごくいい人なのよ、でも暴力を振るの…。
親が尊厳を踏みにじる、それでもママが好き…パパが好き…。
うちの研究室超楽しいのよ、けど超ブラックなんだ…。
うちの会社すごくいいぜ…けど俺めっちゃ社畜…。
うちの大学すごくいいところなんだ、けどクソなんだ…。
うちの国めっちゃいい国だよご飯美味しいし文化イケてるし…でも…。
かわいいウルフという企て
ぶっ飛んだウルフ読み物とウルフ作品を読んで、自分でも書きたいことを書かなきゃと思った。しかし思考がバラバラになったりアトピーと蕁麻疹で死にそうになったり、統合され得ぬ断片たちをどうにかするのはどうしたらいいか、わーーーとなって、でもとにかく書かなくちゃ、部屋にS先生降臨システム(画像)を貼ったら怖くなって家の中にいることができなくなって外に逃げるしかなくて多動していろいろな人に会いに行って地雷踏んだり謎の挙動をしてしまって、思考が散乱してまくった。

今後私は大学の中や外で対等な立場の人たちが支え合える仕組みをつくったり、困難さをピアな人たちのグループで研究し研究をもう一度民主化する当事者研究によって意味を編み直し声を形成していくこと、また日本のアカデミアの状況をマシにする動きをしていく。まだ男性も怖いし社会も怖いけど。自分に力をくれた方々やお世話になった環境になにかできたらいいな。
サポートしてくださるんですか。ありがとうございます(;_;)
