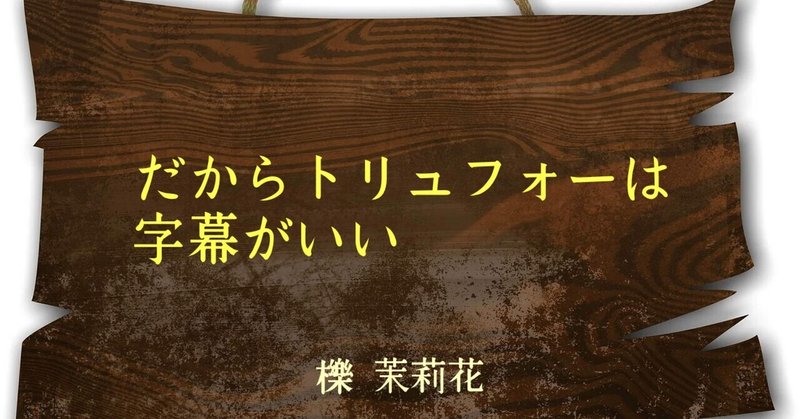
だからトリュフォーは字幕がいい
(本作は3,565文字、読了におよそ6〜9分ほどいただきます)
ついてない日もあるもんだ。
久しぶりの休日に、フラッと映画でも観ようと思ったまでは良かったが、下調べもせずに直感だけで選んだ洋画が大はずれ。しかも、吹替えときた。洋画は字幕に拘る俺にとって、吹替えの洋画なんて邪道中の邪道なのだ。だって、フランソワ・トリュフォーもジャン=リュック・ゴダールも、字幕だから素晴らしいんじゃないか。娯楽性も芸術性も、字幕で観るからこそ高められるのだ。少なくとも、俺はそう信じている。なのに、吹替えだなんて……
更に言うと、この映画はクソだった。音楽も効果音も、ただただうるさくて派手なだけで、知性が感じ取れない。大袈裟で仰々しい。映像との調和もチグハグだ。だから、アメリカ映画は嫌いなんだ。数パターンしかないキャラクター設定に、最初と最後の10分ずつを観るだけで全て想像出来てしまう陳腐なストーリー。貧弱な構成を、CGによる映像技術で誤魔化す。退屈の極み。時間の無駄だった。
気を取り直して入った喫茶店は、とても混雑していた。そのまま回れ右して出ようとした時に、「おひとり様ですか?」なんて、可愛いらしい店員に聞かれもので、ついつい「はい」と答えてしまった。
で、やっぱりついてない日なんだなって再確認、案内された席が一番奥の角にある小さなテーブル席で、隣は5~6人のおばさん集団に完全に塞がれた状態。「こちらでよろしいでしょうか?」なんて、とびきりの笑顔で言われちゃったら、気弱な俺には「いいわけないだろ?」なんて口に出来るはずもなく、「はい」としか答えようがない。
しかし、おばさん達は買物帰りなのか無駄に荷物が多く、バリケードで閉ざされた感じの席だ。座る時にこそ面倒臭そうに脇に引寄せた荷物も、俺が着席するや否や、邪魔なところにどかっと置き、退路を塞ぐ。そして、予想通り下品なぐらいうるさい。フェデリコ・フェリーニの作品には、絶対に出てこないであろう舞台設定と配役だ。
俺は隅っこの小さなテーブルで、一人小さく座っているしかない。本も持ってこなかったし、スマートフォンはバッテリーが切れかけており、使いたくない。本当についてない。
しかも、店員はこんな酷い席に案内しておきながら、それっきり俺の存在を忘れたようで、水もおしぼりも持って来やしない。もちろん、オーダーもまだだ。
隣のおばさん達は、ノンストップのフォルテシモで不協和なノイズを口から発し続ける。いや、口だけでなく、身体中がうるさい感じだ。席を立とうにも、奴等の荷物がどうにも邪魔だ。こちらを見向きもしないし、気遣いなんて出来る人種じゃない。店員も、おばさん集団が陣取るこんな一番奥の席には、呼ばれない限りは近付かない。かと言って、遠くの店員を、大声で呼ぶ度胸は俺にはない。
最悪なことに、おばさんの一人がタバコに火を付けた。おいおい、ここは、禁煙じゃなかったのか。これで、アメリカ映画より劣悪な舞台になってしまった。煩くて煙たくて息苦しい。やることもなければ移動も出来ない。全くもってお洒落じゃない。ましてや、クールでもシリアスでも、もちろんファンキーでもセクシーでもない。せめて、今この世界が字幕だったら良かったのに。でも、吹替えよりも下品な笑い声が、あちらこちらで響き渡る。誰も俺を見ない。透明人間にでもなった気分だ。
その時、おばさん達の向こう側にいる女子高生集団が、大声を上げた。彼女達も、この舞台の喧騒を演出していた構成分子だ。どうやら、おばさんのタバコに文句を言ったらしい。そのことがキッカケで、女性同士の世代別抗争が始まる。
ここは禁煙席だと主張する女子高生に、禁煙タイムは17時までだと開き直るおばさん。時計を見ると、17時5分だ。なるほど、ついさっきまでは禁煙タイムだったのか。となると、おばさんに分がありそうな展開も、女子高生集団も口が達者。感情のぶつけ合いはいつしか罵しり合いに発展。
ババァは厚かましいだの図々しいだのふてぶてしいだの、本題の趣旨から大きく外れた意見をぶつける。もう、単なる悪口にしかなっていない。すると、最近の若い子は本当に非常識で礼儀も知らないと、おばさん達も負けずに言い返す。親の顔が見てみたいだの、育ちが悪いだの。
余裕を装うおばさんの笑い声と女子高生の汚い怒号が混じり合い、なんとも醜い合成音が作成され、その神経を逆撫でするハーモニーが、不快な感情と苛立ちを俺の中から引っ張り出した。
店内は、ますます混雑してきた。喧騒もビルドアップされ、いつしかタバコの煙が充満している。湿気を帯びた空気は澱み、女子高生とおばさんの口論は続き、どこかで赤ちゃんがけたたましく泣き叫び、違う場所では若者達のバカ笑いが鳴り響いた。この環境で、唯一及第点を与えてもいいかな、と思っていたBGMのMinnie Ripertonも、完全に掻き消されてしまった。店員は忙しく動き回り、誰も俺の存在に気付かない。水もおしぼりもない席で、一人でジッと座っているしかない。ますます席を立ち難くなっており、店員を呼び止めることも出来ない。
俺の中のイライラは、沸点に接近した。そもそも、映画なんて観なきゃよかった。しかも、吹替え……やっぱり映画は字幕に限る。
繰り返すが、ルキーノ・ヴィスコンティもルイ・マルも、字幕だからこそ素晴らしい。何故?って……そう、必要な言葉だけを選択するからだ。必要のないバックの喧騒なんて、いちいち訳さない。大切な台詞だけを訳すのだ。だから、喧騒は喧騒のまま、無視され、聞こえてこない。この店のMinnie Ripertonと同じだ。必要のない音は風景の一部と化し、通過するだけ。だからこそ浮かび上がる字幕のセリフ。オリジナル言語の音声と呼吸とリズム。声を、音と言葉にシビアに分類する。それこそが、字幕映画の素晴らしさなのかもしれない。
もし、今のこの環境が字幕で再生されているのなら、おばさんと女子高生の口論も、赤ちゃんの泣き声も、若者達のバカ笑いも、全て必要のない音と判断され、スルーされるだろう。訳されるのは、俺の心の葛藤だけだ。それが活きる言葉となり、字幕を介して伝達され、受信者に消化されるのだ。そうだ、現実の世界も字幕で表現すべきなのだ。
「みんな、黙れ! 早くオーダー取りに来い! せめて、水とおしぼりぐらい持ってこい!」
俺は、破り取った手帳のメモのページにそう書込んで、大袈裟に立ち上がった。しかし、ほんの幾人かが一瞬怪訝な目を向けただけで、俺の存在はやはりスルーされた。誰も関心を示さず、水もおしぼりも持って来てくれないことには変わりない。
おばさん達は激しい口論に全員参加、邪魔な荷物を除けてくれる気遣いなど皆無、かと言って、こちらから頼める雰囲気も全くない。閉じ込められた角の席で、無言で紙を手に立つ俺を、遠くのカップルが不審そうに見つめている。唯一、彼らだけには、透明人間が見えるようだ。そして、彼氏が実にスマートに店員を呼び止め、何かしら耳打ちした。俺も、ああしてさり気なく店員を呼び止められると、今頃はコーヒーにあり付けたのだろうか。
彼氏に何かを伝えられた店員が、怯えるような目で俺を一瞥し、厨房の中へ消えていく。さっきの可愛いらしい子だ。そうだ、この子も俺のことが見えたはず。それに、元はと言えば、彼女のせいで俺は軟禁され、透明人間になったのだ。可愛い顔した悪魔……おぉ、クロード・ルルーシュ作品にピッタリのキャストじゃないか。
可愛い悪魔は、店長っぽい男性と一緒にこっちにやってくる。男性は、顔が強張っており、口を真一文字に結び、とても緊張している様子だ。どうやら俺は、不審者扱いされたようだ。告げ口したカップルは、既にいない。相変わらず、おばさん達の荷物が邪魔で、俺は席を離れることもできない。
店長が俺との距離を詰める。可愛い悪魔は、離れたところで見ている。怯えている感じだ。確か、レオス・カラックスに似たようなシーンがあったな、なんてことを思い出す。しかし、現実の世界を字幕にしてみたのはよかったが、映画のような感動は生まれないようだ。
やがて、店内片隅から発信される異変は空気を伝播し、店中に拡散された。辺りが急に静まる。様々な角度と距離から、沢山の視線を感じる。でも、そのおかげで、Minnie Ripertonの天使の歌声が、ようやくはっきりと聴こえるようになった。そう、やっとミニーの声が聴こえたのに、よりによって、今天使が歌っているのは『Lovin’ You』だ。もちろん、ミニーの中では一番好きなナンバーだが、何で今なんだ? 映像と調和しないじゃないか。
ついてない日もあるもんだ。
