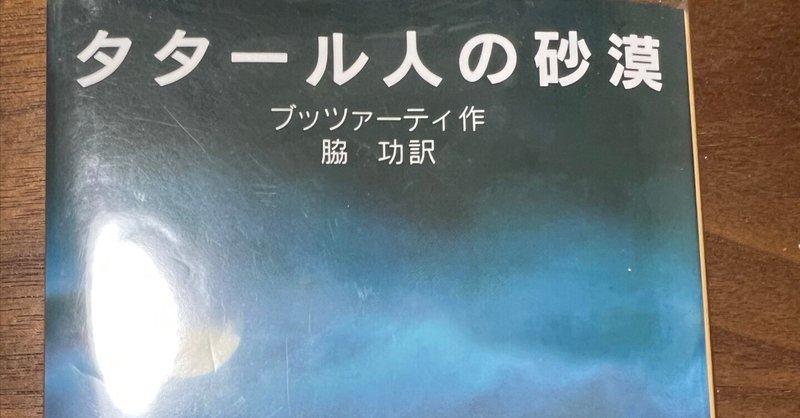
『タタール人の砂漠』ブッツァーティ①中川多理 Favorite Journal/今月の[読みたい本]の一冊
国立劇場、さよなら文楽公演、近松特集の第二部は『国性爺合戦』、近松の時代物。父は唐土(もろこし)母は日本の、和藤内(わとうない)…和と唐ね…だからわとう…。日本人の血を引き、明王朝再興をめざす鄭成功を和藤内として描いている。そして明を滅ぼした清を「韃靼」という名に変えている。なので冒頭から韃靼の名がぞろぞろ出てくる。気にするとどこにも韃靼がある。ちなみに、二月堂御水取りにも達陀は、あって、何やらトルコ帽のようなものを子供に被せたりもするが、実際の韃靼、タタール、モンゴルとをつなぐ資料は、ぼくは見ていない。ここから初代松緑が『達陀』という、踏鞴を踏みまくる豪快なそしてストイックな踊りを作り、松緑と菊五郎劇団の宝物のような出し物になっている。
さて、韃靼あるいは韃靼人は、…遥か遠く、由来が杳として知れない…何か不思議なものが起きるところ…実体が曖昧な[地理]のどこかに漠として、しかしながら間違いなく存在する…場と存在の一体となった[地勢]のようなもの…として受け止める。清国を滅ぼしたモンゴルの何だか分からない強い国、御水取りの儀式に関しての達陀、そしてその彼方の妄想がとてつもない踏鞴の舞踊を生み出す。自分が唯一創作活動したダンスの台本は、仏蘭西で韃靼の基督と称された泉勝志だった。韃靼の基督の、韃靼の意味を思ったことはなかった。なんとなく異形の、美しい、亜細亜と欧羅巴の遺伝子を同時にもっている…とぐらいのイメージでずっと付き合っていた。
地理的に離れうやむやに場所を確定出来ないが、そこから得体のしれないものが到来する。そんなものの総体として韃靼という言葉がある。そう確信する。『タタール人の砂漠』のブッツァーティは、1906年来たイタリア生まれであって、ここに書かれているタタール人=韃靼人が攻めてくるかもしれない砂漠の向こうから…は、まさに韃靼人の名で表現に相応しい。
[韃靼]は、攻めてくるイメージと不可避にあって、安西冬衛の韃靼海峡も、中国の向こうに列強露西亜が控えている時代に書かれている。得体のしれないものが具象を得る時に、文学は魅惑を見せるもので、たとえば、カルパチア山脈の彼方から得体のしれない疫病(ペスト)が来るとロンドンでは大まか信じられていた訳で、それが具現化したのが、ブラムストーカーの『ドラキュラ』。疫病は海峡越えて伝播することはなく、それゆえに棺桶に砂を入れてネズミとともに船で欧羅巴に移動すると云う手間な、地理的リアリティを文学上でも行うわけで、この原形が素敵に地勢的地理的背景をもっていたがゆえに、恐怖は文学に亜流を量産しながら、時代を超えて現代にまでたどりついている。[韃靼]は、病理ではなく戦争的地理として位置づけられるので、けっして流行的に広がることはない。
さてこの本の読み方だが…。
もちろん自由。
だけれども『タタール人の砂漠』や『神を見た犬』の解説にあるように人生そのものが描かれているとか、あるいは他の解説ではカフカと似た寓意的な…とかで読まれている例を目にするが…そしてとてもよけいなお世話だけれど、カフカに寓意はなくて、あのように表現したかったから書いたのであって、別の意味を、あなたの人生の意味を、読み取ってもらうことを念頭にはおいていなかった。読み取るべき意味を込めてある文学ではない。(そういうのもあるけど)『タタール人の砂漠』にもそれはない。そして人生そのものが描かれてはいない。ブッツァーティの人生は、その思考や体験の一部は、色濃く描かれている。でもそれはあなたの人生ではない。彼の人生だ。そこが当てはまらないから、この小説は面白いのだ。
少し別の話をする。
フィレンツェ、サンマルコにあるアンジェリコの『受胎告知』は、元修道院の二階に上がっていく踊り場のようなところに掲げられているが、二階は修道士たちの瞑想の小さな部屋が並んでいて、壁に小さな絵が掛けられて、小さな外を見る窓がついている。修道院史を研究していた父親が、脇で、この小さな窓から世界を見るということが大事なのだ、修道士にとって…と教えてくれた。そのとき、チベットの山奥に友人がダライラマを撮影しに行ったときの話を思いだした。建物の最上階にある小部屋でずっと暮らしていて、小さな窓から世界を見下ろしていて、それで世界が分かるのだと云っていたと…。
小さな窓からでも世界が…ではなく、小さな窓だからこそ世界が見えるということなのか?…と、思ってみたりもした。たぶん…。サンマルコから離れて、サンミニアートの修道院では、やはり二階の部分が瞑想の部屋になっていて、入ることができた。窓からは中庭と、そして遥か彼方にフィレンツェの町並み、その煉瓦色の屋根とドーモが見えた。下界が見えて、なおかつこの窓だけ…。一時間ほどそこに坐っていたが、もちろん、視座が変わることも、変わった視座を想像することもかなわなかった。
フランチェスコが好きで、托鉢巡礼したところすべてを通りたいと思って旅行していたことがある。アッシジにも何度も足を運んだ。アッシジの最も高いところにロッカ・マジョーレという砦があって、登るとウンブリア地方を遥かに、地平線のあたりまで見わたせる。360°。少し寒い朝にロッカから平原を見ると、地表から蒸気が沸き上がり地面近くに雲のような霧が立ちこめる、幻想と云う言葉で表現すると陳腐に思える風景を体験することができる。城壁はかがんでどうにか通れる通路で繋がっていて、一周することができる。かつては、だいぶ離れたもう一つの砦まで通路でつながっていて、峰を全体で防御していたかと思われる。夕方まで滞在して、平原なので陽は一気に没し、闇が来る。通路の中途に屈み小さな銃眼からアッシジの町の灯の瞬きを見ていると、世界から自分が離れているかのような気持ちになる。
フランチェスコは、瞑想を良くしたので、アッシジには瞑想場所、カリチェリ庵があり、まるで東洋のような風景を配した庵は、高所の中途にあり、ここもまたフランチェスコの孤独と信仰を暖めた場所であると思える。砦の中に閉塞させられる軍人と、フランチェスコとの違いは歴然であるが、改めて云えば、閉塞された空間に居て、でて、托鉢をしながらイタリア全土に近い広域を托鉢修道した内面の深奥と広域な凡庸さとを同時に聖なるものとしたフランチェスコと、誰かの命によって人生の動きを定められ、砦に居続けた軍人との心の動きよう、頭の動きようはまったく異る。そのどちらでもない、人間が、自分を含めた人生を描いていると云ってしまう/思ってしまうところに、ブッツアーティの文学の魅力があり、また不可解な中途半端なところに気持ちが吊り下げられた様になってしまう魔力もある。ましてや意味を読み取ろうとすると、誰でも起こりうる人生とか、とりかえしのつかない人生とか…死ぬほど凡庸な感想を述べることになる。
『タタール人の砂漠』には、従軍した、そして戦争を通過した、肉体の残滓が描かれている。ブッツアーティ16歳のとき、ムッソリーニの政権が成立し、20歳で兵役に召集されている。34歳のときにこの本を著わし、従軍記者として巡洋艦に乗り込んでいる。
戦争がはじまると、自分の行動を決めるのは自分ではなくなる。運命が向こうから、いや命令が向こうからくるのだ。いつでも砦からでられると、云いながら、北方から攻めてくる、もしかしたらタタール人の軍隊を待機し続け、そして、いざ軍が迫ってきた時に…という流れてになっているが、ポイントは、嫌々だった砦の勤務が、とちゅうからそうでなくなるときがあり、その瞬間に、[幻想現実]が起きるのである。その風景の描き方が『タタールの砂漠』を超一級の幻想文学にしているのだ。
この主人公の心の変位と行動の執着に、そして時々に起きる偶然のような方向を決めていく出来事が、とてつもなく特殊なことであるのに、なだらかに、とっぴなことでないように見せて、砦にとどまらせ続けるのだ。
また話を切り替えるが…
今の戦争、ロシアの侵略戦争は、地政学によってある程度、説明がつく。もちろんある程度だ。プーチンがウクライナを[勢力圏]と見ていることから、ことはじまり、双方に死者の群れを作りながら、執着している根底にはロシア、プーチンからの地政学が働いている。
で、ちょっと難しい感覚だけれども、地政学というのは強い側が見定める勢力圏であって、つまりロシアから云うとウクライナが勢力圏になる。(正義とか正当とか、すべて吹っ飛ばして話をしていく。戦争はしかけたプーチンの起した悪であり、プーチンが止めようと云えば止まるのだ。世界のプーチン以外の人間が辞めようと云っても、おそらく戦争は終わらない。すべてはプーチンの決断にある)。ウクライナの側から云うと、ロシアは勢力圏ではない。で、視点を[勢力圏]に置かれて併合という行為をされてしまった側に置いてみる。[勢力圏]の側から見る——TVのニュースでもその視点は作り得ない。どうにか俯瞰してみるくらいだ。もちろんプーチンの頭の中も見えないから、地政学で、どう動かしているかも細かくは分からない。もし分かっていても、ウクライナのために報道することはない。
小説の『タタール人の砂漠』なら、全体を風景的に、一般化して見ることなく、ウクライナ側からの視点——被勢力圏視点を使って読んでみると、俯瞰とは別の風景が見えてくる。これは小説であるし、実は、俯瞰ではなく、窓から砂漠を覗くようにして書かれているからだ。この本は、受け身的地政学…勢力圏とされてしまった側、そこにいる人間の方から見るようにして、読むととてつもなく面白い。
自分で、自分の意志で動いている様に見えて、そうしていているつもりだったが、そうではなかった生き様が描かれている。そしてそこに実は後悔も描かれていない。もちろん絶望も。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
