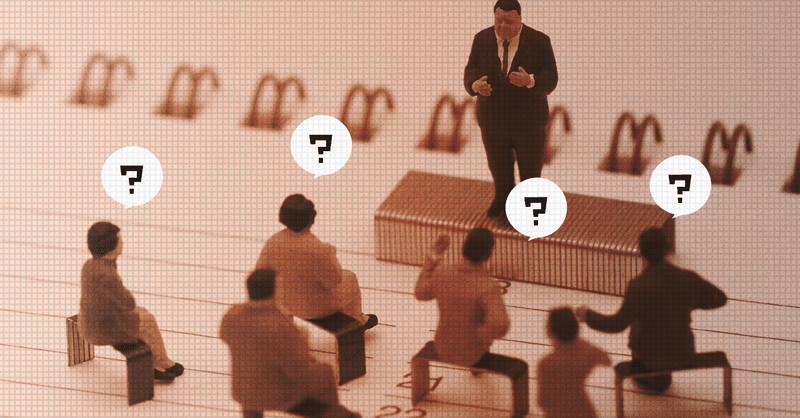
ふと考える夜④
◉ 就労の分野として取り組める業務分担
例えば...
店舗系(100均一、ドラッグストア、雑貨屋):レジ、品出し、レイアウト、発注、清掃
スーパー:レジ、品出し、レイアウト、発注、清掃、調理、盛り付け、梱包、集客
マンション経営、駐車場管理:備品管理、清掃、草取り、経理、集客、掲示
ウーバーイーツのような料理配達:電話対応、地図共有、配達、集金、集客
仕事って分ければ、どんな分野であっても障がいを持った方が取り組める作業があると思う
要はどう分けるかと、障がい福祉として行政通す場合は人件費、支援費の兼ね合い。行政通さない場合は人件費を何でカバーするかのアイデア次第。
『タイムイズマネー』というが「作業工程を分ける任せる」は「自分が楽になる」に繋がることをいかに実感するかで、分け方や依頼する内容も変わってくるはず。
◉ どうして欲しいビデオレター、やり方ポイント動画集
→ 引き継ぎって難しい。文章読むだけではピンとこない。利用者さんが実際にどうして欲しいのかをインタビュー受けている動画があれば、それを見てもらうことをスタートとすれば、利用者情報が分かった上で対応出来るのでは?食事介助、入浴介助、清掃、コミュニケーション等テクニックがいるものは動画で残しておけば、何度も何度も確認出来ないかな?
◉呼称問題『さん、くん付け』『ニックネーム』
→呼称問題よりも取り上げるべき問題は山程ある。そりゃもういっぱい。支援の内容をもっと取り上げるべきかと。呼び名が問題視されるのは悪意が見える感じられる。言うたら取り上げやすい表面的な課題だから。本当に表面。上澄でしかない。僕ならむしろ読んでもらいたい名称を自分で決めたいな。自己肯定感を上げられる名称がいい。ハッピー○○、ハートフル○○、安定の○○...一番いいのは『ありがとう○○』かな。○○には苗字でも入れようかね。なんだか芸名みたい。でも福祉で働くヒト、福祉に関わるヒト達には福祉ネームみたいなのがあっても面白いかもしれない。
◉VRを使った体験
→実際に利用者さんに360°カメラを装着してもらい、支援を受けてもらう。支援者側がVRで支援受ける側の視点や感情が学べたりしないかな。手の差し伸べ方や角度、声掛けのボリュームや内容、目線なんかが受け手として体感出来たら、めちゃくちゃ勉強になるのでは?
足が悪い身体的に障がいがある、公共交通機関の利用が難しい。そんな方々がうちにうちにこもって、入所しか知らない。そんな悲しいことがあってもよいのだろうか。VRで色んな場所を知ったり、体感することで、やりたいこと、夢や希望の選択肢開拓に繋がらないかな。知らないから選べない。そもそも選択肢にあがらない。それが今な気がする。テレビだけで羨ましく思えるのは、想像出来たり、近しい体感をしたことがあるから。『田舎の暮らし』なんてVRがある時代。家族って、田舎ってコレ!なんて概念も、気付けるかもしれない。
今日はここまで。
さぁ何する?どうする?
サポートがなんなのかすら理解できていませんが、少しでも誰かのためになる記事を綴り続けられるよう、今後ともコツコツと頑張ります!
