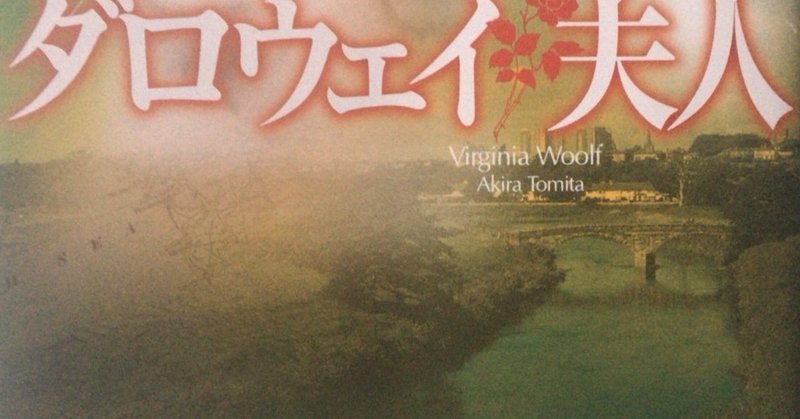
ダロウェイ夫人
"でもなんてへんな晩だろう!なぜかわたしはそのひとにとっても似てるような気がするんだものー自殺した若い男のひとに。"1925年発表の本書は、20世紀モダニズム文学の主要作家による裕福な50代の中年女性の一日。生、死、時を過去との記憶も織り交ぜて描いた『意識の流れ』の代表作。
個人的には主宰する読書会の課題図書として『灯台へ』に続く2冊目として手にとりました。
さて、そんな本書は『お花は自分で買いに行こう、と言った。』という有名な1行目から始まり、ダロウェイ夫人ことクラリッサ・ダロウェイが保守党政治家の夫人として6時から開く【手の込んだホームパーティを準備をしているたった1日の物語】を自身の過去の思い出を振り返ったり(直接は絡まず)並走して戦場で心の病を抱えた青年の自殺が『人間の思考を秩序立てたものではなく、絶え間ない流れとして描こうとする』"意識の流れ"によって描写は美しくも【突然、視点が別の人になったりする】複雑さの中で描かれているのですが。
まず全体に対して思ったのは、イギリス上流夫人としての人生を選択した自分を『常に正しい』と思いつつも、どこか疑っていて、また他者への配慮に欠けるダロウェイ夫人の生と"死ぬのはいやだ。人生はいい。太陽は熱い"と窓から飛び降りる青年、セプティマスの死の【対比は何を指しているのだろうか?】ということ。著者自身の人格の投影とか諸説はあるみたいですが。個人的には映画ミッドサマー『恋人は犠牲として捧げられ、女性はカルト教団コミュニティに受けいられる』を思いだして、少なくとも【著者自身にとっては絶対に必要だったのだろうな】と色々考えてしまいました。
また、登場人物の中では若き日のダロウェイ夫人の恋人、ピーター・ウォルシュ。ナイフ遊びの癖があり、恋とロマンを追い求め続け、自身は求職中にも関わらずインドで出会った人妻に恋している(でも本当はダロウェイ夫人に未練あり)が皮肉屋ではあるもチャーミング(笑)に描かれていて気にいりました。物語自体はある意味シンプル、悪く言えば単調な本書ですが、彼以外にも【登場人物それぞれはとても魅力的に描かれている】と思いました。
"意識の流れ"の代表作として、また物語自体の起承転結や起伏を楽しむというより、感じる文体が好きな方や人生の午後世代にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
