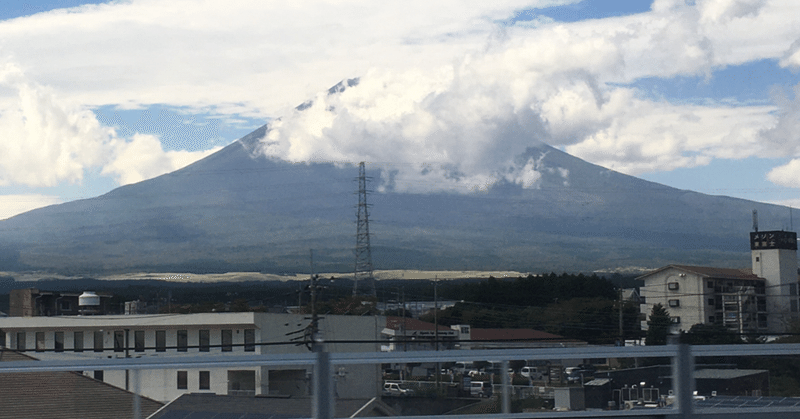
はじめに
これ、ワイン飲んで書いていますので
ごめんなさい 最初にお詫び 駄文 過ぎた
もう20年以上も昔の話になりますが
当時アメリカでは、 #ベビーブーマー 向けのマーケティングというテーマが少しだけ流行ったことがありました。これは、日本で言う #団塊世代 へのマーケティングが目前の課題になっていて、少しだけ先行して、消費のボリュームゾーンがリタイヤするアメリカに学ぼうというものだったのです。
そこで見えたものは・・・・・・
アメリカと日本は根っこが違うと言ったエビデンスの無い結論
当時のアメリカで僕らが学んだものは、 #AARP という巨大組織について学ばせていただいたり、砂漠の真ん中に老人コミュニティーを出現させたデベロッパーの視察、シニア層にスポーツカーを提供するCM戦略など、見るもの、聞くものがやがて日本の姿にどう反映するのか必至に考えたものでした。そんな環境で、僕ら日本人が出した様々な検証結果は、極めて排他的と言うか、アメリカで今見たものは、「日本では出来っこない、やれっこない」というもので、唯一そのまま活用できそうと考えたのは、スペシャリティGTカーの販売戦略くらいだったわけです。
「出来っこない」その根拠はネガティブではあるけれど、実に実に、一見して的を得たものでした。
⚪日本は原則、健康保険は皆保険制度なので、老いて病んだ時にもケアが充実しているから、アメリカのように如何に健康なまま歳を重ねるかが国益に直結するという意識が薄いので、老いて病んで入るタイプの老人ホームは考えられても、健康な老人にコミュニティーを提供するというビジネスは難しい。
⚪米国は経済格差が如実にあるために、富裕層の絶対数が日本より多く、更に日本と比較して物価が安く、国土が広いために、日本では誰も購入できない様なサービスが、現実的に中間層よりも少し上の層であれば購入出来る価格で提供される。
⚪生活スタイルが個であり、夫婦という単位での移住などは比較的容易であり、子どもたち親戚、地元での柵という縛りが弱い。地元に根付く日本人には難しい。
⚪投資よりも貯蓄に資金が流れ、運用という意識が薄い日本人シニアでは、年金に対する依存が強く、受け身な生活にならざる得ない。
小金はあっても、大きな購買は難しく、自己判断基準も世間や公の発信が優先する。
これらは、20数年を経た日本にどれだけ当てはまるだろうか?
20年前に、このように分析した結果、無理だとしたものがどう変化したかもまた面白いのです。
20年の時を超えて
現在は、ウエルネス思考の老人コミュニティーは日本にも存在します。
皆保険制度は財政面で厳しさを増し、日本でも健康寿命を伸ばすことは不可避です。内容はともあれ、貯蓄は貸金庫と変わらないものであり、年金制度も薄くなり、自助の活動が避けられない状況になっています。以前から怪しかった終身雇用の崩壊と年功序列の撤廃は、働く側の可能性によって実現したのではなく、経営者の都合で構築され。全体の人件費を変えずに分配割合を変えたのならまだしも、全体に占める人件費の割合を低減させたのではないかと思わせる現実さえあるのです。
この20年の流れは、当時想定した日本の未来を変えたのかもしれません。
つまり、当時、日本は米国と並べて考えることが出来ない状況があったのは確かなのですが、そこから試行錯誤してより良い未来を構築するならまだしも、結果として、当時は考えもよらないアメリカ式の次女制度に推移しつつ、アメリカほどその原資となるチャンスと所得とが得られることがないのに、制度だけがハングリーになったと言わざるをえません。
では、我々はどうしたら、明るい未来を生きることができるのでしょうか?
本当にwell-being(ウェルビーイング)を口にするのなら
これを実現するためには、well-being(ウェルビーイング)という概念を、官も民も個も一緒になって先ず最初に、言葉の持つ概念を捨てることです。
#ウェルビーイング という概念があるから、そこには縛りが生まれます
その縛りが、権威を有する機関が提唱するものであったり その実行を高らかに謳い上げる企業があったり アカデミカルな専門家が居たり それらの柵こそが、足枷になるのです。
#働き方改革 は万人に富と幸せを与えますか
#ダイバーシティ は、ダイバーシティは良いことと押し付けをしていませんか?
多様性を認めることを強いる事は 多様性に反するという疑問が生まれない社会は危険です。
だからこそ、極論を言えば 健康とは精神的にも肉体的にも社会的にも満たされる状況 これが、万人にとって、無条件に幸福なのかを考えた時に、疑いなく、これが幸福だと定義してしまうことで、万事が解決するとは思えないのです。
真の意味でのウェルビーイングは、定義できないものだと知るべきです。
1曲の詞が幸せを描いた
ドラマ『青が散る』の主題歌 聖子さんが歌った #蒼いフォトグラフ
作詞:松本隆,作曲:呉田軽穂 天才 松本隆 さんの傑作です。
曲は呉田軽穂 つまり #ユーミン さんです。
一度聴いて下さい
ここに出てくる若者たちは、何処か不器用で 悩みながら 迷いながら 生きています。 こんなにも 切なく 苦しみながらも 自分を生きる
結果、彼らは人生の中で、一番綺麗な風の中を生きたと 後で感じる事が出来ている それこそが生きる意味だと感じます。
これは何が言いたいかと言えば、幸せの評価は 外から観たものではなく さらに言えば、箇条書きにしたり、ポイント制にで積算するものでもなく、
自分自身でさえ、その時点では気づいていないものだっりする、そういう事なんです。
自分の人生ををディレクションすることです
⚪人生の最初は人任せです だって、生まれるため努力していないし・・・
⚪人生の一定部分は依存です 当然のこと誰かに生かされてもいます
⚪でも、人生の総てを依存するのは違う だからこそ
⚪人なのですから、どこかで自分の人生を自分で作りましょう
自分の足で転ぶ方が誰かの背中で震えるよりも良い
ウェルビーイングとは、自分が自分を生きること たったそれだけの事なんです。 病気だって 障害があったって 老いていようが 問題じゃない
そう、健康であることは生きるための一つの手段であり
決して目的じゃないのです。
僕らは、自分の意志に対して自由です
そうでないとしたら、それは自分がそうしているのです
何処に居ても、何をしていても 自分の意志は常に自由です
活きてみませんか 生きてみませんか
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
