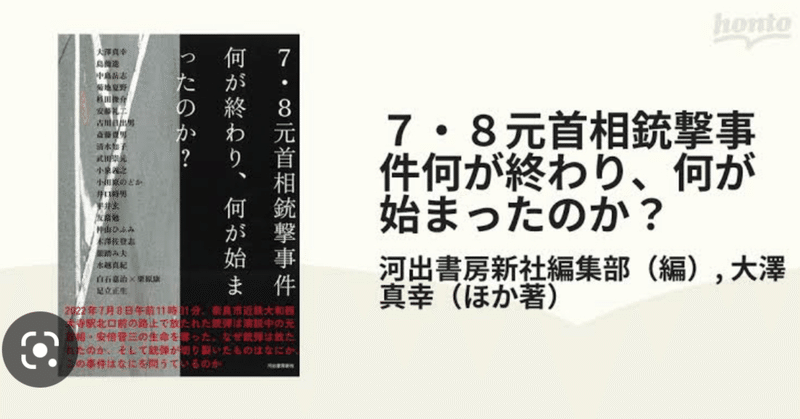
7・8事件で追放されるわたしたち
『7・8元首相銃撃事件何が終わり、何が始まったのか?』(河出書房新社)を「テロの定義」というタイトルでAmazonにレビューを書きました。以下が本文になります。中盤で太字にしたのはnoteで加筆した部分です。
テロの定義
元首相銃撃事件がテロか否か未だに意見が分かれるが、そもそもテロの定義すら違う者同士が争っている様相では何も見えてくるわけもない。テロという言葉がいかに曖昧で漠然たるものかをかろうじて気付かさせてくれるのはおそらく本書なのである。
本件をテロだと捉え、山上徹也を含めて全否定するのなら話は簡単なのだが、テロだと捉えながらテロの存在や山上を肯定することもあれば、その逆で単なる逆恨みということでテロとは捉えずに山上を全否定することもある。さらに自分が「反アベ」か「親アベ」かで持説を曲げてしまう場合もあり、あまりにねじれが複雑すぎて、本質に辿り着けることすら難しくなっている。
一般的には「公憤」のための行為はテロであり、「私怨」のための行為はテロに当たらないということになっているが、井口時男はその間にあるグレーゾーンの存在を読み解いている。
「オレが憎むのは統一教会だけだ。結果として安倍政権に何があってもオレの知った事ではない」と既に流行語と化している山上の投稿を、井口は「あくまで統一教会に対する『私怨』に発する行為であって、『政治的』影響には関知しない、という意味だろう。」と翻訳している。しかし結果的には「多数の旧統一教会被害者を救い、問題に焦点を当てて政治権力との根深い関係をあぶり出す仕事はマスコミが代行し、安倍政権に萎縮させられてきたマスコミにとっては格好の、『意趣返し』の機会到来にもなった」ことを指摘する。ただ「オレの知った事ではない」ので、あくまで「彼にとっては副次的な結果の一つにすぎなかったはずだ」ということは補足している。ざっくり言うと井口は本件をテロだったかもしれないが、ある意味肯定的に捉えているところは、本書の代表的意見と言ってもいいだろう。
テロという言葉の曖昧さは、平井玄も指摘している。「私怨」と「政治」を明確にし、
「私怨こそ『政治を破壊する政治」の端緒である」と力説する。
井口自身も平井が指摘しているように、山上が「反アベ」の「サヨク」ではなく、「安倍の政治姿勢を高く評価していた」ことも認めて決して無碍にはしていない。
だが、無碍にはしないだけではやり過ごせないのが杉田俊介である。「安倍の政治姿勢を高く評価していた」はずの山上に「我が身を犠牲にして、身代わりとしてあのような事件を起こさせ」間接的ではあるが「意趣返し」の代行までさせたことで、塩を送られた格好になり、借りを作ってしまったことが許せないのである。しかも自分の片想いだと思っていた相手から過去に「だがオレは拒否する」というラブレターとも言えるようなツイートが発覚してしまったということもある。端的にいえば、杉田の持説である「弱者男性」の記事(文春オンライン)を読んだ山上の感想ではあるが、杉田の贔屓目とはいえ、「だが」にはやはり両義性はあり、一度は杉田の主張を受け入れていることを意味している。しかも他者に期待をしないはずである山上が助けを乞うていたのではないか(杉田フィルター)と俄然やる気になり、山上からの「だが」という応答の両義性をライフワークに加えてしまう杉田であった。
「反アベ」でない山上容疑者に負い目があるだろうことは薄々読者もわかっていただろう。
杉田は矛先を自身にも向けているが、右も左も皆がこぞって「民主主義国家で暴力は許されない」とコピペのようなことしか言わないことにも複雑な思いを抱いている。ただでさえ本来は「反アベ」側が言論で行うべきことなのに「反アベ」でない山上に、繰り返すが「我が身を犠牲にして、身代わりとしてあのような事件を起こさせてしまった」のに、この後に及んでまだ自分たちは綺麗なままかと特にリベラル左派には嫌気が差したのだろう。
杉田は山上が「反アベ」ではないことを前提に論じているが、「だが」の両義性でわかっているように「安倍の政治姿勢を高く評価していた」とはいえ、山上が必ずしも安倍に心酔していたわけではないこともわかっていたはずだ。
そのことは平井も指摘している。
「北朝鮮もまた別種の大日本帝国の模倣である」という山上のツイートの一部に目を向くと、「単純なヘイトとはやや方向が異なっている」ことが分かってくる。何よりあの
「ネトウヨとお前らが嘲る中にオレがいる事を後悔するといい」が物語っているからだ。
決してテロを義挙と称えるというわけではないが、「民主主義国家で暴力は許されない」とどの口で言うかなどという反語的な主張が本書には見え隠れなしに現れる。
本件がテロなら、「井伊大老を襲撃した水戸烈士を靖国神社に祀る日本はとっくに立派なテロ国家」と看破する武田崇元や、山上に稀代のアナキスト奥崎謙三の姿を思い起こす木澤佐登志の主張にも一部は当たっている面はある。足立正生が本件を題材とし国葬の日での公開を決行された映画『REVOLUTION +1』にもその傾向はある。足立が若松孝二の影から逃れられないからだ。
だが一番頷いてしまったのは水越真紀の論考だ。
当たっている面はあるにしろ、あたかもテロは革命と言い切る上記の論調には危うさも感じるが、水越も決して革命を否定はしない。「『民主主義の手続き』とやらを待っていたら、宗教2世の苦しみに公的機関が介入することなどあり得なかったに違いない」とまで言い切っている。しかしこうも言う。「わたしたちのほとんどは、山上徹也の『革命』によって解放される側ではなく、追放される側にいるのだから」と。
それだけではなく水越の調査は念入りだ。メディアでも高額な献金をしていた山上の母親ばかり責められていたようだが、自殺した父親も妻に暴力を振るっていたことも水越は見逃さない。恥ずかしながら筆者もそのことは初めて知った。丹念に追っていた水越は、
「オレは祖父に見捨てられない為に演じた。いや、母を殴る父の機嫌を損ねない事が始まりだったのか」という山上のツイートに辿り着き、山上の家庭環境はメディアで語られるストーリーとは違うことだけでなく、「安倍晋三と山上徹也は考えれば考えるほど似ている」ことも導き出しているのだ。
本書で惜しい点もある。
まずは、太田光の統一教会への擁護について誰も言及しなかったことだ。安倍と付き合いがあったから単純に批判するのではなく安倍と異なる思想を持つ太田をより深く掘り下げることが本書の役割ではないのか?
そしてその太田の代わりにひろゆきが斎藤貴男に生贄にされていたが、
話題にするのに太田よりは容易だったのかは知らないが、ひろゆきは辺野古新基地に必ずしも賛成しているわけではないので、言及するならもっと突っ込んでやるべきなのである。
いちばん意外に思ったのは、共著の中に雨宮処凛がいないことだ。
山上必須のキーワードの一つでもあるロスジェネ世代について語るのは、中島岳志(テロ自体が中島の代名詞だが)、杉田、雨宮が中心となっただろう本書に雨宮がいないのはなぜなのか?
本件にテロという言葉を安易に結び付けることはしない雨宮を平井も買っていたにもかかわらずだ。
雨宮がいない理由は同じテーマで単著を出すからなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
