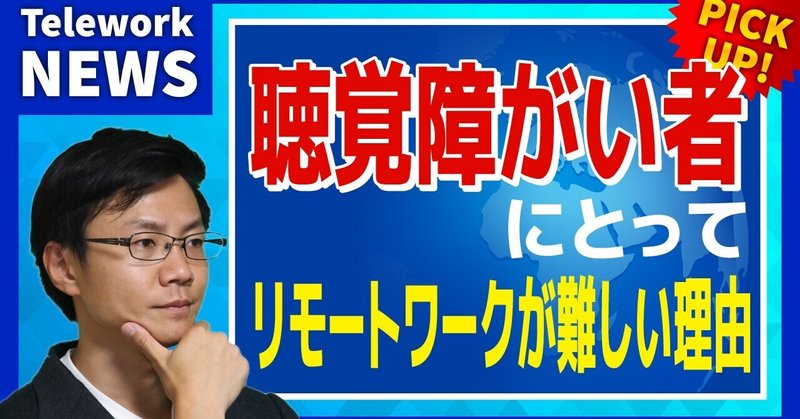
【現状改善】聴覚障がい者にとってリモートワークが難しい理由|世界の最新テレワークニュース
テレワークに関する日本であまり知られていない世界中の最新ニュースについて、その要点&考察をお届けする「世界の最新テレワークニュース」。今回は、Forbesのリリースである「聴覚障がい者にとってリモートワークが難しい理由」という記事を基に、要点と今すぐ使える対策について解説します。
やはりこういった知識や理解があるかないかで、今後配慮や心遣いしたり、取り組んでいく時の姿勢や内容が全然変わってくるのではないかと思います。そこで今回は改めて非常に重要な内容としてお伝えしていきたいと思います。(元記事は英文ですがとても興味深い内容になっています。ぜひこちらもご覧ください)
▼今回の内容は以下の動画でもご覧頂けますので、ぜひご覧ください!
●課題と解決方法とは
まずは記事のサマリーを日本語訳した内容からお伝えしたいと思います。
・米国成人の13%が何らかの聴覚障がいがある
→日本は11%(約1,400万)と言われている
・難聴の方にとって、ビデオ会議が難しい理由
→誰が喋ってるかわからない
→顔が小さくて見えない(唇が読めない)
→身振り手振り(ボディランゲージ)がない
→ノイズが多い
・改善の工夫
→ライブキャプション(自動文字起こし。自動音声認識(ASR)
→速度・精度には課題がある
→人が文字起こし・手話するサービスも(コミュニケーションアシスタント)
→参加者ミュート
→なるべく1:1にする(顔が見えやすい、声もクリア)
・デジタルの価値
→ライブキャプションの進化
→ライブキャプションと人の紐付け
・会社が支援できること
→ネット環境
→ノイズキャンセリングヘッドフォン
→読唇・ボディランゲージが見やすい工夫(カメラON)
→発言者以外はミュート
→録音(後から見返す
記事ではまず、耳が聞こえにくい人がどれ位いるのかということで、「アメリカの成人の内13%の方には何かしらの聴覚障害がある」というデータを紹介しています。
これに対して日本はどうなっているでしょうか。別のパナソニックさんのサイトで紹介されているデータによると、日本の成人の内の約11%にあたる訳1,400万人ぐらいが耳が聞こえにくいと言われているそうです。つまり100人いれば10人位は何かしら聞こえにくいハードルがあることを意識した方が良いと言えると思います。
●参加者が多いと誰が発言しているか分からない
次に記事は、「耳が聞こえにくい方にとってなぜZoomやビデオ会議が難しいのか」ということに触れています。
まず紹介されている理由は、参加者が多くなればなるほど「誰が喋ってるかわからない」というものです。音声が全部同じスピーカーから聞こえてくるので、リアルの様にどの方向から発されているかが分からないということです。
次に「(画面に表示される)顔が小さいので見えない」。聴覚障がい者の方は、リップリーディング(=読唇)ということで、唇の動きを読んで発言を理解する方法を習得されている方が多いのですが、表示画面が小さいので見えにくい訳です。
同様に、表示画面が小さいので、「身振り手振り(ボディランゲージ)もリアルに比べて全然見えにくい」ので情報が得にくいということです。
さらに「ノイズが多い」。耳が聞こえにくい方にとっては声とノイズを分けることもハードルが高いそうで、ノイズが多いことによってもより聞こえづらくなって困ることが紹介されています。
私は、実はこれらの課題は聴覚障がいがある方以外の方も同様に当てはまる内容だと考えています。程度の大小の違いはあれど、ここで書かれている課題は、全て聴覚障がいが無い方も同様に困りがちなことばかりですよね。むしろこういった課題を全ての人に当てはまる内容として意識して、配慮や工夫をすることで、全方位的に便利度や快適度が格段に向上するのではないでしょうか。
●改善の工夫方法
次に記事では改善の工夫が紹介されています。
改善の工夫1:ライブキャプションを使う
最近Zoomなどでは自動で発言を字幕化する機能がスタートし始めています。まだ英語のみで日本語は対応していないようですが、この機能を使うことによって話すと下に字幕が出るんですね。 その字幕を見ると声が聞き取りづらくても目でカバーすることができると。実際は速度や精度にまだまだ問題があるらしく、記事では今後の発展が期待されると書かれています。
改善の工夫2:コミュニケーションアシスタントを活用する
記事ではその他に、人が文字起こししたり、間に入ってサポートしてくれる「コミュニケーションアシスタント」のようなサービスも有益で、ますますサービスの成長が期待されると紹介しています。
改善の工夫3:発言者以外はミュートにする
これはつまり、発言者人以外はミュートにして無駄なノイズが入らないようにするということです。
改善の工夫4:なるべく1:1にする
人数が増えれば増えるほど誰が喋ってるのかわかりにくくなります。表示される顔も小さくなり声のノイズも入りやすいくなるので、人数が少なければ少ないほどコミュニケーションが取りやすいということが紹介されていました。
●デジタルの価値
次に記事では課題に対するデジタルの価値についても触れられています。デジタル化が進むことによって、前述のようにライブキャプション=自動文字起こしもこれからますます進化が見込まれます。現状では、複数人の発言が下にまとめて表示されていますが、発言者がそれぞれしゃべってるような形で、吹き出しのようなイメージなってくるとより良いのではないかという提案が書かれていました。
●会社が支援できること
さらに記事では「会社が支援できること」として、以下のような施策が紹介されています。
・ネット環境を良くする
・ノイズキャンセリングヘッドホンを提供する
・読唇とかボディランゲージが見やすいようにカメラONのルールを徹底する
・発言者以外はミュートにする
・録音をして後から見返しやすいようにする
記事では会社向けとして紹介されていましたが、これらは会社に限らず個人間のコミュニケーションの際にも有益だと言えると思います。
●別記事で紹介されていたポイント
次に別の「BUSINESS INSIDER」というサイトで、ほぼ同じタイミングで同様の記事が上がっていたので紹介します。
こちらの記事は、32歳の聴覚障がい者の方の面接が通りにくいという体験を紹介したものです。以下は記事のサマリーです。
・リモート面接がなかなか通過できない
・聴覚障がいはあまり伝えたくない(影響がある懸念がある)
・様々な配慮をしてほしい
→キャプション利用(Zoom)
→読む時間を待つ
→通訳サービスの提供
→なるべくゆっくり
記事では、「リモート面接がなかなか通過できない」という現状と、そして採用に影響があるのではないかという不安から「聴覚障がいがあることはあまり伝えたくない」という気持ちがあること。そして「キャプションを利用して欲しい」「問題や説明を読む時間も待って欲しい」「通訳サービスを提供して欲しい」「なるべくゆっくりしゃべってほしいい」といった配慮を希望していることが紹介されていました。
●当然のように配慮や心遣いと工夫をしましょう
私もかねがね、色々な条件や環境といった多様性の方がいるということを理解することは非常に重要だと考えています。例えば今回のケースでは、私が紹介している「会議前にアジェンダを作って事前に文字で送付しておく」「会議が終わった後に議事録を作って送る」といったことも、聴覚障がいのある方が快適にオンライン会議に参加して頂ける一助になるのではないかと思います。
そして前述の様に、今回紹介した内容は、聴覚障がい者の方だけの課題でなく、それ以外のほぼ全ての人に該当するものだと思います。こういった課題を解決できたり、もっとよく改善していくことができたら、多くの方にとってより快適で便利なオンライン会議が実現すると言えると思います。まずはこういうケースや課題があることを理解した上で、それぞれがお互いに配慮や心遣いをしていくことで、皆にとってより良い環境が築いていけることに繋がるのではないでしょうか。
***********
▼動画はこちら。参考になりそうであれば、ぜひチャンネル登録お願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
