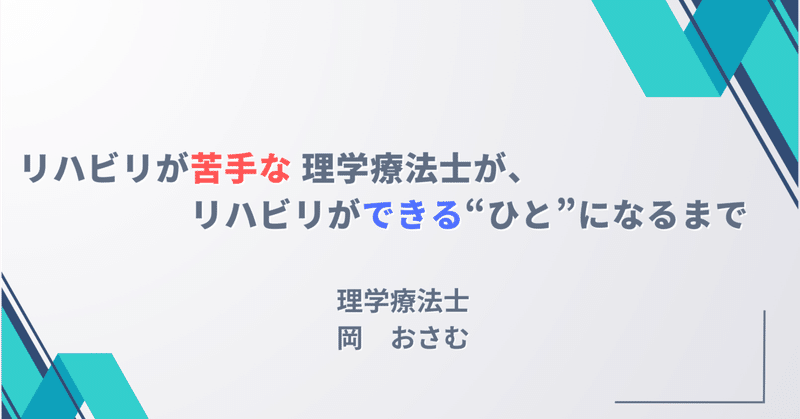
リハビリが苦手な理学療法士が、リハビリができる“ひと”になるまで 〜第1話〜
あらすじ
訪問看護ステーションで理学療法士をしている澤は、末期がんの利用者である土谷さんから「これ以上良くなることはないから、もう来なくていい」と言われてしまった。もちろん、土谷さんが良くならないことは澤にもわかっていたが、“理学療法士として”できることはまだあると思っていたので、拒否されたことはとても悔しかった。
しかし後日、澤は同僚の看護師である村田から電話で「土谷さんが呼んでるから家に来て欲しい」と言われる。一度は澤が来ることを拒否した土谷さんが再び澤を呼んだ理由とは…?
8月の終わり。夕方を迎えてもまだまだ暑い。
理学療法士(PTと略される)の澤は、この日最後の6件目の訪問リハビリを終え、事務所に帰えろうと利用者宅の前に停めていた原付バイクにまたがった。
蒸し暑さの残る気温に加え、バイクを日なたに置いていたものだからシートはかなり熱せられている。
焼石に座るようなこの不快感にはなかなか慣れない。そしてこの日は、この不快感に更に追い討ちをかけるような“ある出来事”があった。
10分ほど原付バイクを走らせ、澤は事業所のある一軒家に到着した。
表札サイズの看板にはこう書かれている。
訪問看護ステーション“あさひ”。
彼の所属する事業所の名前だ。
玄関ドアを開けて、
「お疲れ様です。戻りましたー」
と言いながら、中に入って行くと、
「おかえりなさい」
と、どん突きの正面のデスクに座っている女性が、パソコンの横からひょこっと顔を出して澤に答えた。
彼女は“あさひ”の管理者である看護師の村田だ。
ちょうど良かった。澤は“ある出来事”について管理者に報告しなければならない。
「お疲れ様です。師長さん、ちょっといいですか?」
「いや、もう師長じゃないけど、どうしたの?」
村田は澤の元職場である病院の師長だった。
澤が新卒で就職してから10年間、同僚として働いており、後半の5年間は村田は病棟の師長をしていたので、澤は時々昔名残で「師長さん」と呼んでしまう。
「あ、すいません。つい相談事の時は師長って呼んでしまいます」
「師長時代、めっちゃ大変やってんから、思い出させんといてよ!」
笑いながら言う村田に、澤は敢えてめんどくさそうに、
「本題、言っていいっすか?」
と返した。
「どうぞ。土谷さんのことじゃない?」
図星だった。
「え?何で知ってるんですか?」
「ちょうどさっき、土谷さんの奥さんから電話があって。『主人が澤さんに申し訳ないことを言ったんやけど…』って。リハビリ、もういいって言われたの?」
「そうなんですよ。『もう良くならないからいいよ』的な感じで言われました。そりゃあ、土谷さんの言うこともわかるし、あの人、頑固というか自分で決めたらもうそれしかないじゃないですか?やから『分かりました。また、必要に感じたら看護師さんでもケアマネさんでもいいし、いつでも言ってください』とだけ言うて帰ってきました」
「まぁ、がん末(末期がんのこと)だしねぇ。最近しんどくなってきたみたいだし、リハビリで動くのもしんどくなってきたかなぁ?」
うーん、といった表情の村田に、澤は土谷さんの最近から今日の状況を話し始めた。
「今日訪問した時に『今日は少し疲れてるし、マッサージだけでいいわ』と言われたんです。でも、そもそも最近は車いすに乗り移った後でも息切れしてたし、現状はポータブルトイレに行けているから、それができているならリハビリで無理に負荷をかけなくていいと思って、マッサージと褥瘡ができないようポジショニングぐらいしかしてなかったんですよ。だから今日はリハビリの前に何か特別なことしたんかなって思って、『何かして疲れたんですか?』って聞き返したら『そんな日もあるやろ?病気やねんし』ってめっちゃ不機嫌そうに言われたんです。そっからしばらく無言で、いつも通りストレッチとマッサージして…で、最後に『今までありがとう。ただ自分はこれ以上良くなることはないし、もうリハビリは来なくていいよ』と言われました」
うん、うん、と村田は聞いてくれている。
「僕はまだ訪問で1年ちょっとしかしてないですけど、がん末の方でも、褥瘡ができないようなポジショニング考えたり、安楽になるようなマッサージしたり、まだ介入の余地はあるんじゃないかなって思ってたんです。それをちゃんと前もって説明できず、機能回復(筋力が上がったり、歩けるようになること。つまり、身体機能の回復)にしかリハビリの良さを感じてもらえなかったのは僕の実力不足です。すいません…」
「いやいや、別に謝ることじゃないし、澤くん真面目すぎるって!私はPTじゃないけど、そんなことよその事業所でもよくあることだと思うよ?」
「それもわかってるんですけどね。拒否されるって結構久しぶりのことだったので久々にズシっときただけです」
「まぁ、あなた病院のころからいろんな患者さんとうまく付き合ってたからね」
「そうですね。勝手に自信持ってました」
苦笑いしながら答える澤に、村田はこう言った。
「でも土谷さんの奥さんも言ってたけど、『澤さんにはホントに感謝してる。病院を退院してきて、家では車いす生活ですって言われて帰ってきたのに、歩行器で歩けるようにまでしてくれて、その上息子の家まで行けるようにしてくれたのは間違いなく澤さんがリハビリしてくれたから』って。私もそう思う。ただやっぱりね、がん末の痛さとかしんどさって相当きついんだと思うのよ。だからこれはただのタイミングです」
「そうですよね。どこかでそんな人にでも自分は何かできるって思ってたんやと思います。肩肘張らずに、これからも頑張ります」
「うん、そうして!そして記録書いてサッと帰る!うちみたいな極小事業所を残業の支払いで悩まさないでね」
「はーい」と言い、残りの記録を終えて澤は退勤した。
村田はすごく優しい看護師だというのは病院時代から知っていたし、終末期に携わりたいという熱い想いを持って起業したのも知っていたので、澤は転職先に“あさひ”を選んだのだが、今回の件で改めてここに就職して良かったと思えた。
しかし、土谷さんの件はまだ言い表しにくい“しこり”を胸に残したままだった。
この日の夜、澤は元同僚の理学療法士である井上と飲みに行く約束をしていた。
井上との約束は駅前に18時30分。澤は定時の18時に事業所を出たので、18時15分には駅前に着いた。
LINEを開いても井上からの連絡はまだなかったので、『駅前の本屋にいとく』とメッセージを送り、駅前の大型書店で時間を潰すことにした。
普段から読書が趣味の澤はよくこの本屋を訪れる。いつもは漫画、小説、自己啓発と、いろんな分野の棚を回るのだが、この日は医療・看護コーナーに直行した。
そして“終末期のリハビリテーション”とタイトルにある本に色々と手を伸ばしてみた。
パラパラと中身を確認すると、どの本にも同じようなことが書かれている。
終末期のリハビリテーションに求められるのは、
・身体的、精神的な痛みのケア
・安楽なポジショニングの提案
・安全・安楽な動作、介助の指導
・本人、家族のメンタルケア
だと。
ーそうそう。わかってるよ。それをしようと思ってたんだー
この知識は澤はすでに持ち合わせていた。しかし、土谷さんではそこに辿り着けなかった。
自分がしたかったことであろうが、相手から望まれなかったら意味がない。
知識が活かせる土俵に上がらなければ意味がない。
これがこの件に関して理屈でわかっていても、モヤモヤした感情が残る理由だった。
澤は、自分は土谷さんから信頼を得ていると思っていたから、拒否されるとは全く思っていなかったのだ。
実は土谷さんのリハビリにはとても手応えを感じていた。
土谷さんは元々肺がんを患っており、8ヶ月前に急に足に力が入らなくなりふらふらするからと病院を受診した。そこで脊髄の一部である“胸髄”に腫瘍があることを指摘された。
いわゆる転移性腫瘍である。その腫瘍が神経を圧迫して、足に力が入らなくなっていた。手術や化学療法、1日2回のリハビリを行ったが、腰から下に麻痺が残ったままであり、土谷さんが1人で歩けるようにはならなかった。
入院生活が3ヶ月経過した頃、肺がんの状態も小康状態であるため、家で過ごすなら今がラストチャンスだと医師に言われ、土谷さん夫婦は退院することを決意した。
しかし同時に、病院でもリハビリの時に歩行器にしがみついて歩くのがやっとであることから、家では車いす生活になること、介護用ベッドやポータブルトイレなどの介護用品が必須になることも伝えられた。
このような状態の人が退院後に混乱しないように、退院前には在宅療養を支えるチーム(訪問看護事業所やケアマネジャーなど)と病院スタッフ、そして本人と家族が一堂に会するカンファレンスというものが行われるのが基本だ。
土谷さんも例に漏れず、カンファレンスが行われ、澤と村田はそこに参加していた。
全体的な内容として在宅生活で必要な介護用品は何か、どのように過ごすのか、土谷さんや奥さんの生活のリズムや希望は何かというすり合わせが行われ、その後、澤は土谷さんの病院でのリハビリを村田とケアマネジャーの藤中さんという女性と一緒に見学した。
リハビリ全体を見学したわけではないが、澤は違和感を覚えていた。
ー足の筋トレだけしていきなり立って、歩く練習をするんや…?ー
胸髄に障害があるので、土谷さんは腹と腰から足にかけて麻痺が残っていた。足はどんな人でも腰から下に生えているので、腰がしっかりしないことには足に力は入りにくい。
澤はその場では何も言わなかったが、病院を後にしてから村田に「あの人、もうちょっと良くなるかもしれません」と伝えていた。
この澤の仮説は当たる事になる。
入院中は毎日リハビリをしていたが、退院後の訪問リハビリは週2回となる。頻度が減る上に病院のように平行棒などの大掛かりな物品があるわけではないので、身体機能の回復は訪問リハビリにはあまり見込まれないのが一般的だ。
求められるのは、自宅の生活環境と身体機能を合わせて評価し、安全かつ安心した生活を送れるようにすることである。
しかし、澤が体幹(腹筋や背筋)のトレーニングの方法を創意工夫しておこなったことで、土谷さんはみるみる動けるようになっていった。
土谷さん自身も手応えを感じてくると、
「退院したかったからポータブルトイレでもしゃあないと思って受け入れてたけど、こんなん普通は嫌やで!」
と言い出し、自宅のトイレを使いたいという希望が強まったことがリハビリの意欲を後押しする形となり、歩行器を使って奥さんの見守りで自宅のトイレまで歩いて行けるようになったのだ。
トイレだけでなく、食卓まで歩行器で歩き、そこで食事することも可能になったことで、車いすは外出専用とした。
そして、その車いすを利用して、介護タクシーと新幹線に乗って、県外にある息子さんの家まで遊びに行くこともできた。
そう。土谷さんは自身や奥さんの希望や退院時の想定を大きく超えて良くなっていったのだ。
そこには間違いなく、澤の貢献がある。
時期にしておよそ3ヶ月ほど前のことであった。
ーこれだけやって、終末期まで寄り添えられないなら、本当にしょうがなかったんやろうなー
当時を振り返りながらそう思ったところで、ポケットのスマホが震えた。
井上からの着信だ。
「ごめん、今着いた」
「オッケー。今から出るわ。本屋の出口におって」
そう伝えて、澤は本屋の出口に向かった。
出口を出てすぐに、
「おう!」
と、井上に声をかけられた。
「久しぶりやな。で、どこ行く?」
会って話さえできればいいので、店はどこでもよかった2人は、すぐそばにある焼き鳥チェーン店へ入った。
「とりあえず、生2つ。あと枝豆と焼き鳥の盛り合わせ」
最初のオーダーを店員に伝えると、2人はお互いの近況を話した。
澤たちが就職した頃、同期にはPTとOT(作業療法士)合わせて5名いたが、昨年澤が退職したことで、今は井上ただ1人になっていた。
「澤が辞めて初めてよな、2人で会うの?」
「そやで。1回勉強会であったけど、あん時は飲みに行かんと帰ったしな」
「どうなん?村田社長は元気?」
村田社長とは、もちろん管理者の村田さんのことだ。
「元気やで。やっぱあの人はええ人やわ。俺が知ってる限りやけど、ケアマネさんのウケも良さそうやし、事業所の規模の割には地域で存在感ありそうやもん」
「まぁ、できる人はどこ行っても…やな。訪問自体はどうなん?そろそろ急性期が恋しくない?」
井上の意地悪な質問が出たところで、ちょうどビールと枝豆が運ばれてきた。乾杯をしてその質問に澤が答える。
「まぁ、たまに恋しくなるな。でも、訪問したかったし、訪問先ではその場でアセスメントしたり、異変を1番に発見するってこともあるから、急性期の経験って活きてるよ」
「後輩らも言ってたで。『澤さんは術後急性期しか興味なさそうな感じやったのに』って」
「それはアレや。俺のごく一部しか見てへんからやて。そっち系の学会発表とかしてたからやろ?病院におる限りは、やっぱ急性期を見るわけやからそこの勉強するのが当然やし。でも俺は元々地域リハがしたかってんから」
澤の元職場、つまり井上の働く病院は、この辺りで最も病床数の多い急性期病院である。その上、3次救急指定の病院なので、超がつくほど重症な患者も多く運ばれてくる。
澤も井上も、経験が10年を超えており、リハビリテーション課の中ではベテランの域に差し掛かる年齢であったため、より重症な患者を多く担当していた。
そのため、澤が辞めた時は看護師たちに『大変な人ばかり担当してしんどかったんでしょ?』と言われたが、本人にその感覚は全くなかった。
「真面目な話、退院した人がどう生活してるかも知りたかったし、何回も心不全で運ばれてくる人なんかは在宅の管理で予防できる部分もあるやろうなって思っててん。ただ、在宅って理屈でわかっててもうまくいかんこともいっぱいあるやろから、そういうとこが面白そうやなぁとはずっと思ってたよ」
「ふーん。俺、あんまり興味わかへんねんなぁ。うちの病院でも訪問リハ立ち上げたん知ってるやろ?そこに所属してるPT、あ、お前の知らん人やわ。入れ違いで入った中途採用の人やから。その人とちょっと話しててんけど、ケアマネさんとの関係性とか、いろんな人巻き込んでどう支援していくかとか、そういうとこが大事なんですって言ってて。そらわかるねんけど、俺はなんか勘弁やなぁって思ったわ」
笑いながら井上がぶっちゃける。
「井上はあんまり向かん気がする。俺はお前と違って、平和主義やん?ケアマネとかともうまいことやるで。ただ、今日初めて利用者に拒否られたわ」
その利用者とは、もちろん土谷さんのことである。
「まぁ、そら拒否られることもあるやろ?」
「うん、まぁそうやねんけどな。ただその人に拒否られるのは1番意外やってん」
個人情報は話せない中、澤は「病状を考慮して訪問でも工夫して負荷をかけたリハビリをおこなったことで、退院時の予後予測より大きく上回ったパフォーマンスを獲得できた利用者」ということがわかるように伝えた。
そして、
「まぁ、そこまで結果は出しても、どこかで頭打ちになって『これ以上良くならんからいい』って言われんねんな。病気や老化があって一生元気になっていくわけじゃないから、それもわかるんやけどさ」
と、付け加えた。
それを聞いて井上は、
「何も気にすることないんちゃうん?」
と、言った。
「いや、俺も他人がそれ言ってきたらそう答えてるわ。でも、自分のこととなるとなぁ。訪問って終末期に差し掛かる人も多いし、その場合これから大変な時期迎えるのにそこを担当できひんてことがなんか引っかかって…」
「まぁ、リハは万能じゃないしなぁ。でもさ…」
井上はグラスに半分ぐらい残ったビールを一気に飲み干して澤に続きを言った。
「俺は、お前のしてたリハビリええと思うし、さっき話したうちの訪問のPTの話より、その人にしてた訪問リハの話の方が面白いなぁ。やっぱ急性期やろうが在宅やろうが、基本は身体機能の向上やろ?それが叶わん部分をヒトやモノいろんなことで補うのはいいけど、最初から身体機能から目を離してる訪問のPTって多いんと違うかなって勝手に思っててさ」
「それは何となくわかる。俺も井上みたいに考えてるとこあるもん。まぁ、“あさひ”にはリハは俺だけしかおらんし、比較できひんけど。結局大事なのは引き出しの多さよな。身体機能をガンガン上げるリハビリしかできないと、訪問では苦しいやろし。家族やケアマネとの関係性を大事にするとか、話をしっかり聞くとか。まぁそういうハイブリッドなことができるPTでいたいわけよ、俺は」
「ハイブリッドて車みたいやな。ジェネラリストってことやろ?」
「まぁ、そうとも言う」
「で?何の話やっけ?」
「俺が利用者に拒否られた話や」
「あー。いや、もうそれはしょうがない!それ以外ないやろ?クヨクヨせんでいいやつやん?」
「多分やで?俺、井上と話して思ってんけど、ジェネラリストとか言いながら、だいぶ身体機能面のリハビリに寄りすぎてた気がするわ。もちろんそれが大事な時期っていうこともあってんけど、しんどい時とかはマッサージだけして終わったりしてたし。なんか病院でリハ拒否られたら、何とかその場でマッサージだけでもみたいに粘って、患者の気持ちを乗せたところで離床させるみたいなんあるやん?あれの名残りがあった気がする」
「それ、今日も俺してたやつや」
病院のリハビリあるあるに井上は笑いながら答えた。
「やろ?ただ、この人に関してはもうちょっとしんどい理由とか、家族に話聞くとか、いろんなことできたような気がするわ」
「真面目だねぇ」
と、井上が茶化したとこで、真面目な話は一旦終えたのだが、澤は井上と話せたことで、土谷さんへの関わりを振り返ることができたので、気持ちが少し落ち着いた。
その後2人は、病院時代の同僚の現在の話や、お互いの家族の話などで、23時の閉店間際まで過ごしたのだった。
第2話へ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
