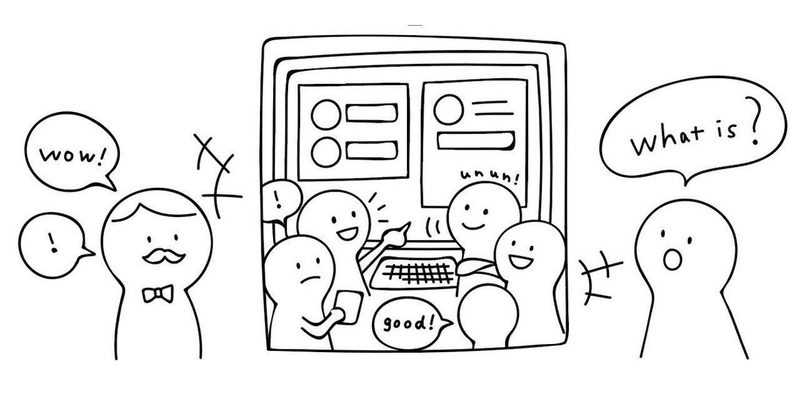
入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ⑨ ~議事録を書くポイント その2~
こんにちは、茶っプリン@中小企業診断士試験合格者 です。
寒かった冬もようやく終わりに近づきましたね。
私は春に生まれたので、やっぱり春が一番好き。花粉症には悩まされますが、それでもこの春のワクワク感はたまりません。世界情勢は非常に混沌としていますが、季節の移り変わりとともに雪解けになってほしいものです。
■前回のおさらい
さて、前回に続いて、議事録のお話をしたいと思います。前回のおさらいをしておきましょうね。
議事録を書くときの大事なポイント
議事録で重要なのは「必要な時に、パッと見てパッと確認できること」
発言や決定したことの一番大事なところを、短い文章で記録する
次にどういう行動をすれば良いのかを明確にする
これを踏まえれば、議事録は簡単に書けますよ、というお話をしました。では、どうやって書けば良いか、具体的に見て行きましょう。
■「正しい行動につなげるためのポイント」を記録する
議事録を作る目的を言い換えると、「正しい行動につなげるためのポイント」を記録することだと思います。例えば、こんな感じです。
どういう内容で方向性を決めたか?
今回決めきれず、次回に持ち越しになったのは何か?
次にどんな行動をするか?
決めたことがきちんと実行されているか?
要は、「みんなが共通のゴールに向かって行くために、認識の違いや行動の抜け漏れが発生しないように、記録しておきましょう」ということなのですね。
■議事録を書くポイント
それを踏まえて、議事録を書くポイントをまとめると、以下の5点に集約されます。
(1) 議事録はA4で3枚以内に。見た目を美しく。文章は「である」調で。
打合せの密度の濃さにもよりますが、だいたい3枚以内に収まります。1枚半〜2枚半くらいがちょうど良い。それ以上だと、「パッと見てパッと確認」できません。
また、一文はできるだけ短くし、文字で埋め尽くさないこと。見出しやフォント、太字、下線などを駆使して、見た目を美しくし、「後から思わず読み返したくなる議事録」を目指しましょう。
たまに、「ですます」調と「である」調を混ぜこぜにする人がいます。「ですます」調は文章が長くなるし、混ぜると読みにくいので、「である」調に統一し、できるだけ体言止めを心がけます。
(2) 5W1H (誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)で簡潔にまとめる
よく「要点をまとめてね」と言うと、必要な部分まで省いてしまう人がいます。5W1Hを意識すると、大事な点を外しにくくなります。「なぜ(Why)」は、「目的」「ねらい」と読み替えると、わかりやすいでしょう。
(3) 質疑応答は、質問・回答とも、 1行ずつに凝縮する
要約力が問われ、一番難しい部分ですが、「一言で表すとどうなるか」を常に意識し、数をこなせばできるようになります。次の例を参考にしてみてください。趣旨は変わらないし、意味も通じます。それでいて、字数は3分の1です。
<例>
【実際の発言】
今の報告を聞いている限り、新規の顧客開拓が想定より遅れているようだが、どのように挽回していくつもりなのか?(53字)
【議事録への書き方】
新規顧客開拓の遅れに対する挽回策は?(18字)
(4) 結論を書く
これ大事ですねぇ。
営業会議などでは、報告された数字だけ書いて終わり、という議事録もよく見かけます。それだと、次の行動につながりません。
少なくとも、営業が順調なのか不調なのか、不調なら原因の分析や対策などの話が、必ず出ているはずです。それを聞き漏らさないようにして、しっかり記録しましょう。
(5) 次のアクションと、「誰が」「いつまでに」行うのかを書く
これも大事で、議事録の一番のポイントと言っても良いでしょう。打合せのたびに、同じ報告がなされて、いつまでも次のアクションにつながらない、ということは、どの会社でもあるあるです。反対に、これをしっかり記録しておき、次回の打合せで確認する習慣をつければ、会社は劇的に変わって行くと思います。
■議事録に盛り込む内容と、ちょっとしたコツ
お話ししたポイントを踏まえて、議事録に盛り込む内容を整理してみましょう。
<議事録に盛り込む内容>
・打合せ日時、場所
・出席者、欠席者、議事進行者、議事録作成者
・議題
・議題の要点
・結論
・質疑応答
・今後のアクション、「誰が」「いつまでに」行うのか
<ちょっとしたコツ>
打合せのときに「後で確認します」と言って、終了後すぐに調べて、電話やメールで回答があったようなケース。律儀な人になると、「終わった後にわかったことは、打合せの議事録に入れちゃいけないんだ」とか考えて、回答した内容を書かない人も多いんですね。
でも、「次にどんな行動をすれば良いか、明確にする」という目的を考えれば、議事録に注釈を入れた方が親切ということがわかります。
そういうときは、以下のような注釈を入れることをオススメします。
<例>
【結論】打合せ終了後、A氏が状況確認して回答する。
※終了後、A氏より回答あり。「2月20日に顧客稟議終了。現在、発注書の受領待ち。3月20日までに受領予定」。
■議事録作成後は、関係者の間で確認を!
最後に、取引先や他部署と打ち合わせしたときの議事録は、作成後に双方で確認し合うのも大事です。会社によっては、確認印やサインを求めるところもあります。そうすると、認識の齟齬があったとしても、「あのときの話は、こういうことだったよね?」と文書で確認することができます。
議事録を双方で確認していないと、「そんな話だったっけ?」とか「そんなことは言ってない」と、後々揉め事になる場合もあります。それを防ぐために、「議事録を作ったら、関係者に確認を求めて、できれば承諾の意思表示をもらう」ということを意識しましょう。メールで送って、承諾の旨の返信をもらうのも良いですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
