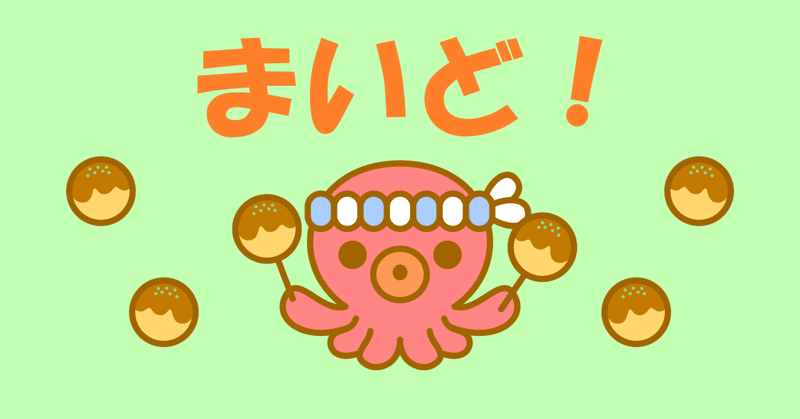
Photo by
yo_yo_create
たこ焼き学(エッセイ#4)
何を隠そう、たこ焼きが好きだ。
カリッとした表面。ふわっとした中身、弾力に満ちた歯ごたえ。
こんにゃくを入れるだとか、明石焼きのように潔く中身を抜いてしまうだとか。様々なバリエーションがあるが、もちろん全て邪道である。愛すべきはシンプルなたこ焼きただ一つ。世の中に通用するのはシンプルなたこ焼きただ一つきり。
これをたこ焼き本位制と言う。他のものはたこ焼きに対するレートが設定されているだけで、うたかたの存在である。
そうまで言い切る私だが、食べる専門で、作るほうはからきしダメだ。
ところが、関西の家庭の常として、家でたこ焼きを作る機会が多々ある。
父も母も実にうまく焼く。たこ焼きピックがロンドを踊るように舞い、たこ焼きもそれにリードされくるくると回転する。真球に近づくにつれ、たこ焼きたちの幸せなじゅうじゅうという声が聞こえてくる。
長年の経験があの手際を作っていると思うだろう。
しかし、そうではない。あれはセンスなのだ。きっと。
この私だって、幼少期から数えれば二十年ピックを握っている。
ところがどっこい、私のたこ焼きはビギナのロボットダンスのようにぎこちなく震え狂い、最終的にそろばんの玉のような形に落ち着けば御の字で、半分以上はただれたパックマンのように無様な口をあけた状態で生れ落ちるのだ。
これをセンス以外の言葉で説明できる人がいるのだろうか?(いたとしても、私には伝えないでもらいたい。例えば「不器用なだけ」とか)
強がりの言い訳ではないが、タネは母が作ったしっかりしたものなので、真球だろうがそろばん玉だろうが、味はさほど変わりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
