
金星とロビンソン
夢を見た。
重い耐熱スーツを身につけ、硬い地表を掘り起こしている。スーツの中は熱い。ヘルメットは曇っている。
汗は目頭のそばを通り、鼻の横を通り、口の端を通り過ぎる。
流れる汗をそのままに、黙々とつるはしをふるっている。夢の中で男は、淡々とふるっている。
いや、これは記憶だ。
カワシマの遠い記憶。炭鉱夫だったときの、記憶。
「……うーん」
右頬に貼り付いたしびれを感じながら、カウンターに伏した顔を上げた。 針時計は3時を指していて、窓の外では人口太陽がうららかな昼下がりを演出している。どうやら一時間ほど眠っていたらしい、とカワシマは思った。
「おや、起きたのかい?」
むくりと上体を起こし、声の主に目をやる。サトウはお湯を沸かしているところだった。あくびをしながら腕をぐっと伸ばすと、広い肩幅にTシャツが貼り付く。眠気で頭ははっきりしない。
「悪い、寝てたようだ。客は来たか?」
カワシマの様子を見ていたサトウは苦笑いを一つ浮かべた。
「いいや、暇だから店を閉めといたんだよ」
気が利くところと気の合うところが気に入って、カフェを始める際に一緒に連れてきた。歳が3つほどしか違わないということもあり、兄弟のような仲である。
「ハーブティーはいかがかな」
「もらうとしよう」
「サトウは?」
「ああ、シュガーを一つ」
サトウは奥歯に力を入れて無表情を装っているが、目が笑っている。カワシマは不機嫌に横目で見る。
「なんだよ」
「なんでもないよ」
笑いをこらえながら紅茶の準備をするサトウに、カワシマはふてくされて窓の外を眺める。そして先ほどの夢の続きでも追うように、機械仕掛けの日差しに目を細めた。
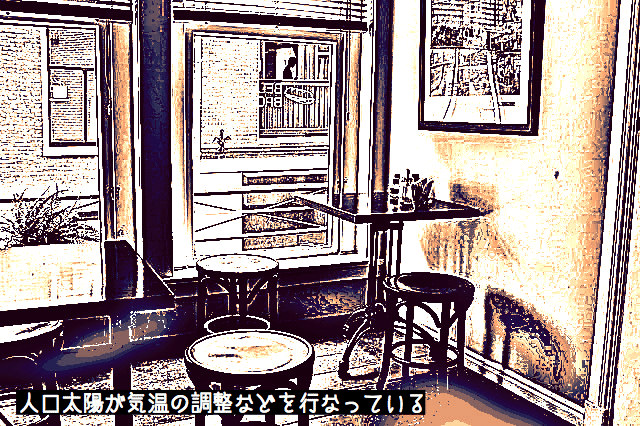
今日も味気ない一日が終わった。採掘の仕事が終わった後は床に就くか、“ウロコの残り火”がひどいときは人気のない倉庫で本を読む。とはいっても、保存状態はかなり悪く、やっと最近タイトルの『ロビンソン・・・・・・冒険』という文字を解読できたくらいである。木箱にもたれ、ページに目を落とす。薄く乾いた音がひびく。背中がひんやりと気持ちいい。
「あれ、もしかして小説を読んでいるのかい?」
思わず肩が跳ね、息を飲んだ。痛いほど心臓が早鐘を打つ。熱がこもっていたはずの体から一気に血の気が引き、冷たいしずくが背中を伝う。意識が遠のいていくのを、カワシマは感じた。
「びっくりさせてすまない。別に、取り上げようなんて思ってないさ」
童顔を困ったようにしかめた男は、水筒とフチが欠けたカップ二つを手に持っている。落ち着きを取り戻したカワシマは、やっと彼が誰だかわかった。
「なんだ、サトウか」
入ってきたので、木箱をずらして席を作ってやる。金星に不時着した彼を、仕事中に見かけてこの宇宙船に連れてきたのが2カ月前。それから一緒に働いている。サトウは唯一、カワシマが共に昼食をとる炭鉱夫であった。
「“ウロコの残り火”に、ハーブティーはいかがかな? ここは肌寒いし、体調をくずしちゃうよ」
体内に熱がこもって寝付けないことを“ウロコの残り火“と呼んでいる理由は、この船の人間が金星の地表で採れる“女神のウロコ”と呼ばれる鉄鉱石を採掘しているからだ。
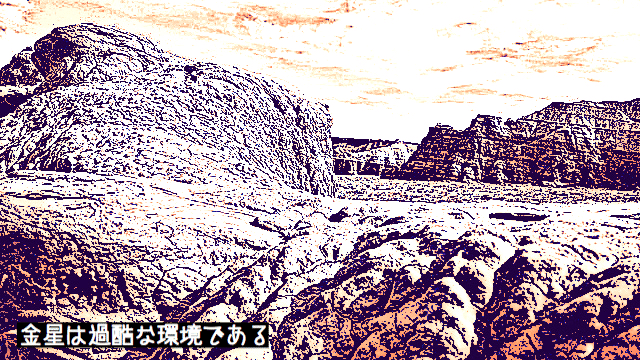
「すまない、一つもらおう」
テーブル代わりに用意した樽の上のカップを手に取り、口をつける。それからぐいっとあおった。ほどよく冷ましたハーブティーがのどをさわやかに流れ、気持ちがいい。サトウがおかわりを聞くように水筒を持ち上げて、振って見せる。
「もう一杯もらいたい」
「どうぞ、サトウはいかがかな」
「……その手にはのらないぞ」
この前、昼食のとき「砂糖を一つ」と答えると指を入れられたのだ。それからカワシマは警戒するようになった。
「シュガーを一つ」
サトウは口元を押さえて背中を震わせている。カワシマは水筒を取り上げ、自分の分を注いでから角砂糖を一つ落とす。それから口を結んだままサトウのカップにも注いだ。
「そうだ、今日はこれを見せたくて探したんだよ」
サトウはポケットの中からコードやら何やらを取り出し、樽の上に置いた。おんぼろの四角い機械が、蛍光灯の光を鈍く受けている。
「おい、それって」
「そう、ミュージック。空賊から買ったのさ」
空賊というミュージックを密売している組織の人間がいる、ということはカワシマも知っている。が、会ったことはない。当然、ミュージックも聞いたことがないし、耳から快楽を入れるということがどんな感覚か、わからなかった。
「おい、聞かれたらどうするんだ。アート法に引っかかるぞ」
「じゃあ、しまおうか?」
不敵な笑みを浮かべているサトウをにらみ、奥歯を噛みしめた。言ったもののカワシマの目はプレーヤーに釘付けである。ミュージックとはどんなものか、一度は試してみたいと思っていた、というのが本音だ。
「……わかったよ。誰も来やしない」
「そう来なくっちゃ」
サトウは勝ち誇ったように言うと、さっそく準備に取り掛かった。コードに不備がないかくまなく確認し、プレーヤーに慎重に挿しこんでいる。
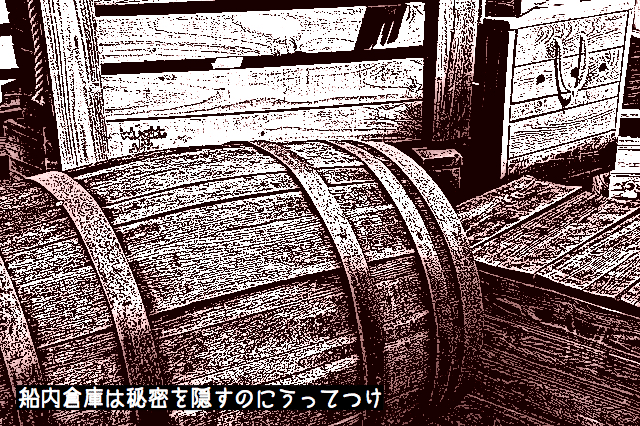
「で、どんなミュージックなんだ?」
興味津々のカワシマに、サトウは答える代わりに再生ボタンを押した。
「静かに。聞けばわかるよ」
沈黙。
数秒の間があり、機械音。
それから流れ出す、初めてのミュージック。
無機質な倉庫内に彩りを与えられたかのようで、二人がいる空間だけ別世界だった。
はっとした。サトウみたいだなと思った。
そこにハーブティーに似たさわやかさと、体感したことのない優しさがあった。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ミュージックが終わった後、カワシマは秘めていたものを打ち明けたくなった。
「実はずっと考えていたことがあって……カフェをやりたいんだ」
今、希望というものに、気持ちが高ぶっている。なぜ金星で炭鉱夫をやっているのか、思い出した。開業資金をためるために、夢を追いかけるために地球を出たのだ。
「いいじゃない。面白そう」
サトウは穏やかにうなずく。プレーヤーが止まった後も、余韻は残っている。
「不思議な符合だな。金星で出会って、こんな風に夢を語っている。そしてこのミュージックの名前がロビンソン」
サトウはくすくすと笑っている。サトウはカップに口をつけると、好奇心旺盛そうに目を向けた。
「ところで、”ルーララ”とは一体何だろうね?」
出し抜けの質問に、カワシマは思わずあごに手を当て、考え込む。それからひらめいたように眉を上げた。
「さあな。でも、カフェの名前にはうってつけじゃないか」
パズルのピースが気持ちよくはまった時みたいに、それはしっくり来た。同時に“ルーララ”というカフェには何が必要なのかも、すぐにわかった。カワシマは真っ直ぐ前を見た。
「それには、”サトウ”が必要なんだよ」
目が合う。サトウの茶色の瞳は明るい。頬に赤みが射したところではたと気付き、カワシマは目をそらした。サトウは涙目でにらむ。そしていたずらっぽく笑うと、カワシマのカップに指を突っ込んだ。
二人でカフェを開こうと決めた、夜のことである。
作中に出てきた楽曲
スピッツ「ロビンソン」
お金が入っていないうちに前言撤回!! ごめん!! 考え中!!
