
【子育てコーチング】子どもに●●して欲しいとき
パパママ子育て真っ最中の方へ。
わたしもその一人です。
コーチングやらパーソナルコンサルタントの専門スキルを得て仕事をしていても、我が子への対応は、簡単ではありません。
愛情が深いから、幸せになってほしいと心底、願うから、
こうしろ、ああしろ、今こそこれをやった方がいい!と
気づくと自分「正義の押し付け」オンパレード!
先日、人材育成のプロの講義を聞きました。
その中で、印象に残ることがあったので書いてみます。
子どもに●●して欲しいときの伝え方
ポイント① 命令・統制は百害あって一利なし
「●●しなさい」
「できなかったら◯◯を取り上げます!」
「今度、同じ悪さをしたら▲▲するよ」
子どもの内側から「やろうかなあ」「やってもいいかなあ」という気持ちをいかに引き出せるかが親としての腕の見せどころ。
上記のような「命令・統制」による働きかけは、子どもの内面からのモチベーションの誘発には、思いっきり逆行します💦
恐怖政治、罰則による統制は、短期的には効果が出ることもありますが、効果は続かない。
それ以上に、恐怖政治がヤバいのは、
「考えなくなる」
「表面的に合わせておけば嵐が過ぎる」という成功体験を
子どもに積ませてしまうことです。
大人になっても、そんな習慣がついてしまっている人を、結構、見かけませんか。仕事の場面で
「なぜそのままやっちゃったの?」
ー部長に指示されたので。
「そんな表面的な作業でOKだと思ったの?」
ーまあ一応、やったので。
おいおい、、、ということになりかねません。
恐怖政治によって、取り急ぎ現状を改善させるよりも、
時間がかかっても内発的な動機によってやろうと思う気持ちが出てくるのを待つ方が、親にも子どもにも、実は幸福な選択だと思います。
確かに、短期的な成果が出ても、徐々に効き目がなくなる。
表面的に従ってもらいたいわけじゃない。子育てしていると、そんな経験は山ほどありますよね。
ちなみに「目先の利益で釣る」のもこれと同じで
リスクが高く長期的には悪影響の可能性大。幸せに繋がりにくいと言われています。
ポイント② 他者思考
では、どうすればいいのか?
講義の中で印象に残ったのは【他者思考】のGiverであれという言葉です。
Giverとは、Takerに対する言葉。
Giver=人のために与える人。相手の利を優先してそのために行動する人。
Takerはその反対で、自分の利のために人を利用したり人から搾取しようとする人です。
Giverは一歩まちがえると、Takerの”食いモノ”にされます。
それが長期間続くと、燃え尽きるGiverがいたり、
ある日、堪忍袋の緒が切れてブチ切れ爆発するGiverも現れます。(これも一種の”燃え尽き”です)
人にポジティブな影響を最も与えられるのは、
『他者思考のGiver』だというのです。
どういうことか?
”燃え尽きるGiver”は、相手に与えよう、相手の期待に応えようとする中で、【相手の気持ち】にフォーカスして対応する。
一方、”他者思考Giver”は、相手のために動くことを是とするのは同じだが、相手の気持ちではなく【相手の思考】にフォーカスして対応する。
ん?
まだよくわからないですよね。
具体的な例を挙げてみます。

事例:計算ドリルの宿題をやらずにTVを見まくっている子どもに、親としてどう関わるか?
燃え尽きGiverの関わり方
「やりたくない」気持ちにフォーカスして相手のために行動する
▶︎ やりたくない気持ちに寄り添って同化してしまう
分かるよ、、、わたしも宿題、嫌いだったよ
▶︎ やりたくないものはやりたくないだろうと理解する
▶︎ とはいえ看過するわけにはいかない(見栄?メンツ?躾の責任感?子どものため?)と考える
▶︎ ママと一緒にやろう!とリードする
▶︎ 好物のお菓子をご褒美に用意して釣る(命令・統制と同じ)
一緒にやろう!という呼びかけに応じて、子どもがどうにか机に向かったとしても、ここに主体性はありませんね。
きっと、10分もしないうちに、
「ちゃんと問題読んでるの?!」
「あー、もっとキレイな文字で書きなさい!」
と消しゴムを片手にと叱りつけてしまい、子どもは泣くという展開になって、親も凹む。
親子の関係にもガサガサした傷がついてしまうのがオチですよね。
他者思考Giverの関わり方
「やりたくない思考」にフォーカスして相手のために行動する
「やりたくない」子どもをみたら、
何らかの考えが背景にあって、やりたくない気持ちに陥っていると考えます。
そこで出てくるのが質問です。
▶︎ テレビ、おもしろい?どんな話?
▶︎ 宿題、いつ頃やるの?
▶︎ 正直、やりたくないの?
▶︎ なんでだろう?
▶︎ 何が変わったら、やる気が出そう?
相手の思考の流れを探ります。
そもそも学校が面白くないのか、
勉強がつまらないのか、
分からないからつまらないのか、先生がキライなのか、
前に出て解いたときにミスして恥ずかしい思いをしたのか、
聞いてみないとわかりません。
もしかしたら、テレビがめちゃくちゃ好きなのかも。
強い興味関心が見つかれば、しめたものです。
また「邪魔するもの」がわかったらこれも大収穫。
子どもの「思考」をつかんで、
① 恐怖や嫌悪を取り除くために何かできることはないか、と考えたり、
② 興味関心の高いこととつなげるために何かできることはないか、と考えたりする。
これが、相手の思考に寄り添うアプローチです。
ポイント③ 考える力を刺激する関わり方
極論に聞こえるかもしれませんが、
実は、子どもの人生を考えた時、今、ここですぐに
宿題の計算ドリルをやるか、やらないかはどっちでもいいかもと思いませんか。
やりたくない!
という強い気持ちがあるなら、糸口はゲットしたようなものです。
裏側に、自分がなぜやりたくないのか?
自分の中にある気持ちを感じる力や、それを言葉にして他者に伝える力を伸ばす貴重な機会です。
怠惰やただのルーズでやらない、という自分に気づいたら、
僕はこのままルーズに暮らしていきたいのかな。それでいいのかな。
宿題をきちんとやっていく=ガリ勉=格好わるいという価値観を持っているなら、そう思うようになった背景にどんな体験があったのかな。
誰かの影響かな、誰かをみた時にわたしは何かを感じたのかな。
無条件に「先生が言ったからやるものでしょ」というタイプより、
やらない、やる、自分はこう思うから、と思考している子の方が面白い!
なんてわたしは思います。
幼くても、言語表現力が乏しくても、何でだろ?自分はどう思っているのかな?と思考することをスタートできる、良いきっかけになるかもしれません。
やらないと、ロクな大人にならない!
小学校の算数で躓(つまず)いたら将来、本当に苦労する!
という気持ちは、親の愛情ゆえのこと。
本当によくわかります。
でも、思考に寄り添うとき、親の邪魔になるのは、
「自分の正義で思う”着地点”に誘導しようとする気持ち」です。
ここは一つ、えいっと腹を据えて、
親の正義を一旦、脇におき、
愛する我が子のなかでどんな思考が起きているのか
ニュートラルな探検家の気持ちで、探ってみませんか。
遠回りに見えて、そのほうが、子どもと自分、優劣のない一つの人格として信頼関係を作っていくための近道かもしれません。
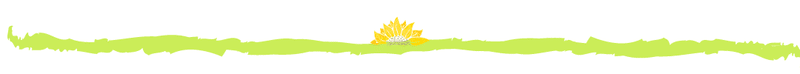
大澤 弘子
日テレHR代表/人材育成事業
サラリーマン応援📣ライフコーチ
キャリアビルディング【大人のための自分さがし】パーソナルコンサル
パパママ・上司・先生に伝えたいコーチングのスキル
詳細は、messengerでご相談ください。
なかなかの男性社会で30年働いてきたテレビマンが、コーチングやカウンセリングで「自分らしく生きる」を支援中。限定少数しか出来ませんが小学生からシニアまで。
