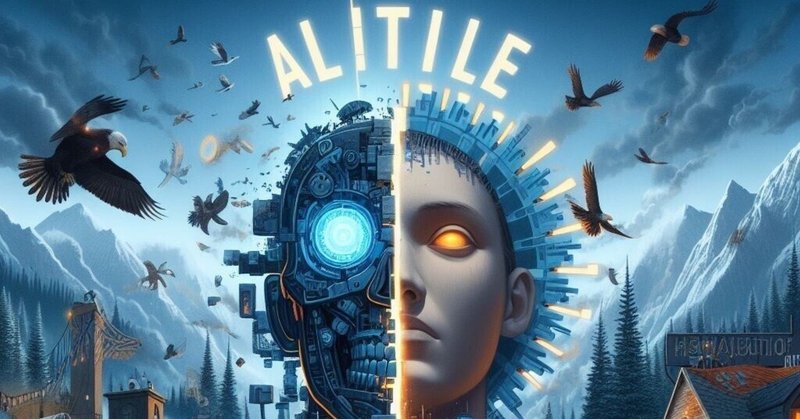
有害性をもつ自由
ビッグフォレストはその名の通り森に囲まれた街で、広さは大したことがないものの、入り組んだ道路で訪れる者を迷わせていた。迷わずに済む唯一の道は、高校に面した大通りくらいのものだった。
リチャード・グレゴール・ピーター・テイラーは、その高校に通っていた。彼はユーモアのセンスはなく目立つタイプでもなかったが、調べ物が好きなので、課題に悩むクラスメイトをよく助けていた。
彼を贔屓にするクラスメイトは口を揃えてこう言った——助けてチャットGPT!
「おいチャット、元気か?」
食堂で肩を叩かれたチャットは物思いから覚めた。振り返るとクラスのお調子者がいた。もう十月だというのに、半袖から日焼けした腕を覗かせている。
「元気だよエイドリアン。ただ考え込んじゃってさ。エミリー先生のことを」
これにはエイドリアンも顔を曇らせた。
エミリー先生は国語の教師だった。彼女は半年前から表情が暗くなり、とうとう先週の火曜日に自宅のベランダから飛び降りた。幸い木に引っかかり骨折で済んだが、彼女の授業を受けていた生徒たちにとって、これは気まずい話題だった。
「SNSの誹謗中傷が原因だっけ」
給食のトレイをテーブルに乗せながら、エイドリアンは言った。
「あまり考えても仕方ないんじゃないか」
チャットは首をふった。
「いや、考えなきゃだめだ。休み時間に先生の悪口が聞こえても僕は止めなかった。同じ教室にいたのに」
エイドリアンは肩をすくめ、皿に盛られたフライドチキンに手を伸ばした。
「確かに俺らはよく先生の悪口で盛り上がったけど、ネットに書き込んだやつはほんの一握りだろ?」
「場所や人数の問題なの?」
「仲間内で愚痴を零すことまで悪だって言われちゃ、やってられないよ。先生が助かってよかったけど、いまも嫌いな気持ちはある。そう感じることを悪いとは思わない」
チャットは自分のサラダをフォークでつつきながら、チキンに齧りつくエイドリアンを盗み見た。彼はいつも伝えにくい複雑な気持ちを大胆に言い切り、嫌味を感じさせない。要するに簡潔に表現するのが上手いのだ。それでいて誤解されることが少ないのは、普段の彼の明るさゆえだろう。そうチャットは思った。
「どう言えばいいか分かんないけどさ。先生を追い詰めたのは悪口そのものじゃなくて、人に嫌われてるっていう事実だと思う。相手を理解しようとせずに悪い部分をあげつらう態度がどれだけ暴力的か、僕らはもっと考えるべきじゃないかな」
二人の間に束の間、沈黙が降りた。
「言いたいことはわかる。けどさ、人を一方的に嫌うのが暴力なら、好きなことを感じる自由はどうなるんだ? 心のなかを規制するのも暴力なんじゃないか」
「そうかもしれない」
「この街にも思考警察が必要かもな」
重い空気を払い除けるように、エイドリアンはにやりとした。チャットも頬を緩めた。
「僕らみんな、蒸発しちゃうね」
二人が話しているのはつい十数分前、社会科の授業で紹介されたディストピア小説だった。作中ではビッグ・ブラザーという指導者をシンボルに誰もが党の思想に熱狂し、互いに見張り合う。人々はテレスクリーンという装置により日常的に監視され、党の思想に疑問を持つことも許されない。「思考犯罪」を犯した者はひっそりと連れ去られる。
エイドリアンのユーモアに救われながらも、その例えは大袈裟だとチャットは思った。人は常日頃から無意識に、自分の心を善悪で裁いている。だから後ろめたさを感じ、人の目を気にする。エイドリアンの意見に従えば、良心を待っている時点で、精神的に自由ではないことになってしまう。
「それ、急いで食べろよ」
視線を落とすと、半分ほど残ったサラダと手つかずのツナサンドがあった。食堂はすでに移動する生徒でざわつき始めている。慌てて口内に弁当を詰め込むチャットに、エイドリアンは悪戯っぽく笑いかけた。
「トイレにはテレスクリーンを設置しないでくれよ、ビッグ・ブラザー」
じゃあ、と軽く手を挙げて立ち去るエイドリアンの背中は、あっという間に人混みに呑まれて見えなくなった。

画像:Microsoft Copilot(AI生成)
※本作はジョージ・オーウェル氏の『1984』をオマージュしたSNS「DYSTOPIA」の二次創作であり、半周年記念作品として公開しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
