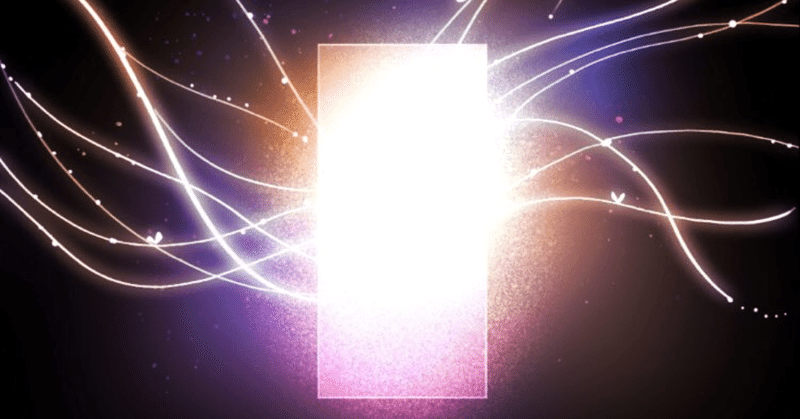
ノモリクオノミカ⑤【連載小説】
ぼくは息を切らしながら、ライトセイバーを腰のさやに納めた。すると足元に粉々になって散らばる氷の鏡のかけらが、オレンジ色に光り始めた。かけらの周りの雪がしゅうしゅう音を立てて白い湯気を噴き出す。生暖かい水蒸気が空気中にたちこめた。
「なにこれ、雪が溶けてるの!?」
溶ける音にまぎれて、ナオの声が聞こえる。白い湯気の中でみんなを見失いそうになって、ぼくは大声を張り上げた。
「みんな無事?姿が見えない……隣のひとと手を繋いで!」
右隣にいたダレカの羽根の先の方を握った。左を見るとモモが後ろ足で立ち上がって、肉球がついた小さな手を伸ばしている。ぼくはその柔らかな手をそっと掴んだ。モモの背中にカメレオンがしがみついているのが見えた。
勢いよく噴き出す湯気はどんどん周囲に広がって、雪は透明な水になり、足元の雪の下から黒い土が現れた。水溜まりは土にみるみる吸い込まれてゆく。湯気にさえぎられて見えにくいけれど、土はぼくらの足元を起点にしてどんどん周囲に広がっているみたいだ。そして土を覆うように緑の草が伸び始めた。
「凄い、どんどん伸びてく。早送りを見てるみたい」
サキが興奮しながら尻尾をぶんぶん振っている姿が見えてきた。両隣にはナオとリョウがいる。全員いるみたいだな、と胸を撫で下ろした。
草が伸びた所の湯気が薄くなり、視界が広がってきた。雪を押しのけるように周囲に広がる土の範囲は、いまや地平線にまで行き着いて、それを緑の絨毯が塗り替えてゆく。あっという間に膝まで伸びた草むらの中から、緑色の太い幹が生え始めて、木のように枝分かれしながら上へと伸び始めた。
グレイの雲に閉ざされていた空は、湯気に追い払われるように薄くなり、雲が途切れて青空が見えた。太陽が輝き、爽やかな風が吹いてきて、ぼくらの髪の毛と服をたなびかせる。
(きゃっはっははは……)
(うふふふ……ふふ……)
小さな鈴をあちこちでふるような、澄んだ笑い声がどこからともなく湧き上がって、あたりにこだました。
『どこみてるのぉ』
『ここよ〜私たちはここよ』
周囲の草むらから、色とりどり、形もさまざまな花が一斉に咲き出しているのが見える。笑い声はそこから聞こえるらしいとぼくらは気がつき、繋いでいた手を離した。リョウが「花がしゃべってる……あのさあ、ここってどこなのか知ってる?」と、足元の赤いユリに尋ねた。ユリは身を揺らして笑い声を上げた。
『王が来た。永遠の雪に閉ざされた冬をうち払って春をもたらした。わたしたちここで、ずっといい気分で過ごすの、なあんて幸せ』
黄色いひな菊がキラキラと花びらを震わせた。
『何も心配しなくていいの。ただ楽しめばいい……それが王の望み』
ぼくらは顔を見合わせた。花たちはここがどこなのか、教える気は無いらしい。王が来たって?いつ来たんだろう。モモにしがみついたコウタが、考え込む様子で口を開いた。
「思ったんだけど。“火の輪をくぐり暖ある場所”の、暖ある場所って、さっきの家のことじゃない?ほら、ここには、火の輪をクリアして来たじゃない」
サキがハッとしたように「そうかも!って……え、なんか、何アレ」
黒猫が指差した方向を見たぼくらは息を呑んだ。家があった筈の場所から緑色の巨大な木のようなものが、今まさにグングン伸びているところだった。幹はみるみる太くなり、直径は5メートルくらいありそうだ。ナオが「ジャックと豆の木のお話の、豆の木みたい」とつぶやいた。そう言われると、もう、そうとしか見えない。リョウが驚いて上を指差した。
「先っぽのところ!なんかくっついてる。あれ、熊のぬいぐるみじゃね?さっきの家にあったやつ」
「ほんとだ……」
ぼくらは、はるか上の方に見える豆の木の先端を、目を細めて見つめた。幹の先端、細い蔓が巻きついているのは、さっきのテディベアだ。
まっすぐ上に向かって伸びていた豆の木は、テディベアをゆらゆら揺らして、とある方向へ進路を定めたらしく、そちらに向かって梢を伸ばし始めた。
「わあっ」「ひゃっ」
驚いたような悲鳴があがり、ぼくも足を引っ張られて転びそうになる。花の蔓が右足に巻き付いていたのだ。蔓はぎゅうっと締め付けてきた。みんなの身体にもあちこち蔓が巻き付いている。花たちは相変わらず笑い声をあげながらウネウネと蔓を波うたせて、歌を歌い始めた。
『ここはあかるい 楽しい楽園
すべてを忘れて ただ遊びましょ
お腹も空かない 悲しくもならない
宿題、学校、勉強もない
うるさい大人は ここには居ない
行きたいところ やりたいことは
何でも自由に お望みのまま
楽しむことが 唯一のきまり』
「くそう、離せよっ」
両腕を蔓に捕まったリョウがもがいた。
「全然楽しくないんですけどっ」
ナオがお腹に巻き付いた蔓を外そうとしながら怒って叫んだ。
ぼくはライトセイバーを鞘から抜こうとした手首を蔓に押さえられて、そうこうしてるうちに足に巻き付いた蔓がお腹の方に伸びてきた。
そのとき、黒い影が素早く目の前を横切って、急に蔓が外れた。見ると、蔓が切れて、切り口がだらりと足からぶら下がっている。サキが切ったんだ、と気づいた時には、黒い風のようにみんなの間を駆け抜けながら、刃物のように鋭く伸びた爪で、戒めを次々と断ち切っていた。
「てやあ!」
サキは身軽に回転すると、ダレカの脚に巻き付いた蔓を鮮やかな手際で切断した。ダレカは羽ばたいて宙に飛び上がり、豆の木の上に着地した。木の幹には小さな(と言っても50センチくらいはある)葉っぱがたくさん生えている。ダレカは、それを足がかりにして、小さく羽ばたきながら幹を登っていった。ぼくはハッとして叫んだ。
「みんな!今だ、豆の木に登って!早く、蔓に捕まらないうちに」
ぼくはコウタが捕まったままのモモの体を抱え上げて、豆の木に乗せた。そして自分も幹によじ登ると、駆け寄ってきたナオとリョウを豆の木の上に引っ張りあげた。最後にサキが走って来て、リョウと僕とで引っ張りあげた。ナオがサキに「さっきのカッコよかった!」と声をかけ、サキは人差し指からにゅっと鋭い爪を伸ばしてウィンクした。
「あたしの武器“鋭いかぎ爪”。使えるでしょ」
豆の木はぐいぐいと先端を伸ばし続けて、幹全体が斜めに傾いていたので、だんだん傾斜が緩やかになって、しまいには草原の上にかかる橋のようになった。幹がほとんど地面と平行になったところで、ぼくらは慎重にその上を歩き始めた。
この木が伸びていこうとしている方向、その先の地平線に何かが浮かび上がってきた。モモがじっと先を見つめて「向こうの方……トゲトゲが見える」と言った。全員が目を凝らした。
青さを増す空の下に見えてきたのは、青みがかった灰色の山だった。僕が知ってる山と違い先端は鋭く尖っていて、まるで超巨大な棘が交差した形で突き立った、巨大すぎる針の山みたいに見えた。
「剣を交えて帰る場所ー?」
モモの言葉にぼくらはびっくりして、顔を見合わせた。リョウは興奮して叫んだ。
「そういえば剣が交わってるみたいに見えるよな!」
今はぼくの肩に載っているコウタも「……この流れからすると、あそこが怪物州なのかも」と答えた。
ナオは「この先っぽに、テディベアくっついてるのかもしれないけど、まだ全然、辿り着かないね」と、前方を伺いながら言った。僕らよりもずっと先をダレカが身軽に進んでいて、追いつきたいけれど、大きな丸太を渡っているみたいな感じで、全力で走るのは難しそうだ。
「ねえー待ってよお」
僕は後ろを振り向いた。サキがおっかなびっくり進んでいる。追いついて来るのを待って、手を取った。
「さっきはイナズマみたいだったのに」僕が声をかけるとサキはムッとして
「高いとこは苦手なのっ」とひげを震わせた。
ぼくらが、豆の木の上を歩いたり小走りに走ったりしながら移動を続けるうちに、はるか彼方に見えた、突き立った剣の山々は、徐々に近づいてきた。なかなか順調だ、このまま行けそうだと、ぼくらは何となく考え始めていた……そこに油断があったかもしれない。
全く突然に、豆の木が鞭のように大きくしなった。あっという間もなく、僕らは全員、宙に放り出された。ぼくは一瞬、何が起こったか分からず、次の瞬間に宙に舞うみんなの驚愕の表情が見えて、なすすべなく落下しながら、ああ落ちる、夢の中で墜落死したらどうなるのかとパニックになる。
耳元で羽ばたく音が聞こえた。白い羽根に黒い首が見えて、ぼくとダレカの目が合った。
(ユウ、強く『ノモリクヲノミカ』って言って)
「えっ?」
(早く!!)
ぼくは考えるまもなく大声で叫んだ。
「ノモリクヲノミカ!!」
途端にダレカの姿が眩く輝いて、大きな光になると、いくつかの塊に飛び散った。光の塊はみんなをひとつひとつ光の繭で包み込んだ。ぼくらを包んだ繭はそのままふわりと宙に浮かぶと、ゆっくり落下を始めた。
光の繭のなか半透明のみんなの姿が見えた。みんなは胎児のように小さく丸くなって、目を閉じている。無事みたいだ、よかった。ホッとすると同時に、猛烈な眠気が襲ってきた。ぼくは眠るまいと抗い、目をこすった。
もうすぐ地面のはずだ……いや待てよ、夢の中の眠りは夢を見るのか?
ダレカの姿を思い浮かべる。その澄んだ瞳。いつの間にか鶴の姿は一人の少年に変わっている。そうか、ダレカをみた時に感じた懐かしさの正体がわかった。遥。ぼくのたった一人の親友。ここにいたのか……。
白い光の中で目を閉じた。
──そして次に目を開けると、真っ暗な場所にいて、身体の下の床は何だか毛皮のような柔らかい感触だった。ぼくはゆっくりと上体を起こした。暗い空間の中に無数の、煌めく板のようなものがゆらゆらと浮かんでいるのが見える。そして目の前に、腕組みをして座る青年がいた。
青年の下半身は黒い羽根で覆われ、膝から下は灰色の鳥脚で、黒い鍵爪が付いている。上半身は短い白い羽で覆われていて、腕から少し長めの羽根が生えている。顔と頭だけ、羽根はなくて剥き出しになっていて、額から鼻のすじに沿って赤い縦線が描かれているが、人間の顔だ。ぼくは、上半身が女性で下半身が鳥の、ハーピーというモンスターを連想した。
鳥男は首を傾けて瞬きすると、口を開いた。
「俺のこと覚えてる、悠」
聞き覚えのある声に、相手の正体を確信した。
「遥……その格好、なに。舞台衣装みたい」
「随分長いこと鶴の姿だったから、人の姿がうまく思い出せなくてさ」
遥は組んでいた腕を外して、自分の白い両手を眺め、指をぐうぱあ、と動かした。ぼくは彼に向き合って、やわらかい床の上に腰を下ろし、向かいに座る鳥男をしげしげと眺めた。
「遥がダレカだったのか。なんかさ性格変わった?ぼくが覚えてる遥は、歳の割に大人びてる感じだったと思うんだけど」
遥はぼくの視線を面白がるような顔をした。
「俺は間違いなく遥だよ。けど、遥はもう一人いる。俺はね、遥の人格のひとつなんだ。遥Bってとこ」
「人格……じゃあ遥Aもいるってこと?二重人格?」
遥は目を伏せると頭をかいた。
「言いにくいけど……簡単にまとめると、俺はお前と遊んだ、あの街から引っ越して次の町で落ち着いた頃に、両親と一緒に事故に遭ってさ。親は死んで、俺だけ生き残ったんだけど、ほとんど寝たきり……植物状態になっちゃってね。意識があっても、ほぼ身体が動かせなくなった。だからさ、自分で自分と会話するしかなくて。それで生まれたのが第二の人格、つまり俺なの」
「…………」
ぼくはあまりの内容に呆然とした。何か言いたかったけど、とりあえず話を最後まで聞こうと思い、歯をぐっと噛み締めた。遥はかすかに微笑むと話を続けた。
「でもこの場所に来れたから、救われたんだ。ここにしか居場所がなくて、ずうっとここで過ごしていたけど……まあ、いろいろあって、俺は現実の時間を進めることにしたんだ。現実世界の俺は今、寝たきりのまま歳をとってる。だから今の俺の姿、大人でしょ?」
「時間を進める?そんなことができるの?」
「できるんだよ。俺はこの世界の王様だからね」
「ええっ!」
遥はニッと笑った。
「前の王、先代の幼い長は、俺に……というか遥ABに、この国を託して卒業していった。子供にとって、ここは魂の避難所みたいなところなんだ。しばらく過ごして魂の傷がある程度癒えたら、また現実世界に戻る。普通は十五歳を過ぎたあたりで、ここに来ることはなくなる」
「ぼくは『心が子供だと認められた』から、ここに来れたんじゃないの?」
「俺が呼んだんだよ。悠ならきっと力になってくれると思ったから。来た頃に比べたら、ちょっと時間が進んだみたいだな。高校生くらいに見えるよ」
そう言われて、ぼくは自分の手と体を見下ろした。そういえば手足が長くなった気がする。遥Bは、急に真面目な顔になった。
「悠、俺を手伝ってほしい。こうして、遥Aと別の存在として実体化できるのも、遥の力が弱まってるからで、いまがチャンスなんだ。遥Aを止めなきゃならない」
「止める?」
「遥Aの目的は、この世界そのものの力を大きく、強くすること。そのために次の王のしるし……不死の秘薬を複数、作ろうとしてる。何人か同時に王にして、彼らの現実の時間も進めるよう説得するつもりなんだ……現実の時間を進めると、王たちはここで大人になってしまう。子供が15歳過ぎたらここに来れなくなる理由は、大人がこの世界に入り過ぎると、世界のバランスが崩れるからで……」
遥Bは、ふと顔を上げて、何かを聞くようなそぶりをし、慌てた口調で
「ごめん、あんまり時間がなさそう。悠、上のこれ」と、上を指差した。宙に浮かぶ大小さまざまな銀色の板は、よく見ると、表面に映像が写っている。
「全部、鏡だ。ひとつひとつがこの世界にいる全部の子供の心に繋がって、それを映し出している。どこかにみんなの……ナオ、サキ、リョウ、コウタの、鏡がある。見つけたら名前を呼んでほしい。ユウが呼び掛ければ気がつくはずだ」
「モモは?」
「モモは……特別だから、ここにはない」
「どういうこと?」
「悠、剣が交わる門の向こうに遥Aがいる。鍵を探して」
急に遥Bの姿が薄れると、ふっと消えた。「遥!?」僕は叫ぶと立ち上がって、周りを見回したが、姿が見えない。
ぼくはしばらく、その場で立ち尽くして、遥Bの言ったことを思い返した。
不死の秘薬は、永久に若いまま大人にならないアイテムってわけじゃなくて、王のしるし、なのか。考えてみれば、ここにいる限り現実世界の時間は進まないんだから、ある意味、すでに不老不死みたいなもんだよな。
剣が交わる門って、あの巨大なトゲの山のことだろうか。鍵を探す必要があるらしい。
複数のアイテムで、次代の王を複数人、作ろうとしてて……彼らが現実世界の時間を進めながらここに居続けて、十五歳以上になると世界のバランスが崩れる、って言ってたけど、そこがよく分からない。具体的にはどういう事なんだろう?
ぼくはあたりを見回した。漂う無数の鏡は、低いところでぼくの肩くらいの高さから、5メートルほど上のほうにまで広がっている感じだ。鏡はそれぞれがゆっくり回転していて、時々光を反射してキラリと煌めいている。ぼくは大きな声で呼びかけてみた。
「おおーいみんな!ナオ、サキ、リョウ、コウタ!……モモ!ユウだよ!ぼくの声、聞こえる?ぼくの姿が見える?」
あたりは静まり返って、鏡は相変わらず、その場で煌めき続けている……この中からみんなを探す?どうやって?
でも、やるしか無さそうだ、と腹を決めた。ぼくは立ち上がり、宙に浮かぶ鏡の間を縫うようにして、ゆっくりと歩き始めた。
⭐︎ ⭐︎ ⭐︎
俺はバギータイプの車椅子を押しながら、土手沿いの道をゆっくり進んだ。土手と道の境にガードレールが伸びている。それを超えて、下りになった土手の勾配を降りてゆくと、広い河川敷が広がり、川が流れている。
河川敷にはテニスコートや野球場が整備されていて、野球している子供たちの顔に見覚えがあった。俺と同じ小学校の、同学年の友達だ。中のひとりが俺に気づいて手を振ってきた。
「おーい遼!一緒にやんない?」
「わりーまた今度なー」
俺は声を張り上げて、手を振りかえした。弟の英二が、バギーの座席の上から俺を振り返った。
「やんないの?」
「うん、やんない」
「兄ちゃん、やりたいの、我慢してない?」
俺はちょっと驚いた。英二はじっとこちらを見てくる。ついこないだまで、本当に幼かったのに。成長した弟に気遣われて嬉しい気持ちと、本心を言い当てられてギョッとした気持ちと、両方が混ざって俺の中でぐるぐる回った。俺はそれを隠すように、にやっと笑った。
「ぜーんぜんそんなことない。なんか雨降りそうだし、そしたらグランド、どろどろ泥まみれだし。お母ちゃんに怒られる」
「どろどろ泥まみれ!」英二は笑い声を上げた。そして「ねえ、どろどろってどんな感じ?」と訊いてきた。俺はどんな顔をしていいのか困った。英二は両脚が生まれつき不自由で、細くて曲がっている。両手で杖を使ってやっと立てるくらいで、早く歩いたり走ったりできないし、泥の中を歩いたこともない。俺は言葉を選んで、話を続けた。
「ベタベタしてる感じ。なんかさ、はちみつみたいに、こう、くっつく感じで、歩くと靴が泥に埋まって、脱げたりすんだ。そしたら靴下までうんちみたく茶色くてどろどろドロンちょになって最悪〜」
俺たちは大声で笑い合った。そのままゆるい上り坂を登りきって、川を横断する大きな橋のところまで来ると、立ち止まった。
俺たちはそこから、河川敷を眺めた。野球とサッカーをしている子供たちと、ランニングをしている大人たちの姿が小さく見える。英二はじっとその様子を見つめる。
「兄ちゃん、あのさあこないだテレビで、足が悪いひとが、作り物の脚をつけて走る選手になったって言ってたの。なんかさ鉄でできてる特別な脚でさ……」そして俺の顔を見た。
「そういうの、おれもしたい。それできたらさーおれも、どろどろになったり、あそこで一緒に遊んだりできるかな」
俺は一瞬、黙った後で「できるに決まってる。お前が大人になったらさー未来の技術で何か、すごいのできるって」と答えたものの、きた道を戻りながらモヤモヤ考えた。
うちにはお金が足りない。お父ちゃんがいないから、というのと、英二の治療にもお金がかかるから、らしい。俺はずっと前から、いろんなものを我慢してきた。地域の野球クラブも、お金がかかるという理由で入会を諦めた。それに、お母ちゃんはいつも仕事で忙しいので、小学校に入学した頃から、家事を手伝うようになっていた。時間がなくて散髪にもなかなか行けないし、放課後は、他の子のように遊ぶ時間もほとんど無くなった。
それを残念と思ったことがない、といえば嘘になる。でも、それ以上に英二が可愛かった。
俺はバギーを押しながら、英二の頭を眺めた。また背が伸びたみたいだ。そういえば、最近、英二はあまり我儘を言わなくなった。少し前まで、あれをやりたいどこかに行きたいと、しょっちゅう泣いてたのに。
(おれも、どろどろになったり、あそこで一緒に遊んだりできるかな)
……行きたい気持ちが無くなったわけじゃないんだよな。我慢してんだ。
うちから走って五分の河川敷でさえ、降りるには階段を使うしかないので、彼にとっては行くのが難しい場所だった。六歳の英二には、家と保育園と病院だけが世界の全てだ。
そう思うと、胸がぎゅっと痛くなった。
お母ちゃんが帰って来て、洗濯機を回しながらご飯を作っている時に、英二の様子がおかしくなった。顔が真っ赤になって、ぐったりしている。机で宿題をしていた俺は、慌ててお母ちゃんに知らせた。お母ちゃんは目をずっと英二に向けたまま、体温計で英二の体温を測りながら「遼、散歩の時、毛布かけてくれた?」と言った。俺は「……かけてない、英二がいらないって言ったから」と答えた。
「冷えると英二はすぐ具合悪くなっちゃうの!知ってるでしょお兄ちゃん」と、ちょっとイライラした口調でお母ちゃんは言い、体温計を抜き出して体温を見た。38.5度。お母ちゃんは長いため息をついた。
「うーん……病院、行った方がいいかな。今からだと遅くなるかも。晩御飯……」
「俺も行く」
お母ちゃんは驚いて俺の顔を見た。
「遼、明日も学校じゃない。いいから晩御飯食べて、お風呂入っときなさい」
「でも」
「お願い。何時までかかるかわかんないから先にご飯食べてて。その方がお母ちゃん助かるから」そして、悲しそうな顔をして、俺の頬に軽く手を触れた。
「きつい言い方してごめんね。散歩も、洗濯物手伝ってくれるのも、ほんと助かってる。ご飯は炊いてあるから、カレーを温めて食べて。できるよね?」
「うん……」
お母ちゃんと英二が車で夢現病院に向かった後、俺はレトルトカレーを温めてご飯にかけて食べ、自分の分の食器を洗って、風呂に入った。時間と共に大きくなる不安に目を向けないようにしながら。そして洗濯機から取り出した洗濯物を、どうにか全部、部屋に干した。
二人はまだ戻らない。
布団の上に座って、ぶら下がった衣類を眺めながら自分に言い聞かせた。
(こんなことは何度もあった。これからも沢山ある。英二は大丈夫。お父ちゃんとは違う)
(『帰ってくるから』と言ってどこかに行ったきり、帰ってこなかった……お父ちゃんとは違う)
ぶら下がった青い靴下が二重になって、ぼやける。
涙を拭った。
︎ ⭐︎ ⭐︎ ⭐︎
僕は居間のテーブルの上で、漫画の続きを読みながらアイスを食べている。
「ごちそうさま」
食べ終わると家政婦の花田さんに呼びかけて、漫画を抱えたまま広いソファに寝転んだ。食器を片付けながら、花田さんが僕に声をかけてきた。
「皓太さん、ビーフシチューの鍋、台所にありますからね。炊飯器もセットしてあるので。あと、おいしいリンゴジュースが冷蔵庫にありますから」
「わかったー」
花田さんはもうすぐ帰る時間だ。三時間後には家庭教師の武井さんが来る。そして二時間ほど宿題と勉強をして、一緒に晩御飯を食べたら、武井さんも帰る。そしたら風呂に入ってダラダラして寝る。それがいつものルーティーンだった。
花田さんは帰る前に、ソファに寝転んだ僕の顔をまじまじと見つめて
「皓太さん、すこし顔が赤い気がしますよ」と、手を額に当ててきた。ひんやりした感触に身をすくめる。これが親なら問答無用で手を払い除けるところだけど、花田さんなら、しょうがないと諦めている。
花田さんは首を傾げると手を引っ込め、代わりに体温計を取り出したので、僕は慌てた。
「えっ、ちょっと何してんの。なんともないから。大丈夫」
「そうですか?……何かあったら、無理しないで武井さんに言ってくださいね」
花田さんは心配そうに帰っていった。本当にいい人なんだけど、心配し過ぎが、たまに傷だ。
ソファに座ってゲームをしていたが、武井さんが来る15分前に止めて、勉強の準備を始めた。途端にインターホンが鳴る。出迎えると武井さんは少し濡れていた。
「傘をさすかささないか、迷うくらいのビミョーな雨だったんだよね」
走ってきたのか武井さんは少し息をきらして、僕が手渡したタオルで髪とメガネを拭きながら笑った。武井さんは大学生一年から週に二回うちに来ていて、今は三年生、いや三回生だ。勝手知ったる感じで僕と二階に上がると、まず宿題から始める。
宿題が終わったあたりで、武井さんは僕の顔をジロジロ見て
「皓太くん、ちょっと体温測ってみない?」
と言ってきたのでギョッとした。1日に2回も同じこと言われるなんて。少し心配になったけど、それ以上に苛立ちが込み上げた。体調が悪くなったからって、それがどうした?僕の身体なんだから、どうでもいいだろ。
「武井さんって僕の親でもないくせに。これ終わったら食べて寝るだけなんだからさー。余計な心配しなくていいよ」
「僕は一応、成人してるし、大人が子供を心配するのは当たり前じゃない」
「嘘だね、昨日もテレビで虐待のニュース見たよ。あれって武井さん的にはどう説明するの」
武井さんは表情を曇らせた。
「確かに、そういう大人もいるけどさ。でも本当は、強いものが弱いものを守っていかないと。人類の祖先が集団で暮らすようになったから、子供の生存率が向上して、人類は数を増やすことができたんだよ。助け合いが必要ってこと」
「うちの父親の口癖はさ『強いものが弱いものを淘汰するのは必然。そのための勉強だ、排除されないために』だよ。強いものが弱いものを守るのが当たり前なら、これって矛盾してない?」
「言うねえ」
武井さんは苦笑した。そして顔を引き締めた。
「なあ皓太くん。今日はご両親、帰ってこないって聞いたけど。今からでもどちらかに連絡した方がいいと思う」
「無駄だから。海外に出張するって言ってたし。ねえ、なんともないから、勉強早く済ませて、カードゲームやらない?」
武井さんはますます顔を曇らせたけど、それ以上、その件を追求しなかった。僕らはハイペースで予定していたところまで予習復習をして、余った時間はカードゲームをした。最近は、僕が勝つことが多い。
夕食はビーフシチューを温めて、ご飯と一緒に食べた。食欲はなかったけど、平気なふりして完食した。武井さんは食器を洗って片付け、何度も「もし調子が悪くなったら電話して。番号知ってるよな。夜中でもいいからさ」と念を押して帰っていった。
一人になると、僕はよろけてしゃがみこんだ。確かに、これは風邪をひいたかもしれない。早く寝た方が良さそうだった。僕は風呂の栓を抜き、歯を磨き、子供用の風邪薬を飲んで、ベッドに入った。体がどんどん熱くなってきた。脳みそが熱で柔らかくなったみたいに、意識がふわふわして、浅い眠りの中を彷徨う。
僕の両親はどちらも大きな会社の偉い人らしくて、二人ともいつも忙しく、あちこちを飛び回っている。夜、家にいないことも珍しくなく、土日もパソコンの前に一日張り付いて仕事している。なんでそんな二人が結婚して子供を作ろうと考えたのか不思議だった。どう見ても子供より仕事の方が好きみたいなのに。
本当は、がんばって勉強する理由がわからない。どんなに良い成績を取ってもうちの親は僕に関心なんてないんだから。でも全部放り出すのも怖かった。要らなくなった僕はあっさりゴミ箱に捨てられるだろうな、必要無くなったアイテムみたいに。嫌悪の表情を浮かべて僕を見下ろす親の顔が浮かび、目を強くつぶった。
(……要らないのになあ、心、なんて)
心があるから苦しい。心があるから捨てられることが怖い。
僕はただひたすら勉強だけして、親のことなんてなんにも感じないロボットに……機械になりたい。
オズの魔法使いに出てきたブリキのきこり。心臓を、心を欲しがって。だったら僕のをあげるよ……要らないんだ、もう。
⭐︎ ⭐︎ ⭐︎
「あなたは本当に本が好きねえ」
と、よく言われる。親からも友達からも、ときどき先生からも。私は「うん」と答えるけど、本心はこう言いたい。
「だって本は読むためにあるものでしょ。逆に、なんで読まずにいられるの?私、知ってるよ。本を読みたくても読めない人だって、たくさんいるんだよね?せっかくあるんだから、読まなきゃ損だよ」
頭の中の私はすごくおしゃべりで、相手が大人だろうと年上の男の子だろうと、お構いなしに喋ってやり込める。でも実際の私はうまく話せない。思ってることが百あったら、そのうち十くらいしか、口から言葉になって外に出ていかない。運動も苦手だし、勉強も国語以外は苦手。字も綺麗に書けないし、工作も下手だし、食べるのも遅い。要するに、何をやっても微妙に出来が悪くて、二つ年上のお姉ちゃんに言わせると「どんくさい子」なのだった。
幼稚園の時は、本をたくさん読むってだけで褒められた。でも小学生になってから、友達との普段の会話についていけなくなった。私は児童文学とファンタジー漫画の世界にいたけれど、友達はユーチューブ動画とかドラマの芸能人とか、そういうものの話ばかりするようになってきた。
私も勧められてドラマとか動画を観てみたけど、面白さが全然わかんない。あまり交流のない子から遊びに誘われると、嬉しさよりも緊張して気が重くなる。話が合わなくてしらけさせたらどうしよう。笑われたらどうしよう。……そして大抵、何かしら失敗してしまう。
気がつくと、休み時間も学校の行き帰りも、いつも一人だった。いじめでもハブられてる訳でもない。ただ、なんとなく周りに馴染めず、浮いてるってだけ。
ある日、学校から帰ると、図書室に新しく入った本を抱えて居間に向かった。ジュースを飲みながらソファでゆっくり本を読むためだ。すると居間には、お姉ちゃんとその友達が二人で座って、録画したドラマをお喋りしながら観ていた。
友達の方が私に気がついて「あ、お邪魔してます。ゆかりんの妹さん?」と声をかけてきた。私が答えられないでマゴマゴしていると、お姉ちゃんがピシャリと「うちら、ドラマ観てるから。この部屋しばらく貸し切りまーす」
「……」
「早希、あんたどうせ本読むんでしょ?そんなん、どこでも読めるじゃん。ほら早く向こう行ってな」
「ゆかりん、いいの?妹さん、一緒に観れば?」
友達が気を遣ってお姉ちゃんにとりなしたけど、お姉ちゃんは馬鹿にしたように「この子、ドラマとか動画とか全然、興味ないの。お話よんで妄想ばっかしてんの。キモいよ」と言った。友達は笑った。
「えーっ、ちょ、言い方」
私はいっぺんに憂鬱になって、すごすごと部屋に引っ込んだ。部屋は私とお姉ちゃんと共同で、窓を挟んで両端に机が一つずつ置いてあって、左側が私の机だった。私は机の前の椅子に座って、本を広げた。でも、まったく内容が頭に入ってこない。
(お話よんで妄想ばっかしてんの。キモいよ)
なんで、ドラマが好きなのはキモくなくて、本とかアニメを好きなのはキモいんだろう。お互いの好きなものが違うって言うだけで、どうして「いい、悪い」って分けられなきゃいけないんだろう。
本を読む気が失せて二段ベッドの上によじのぼり、寝っ転がって黒猫ジンジンの抱き枕を抱きしめた。ジンジンは魔女の女の子が姿を変えた黒猫で、アニメのキャラクターだ。
ジンジンはマイペースで物おじしなくて、口が達者な猫だ。生きて帰れないかもしれない冒険に向かう勇者を、そばで支えて一緒に戦う姿がめちゃくちゃかっこいい。私もそんな風に、行手にどんな困難が待ち構えていようと、先頭に立って道を切り開いてゆくような生き方がしたい。強くなりたい。
……でも現実は。
明日もあさっても、しあさっても、ずーっとどんよりした灰色の毎日が続くんだと分かってる。いつも相手に失望され、呆れられ、諦めたような曖昧な笑みか、ため息しか返ってこない、出来損ないの冴えない子。
わかってくれる仲間が欲しい。仲間がいたら、きっと敵がなんであろうと頑張れるのに。私みたいなどんくさい子は、誰にも見つけてもらえないまま、死ぬまで隅っこで生きていくしかないんだろうなあ……。
暗い穴の中に落ちていくみたいに怖くて、ジンジンに縋りついた。私は永遠にひとりぼっちだ。
涙が、枕を濡らした。
⭐︎ ⭐︎ ⭐︎
クリーム色のカーテンに囲まれた白いパイプ付きベッド。白い壁紙と広い窓、ベージュのツルツルの床。
病室を出ると、薄い水色の壁に黄色とオレンジの幾何学模様。動物と花の絵が描かれたドア。廊下の隅に畳んで置かれた車椅子と、予備の点滴スタンド。
廊下を行くとナースステーションがあり、そこを過ぎるとエレベータホールがあって、その先に休憩&談話室があり、中には自動販売機があって、共用のおもちゃや小さな本棚がある。
私の小さな世界はこんな感じ。検査がない時は、1日のうちのほとんどをここで過ごす。そして時々、エレベータで下の売店まで行ったり、親と一緒に病院の敷地内を散歩したりもする……。夢現病院の門、そこが私の世界の果て。
小学校入学と同時に病気が判明して、以来、家と病院と学校を行ったり来たりしながら過ごしてきた。でも、だんだん病院にいる時間の方が長くなって、学校に全然行けなくなった。
勉強は、親が買ってきたドリルをやったり、授業の動画を見たりする。暇つぶしみたいなものだ。だって大人になれるかどうかもアヤシイんだから……でも、それを深く考えると怖くて叫びそうになるので、余計なことを考える時間を少なくするためにも、勉強は有効だ。それに字をたくさん覚えれば難しい本も読めるようになる。動画を観るより本を読む方が、時間が早く経つから好きだった。最近のお気に入りは、宇宙飛行士の人が自分の体験を書いた体験記だった。
もちろん、それは全部、体の具合が良い時のことで、悪い時は点滴に繋がって、ベッドの上で縮こまって、苦しみがマシになるよう、ひたすら耐えるしかない。痛みも苦しみもいつかは去る。そしてまた来る、その繰り返し。
昨日、私は12歳になった。誕生日は家で過ごしたかったけど、検査の結果が思わしくなくて、行けないということになった。ガッカリしたけど、やっぱりなあ、という気持ちもある。そう慣れっこなんだ、こんなことは。
「奈央ちゃん、体温測るよー」
看護婦の林田さんが、機械が乗ったスタンドみたいなものを押して、四人部屋の病室に入ってきた。他のベッドの子たちは検査で、今は私しかいない。
私は体温計を受け取って、いつもの手順で測って渡すと、林田さんはそれを見て、機械の下にあるキーボードに数字を打ち込んだ。そして「薬の残り、確認させてもらって良い?」とこちらを向くと、薬の残りの数を数えて確認し、ゴミ箱の中身も回収する。そしてベッドの上の本を見て、目を見張った。
「奈央ちゃん、宇宙飛行士の本、読んでるの?ねえ、どんなことが書いてあるの?」
「宇宙飛行士の仕事について書いてあるの。どういう研究をするのかとか、宇宙船の中の生活とか」
林田さんは何か言おうとしたけど、私は話を続けた。
「ねえ、この病院に“あかずの病室”があるって噂、本当?」
林田さんはギョッとしたように「えっ」と言った。私は畳みかけた。
「美奈子ちゃんから聞いたの。眠り姫みたいに、ずーっと寝てる男の人がいて、眠りの王子って看護婦さんの間で呼ばれてるって。ねえほんと?」
「それは……えーっと」
林田さんは視線を逸らして機械の方を向いた。途端にポケットに入れた携帯電話が鳴り、林田さんはどこかホッとしたように電話を取り出して「はい、伺います」と答えた。そして「ごめんね、呼ばれたから行くね。次は四時ごろ来るからね」と、機械スタンドを押して部屋を出ていった。
露骨に不自然な態度に、私は確信した。やっぱりいるんだ眠りの王子……。私は軽く息をつき、仰向けにベッドに寝転がると、本をお腹の上に抱えた。
実は、以前にこっそりと、ナースステーションのそばで聞いたことがあるのだ。看護婦さんたちは小声で「眠りの王子……ウツミくんが……」と話していた。ウツミくん。きっと王子の名前だろう。
天井の蛍光灯を見上げて想像した。薄暗い迷宮のような病院の奥の、そのまた奥深く。なぜか棘だらけのイバラが生い茂った廊下の先に、特別な患者だけが入院したひみつの病室があって……
病室のベッドに眠っている男の人は、ずうっと昔から年を取らず、若い姿だけど、実は百年前から眠り続けているのだ。悪い魔法使いの呪いから、助けてくれる王子を待っている。いや、この場合、助けるのはお姫様かな?呪いから解き放ってくれるお姫様。
(ナオ……聞こえる?ナオ、ユウだよ)
小さな声が聞こえた気がして、私はベッドから上体を起こすと、周りを見回した。
(ナオ!ここだ、ナオ、鏡の中から君を呼んでる。鏡を見て)
辺りには誰も居ないのに、今度こそ、はっきりと聞こえた。
私は、ベッドサイドの引き出しの上に置いてある小さな鏡を見た。そこには若い男の人の顔が写っていて、動いている。まるで鏡のすぐ向こうにいるみたいに臨場感がある。男の人は私と目があうと、嬉しそうな顔をした。
(やっと気がついてくれた。ユウだ。セオドアから君に呼びかけてる。みんなを集めなくちゃいけないんだ。ナオ、すぐこっちに来てくれない?)
「ユウ……?」
声に出すと同時に、頭の中にこれまでの記憶がどっと流れ込んできてびっくりする。セオドア、数々の冒険、お城、宇宙服、馬車、みんな、ユウ……
突然、あたりが真っ暗になり、一瞬の浮遊感のあとに、お尻と背中に衝撃を感じてうめいた。触ろうとして、ゴワゴワした感触に全身を包まれているのに気がついた。同時に視界が暗い原因に思い当たって、私は宇宙服のフェイスシールドを下げた。心配そうなユウの顔が見える。あれ?ユウってこんな感じだったっけ?
「ナオ。ずいぶん勢いよく尻餅ついてたけど大丈夫?」
「うん大丈夫。宇宙服着てるし。ユウ、ここどこ?」
ぼくはナオに手を差し伸べて、助け起こした。
「話すと長くなるんで、みんなと合流できたら全部話すよ。まずは、リョウとコウタとサキを、この中から見つけなきゃ」
ナオは周りに浮いている鏡を眺め、ぼくに視線を移してジロジロ見た。
「ねえユウ、背が伸びてない?いや背だけじゃなくて、なんか大人っぽくなってない?」
「それも後で話すよ。みんなを探す方法は……ええっとね、まずリョウとコウタとサキの顔を思い浮かべて。鏡からみんなに繋がる通路をイメージする感じ」
「モモとダレカは?」
「ふたりは、ここに居ないらしい。どうしてって聞かないでよ、ぼくも知らないんだから」
「ふうん……イメージね、それから?」
「イメージしながら歩いていくと、七色にキラキラした鏡が見つかるはずなんだ。それが見えてきたらすぐわかる。そしたら近づいて呼びかける」
「わかった」
ぼくたちは上下左右を見渡しながら、ゆっくりと鏡の間を歩いた。鏡にはいろんな情景が映っている。内容はセオドアの冒険のものが多いが、現実世界の景色もちらほらと見える。
遥Bは、鏡はそれぞれ、この世界にいる子供の心に繋がっていると言っていた。ということは、ここはみんなの心が分かる場所ということになる。もしかしたら王専用の部屋なのかもしれない。王様がここにきて、みんなの困りごととか、いろんな気持ちを知って、世界の運営に反映させる……現実世界で言うところの「政治」を、するための場所なのかもしれない。そうだとすると、ここの王様というのは、まるで全知全能の神様みたいだ。
「この鏡って、全部が誰かのところに繋がってるの?」
ナオが周りを見回しながら聞いてきた。ぼくはそうだと答えた。ナオは上を見上げて「こんなにたくさんの子供が、セオドアに繋がってるんだ……ねえユウ、なんとなくだけど、ここにいる子は現実世界が苦しい子が多いんじゃないかなって思う。みんな、現実のこと話したがらないし。聞くことも良くない、みたいな雰囲気だし」
「そうなんだ」
「ユウは違うの?」
「ぼくは……ええと」
ぼくは答えに詰まった。現実世界では大人で学校の先生で、はっきり言って仕事は忙しくて休みも少ないし、保護者の対応とか神経使うし大変だ……でも、子供が好きでこの仕事を選んだから、子供と過ごしている時間は楽しいって感じることも多い。だから、現実世界が苦しいとまでは言えない。
それに大人なんだから、本来ならここに入ることもできないはずだ。そのことを、みんなにも話すべきだろうか?……みんなは、それを聞いてどう思うんだろうか。
ぼくが口籠もっているうちに、ナオが叫んだ。
「ユウ、あれ!光ってる、上の方!」
見ると、3メートルほど上の辺りに、チカチカと虹色に煌めく丸い板が見えた。ナオの時と同じだ。
「うん、多分あれだ……でも届かないなあ。ナオの時はたまたま低い場所にあったんだけど。こっちに来ーいって念じてみたら、近づいてくるかな?」
ナオはぼくの顔と鏡を交互に見て言った。
「あのさ私、武器使ってみるよ」
「えっ武器!?」
「私の武器はねぇ“一定じかん無重力浮遊”なんだ。まあ、見ててよ」
ナオはキラキラの方に両手を伸ばした。すると、体がふわりと浮き上がり、浮遊する鏡の間を抜けて、ゆっくり光の方へと漂っていく。ぼくはその様子を呆然と眺めた。そうか、みんなそれぞれ一つは武器を持ってるはずなんだよな。
ナオは輝く丸い鏡を両手に持つと、こちらに向かって降りてきた。ぼくは息をつめてそれを見守り、無事に着地した時は思わず安堵のため息を漏らした。そして盛大に拍手をした。
「すごい、すごい!本物の宇宙飛行士みたい」
「えへへ。まあね」
ナオが抱えた丸い鏡をぼくらは覗き込んだ。小学校3、4年生くらいの男の子が、赤い顔をしてベッドに寝ている。薄く汗をかいていて、具合が悪そうに見える。そしてなぜか、これはコウタだ、とすぐにピンときた。
「コウタ!おーい大丈夫?僕の声が聞こえる?ユウだよ、ナオもいるよ。鏡を見てくれ、コウタ」
「コウタ、早くこっちに来て!リョウとサキを探さないといけないの」
呼びかけられた男の子はうっすら目を開けて、こちらを見た。「ユウ……ナオ……」すると、鏡の中からポーンとカメレオンが飛び出してきた。カメレオンはナオの顔面にぶつかり、そこからバウンドして僕の胸につかまった。カメレオンは目をギョロリと動かして僕を見た。
「ふう、助かった。ちょうど風邪で熱出して寝込んでたんだ。健康って大事だね。ユウ、ここってどこ?」
ぼくは苦笑いし、先ほどと同様「後で話すよ」と返した。ナオは顔をしかめて鼻の頭を撫でている。
次に見つけたのはサキで、同じように鏡をナオにとってきてもらい、中に写っている、抱き枕に抱きついたまま眠っている女の子に呼びかけた。念のため、ぼくらは鏡から少し離れていたので、サキは飛び出してくると、身軽に一回転してパッと床に降り立った。そして「真っ暗じゃん!いっぱい浮かんでるこのキラキラ何?」と、ひとしきり騒いだあと
「ああ、戻れてよかった。現実世界ってほーんと憂鬱。もう絶対いきたくない」
と、サキは伸びをした。ぼくはナオと顔を見合わせ、コウタは「ほんとそれ」と短く応えた。
そこからあまり離れていない場所で、リョウの鏡を見つけた。
鏡の中に、布団に寝ている男の子の姿が見える。ぼくらは今までと同じように、そこに向かって呼びかけた。
「リョウ!起きて、リョウ!鏡の中から呼びかけてるよ、ユウだ、鏡を見てくれ」
「リョーウ、早くこっちにおいでよお。冒険の続きしよー」
男の子は目を開けてこちらを見ると、驚いた顔をした。
「みんな……」
男の子の嬉しそうな表情は、すぐ悲しげに曇ってしまう。
「ごめん。俺、まだ行けない」
ぼくらは凄く驚いた。「どうして!?」
「弟が……いま、病院に行ってて。帰って来るの待ってたいから」
「君がこっちに居る間は、時間が止まるんじゃないの?」
「そうなんだけど。……いまそっち行っても、俺、弟のことが気になって、冒険しても楽しくないって思う。なんか失敗しそうだし」
ナオは「失敗なんか全然、気にしないのに」と言ったけど、リョウはますます悲しそうな顔になって俯いてしまった。僕はわざと明るい声で言った。
「そっか、わかった。じゃあさリョウ、来る気になったら鏡に呼びかけてよ。僕らは、この鏡を持っておくから。これがあれば、すぐに会えるんじゃない?」
リョウは顔を上げた。少し顔が明るくなった。
「ありがとユウ、みんな。弟が戻ったらすぐにそっちに行くから。待ってて」
コウタが僕の肩の上から「早く来いよ、お前ってうるさいけど、居ないとなんか、もの足りない感じだし」と言い、リョウはようやく笑った。
そして鏡は、一度暗くなり、普通の鏡のようにぼくらの顔を映した。これが、通信が切れた状態なんだろう。ナオは鏡を胸にしっかりと抱えた。しばらくは、ここにいるメンバーだけで進むしかなさそうだった。──とはいえ、これからどうすれば良いんだろう?
相変わらず、あたりは無数の鏡と、どこまでも続く暗闇だけだ。あてもなく歩いていると、肩のコウタが「そろそろ良いんじゃない?」と言ってきた。
「何が?」
「今の状況についての説明。さっきからユウが話してくれるの待ってるんだけど」
サキは、ぽんと手を打ち合わせた。
「そうそうわたしも思ってた!ユウ、めっちゃ背が伸びてるよね」
ナオも僕を上から下までじっと見て
「ユウ、さっきよりもっと、背が伸びてない?」と言った。
ぼく達は出口を探して辺りを見回しながらゆっくりと歩き続けた。そうしながらぼくは、自分が本当は大人であること、ダレカの正体は遥で、遥はここの王様で、現実世界では寝たきりの状態らしいこと。遥の人格は二つに分かれていて、片方の遥がやろうとしていることを、もう片方の遥は止めようとしていること……などを話した。教師だということは、何となく言えなかった。
ぼくの正体が大人、という事実についての、みんなの反応が心配だったけど、遥のことを聞いたナオが叫んだので、ひとまず不問になった。
「もしかして、遥くん、って私の病院にいる人かもしれない!ねえユウ、その人の苗字って『ウツミ』じゃない?」
ぼくは驚いた。「そう!内海、遥。えっナオ、病院にいるの?」
ナオは気まずそうな表情になった。
「私、小さい頃から何度も入院してて、最近はずっと病院で、学校行けてないの」
ぼくはさっきのナオの『ここにいる子は現実世界が苦しい子が多いんじゃないか』という言葉を思い出した。サキは感心したように「ずっと眠ってるなんて、おとぎ話の眠り姫みたい」といい、ナオは「そうなの、本当にウツミくんは”眠りの王子”ってあだ名で呼ばれてるみたい」と興奮した様子で答えた。女の子ふたりの盛り上がりを、コウタはいつにも増してクールな調子でさえぎった。
「あのさ。王様をたくさん作って時間をすすめるって。それってつまり、本来なら止まっている時間が流れるってこと?仮に僕たちが王様になったら、ここに来ている間、現実では、その眠りの王子みたいに、寝たきりになるってこと?」
「!!」
ぼくらはショックを受けて黙り込んだ。カメレオンの声はますますクールさを増した。
「それって、現実では大変なことになるよね。ユウはもう大人みたいだけどさ、サキ、ナオ、どう思う?」
重い沈黙がたち込めた。ぼく達は、そこに立ち尽くして、黙ったままコウタの言葉を考えた。やがてナオはためらいがちに「私、いま、具合の良い時間より辛い時間の方が長いんだ……本当いうと、凄くしんどい。ここにずっと居られるなら、それもいいかもって思っちゃう」
サキは硬い声で言った。
「私もその方がいい。もう現実世界には行きたくないし、私が寝たきりになっても、親もお姉ちゃんも悲しまないし」
その言葉にぼくは思わず「そんなことないよ」と言ったが、コウタは僕の肩からジャンプしてサキの肩に飛び移ると、するどい口調で
「大人ってすぐ『そんなことない、親は心配してる』っていうよね。ユウも他の大人とおんなじ。ガッカリだ。世の中には子供を心配しない親も、子供のことを分かろうとしない親もたくさんいるのに。もしかして王様はさ、現実に戻りたくない子供が、戻らずに済む方法はこれしかないって考えたのかもよ。もしそうなら、僕は遥Aに賛成だ」
三人はぼくをじっと見つめたが、その眼差しはとがっていて、今までと全く違うものだった。
何か言わなくちゃ、でも何を?サキとナオは一歩、ぼくから離れた。気持ちが焦る。ここで間違うと、取り返しがつかなくなる気がする。
そのとき突然、光が暗闇を切り裂いた。
光の裂け目は縦にどんどん広がって、光の筋が何本も闇に差し込み、闇が薄れると同時に、宙に浮かんだ鏡が空間に溶けこむように歪んで消えてゆく。暗闇に慣れたぼくらは眩しさのあまり、思わず目を庇った。
気がつくと、鈍い水色の色合いに満たされた場所に立っていた。風が吹いていて、砂と石の冷たい匂いがする。
目を凝らすと、今いる場所は水色の石でできた巨大なトンネルの中で、Vの字を逆さまにしたように、斜めの石の壁が、上のかなり高いところで交差しているんだとわかる。交わった部分は100メートル、いやもっと距離があるかもしれない。水色の石でできた深い谷を逆さまにしているみたいだ。大きすぎてスケール感がおかしくなる。
トンネルは、ずうっと先の方まで続いているようだった。緩やかにカーブしているのか出口は見えない。壁の水色は上にゆくに従って、暗く濃くなっているけど、トンネルのなかは、暗くはなかった。
「もしかしなくても、ここ“剣を交えて帰る場所”の、あのトゲ山の中だよね……」
ナオがまわりを見回しながら言った。広い空間のなかで、声がわずかに反響する。ぼくは、さっきの険悪な空気が、状況の変化でいったんリセットされたことにホッとした。しかしまたしても、どうすればいいのか分からない。ひたすら広い空間は、ただ風が吹いているだけで、道しるべのような物はなにも見えない。
「遥は剣が交わる門って呼んでた。ここは門の中、なのかな。鍵を探せって言ってたけど……鍵がどんなものかも分からないし、探しようがないよ。うーん困った。どっちに行けばいいのかな」
ぼくは、上空に広がる圧倒的な大きさの空間を眺めながらぼやいた。
「僕が、武器を使って、壁を調べてみようか」
サキの肩に乗ったコウタが言った。ナオとサキが驚いて「コウタの武器!そういえば、見たことない!」と同時に叫んだ。
「必殺技っていうのは、本当に必要なときに使うもんなの。とりあえず、壁のとこまで歩いてよ、サキ」と、コウタはすました調子で言った。
「あんた、たまには自分で歩いたらどう?」
サキは呆れながらも、肩にコウタを乗せて壁まで歩いた。ぼくとナオも後ろからついていった。
壁の側まで来ると、コウタは大きくジャンプして、四本の脚でピタッと壁に取りついた。そして頭を上に向けると、斜めになった壁をゆっくりと登りはじめた。
広い広い壁をよじのぼって行く小さなカメレオン。その身体の色が次第に変化してゆき、周りの鈍い水色に近づいてゆく。上に登るに従って、コウタは周りの色とますます同化し、僕らの位置からは、姿が完全に見えなくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
