
【小説】誰かでした
原稿用紙15枚。ネット掲載作応募OKの「kinokuni文学賞」に応募中、審査待ちです。
「証明写真機でふざけた写真を撮ってはいけません」ってお母さんに言われていた。あれは、本気で、茶化しちゃいけない機械だからね、って。何百人何千人のひとがあの箱の中の同じ場所に重なってきたか考えれば分かるでしょ、アゴ数mm差のレベルで、そして運命をその数mmの差で動かされてきたの、就職とか、審査とか。だからプリクラとは違うんだからね、もっと、昔からそびえる、プリクラのずっと先輩で、ずっと上等で、ずっと正確なんだから。
お母さんが色々いうのは自分の青春期にプリクラが無かったことのひがみだと思う。そんなこと言わなくても別に何もしない、でも昨日、クラスの島田君が、あの証明写真機の仕切られたカーテンの中でオナニーした、と言っていた。写真は撮らなかったそうだ(だから男子にブーイングを食らっていた、「証拠が無い」「嘘だろ」と。でも本人は「もったいないだろ700円も」と言っていた)。
この話をもしお母さんにしたら、どんなにかんかんに怒るだろうと思う。島田君が使った証明写真機は学校の最寄り駅のらしいから、私はあそこのは絶対使わないようにしようと思う。
そんなことを考えながら私は、朝の通学電車に乗る。私は、あれ、この吊り革だって朝オナニーした人が掴んだかもしれないし、意味無いなと思った。世界は基本汚れている。そういえばお母さんが、証明写真機の中では数mm単位でいろんな人の運命が重なってるって言ってたけど、通学の電車でいつも同じ場所――出入口のすぐ横の、座席の一番端の人の隣――

に陣取っている私も、過去の私何百人と重なっている。私は今高校二年生で、中学一年からこの電車を利用しているから、一日2回、学校がある日が年200回だとすると、一年で400回、それが4年半なら1800回、こうやって毎日毎日、20kmの動線を濃く濃くなぞっているということになる。
あ、でも、そんなこと言ったら家の自分の部屋とトイレの間の廊下の方がずっと濃い動線を書いてるよね、あ、でもそれは厳密には廊下の幅の分ブレている、つまり廊下の右端を通る時と左端を通る時の動線は重ならないから、電車の動線の方がやっぱり濃いかもしれない。電車に乗る今日の私は、電車に乗った昨日の私と数mm単位でしかズレていないかもしれない。
学校に着いたら、由里子が頬を染めながら近づいてきた。
「咲、お願いがあるんだけどさ……、写真、付き合ってほしくて」
「いいよ、でもなにいきなり笑」
私はiPhoneをカバンから出してカメラを起動しようとした。そうしたら
「ちがくて。その、駅の、ボックスのやつで」
「ボックスのやつ、って? ……ああ」
つまり、昨日島田君がオナニーした、あのボックス。そうだ、由里子は島田君が好きなのだった。でも、好きだからと言って、好きな男の子がオナニーした証明写真機で自分も写真を撮りたいと思うか?
「こんなの頼めるの咲だけだからさ、ね」
「いいけど……うーん」
「早い方がいいの。今日放課後空いてる?」
結局、帰りにアイスおごってもらう代わりに由里子に付き合ってあげることに決めたけど、でも、由里子は一体それでなんの気が済むんだろう。一日前の島田君と数mm差で重なるのって。まあ、顔は結構格好良いけどちょっとサイコな匂いのする島田君を好きな由里子もちょっと変わり者なのだった。島田君は、これまでも、電車で痴漢を見つけて証拠動画を撮って相手をゆすったら半泣きの痴漢が財布からビールを持った水着姿の女性の柄のボロボロのテレフォンカードを出してこれで勘弁してくれというのでそれで勘弁することにして後日それをヤフオクに出したら20万円になった、という話をしていて、また他の男子に嘘つき呼ばわりされていた。
放課後、由里子がおごってくれたミニストップのソフトクリームをペロペロなめながら最寄り駅の証明写真機にたどり着くと、まず由里子を写真機のカーテンの中の丸イスに座らせて写真を撮った。ちょっと面白いと思ったからだ。写真を撮る前の記念撮影。由里子はカーテンを片手で寄せて小首をかしげてニッコリ微笑んで、まるでお茶屋の暖簾を片手で寄せて舞妓さんが「おいでやす京都」とほほ笑んでいるみたいな、観光感のある写真が撮れた。由里子はその後、小さいけどきっぱりした声で、
「そこで、見張ってて」
と言った。
「うん?」
「そこで、そのへんにいて、他の人が来ないか見てて。あんまり近いと恥ずかしいから」
別に、カーテンの下から由里子の足が見えるのだから写真を撮りたいほかの人がやって来てもカーテンを開けることはないだろう、ん? じゃなくて、え、もしかして、
「するの……? その、島田君と、同じことを」
由里子はぐんと一回頷くと、シャッと引き裂くようにカーテンを閉めた。動く由里子の顔とカーテンの残像が残った。
私はその後、薄いとも濃いともしれない、なんとも言えない時間を過ごした。由里子の、ローファーを履いた小さな足は床から浮いて、前に行ったり後ろにいったり、緩慢で不規則な動きを繰り返し、まるで空飛ぶ証明写真機で宇宙を探索する宇宙飛行士のシュミレーションゲームをしているみたいだった。
多分由里子は今、島田くんの心を探索している。
なぜだか分からないけれど、私はお母さんが私を生む時に分娩室の外の廊下で夜通し待ち続けていたというお父さんもこういう気持ちだったのかな、と思った。圧倒的無力。不可解。由里子は今、幸せなんだろうか。
わざと作った不機嫌そうな顔で、由里子は証明写真機から出てきた。
「どうだった?」
と聞いて、どうだったってなんだよ、と自分で脳内でつっこんだ。
由里子は力なく首を横に振り、口から魂を出すみたいにしゃべった。
「島田君のことはよく分からない」
そして魂の出切った抜け殻となった由里子は、まるで葬列に参加するように改札の人の流れに向かい、PASMOをピッとして、行ってしまった。
私はそれについていかず、ひとりその、証明写真機と自動販売機と改札とエレベーターと階段の見える、なんでもない駅の空間に佇んでいた。三度、降車する人の流れを見送り、そろそろ自分も帰ろうとしたが、証明写真機が私を呼んでいた。
私は小さい頃から狭い暗い所が落ち着いた。例えば、押入れとか、掃除用具を入れるロッカーとか、台所と食器棚の隙間とか。何か考えたいのにこの場所は人の流れが多くざわざわが頭に溜まる。証明写真機の中に入ることは今の私にうってつけだと思った。
丸い椅子に座ってカーテンをひくと、先ほどまでざわざわしてはっきりしなかった自分の座標がしっかりするように思え、予想以上に落ち着けた。椅子の上に体育座りする。そうすると、自分の重心がぐぐっと中心に集まり、さらに座標がはっきりする感じがして、落ち着く。
島田君を追いかける由里子の気持ちを追いかける私。
島田君の気持ちは分からない(由里子の言う通り)、そして由里子の気持ちも分からない(数mm単位で重なっても)。
もし私が、島田君のことを好きな由里子のことを好きな男子だったら、ここでオナニーするだろうか。いや、しないな。由里子の体温はもう丸椅子には残っていなく、さっそく私の体温で上書きされている。
誰かを好きになるのって何なんだろうな。こんなよく分からない同じ場所にいるってこととか同じ気持ちを味わおうとするとか、そういうことなんだろうか。それでも完璧な無力なのに。そういえば、もし私が毎朝乗るのと同じ電車に乗り、車両違いの全く同じ場所――出入口のすぐ横の、座席の一番端の人の隣――に毎日陣取る人がいるとしたら、私と毎朝数秒違いで数mm単位という奇跡的な重なりを見せることになるけど、その人だってきっと私に対して無力なんじゃないだろうか。逆に私がその人に影響を与えていたら嫌だ。
見張ってて、とか、咲しかこんなこと頼める人いないから、とか言われた割には私は無力で、多分お母さんに祈ってて、とか言われて分娩室前の廊下で祈ってたお父さんも無力で、なんだかイライラしてきた。お母さんに対して。お母さんと私は昔、数mm単位どころか完璧に重なって同じ場所にいたことがある、生まれる前だ。お母さんの中に私がいたらしい。でもだからどうなの。
今の私はカーテンからも足がのぞけないから誰にも私の場所を特定されない。本当にこのまま証明写真機を発進させて宇宙に飛んでたった一人きりになれないだろうか。
操作したいな、と思ったので、700円を投入口に入れた。それは、島田君も由里子もやっていないことだった。
証明写真は撮ったことがある。学生証の写真用に。
お金を入れると、機械が喋り出す。画面のラインにアコと頭頂部を合わせてください。丸イスをくるくると回して座高を調整していると、丸イスと鼻が近づいて、ふいに自分の家の布団の柄が脳みそいっぱいに広がり、
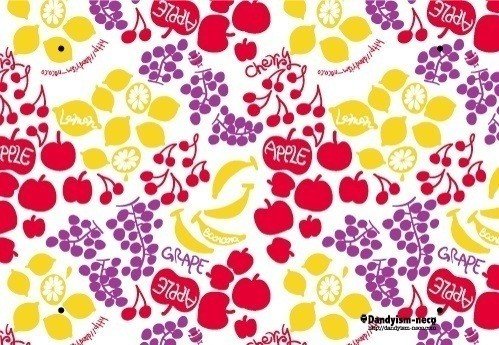
いや、これは、きっと、由里子のオナニーの匂いを私の鼻が察知して、それで私がいつもオナニーする場所――自分の家の布団――が連想されたんだろうな、と結論付ける。ん? ということはやっぱり由里子は本当に、この場所でオナニーしたんだろうな。気持ち悪いとは思わなかった。ただ、ものすごく重なってるなと思った。私たちは。
証明写真機は宇宙探索するには大分雑な、上下左右と決定ボタンの5つしかついていなく、押すとパカパカと音がして安っぽい、蛍光色のボタン。
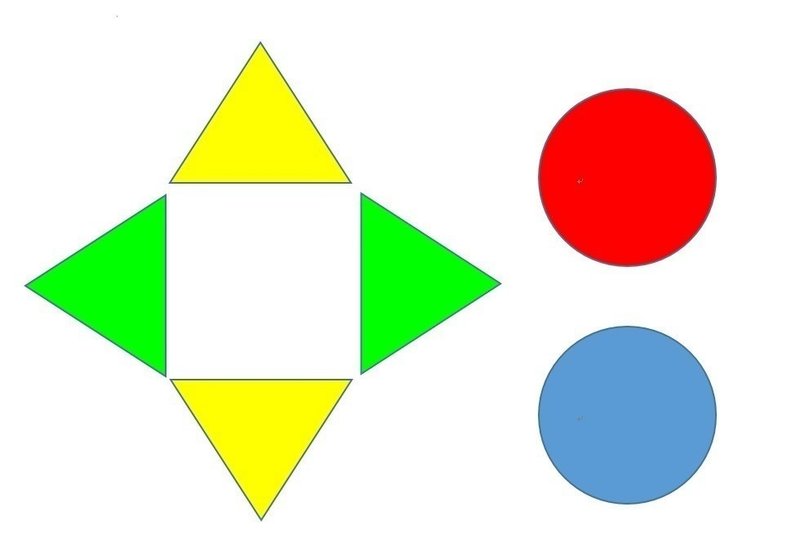
こんなもので、運命が決まる? でも自分のタイミングでボタンが押せるのは良いと思った。自撮りだって自分のタイミングで押せるけど、あんまり自分の思い通りの構図にはならなくて、あと気を付けないと腕も入ってしまうし、あといかにも自撮りしましたという構図になってしまう。
まあ、でも、どっちにしろフェイクだ。
丸椅子の調整が終わったので、一応アゴと頭頂部は画面の中にある2本の水平なラインの中に収められつつある。もう決定ボタンを押せば運命は発進しだすだろう。他の何百人何千人と数mm単位で重なって。
ただ私は誰とも重なりたくないし、足がカーテンの向こうに見えていて撮影の瞬間に誰かに私がここにいると分かられているのも嫌だった。自分で運命を決められるフリをするのも嫌だった。とりあえず丸イスの上に両足で立った。低い天井に頭がつかえて苦しい。機械の声が、早く撮れと急かす。
画面に抱きつくみたいに倒れ込みながら右足で決定ボタンを踏みつけて、そのまま写真を撮ってしまおうと思ったけれど、ふいに島田君が、誰もいない教材室で裸になってコピー機に跨り「チン拓」を取ったというエピソードが想起され、私は咄嗟にスカートをめくりあげて画面に覆いかぶさった。右足がボタンの感触を感じ、機械がピーと言った。私は証明写真機とキスをしていた。なんならペッティングもしていた。
奥の壁にもたれかかるようにしてなんとか体制を直し、再び丸イスの上での体育座りに戻り、決定ボタンを連打した(写真のプレビュー画面を見たくなかったからだ、実物の写真で見たかったからだ)。
すぐに証明写真機の外に転がり出て、焼けた写真が取り出し口から出てくるのを待つ。あ、これは……死んだおじいさんの死相に一瞬見えたけど、ただのモノクロの光と影の模様だった。ほとんどがスカートでおおわれて真っ黒に映り、ところどころ光が漏れているところがあるものの、女子高生のスカートの中にはまず見えない、ただの抽象的な写真だ。
島田君のように人に言いふらすほどの武勇伝でもないし、由里子に打ち明けたくなるほどの感情の動きがあった話でもない。中途半端な冒険の結果がこれで、私はこの写真が私にふさわしいと思った。
私はこの程度の存在。私はこの程度の存在。
家に帰ると、知らない人がいた。当然のように、私の家の中にいた。
足が凍りついたように動かなくなり、顔の筋肉まで硬直し、声にならない声が喉を通り「誰」と呟いた。
「どうしたの虚無みたいな顔をして」
その声でやっと私は弛緩した。なんだ、お母さんか、と分かった。
私は、お母さんの顔が分からなくなってしまったのかもしれない。でも多分、生きていける。
スキを押すと、短歌を1首詠みます。 サポートされると4首詠みます。
