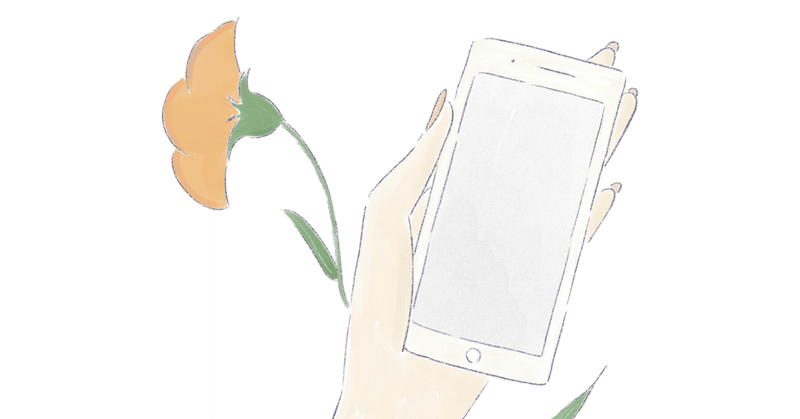
ショートショート『撮りたい理由』
お気に入りのカフェで一緒にお昼を食べているとき、徐に携帯電話を取り出して智美に向けると、それに気が付いた彼女はさっと顔を後ろに逸らしてしまった。起動させていたカメラ画面越しにそれを見たわたしは、むくれながら携帯電話を下ろした。
「…何で撮らせてくれないの?」
「…一人で写されるのが嫌だから」
素っ気なくそう答えて、智美はわたしがもう携帯電話を構えていないことを横目で確認すると、再びカルボナーラの残りを食べ始めた。そうやって食べている姿がかわいいのでもう一度携帯電話を向けたのだが、途端に智美に横目で睨まれ、口にパスタを入れながら「ちょっと!」と怒られてしまった。
写真を撮るのが最近のブームになっているわたしは、今目の前にいる親友の写真を既に何枚か撮っている。ちゃんと視線をもらえているのもあれば、完全にそっぽを向いた隠し撮りもあるし、カメラに気付いてこちらを睨んでいる写真や、顔の半分ほどが智美の手で隠されてしまっている写真もある。
撮る度に彼女に文句を言われ、「消してよ」と言われるのだが、もちろん全部カメラロールに残したままだ。笑顔の写真は一枚も無く、愛想よくポーズを取ってくれるわけもないので、写真はどれも不機嫌そうに見えるものばかりだ。本人が自分でさっきも言ったように、智美は一人で写真に写されるのが嫌いだ。「わたしなんかを写して何が楽しいのか分からない」と彼女は言うが、残念ながらわたしにとっては楽しいことこの上ない。
別に、現像して部屋に飾るとか、待ち受け画面にするとか言っているわけではないのだから、好きに撮らせてほしいと頼んでみるのだが、全く耳を貸してくれない。わたしは、何とかして智美に撮影を認めてもらおうと躍起になっていた。
「…何で? 別に変わんなくない? 誰かと一緒になら撮らせてくれるのに。…納得いかない」
そうなのだ。智美は別に「写真を撮られるのが嫌い」なわけでは無い。その証拠に、わたしのカメラロールには友人や家族、智美の彼氏など、誰かと一緒に写る彼女の写真もそれなりに保存されているが、どれも嫌そうな顔などしていないし、カメラ目線でちゃんとポーズも撮ってくれている。中にはわたしと一緒に写してもらった写真だってあるが、それもいい表情のものばかりだ。普段なかなか見せてくれないような微笑みだって浮かべてくれるし、「もうちょっと笑って」などと言えば意外なくらい素直に従ってくれる。そういう智美を知っているからこそ、わたしが構えるカメラに大人しく一人でも収まってほしいのに、そうなると話は全く別らしい。
わたしの不満を受けた智美は、少しの間無言でカルボナーラを食べ続けていたかと思うと、ため息交じりにこう答えた。
「…だって、飽きるほど見てる顔だよ? 特別何か変わるわけでもないのに」
「…変わるよ、だって、動いてるのと止まってるのとじゃ違うじゃん」
「……じゃあ、小雪は『動いてるわたし』より『止まってるわたし』の方がいいの?」
「…え? いや、そーゆーことじゃなくてさ、」
「じゃあ一体『どーゆー』ことなのか、わたしにも分かるように説明してほしい…」
またカルボナーラに屈みこみながら、智美はわざと意地悪を言ってきた。口調と表情を見ていれば分かる。彼女はわたしを困らせたいのだ。困らせて、写真を撮るのをやめさせたいのだ。親友の考えていることが手に取るように分かり、その途端わたしの意地に火が点いた。
「…分かった。じゃあ分かりやすく丁寧に説明してあげるけど、途中で遮らないでよ」
「……」
「わたしはね、写真を撮るのが好きなの。楽しいから。カメラが好き。好きなもので好きな人を撮りたいと思うのって当たり前なことじゃん? 智美は生きてるから、常に動いてて、静止してるなんてことはただの一瞬も無い。動き続けてて、一瞬一瞬はすぐ過去になっちゃうからもう二度と戻って来ない。一時停止して『さっきのもっかいやって』ってわけにはいかないの。再現はできたとしても、一旦通り過ぎて来ちゃったものを全く同じように繰り返すのは無理。でしょ? でも写真に写したら、そういう『通り過ぎる一瞬』をずーーっと取っておける。見たいときにいつでも見られる。動き続けてて眺めていられない『一瞬』を閉じ込めておけるの。分かる? ほんとは通り過ぎちゃうだけのものを、絵みたいに閉じこめておけるんだよ。わたしはそういうものを撮りたい。智美の『通り過ぎちゃう一瞬』を撮りたい。大好きな友達だから」
「……」
「…これでも納得できない?」
智美は今や動きを止め、じっとわたしの顔を見つめていた。あまり見たことの無い表情だ、と思って、わたしは咄嗟に写真を撮りたくなったが、堪えた。心なしか智美の瞳が輝いているように見え、まるで目の前に突然絶景が広がったかのような、例えるならそんな表情をしていた。
「……小雪、あんたさぁ……」
「…何?」
「…やっぱり、すごいよ」
「………え?」
予想外すぎるセリフに、今度はわたしが固まった。わたしが凝視する中、智美は顔を逸らして俯き、穏やかな声で続けた。
「…小雪の感性が好き」
「………」
「そのままでいてよ。…何も変わらないで」
「……え、智美……?」
智美は顔を上げてわたしを見ると、にっこりと微笑んだ。
「…仕方ないな、反論の余地が無い。参った。……好きにして」
「………」
そう言ってくれた智美はとてもいい表情をしていた。わたしが返事の代りに携帯電話を掲げると、彼女は表情を変えずにまっすぐカメラを見つめ返してきた。カシャ、という音と共にわたしの携帯電話が彼女の表情を閉じ込め、わたしは嬉しくて笑った。
「…いい顔。完璧」
「…良かったね」
顔を逸らした智美は恥ずかしくなったようだった。その頬がほんのり赤く染まっていた。わたしはにやりとして素早くもう一度カメラを起動し、赤い頬のままカルボナーラを食べようとしている智美を撮影した。
「は? なんっ……、なんで今撮ったの?」
「え~~? かわいかったから♡」
「何言ってんの、…意味が分からない」
智美は眉間に皺を寄せたが、「撮るのをやめて」とは言わなかった。その優しさが嬉しかったし、何より、わたしの話を真剣に聞いてくれた彼女が、恐らくはわたしの話に心を動かされ、「感性が好き」とまで褒めてくれたのがものすごく嬉しかった。
素直じゃないようで素直、厳しいようで優しい……、智美が見せてくれるそういう二面性をわたしはこの上なく愛していた。表情も仕草も態度も絶えず移ろう気まぐれな智美。だからなおさら、わたしは彼女の一瞬を逃したくないと思うのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
