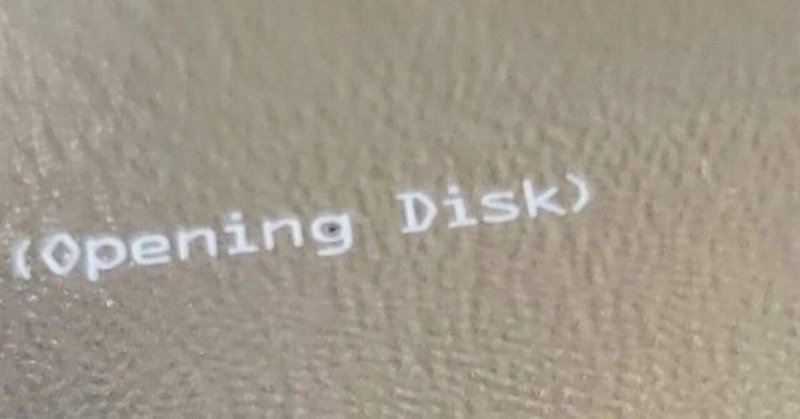
飯野賢治『ゲーム』を読む
飯野賢治 著『ゲーム Super 27 years Life』を読んだ。
1990年代に大きな話題を呼んだゲームクリエイターで、株式会社ワープ代表として活動した飯野賢治氏(2013年没)。
本書『ゲーム』は彼が27歳の時に出版した自伝だ。時期としては1997年頃、自社のタイトル『リアルサウンド 風のリグレット』発売前の段階に書かれ、飯野本人の少年期から現在に至るまでが、彼の記憶をもとに時代を下っていく形式で記されている。
私は読む以前の段階で本書に対しタレント本的な印象を持っていて、それは実際に読んでみても変わらなかった。1ページあたりの文字数は多くなく、「~だよね。~みたいな。」といったくだけた雰囲気の文体は、ふた昔ほど前のインターネット上で見かけた、個人サイトの日記のような印象だ。また当時は許容されていたのかも知れないが、現在ではコンプライアンス的に厳しく思える箇所も散見される。
一方で本書は、彼自身が業界の問題と感じていた部分についてメーカー、個人問わず名前を包み隠さず容赦なく書き連ねていたり、後半には彼が世を離れて隠棲できないか思索するさまが垣間見えたりと、インターネット上で情報をみただけでは感じ得ないことが書かれていた。こうした点については思いがけず新たな発見があり、伝聞のみに頼るのではなく出典にあたることの大切さを今さらながら実感した。
今回の記事は、本書の内容のうちインターネット上で言及が少ないと感じた部分を記したいと思って作成した。なお、見出しに関しては『ゲーム』からの完全な形の引用ではなく、自分がメモを取って要約した形となっていることに留意いただきたい。
『エネミー・ゼロ』はデカルトの方法序説
飯野が中学生の頃、慕っていた教師からのすすめで哲学書を読み、デカルトの『方法序説』を読み非常に影響を受けたという。それに関連し、自らの手がけた『エネミー・ゼロ』と『方法序説』を関連付けて「エネミー・ゼロの物語は方法序説だ。」と記している。実際のところ製作段階で『方法序説』を意図していたのか、それとも本書のテキストを執筆している際に本作が『方法序説』の影響を受けていると後から感じたのかはわからない。実際に『エネミー・ゼロ』を遊んだ自分としては、言われてみればそうかも知れないというくらいであまり腑に落ちてはいない。そもそも自分は『方法序説』をきちんと読んでいないので、改めて『方法序説』を読み直してからプレイしてみるのも面白いかも知れない。
カセットテープを使ったインタラクティブな音楽
高校時代の飯野は通学路の道のりに合わせて音楽を編集し、場所に応じて音楽が変わるカセットテープを作っていた。そうしたインタラクティブなものに興味があったのだという。
また現代美術プロジェクト「アイデアルコピー」の作品に影響を受けたとも記している。
『MOTHER』が良かった。『スクウェアのトム・ソーヤ』もまあまあ良かった。
糸井重里氏が製作に関わったファミコンのRPG『MOTHER』について称賛している。飯野から『MOTHER』の名前が出てくるのはさして不自然なことではなかったが、一方で『MOTHER』と比較する形で『スクウェアのトム・ソーヤ』の名前を挙げて「まあまあよかったが、MOTHERほどではない」と記している。彼が本作を遊んでいたのは意外だった。
自分が『スクウェアのトム・ソーヤ』を遊んでいなかったということもあるが、この二作を並べて考えたことがなく、一風変わった観点だと思った。
任天堂は偉大だけど一個の偉大さ以外もあるべき。悔しいが任天堂カルチャーは偉大。ワープカルチャーはまだない。
飯野があるゲーム誌で任天堂の『スーパーマリオ64』について「宮本さんは所詮2Dまでの人」と発言した、という話は有名だ。この発言をどのゲーム誌で発言したのか、残念ながら自分は出典を見つけることができなかった。
こうしたセンセーショナルな物言いと、彼の反保守的な姿勢もあって、一見任天堂のゲームを否定しているように見えるが、彼は任天堂のゲームカルチャーは偉大だと記している。そのうえでそのカルチャーのものさしから外れたゲームが他にもあるべきだと主張する。ここまでは大方思っていたとおりだったが、この一連の中で「ワープカルチャーはまだない」と記されていたのが意外だった。彼にとっては当たり前の事実を述べたに過ぎないのかも知れないが、自分は彼のことを「戦略的にビッグマウスを装っている人物」だと思っていた節があったため、意外と気が大きい時と小さい時に波がある、そしてそんな状態を本に記してしまうくらい本音を出すタイプの人物なのだなと認識を改めた。
(Dの食卓について)ここまでやって、これでダメならダメでもいいと思っていた。
『Dの食卓』といえば飯野賢治とワープの名を世に知らしめた出世作だ。
当時としては美麗なグラフィックと過激な内容を備えていた本作は、会社規模の小さいワープが多大な労力と資金を投じて作り、開発から発売まで紛糾した様子が記されている。本作のリリース時、飯野は作品に対して自信を持っていたものの、本作が受け入れられなかった場合はゲーム作りをやめていいと考えていたと記している。
また3DO版『Dの食卓』は説明書に凝った仕掛けがあり、自らも良く出来ていると思っているものの、それはあくまでもゲームで人を感動させているわけではなく、そうした部分を描くことを考えたのが『エネミー・ゼロ』に繋がったと記している。
(エネミーゼロ発売当日)アキバはめちゃ売れだけど超めちゃ売れではない。渋谷では売り切れていた。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%BC%E3%83%AD
Wikipediaの『エネミー・ゼロ』の項目には”本作の発売日には飯野自らが秋葉原に赴き、その売れ行きを確認した。その時の感想は「めちゃ売れだけど、超めちゃ売れではないな」。”と記載されている。
情報として間違っているわけではないが、この文章には続きがあり、その後渋谷に出向くと売り切れていたという話や、店舗でファンと交流した話が記されている。ここは本書を読む前と後で大きく印象が変わった部分だ。Wikipediaの項目だけを読むと、思いのほか売れていない様子を飯野が見ているネガティブな印象で終わっている。しかし実際の文章を通して読んでみると、その後出向いた先で売れている様子が記され、飯野本人も安心しているニュアンスが受け取れる文面となっている。
宇宙か海底にドロップアウトしたい。
自分と気の合う者たちだけで、宇宙か海底にドロップアウトし、そこで創作していたいと記している。
本書も後半に入ると、著者のボルテージが相当上がってきていて、特にこのパートは最高潮だ。冗談で言っているにしては妙に現実味を帯びていて、光ケーブルの敷設や外敵から攻められた際の対応など、どうすれば海底にそうした施設を作れるのか、あれこれと具体例を挙げている。いずれにせよ、飯野が外からの声に辟易していて、とにかくここではない場所に行きたいと思っていることが強烈に文章から伝わってきた。
ゲームデザイナーの考えも含めて、ゲームを見るムードがあったらよい。
音楽や小説のように作家の考え方を想像して見てほしいと主張している。
この項目ではゲーム評論について述べていて、「ゲームが合わないのは仕方ないが、理解できないからつまらないと言って点をつけるな。」という、ファミ通での『エネミー・ゼロ』レビューへの反論と同様の展開に繋げている。また、海外のゲームが日本であまり知られていないことへの憤りや、ゲームを取り上げる仕事を自分でもやってみたい、メジャーなゲームを紹介する際にも説明するだけではなく新しい見方を気付かせてくれるようなものであればよい、といった主張が続いている。
こうした「作家性を見てほしい」という主張は当時としてはどれくらい受け入れられたのだろうか。本書の発売当時、自分は小学校入学手前ぐらいでこの辺りのムードはあまりわかっていない。ただ少なくとも2022年現在はゲームの作家性について、特にインディーゲームに関して受け手側がよく考えるものになっていると感じる。
おわりに
実のところ図書館で借りて読んでいたため、今は手もとに現物がない。今回正確な引用をできなかったことをお詫びする。再度『ゲーム』を手に取った際には本記事を書き直すか、手直しして新たに投稿する。
さて、本書に記された内容とネット上で分かる情報を見比べてみると、ネットで見られる情報は大方まとまっていて、著しく違うと感じる部分は見受けられない。それは本書の内容を基にネット上に情報が記され、飯野賢治という人物のイメージが作られているからだろう。しかし実際に飯野賢治による文章を目にしてみると印象が大きく変わる部分は多く、細々した部分がスポイルされていたり、文脈が通じづらくなっていると実感した。本書を読んで得られたことは確かに自分のなかにあるが、記された内容をまとめたこの記事もまた、飯野本人が記したものから様々な要素が抜け落ちてしまっているのではないかと思う。
『エネミー・ゼロ』製作時の技術面の裏話など、彼の考え方以外の部分でも興味深い話が記されているので、興味を持たれたら本書を実際に読んで確かめてみて欲しい。
自分は本書を読み終えて、飯野賢治は「人を個人として見ている」という印象が最後に残った。少年時代から執筆時の27歳に至るまでひっきりなしに個人名が出てくる。時代や役職問わず、貶すのも称えるのも対象は個人で、危なっかしく読んでいるこちらが冷や冷やする。こういった記述が結果的に、その時々のゲーム業界でどのような人間関係があったのかを、飯野個人の視点から読者に浮かび上がらせている。考えてみれば『ゲーム』も、まるで個人に向けて語りかけているような文体である。
そうした彼の会社らしくない、組織らしくない性分や人との向き合い方は、疎ましく感じる人と親しみを感じる人とが、それぞれ両極端真っ二つに存在したのだろうと、自分は想像した。
記事を読んでおもしろかったらサポートをお願いします!
