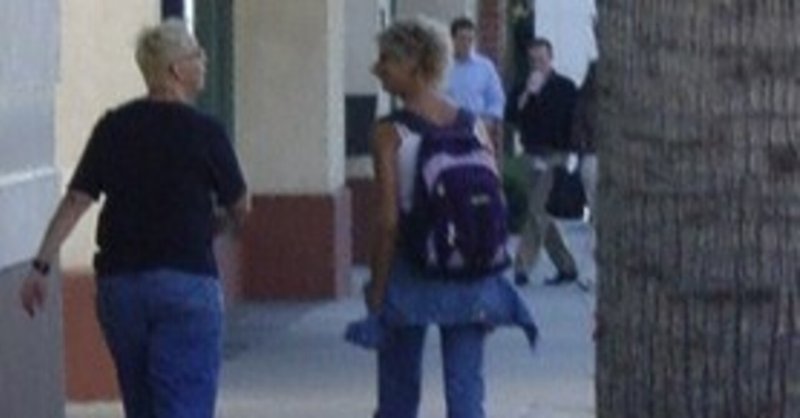
「住民投票という名の無責任システム」の巻
■オバマ大統領に対する期待と不安
バラック・オバマ大統領に対する過度の期待が、筆者は不安であった。ジョージ・ブッシュ大統領の残した宿題を、この「若き英才」がすべて瞬時に解決できるかのような期待がである。マスコミは、まだ就任していないオバマを、FDRやJFK、果ては、エイブラハム・リンカーンにさえ例えていた。保守系ラジオの人気パーソナリティのショーン・ヘネティは「オバマ・マニア」たちが、彼をメサイア(救世主)に祭り上げていると警告を発している。大衆は待つことを知らない。期待の裏返しは憎悪である。難問山積のアメリカ経済、そしてあの、親中派の筆頭であるヒラリー・クリントンが担う外交。希望を唱えて当選したオバマと新政権に暗雲漂うことを感じたのは、筆者だけではあるまい。
■世論を真っ二つにした「住民投票」
一方、大統領選挙の一般投票が行われた2008年11月4日は、連邦議会議員選挙や地方選挙があると同時に、もうひとつの投票が行われていた。それは、日本で言うところの「住民投票」である。
まず「住民投票」という言葉であるが、これは「誤訳」だ。住民ではなく、あくまでも有権者による投票だ。筆者は当時、永住権を持つ地域住民だったが、選挙権がないのでこちらにも投票権はない。そういったことをわかっていながら、マスコミが「住民投票」と言い続けたことに、筆者は何か怪しいものを感じるのだが、それは穿ち過ぎだろうか。とまれ、当日はその、有権者投票が行われ、数多くの法案に選挙民自身が賛否を決めた。
選挙民による投票で法案の採否を決めるやり方には2種類あり、今回のように住民の要求(提案)で法案化され、投票にかけられたものをプロポジション、議会が住民に賛否を問うものをレファレンダムという。
筆者が住んでいたカリフォルニアではその時、何と12もの法案が投票にかけられた。前述の通り、地方選挙の投票もあって、投票に行くのが億劫になるのではないかと思うくらい、アメリカの有権者は、一度に多くの判断をしなければならない。
■議員は何をしている?
今回の住民提案で筆者が気になったもののひとつが「ハイスピード・レールウエイ」、言い換えると、カリフォルニア縦貫新幹線に関するものだ。これは低迷する景気の起爆剤だと考えられている。かつてあった鉄道網を、自動車産業と石油産業が、寄って集って台無しにしておきながら、50年後になって、建設と経営を通じて多くの雇用を創出し、自動車=石油への依存を低くして、環境にも好影響を与えると、素直に見直すところがアメリカらしい。その超巨大事業の建設債について、起債の賛否を問う法案が、今回住民提案という形で問われた。果たしてそんな重要なことを、何の責任もない有権者の投票で決めてよいものだろうか。そもそもその他の法案も、無責任な大衆に決めさせるというのは、代議制民主主義の原理と相反する。いったい州議会議員は何の為にいるのだろう。これは陪審員制度にも言えることだ。陪審員が量刑までするのなら、裁判官などいらないではないか。
■「同姓婚」の真の問題点
さて今回、カリフォルニア州の住民提案で最も注目を集めたのが、同姓婚を州憲法で禁止するという「提案8」である。結果は日本でも報じられたとおり、大方の予想に反して可決された。その後も、反対派は示威運動を精力的に行い、州最高裁に持ち込む構えだ。
しかしこれとて、是か非かで決められる問題ではなかったはずだ。誤解のないようにしていただきたいが、筆者は同姓愛に特に好意的だという訳ではない。伝統的な婚姻制度と家族制度を支持する者であり、ホモセクシュアルの嗜好など100%できないが、彼らにそれを強制的にやめさせることは不可能であるとも思っている。だからこそ、彼らの基本的人権にあたる部分については、何らかの法的保護が必要だとも思うのだ。
現実問題として、事実上の「同姓婚」が行われている以上、例えば、ドメスティック・パートナー(一般には同棲相手を指す言葉だが)の暴力、財産の相続や譲渡、親権などに対する何らかのルールは不可欠だろう。筆者は個人的に「結婚」や「婚姻」ではない、新しい言葉を創出し、通常の婚姻との違いを明確化した上で、同じ権利を基本的に認めることが必要だと考える。今回のように、是か非かで決めてしまうことは何の解決にもならず、永遠に対立が残ることになるからだ。
■吉野作造が見抜いた住民投票の欺瞞
日本史教科書では単なるデモクラシーの宣教師とされている吉野作造。しかし彼は「住民投票」の危うさについて、既に大正の初めにそれを指摘していたのだ。
都合のよい部分だけつまみ食いされている有名な論文『憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず』において吉野は、有権者に全てを託す民主主義は危険思想だと喝破している。そして、所謂住民投票については、「『しかり』『いな』によって決し得るがごとき単純なかたち」に物事を歪めるもので、「代議政治の欠点を補うとはいうけれども、実際の効用はきわめて少ないのみならず、これを頻繁に行うときは、代議制の根底を動揺し、その円満なる発達を妨ぐるの恐れがある」と、指摘しているのだ。
今、アメリカで行われていることは、まさにこの愚行ではないか。ブッシュが起こしたイラク戦争でもなく、世界大恐慌以来の金融危機でもなく、吉野が見破っていた「危険思想」の罠にまんまと引っかかっていることが、実は本当のこの国の危機なのではなかろうか。
『歴史と教育』2008年11月号掲載の「咲都からのサイト」に加筆修正した。
【カバー写真】
サンタモニカで見かけた、一見して同性愛者だとわかる女性のカップル。イエスかノーかで決まった結論は、同性愛問題の本質を単純化し、対立を助長するだけだった。(撮影筆者)
【追記】
オバマ当選直後の記事がベースだが、メディアのはしゃぎ方と、2020年の不正大統領選挙擁護が見事にオーバーラップする。今やFOXでテレビ番組を持つようになったショーン・ヘネティの、「『オバマ・マニア』たちが、彼をメサイア(救世主)に祭り上げている」という警告は、杞憂ではなかったと思われている。史上初の認知症大統領の陰にいるのは、オバマとクリントンだという噂が真実かどうかはわからないが、少なくとも彼らとその仲間たちが明らかな不正選挙に異議を唱えなかったことは確かだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
