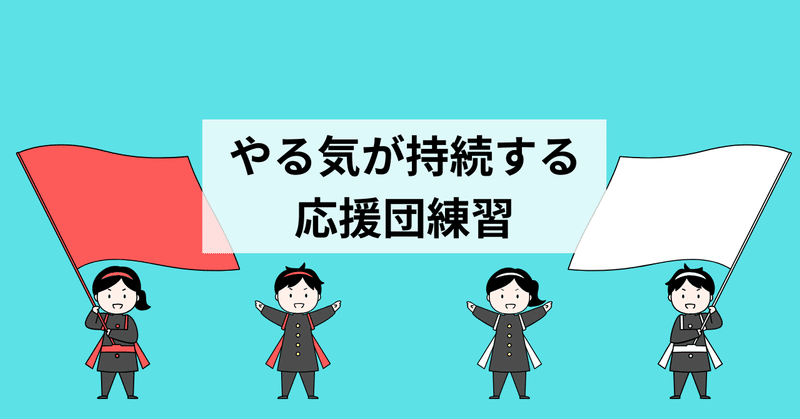
やる気が持続する応援団練習のコツ
応援団の練習どうしたらいいの?
運動会の季節ですね。応援団の練習なんかも始まるんじゃないでしょうか。指導方法の「いろは」も分からない若い頃、若いからというだけの理由で、よく応援団を任されました。どう指導していいやら分からず困り果てていましたが、先輩の先生方のまねをしたり、アドバイスをもらいながら少しずつコツを掴んでいきました。
応援団の練習でも、運動会のダンスの練習でも、劇の練習でも、学習発表会の練習でも同じなのですが、いかに集中を持続し、ピークを本番にもっていくかが鍵になります。
「継続は力なり」と言うことわざがあるように、続けることは成長の近道です。とは言っても人は飽きやすい生き物です。同じことの繰り返しは飽きます。「三日坊主」と言う言葉もありますしね。かく言う私も、ダイエット、筋トレなどなかなか続かないと言うとても人間らしい性格のもち主です(笑)
人はなぜ飽きるのか?
答えは「同じことの繰り返しに飽きるから」です。そうなんです。ここに練習の難しさが潜んでいるのです。人間は「同じことの繰り返し」つまり反復練習をする事によって、上達しそれは手続き記憶として定着していきます。ところが、人間は変化のない単純な反復練習が苦手なのです。すぐに飽きてだれます。
ではどうするか?
「同じことの繰り返し」で飽きてしまうならば、「ちょっとずつ変化」させればよい。ちょっとづつ変化させることによって集中力を持続させることができます。変化していれば人は集中力を持続させることができるんです。運動会のダンスの練習でも同じではないでしょうか。
①振り付けを覚える(覚えるまで変化の連続)
②隊系移動を覚える(同じ振り付けを繰り返しつつ隊形移動を覚えるまで変化の連続)
③衣装をつけてやってみる(衣装をつけたらピーク、あとは変化なしの繰り返しなのでだれる)
大抵どのような活動もこのような流れで変化を失い、だれていくのではないでしょうか。ではどうするか?たったひとつのことを意識するだけで、変化を継続し、集中力を継続させることができます。
見せる場を変化させる
それは、「見せる場を変化させる」です。人は、誰かに見られると緊張します。他者に見せることは、適度な緊張感とよいところを見せたいというモチベーションにもつながります。では、「見せる場」をどのように変化させていけばよいのでしょうか。いよいよ本編です。
※もちろん何のために応援をするのか?という本質を考えていくことは大前提です。今回はあえて、指導技術というところにスポットを当ててまとめていきます。
1 6年生がみんなに見せる
まずは、覚える段階です。三三七拍子・三三一一三七拍子・応援団の歌などの拍子や動きを覚えます。どの学校でも応援団は大抵4〜6年生で構成されていると思います。6年生が中心となって下の学年の子に教えていく段階です。
ある程度、形になってきたらこのように声をかけます。
だいぶ形になってきましたね。今日は最後に、三三七拍子を6年生に見せてもらいます。明日は全員でやってもらいます。みんなしっかりと6年生の演技を見て学んでくださいね。
最高学年であるという自覚
まずは6年生に見本を見せてもらいます。6年生には、最高学年であるという自覚を持ってもらいたい、そして、下の学年から「やっぱり6年生はすごいなぁ」と憧れをもってもらいたいからです。
予告しておく
いきなりではなく、「今日の最後に」と予告しておくことも大切です。終わりの発表を意識する事により、6年生の練習に自然と熱が入るようになります。
よい点を見つける
発表時は、よいところを積極的に見つけるように4・5年生に伝えます。下の学年から、「やっぱり6年生はすごい」「〇〇くんの顔が上がっていてよかった」「キレがすごい」「動きがそろっていた」なんていわれたら、6年生は最高にうれしい。やる気MAXになります。もちろん、慣れていない4・5年生に全てのよい点を見つけることは難しいので、演技を見る視点を与えるということで、教師も積極的にコメントをします。
2 全員で先生に見せる
いよいよ、4・5年生も演技を見せます。ここで、4・5年生を単独で演技させるのは禁物です。慣れていないのに単独でみんなから見られるという経験は、負荷が高く、場合によって慣れていない子は萎縮してしまいます。負荷の低いものから順番に負荷の高いものに変化させていくことが、集中力とモチベーションを持続するコツです。
というわけで、前日に演技をした6年生とともに全員で演技をします。
演技の後は、先生がよいところを中心としアドバイスも含めてコメントをします。
3 男女別に学年ごとに見せる
学年ごとに見せると先生に見せるより緊張感が高まります。何しろ演技している人数よりも見ている人たちの方が多いんですから。当然、集中が持続します。
演技の後は、先生だけでなく、子どもたちにもよいところを中心とし、アドバイスも含めてコメントをしてもらいます。
4 男子は女子に女子は男子に見せる
次の段階は、異性に見てもらう段階です。異性に見せるということで、同性の学年別や先生に見せるだけより緊張感が高まります。予告しておくと、より練習に熱が入ると思います。
演技の後は、先生だけでなく、子どもたちにもよいところを中心とし、アドバイスも含めてコメントをしてもらいます。
5 相手チームの先生に見せる
赤組白組それぞれが相手チームの先生に見せる段階です。この頃になると、動きや歌はほぼ完璧にできるようになり、より高い精度を求める段階になっているはずです。
応援団はやはり応援で相手チームに勝ちたいと思っています。相手チームの先生に見てもらうことは、いや、自分たちの出来を見せつけることはかなりのモチベーションになります。
相手チームの先生にとっては敵情視察という側面もあります。
コメントをもらうときには、プラスのコメントやアドバイスとともに軽い煽りを入れてもらうと、子どもたちのやる気に火がつきます。
例えばこんな風に、
白組の三三七拍子のキレがよかったね。みんな揃っていたのが素晴らしい。ここまで揃えるのはなかなかできることじゃないなぁ。1つアドバイス。団長の〇〇君は、常に顔を斜め上にあげて演技をしていた。しかも、目力がすごかった。ほらみんな見てみて、今も先生を見つめる目の力がすごいでしょう。ぜひみんなもマネしてみてくださいね。ま、赤組も負けてませんけどね。明日の直接対決は赤が勝つからね。
こんな感じで翌日、お互いに見せ合うことを予告しておくとさらに練習に熱がこもります。
6 相手チームに見せる
いよいよ相手チームと対決です。対決相手の演技を見ることで、より客観的に自分たちの演技を振り返ることができます。自分たちの優れている所、相手に学ばなければならないところを実感を伴って理解できます。
演技を見た後は、お互いのよいところを讃えあうことも忘れずに。
7 相手チームと同時に行う
6が終わったら、同時にやってみるのもよいです。同時に声を出し演技をする事により、相手に負けまいと思ってもいないような力が出ます。子どもたちも、「オレたちまだこんなにできるんだ」と自信を持つことができるはずです。
8 応援団じゃない人に見せる
ここまできたらもう応援団の中に見せる相手はいません。そこで、応援団以外の先生に見てもらうと、変化がありよいです。
練習中に下校指導から帰ってきた先生にいきなりお願いして見てもらったり、学校へ遊びにきていた低学年の子どもたちに見てもらったりしたこともありました。低学年の子どもの前で演技する子どもたちがとても真剣だったのが印象的でした。小さな子の前でカッコ悪いところは見せられない。やはり、相手意識というものがとても大切なのだと感じました。
他には、教務主任の先生、教頭先生、校長先生なんかに見てもらうのもよいです。ポジティブで子どもたちのモチベーションが上がるような的確なアドバイスをいただけます。
まとめ
まだ、全校練習まで入っていませんが、変化の付け方だけでも多くの方法があることに気づかれたと思います。コツは負荷の小さいものから少しずつ負荷の高いものへ見せる場を変化させていくという事です。これは、授業でもレクリエーションでも同じです。よろしければ、参考にしていただけるとうれしいです。
今回は、全体練習の前までについて「見せる場を変化させる」というキーワードで書いて見ました。まだまだ色々な指導の仕方があります。機会があればまとめたいと思います。
子どもたちを指導するときのちょっとしたコツについてはこれから下のマガジンにまとめていきます。よかったら登録を。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。記事の内容がよかったらスキやフォローをしていただけるとうれしいです。跳びはねて喜びます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
