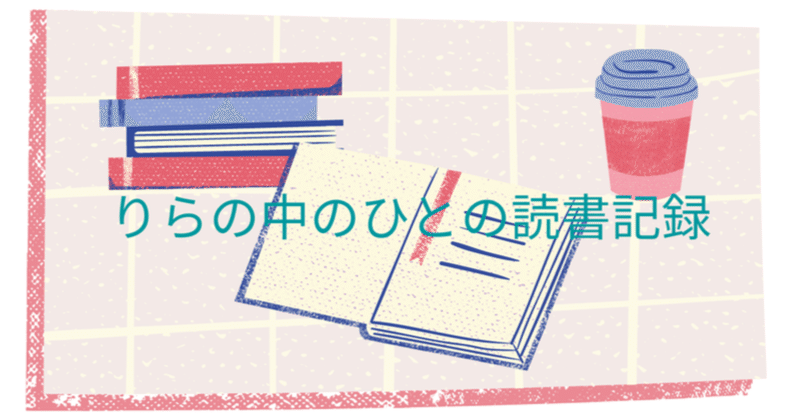
【本のご紹介】国里愛彦、片平健太郎、沖村宰、山下祐一 「計算論的精神医学 情報処理過程から読み解く精神障害」
国里愛彦、片平健太郎、沖村宰、山下祐一 「計算論的精神医学 情報処理過程から読み解く精神障害」 (勁草書房 2019年)
手に取ってみたら、病院在職中にお世話になった方が共著者のお一人でした。縁ですね。
***
主観と裁量に支配されがちな精神医学において、明確な測度(バイオマーカー)を定め、数理的な理解とモデル構築を進めることで、診断や疾病分類の精緻化、情報処理機能とその障害における説明理論(特に生理学と臨床精神医学との橋渡しの面で)の確立に資することを狙う、現代的で野心的なアプローチを紹介しています。
「計算論的」と称するだけに、数学的な(数理言語による)理解が求められ、慣れない読者(私を筆頭に)は、微分方程式を駆使した解説に怖気づくかもしれないが、繰り返し丁寧に解説を付してくれているので、頑張れば読了可能です(高校数学をそれなりにこなし理解を保持している方は、頑張らなくても恐らく大丈夫)。
***
知的障がいの診断では、よく定義された測度と標準化されたテストにより算出された数値が一定水準以下であれば、機械的に(操作的に)診断がなされるものです。ただ、多くの精神疾患では、客観性公共性が必ずしも担保されない症状の記述に基づく“弱い”診断にとどまります。本書は、計算論的手法の精神疾患への適応の可能性を含め、丁寧に論じます。いつか、生理学的な、神経心理学的なマーカーを検査し、精神疾患の診断ができるようになる日が来るのだろうか…
***
7,8年ほど前に、「重力とは何か」という一般向け解説書(文献参照)を読んだことがあります。「重力」とは何か、というテーマを手掛かりに、ニュートン物理学と特殊相対性理論、量子力学を跨いだ宇宙研究において、物理学と数学との連携によるモデル構築とその検証の大切さを論じていたのですが、今日の(今後の)精神医学においても、数学との連携が大切なのですね。勉強になりました。それにしても、若い頃に数学と心理統計をちゃんと身につけメンテナンスしておくべきだったな。学生諸君、基礎学力(特に語学と数学、私はどちらも駄目だったので、自省を込めて)をしっかり身につけ保ちましょう!
文献
大栗博司 2012 重力とは何か アインシュタインから超弦理論へ、宇宙の謎に迫る 幻冬舎
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
