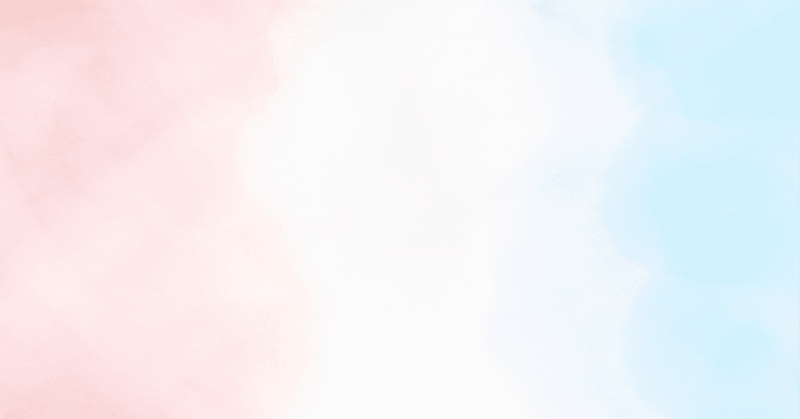
【エッセイ】優しさの起源
「挫折とか、ドロップアウトとか、したことあります?」
居酒屋でTさんから聞かれた。当時、月に3度ほど顔を合わせるメンバー6人ほどで飲みに行った時のことだった。
それぞれの挫折経験や、現在の社会構造に疑問を持ったきっかけを話す流れだったため、それ自体特に不審な質問ではなかったが、私は少々まごついた。小さい失敗や後悔は数え切れないほどだが、特筆するような挫折なく生きてきたからだ。今の社会構造について知りたい、話したい、良くないところがあるなら変えていきたい、私がそう思うようになったことに、たいしたキッカケはなかった。
思い浮かばないですね、と答えてその場は流れたが、お開きの後Tさんが寄ってきて私に言った。
「720さんって、なんでそんなに優しいんですか。」
え、
「いや、挫折経験もなく、政治に特別関心のある家庭で育ったわけでもないでしょ。どうして今の社会の生きづらさに関心があるんだろうって。」
いや、優しくないですよ。
私は優しいわけではない。でも、Tさんの言ってくれたことも何となくわかった。お金に困ることなく健康にぬくぬくと生きてきて、自然災害に見舞われることもなく、両親は健在で、大学も出ていて、就職していて、比較的ホワイトな企業でちゃんとお給料をもらって生活している。実際、今の社会で自分が生きづらい立場に追いやられたことは一度もないように思う。
ただ、「この世の中は生きやすいものだ」という信念を早いうちからなくしていたのも事実だ。
私はこれまで何不自由なく生きてきた。にも拘わらず、この世の中は生きづらいものだとわかっている。そしてこの先、今生きづらさを抱えている人たちにとっても、生きやすい世の中になればいい、そうなるように変えていくべきだと信じている。
それを「優しい」というのなら、私がどうして優しくなったのか、いくつか思い当たることがある。今回はそのうちのひとつについて、とりとめもなく書いてみたい。
お正月は、母方の祖父母の家へ行くのが恒例だ。居間へあがると、祖母が腕によりをかけて作った素晴らしい料理が所狭しと並ぶ食卓に迎えられる。そこにおせち料理やお雑煮はない。もやしとゼンマイのナムル、卵焼き、蒸し豚、ム、天ぷら、そしてトック汁。並ぶのは、最高に美味しいこれらの料理だ。
あれはいつだったろう。少なくとも、まだ小学4年生にはなっていなかったのではないだろうか。4つ歳上の兄が、新聞社のキャンペーンに応募して韓国へ行くとかで作文を書いていた。その内容を母に相談するとき、私の目を憚るような素振りがあって、気になったことを覚えている。私のそんな様子を察したのであろう母が、話してくれたのだ。私の母は在日韓国人3世で、曾祖父母が朝鮮半島から日本へ来た人たちなのだと言うことを。兄はそれを既に知っていて、韓国へ行きたい理由として作文に書いていたらしかった。
じゃあ私ハーフってこと?
ちょっと興奮していたと思う。知らなかった自分の特性に、ファーストインプレッションとしてポジディブな感情を持ったことはまちがいなかった。
当時、母はすでに帰化しているということも教えてくれた。帰化した理由は、私が尋ねたのだろうか。
「兵庫のおじいちゃんおばあちゃんがな、子どもがかわいそうやから帰化しろってしつこかってん」
その時初めて、父方の祖父母が父と母の結婚をよく思っていなかったことを知り、その理由を知り、差別の存在を知り、私の中には差別する側とされる側の血が流れていることを知った。
当時の私がどこまで理解していたのかはわからないが、とにかく泣いたのを覚えている。母の痛みに共感したのか、差別という醜い現実があまりにも身近に生々しく迫ってきたことがショックだったのか。
そんなわけで、母方の祖父母の家では日本の一般的な食卓とは少し違うものも並ぶ。祖父はビールをメッチュと言うし、母は叔父のことをアジェと呼ぶ。(アジェは韓国語で叔父さんという意味。母も小さい頃は、叔父のアダ名だと思っていたらしい。)
母は「人と同じ」を嫌う。服が人と被るなんてもっての外だし、レストランで頼むメニューまで人と同じは嫌なのだ。母の昔話を聞いていると、小さい頃からとても正義感の強い子どもだったのだということがわかる。小学生のころのアダ名はタイガーマスクだったそうだ。母はこれまでにあったことをなんでもよく話してくれる。つらい、悲しいできごとも含めて。昔の子どもは皆少なからず理不尽な目にあってきたのかもしれないが、母やその兄弟(母は4人兄弟の長女で下に妹が2人、弟が1人いる。)はそれにしてもよく理不尽な目にあってきた方だと思う。母の昔の夢は、警察官だったらしい。正義感の強い母に相応しい夢だが、当時韓国国籍だった母にはどうしようもなく叶わぬ夢だった。結局、進学先の大学では児童文学を学んでいる。当時日本で唯一、児童文学を学べる大学だったそうだ。人と同じであることを嫌う母らしい選択だと思う。
母は生涯を、この多様性の乏しい島国の中でマイノリティとして生きてきて、人と同じでいることのできない人生を、人と同じことはしたくない人生に変えていったのかもしれない。生きづらかったろうこれまでの道のりは、正義感と他者への共感力を育て、今の母を輝かせている。ただし、母の嫌いな言葉は「人は悲しみが多いほど人には優しくできる」であることをここに添えておく。母は、自分のつらい経験を誇ってなどいないし、私たち子どもに対しては「つらい経験をたくさんした方が人生に深みが出るなんて嘘だ」と教えてきた。誰もつらい思いをしないのが1番だと母は信じているし、私もそう思っている。
結局なにが言いたいのかよくわからない内容になってしまった。私は社会の中でマジョリティとして恩恵を受けながらにして、その実マイノリティとしての特性とそこに息づく母や祖父母、曾祖父母の物語に誇りを持って生きている。「普通の日本人」としての人生を享受しながらも、アイデンティティはむしろ母側の出自にあるのが不思議だ。
正常な議論が機能しない民主主義は多数決でしかない。そしてこの多数決の世の中で、生きづらさを押し付けられるのはいつもマイノリティ側の人たちだ。
私は母から出自を聞かされた日、初めてマイノリティになった。相変わらず、社会属性としてはマジョリティのままだったから、生きづらさはなかったけれど、心情的には全くマジョリティではないのだ。
昔からよく見る夢がある。母方の祖父母の家で、親戚みんなが隠れているという夢だ。2階の奥の押し入れで、息を潜めて隠れている。そこに、バタバタと足音がする。複数人が近づいてくる。ついに扉が開けられてしまう。そこには日本兵が立っていて、私たちを捕虜として連れていこうとしている…
アンネの日記を読んだ頃から、何度か見ている夢だ。妙に生々しくて、いつも汗びっしょりで目覚める。帰化しているからって、「完全な日本人」ではないのだから、異常な世の中になってしまえば、いつヨソ者として駆除対象とされてしまうかわからない。マイノリティの心には、そういう恐れがいつも燻っていると思う。
「優しくない人」は、自分のことだけしか考えていない。自分さえ良ければいいんだ。それはそうかもしれないが、「優しい人」が他人のために戦う理由は何だろう。もしそれが完全に「人のため」なのであれば、それはそれで異常なことだと思う。でも違うんだろう。
私たちは皆、いつどこでマイノリティになるかわからない。交通事故や病気でハンディキャップを背負うかもしれないし、マイノリティと家族になるかもしれない。海外へ行ったら「普通の日本人」だってマイノリティだ。そのことを自覚している人は、いま生きづらい人たちに優しくならざるを得ないだろう。完全に他人のためではない。自分がこの先、この世の中で生きてゆくことのリスクヘッジとして「優しい」のだ。もちろん、打算でしているわけではないけれど。
以上、本当にとりとめもなく書いてしまった。また機会があれば。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
