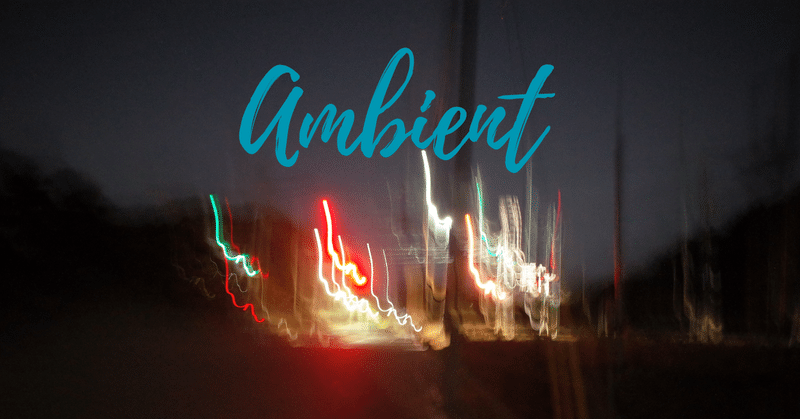
【短編小説】Ambient:地球の送風機能が壊れてしまったかのようだったあの静かな夜に今夜はそっくり
今日はなんとなくあの夜に似てると思うんだ__寒い?暖房が効くまでに時間がかかるのはね、この車を買ったのが、例の干からびた谷間の中古車屋だからだよ__そういえば、まだ小学生だったころによくみんなで行ったよね__レジスターの前の、店主の死角にあったスニッカーズの箱は撤去されてた__そういうのにうっかり気づいちゃうと、悲しい気持ちになるね。やりきれないよ。
当時だってきっと景気は良くなかっただろうけど、今ほどじゃなかったわけだ__あのころは帰り際に一本盗っても大目に見てもらえた__だけど、もう、そういうわけにはいかなくなったんだろうね。ぼくたちはもうスニッカーズに興味を失ってしまっているけど、もしぼくたちより若い世代がふいにそれを欲しがったときに、簡単に手に入れる手段がないってこと、これはね、ただただ悲惨なことだなと思うんだ__この地上じゃ、最悪ばかりが新記録を更新していくみたいだよ。
あの夜の話に戻るけど__というか、ぼくは最近はたいてい投資のことを考えてて、休日はお金が無性生殖していくようすにうっとり見入ってる__金魚やハムスターを飼って育てるようなもので、やってるうちにだんだん愛着が湧いてくるんだ、不思議だよ__で、そんなぼくだけど、とにかく、小説を読んでた時期もあったわけだ。聞いた話じゃ、小説を読むと語彙とか文章力が身につくんで、自分の考えを正確にかつ簡潔に周囲に伝えられるようになって、どういう理屈か知らないけど、結果的に生涯年収が上がるらしいんだって__。
つまりその晩ぼくは小説を読んでいて、たしかセリーヌって作家の本を読んでいたときだったと思う__セリーヌっていうアパレルブランドが大学で流行ってたんだ。だからだと思う__でも、気づいたら眠ってるんだ。10分読んでは5分眠る、みたいな繰り返しで、読む眠る読む眠る読む眠る読もうとしたところで彼女からLINE電話がかかってきて__信じられないかもしれないけど、当時はまだみんなLINEを使ってたんだよ。経営統合の前だったし。
「まだ起きてる?」
頭の取れたしまじろうの置き時計が、トラの爪で夜中の2時をさしてて__永遠に尻尾を振ってるのは興奮してるからじゃなく、昔からずっとそうしているんだ__気味が悪いよね。
「読書をしているところ」
ぼくは誇りっぽく__誇りっぽくって言い方って存在してる?__言ったと思うけど、電話の向こうの反応はとくになくて、
「いま駅にいるんだけどさ、拾ってくんないかな? 終バスなくなっちゃって」
と回らないろれつで言ってきた。ぼくとしては面倒くさいから断ろうと思ったんだ__。
同窓会の一次会が終わって店の外で20人くらいの大人がぐちゃっとして、それでいて探り合いの目つきがまだ多少残っているときに__たしか今から半年くらい前の話かな__急に彼女がぼくに耳打ちしてきた。「あたしね、じつは昔から君のことが・・・・・・」って、そういう引っ込み思案な打ち明けではなくて__あえて昔から、と言うことで青春の香りを漂わせようとしているのが、なんか__でも実際にそんなことは言われなくて、そのかわり「三好、すごい美人だったね。・・・・・・きみ、彼女のことばっかり見てたでしょ」と言われた。変な気分だった。その言い方が、なんか、この同窓会での話だけじゃなく、学生時代にまで遡って言われているような気がして。つまり言葉の裏の「未だに三好に未練があるの? ダサ!」という含み__。
この三好っていうのはぼくたちにとっては完全な第三者だから、今から説明する気も起きなくて__でもこういう記憶って妙なもので、三好のことはなぜか桜並木と一緒に思い出すんだけど、うちの学校の桜はみんな腐ってて、在学中は一度も花をつけなかったんだ。だから、三好と桜の組み合わせを現実で目にしたことなんて一度もなかったんだけど__まあ、記憶っていうのはなんか変だよね。
__ぼくは苦し紛れに「は?」って返事した。彼女は、知ったような笑みだけ残して二次会には行かずに帰っちゃったんだけど、それ以来わだかまりはあったわけだ。
でも、そんなわだかまりはぼくだけの持ち物だったらしくて__彼女はまるで気にしてる様子がなかった。
「こんな世界のすみっこみたいな場所から、あたしが歩いて帰れるわけないの知ってるよね? もしあたしが凍え死んだら、きみも罪悪感で死んじゃうんでしょ?」
「友達はいないわけ?」
「ひどいこと聞くんだね」
「じゃなくて、いま、きみの回りに。いるなら、その友だちに送ってもらえよ」
「一人。・・・・・・気づいたときにはただ一人、だけどそれが人生なんだって」
「酒臭いよ」
「ぜんぶコロナのせい。終バスの繰り上げ運行ね!」
「たしかに、なにもかもね」
「なにもかも、って?」
行きたくないなあ、面倒くさいなあ、って気持ちを振り払うのは大変だったよほんと__上着を羽織って外に出たら風はなくて、虫の鳴き声がきれいだったのを覚えてる。虫の鳴き声をきれいだって思えたのはたぶん小説を読んでいたおかげだと思うな。だってもしぼくがそのとき昆虫図鑑を読んでいたら、鳴き声とともに虫のリアルな画像が頭に浮かんでとてもじゃないけど素直に「ああ、きれい」なんて思えなかったはずだから__そんなこともないのかな、よくわからないけど。
地味に終電も一つ逃してたから、結局のところ最寄りの駅から3つ離れた駅まで車を走らせなきゃならなかった。カーナビが示す一度も通ったことのない道を30分かけて辿って__やっと駅前のコンビニのフードコートでコーヒーを啜ってる姿を見つけた。窓際のカウンターに座っていたから目の前まで近づいてコンコンと窓をノックしたらやっと気づいてニコっと、まさに酒の力なしでは作れないような笑顔を浮かべてコンビニから出てきた。そんな恰好じゃたしかに凍えそう、って言った気がする。なんか黒っぽい服で、とにかく薄着だった__。
彼女は助手席には座らずに後部座席に座って__タクシー扱いだよな__ぼくは車を発進させて、田舎道を走りながら彼女は陽気でさ、歌を歌いだしたりして、あんまり上手とはいえなかったけど__ぼくだって人のこと言えないんだ。大勢の人間が暗闇の中で息するのを我慢してるみたいな、うるさい静けさってのが深夜にはあると思うんだけど、それを踏みにじっていくような歌声__。
バックミラーに小さな星のようなヘッドライトがきらめいたから、もう一台、自動車が近づいてきてるってわかった。その車を、バイト先で包丁盗んで失踪した先輩くらい不気味に思い始めてたときでも、彼女はなんにも問題ないみたいにフンフンと暢気にやってた。__でも、こんな時間に、こんな道を走るなんて、まともな車のはずがないんだ。しばらく並走して横目に見たフロントガラスは、墨で塗ったみたいに真っ黒で何も見えなかった。
「きみTikTokやってないの?」
歌を中断した彼女が唐突に後部座席から声をかけてきて、もしかしたらあの夜の車の中の会話って、これくらいしかなかったかもしれない。__今日とは大違いなんだよね。
「ぼくには読書があるから」
「つまんないね。それって、なんの意味があるわけ? つまんなくない?」
「でも、年収は上がるはずだけど」
ぼくはまたしても誇りっぽい感じで言ったんだ。
「そんなの絶対嘘じゃん。騙されてるって」
破裂するような酔っ払いの笑い声。それは良くも悪くも、単なる無意味な笑いって感じで__なんかよかった。
「ねえ、あたしのアカウント教えてあげる」
彼女が後部座席から腕を突き出して見せてきたスマホ画面に映る投稿動画には、なんか手だけでダンスの振り付けみたいな動きする彼女がいて、谷間のはっきり見えるオレンジ色の水着を着て、朗らかで可愛らしい表情をしながら誘うように舌をちょっと出してみたりしている感じがたまらなくエ__じゃなくて、むしろアーティスティックできわめて学術的だと思ったね__本当の話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
