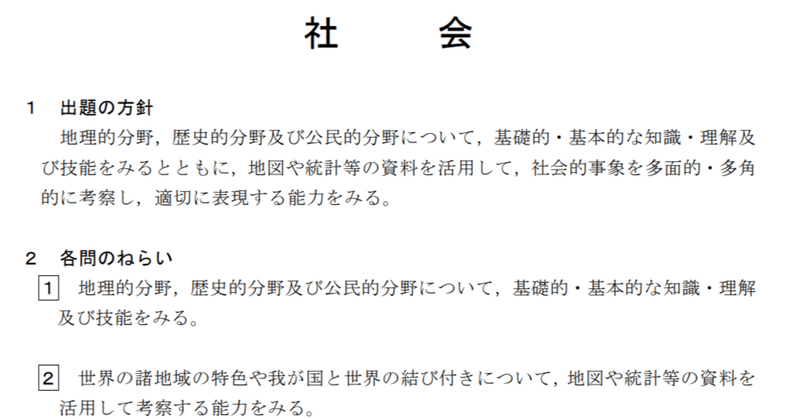
R6 都立高校入試(社会)講評
はじめに
ずいぶんと久しぶりの投稿になってしまいましたが、今回は2024年2月21日に行われた都立高校入試「社会」の分析・講評を「大問別・設問別」に行なっていきます。
主な目的のうち1つは「自分にとっての忘備」、もう1つは未来の受験生に向けて何かの役に立てば……というものです。
興味がある方は是非ご一読ください。
※実際に出題された問題は以下のリンク先にございます。
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/令和6年度都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表|東京都教育委員会ホームページ (
大問1(小問集合)
問1(地理)
例年通り「写真」「文章」「地図」等を組み合わせる問題。
地図記号等のヒントが少ないので、ちょっと手こずるかなという印象。「ある部分」に気が付くと解きやすくなりますが、「試験本番の1問目」という極限状態でそこにすぐ気が付けるかというと……
暖かい部屋でお茶をすすりながらリラックスして解くのと、実際に受験生が起かれた状況とは全くもって異なるので、講評を行うときはそのあたりも考慮しないといけませんね。
この問題だけではなく都立の社会全体に言えることですが、「1箇所だけではなく、様々な部分からヒントを探す」習慣をつけることを普段の学習や過去問演習の時から意識したいですね。
問2(歴史)、問3(公民)
文章を読み、該当する単語を選ぶ問題。
「講師」「社会が得意な生徒」という視点から見ると難易度は相当易しいですが、用語の地道な暗記を「なんとなく」「うろ覚え」で済ませて来た生徒は混同してしまう可能性がある選択肢が並んでいます。
今年の社会で点数が思ったほど取れなかった……という受験生は、おそらく大問1での失点が5点以上あったのではないでしょうか。
大問2(世界地理)
問1
文章を読み、該当する「気候のグラフ」「国の場所」を答える問題。
文章に「コーヒー豆」とあるので、それを見た瞬間「ブラジルやんけ!これはもろたで工藤……!」と思った受験生が多かったことでしょう。せやかて選択肢にブラジルはないので、そこからどう立て直すかが問われます。
答えは「エチオピア」でした。この問題を知った後なら「コーヒーと言えばエチオピアも有名だよ モカコーヒーっていうのがあって……」という風に教えるのは簡単なのですが、試験当日までにそこまで踏み込んで教えていた方は少ないのではないでしょうか。
ちなみにR☆Sの生徒たちは「標高2350m」というヒントで解いてくれた模様です。ケニアやエチオピアの標高が高い、って話は教えてたんですよね。「なぜマラソンなどの長距離種目でケニアやエチオピアの選手が強いかというと…」みたいな感じで。
受験生の中には「コーヒー豆だからブラジルと同じく熱帯かな?」で解いた人もいるかもしれませんし、「タイやサウジアラビアの標高が高いって聞いたことないな……」と「消去法」で解いた人もいるかもしれませんね。
色んな角度から解くことができ、また、日常生活からヒントをとってこられる「都立高校らしい」問題と言えるのではないでしょうか。
個人的には好きです。
問2、問3
地図と資料を使う問題。
この2題については、過去問演習と世界地理の学習をしっかりやっていれば「定番の問題だな」という感覚で得点できたのではないでしょうか。
「大問1」あるいは「大問2の問1」で失点を重ねてしまっていた受験生も、このあたりから調子を取り戻して巻き返し始めたケースが多かったと予想されます。
大問3(日本地理)
問1
恒例の「4つの都道府県の特徴」を答えさせる問題。
色んな角度から解けるので確実に得点したいところです。
問2
文章を読んで「都道府県」と「その都道府県に該当する表」を選ぶ問題。
「都道府県」を「千葉」と「愛知」で迷った受験生が多かったかもしれません。「千葉」が正解だというところまで行ければ、該当する「表」は選べて欲しいですが……
問3
記述。
令和になってからは「解答欄が2つに分割されていて、短めの文章を2つ書く」という形式でしたが、久しぶりに「解答欄が1つであり、文章を1つだけ書く」形式に戻りました。とは言え「設問をよく読む」「与えられた資料のすべてを比較・活用する」という方針は同じなので、正答例に近い内容が書けた受験生は多いのではないでしょうか。
大問4(歴史)
問1
定番の並び替え問題。
与えられた選択肢の中にたくさんのヒントが散りばめられているので、しっかりと対策してきた受験生には易しかったかもしれません。
問2
記述。
近年は「年表問題」であることが多かったので「えっ ここで記述か」と、面食らった受験生もいたことでしょう。
「大問3の問3」の項で書いたように、都立の記述は「設問をよく読む」「与えられた資料のすべてを比較・活用する」というのが2大方針で、この問題もそれに沿っていくことには変わりないのですが、正答例を見ると「うーん、ちょっとこれを書くのは厳しいのでは……」という感想が拭えません。
勉強してきた生徒ほど、正答例の中にある「太平洋」「日本海」というワードを使わない気がするんですよね。代わりに「東廻り航路」「西廻り航路」あるいは「南海路」という言葉を使った受験生が多いのではないでしょうか。設問に「輸送経路」とありますが、少々誘導が弱いように感じますし、「河村瑞賢が幕府に提案した……」と書かれているのでいっそう「東廻り」「西廻り」というワードを使いたくなりますよね。
記述については高校ごとに採点基準が違うので、果たしてどこまで点数が与えられるのか、許容されるのかも気になるところですね。
問3、問4
与えられた4つの選択肢の年代がそれぞれいつなのかを特定していく問題。
2題とも基本的なタイプは同じであり、広い意味での「並び替え」。問4は「図表の読み取り」でも解けるところが問3との違いですね。
大問5(公民)
問1
「憲法の条文」を選ぶ定番問題。
R4のように「精神の自由」にあたる選択肢が2つあって、そのどちらなのかを吟味しなくてはいけないタイプだと難度が上がりますが、今年度は「平等権」にあたる選択肢が1つしかないので容易でしたね。
問2
グラフ・文章の読み取りとちょっとした計算が必要な問題。
「"全体"の数字を使って計算する」という訓練をしていないと少々迷ってしまったかもしれません。
問3
文章を読んで年代を特定する問題。
いわゆる「SDGs」に関する文章なので、学習したことのあった受験生が多かったかもしれません。
「SDGsか……2015年やな!」という解き方もできるし、そんなことを知らなくても「この手のタイプの問題に対する考え方」を訓練してきていれば解ける問題です。
問4
記述。
話題が「成人年齢の引き下げ」という身近なものであったこと、また「大問4の問2」と異なり、設問の誘導が丁寧なのでそれに沿っていけば正答例に近い内容にたどり着けたのではないでしょうか。
(大問4の問2を根に持っている)
大問6(融合問題)
問1
世界地理と歴史を絡めた問題。
地理や歴史の知識で解いた受験生が多かったと思われますが、「美術」や「国語」の授業で「これ聞いたことあるな……」と解けたケースもあったかもしれません。(黒田清輝/ルーブル美術館:フランス 漱石:イギリス 鴎外:ドイツ)
「選択肢のあらゆるところにヒントがある」という都立社会の特性を理解していれば1つ1つクリアしていける問題です。
問2
文章を読んで年代を特定する問題。
国際会議に関する文章でした。
「世界金融危機」についてはR☆S生にはめちゃ教えたのですが、謎に頻出なんですよね。もし知らなくても「大問5の問3」と同じく「考え方」を身につけていれば解けるタイプの問題ではありました。
問3
国連加盟国数の推移に関する問題。
似たタイプの問題を解いたことがあった受験生が多いでしょうし、与えられた文章のヒント量が多いので、時間さえ残っていれば落ち着いて正答にたどり着けたことでしょう。
総評、そして今後の受験生へ
難易度については「例年に比べて簡単だった」といった声も各所の講評等で散見しますが、平均点としては例年と大きくは変わらない数字(50点台後半)に落ち着くのではないでしょうか。
大きな理由としては記述問題が「2題→3題」に戻り、想定していたよりも時間が足りなくなったケースがあったと予想されるためです。
ただし、令和4年(平均:49.2点)のような理不尽さを感じる問題はほぼなかったので、「30~40点しか取れませんでした……」という爆死をした受験生は少なかったかもしれません。(しっかりと準備をしてきたのであれば、ですが)
さて、これからの受験生が勉強していく上で意識して欲しいことは以下の3つです。
①基礎知識の徹底
これはもう各所で繰り返し言っていることですが、「基礎知識の定着なくして社会の点数アップなし」です。やれ「グラフ・資料を読み取る力」だの「思考力」だのが必要とされる風潮ではありますが、「基礎知識がなければ正しく思考することはできない」し、「思考力があっても基礎知識がなければ正しい正解にたどり着けない」こと請け合いです。
「基礎知識?何すかそれ?」と言われれば、たとえば地理なら「都道府県」「県庁所在地」「世界の国々の位置(まずは30か国くらい)」、歴史なら「時代の順番」「その時代がおおよそ何年から何年までか」といったものです。「ほーん そんなことでいいのか」と思った人もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら多くの中学生は上記に関する知識が不足しているというのが現状です。恐るべし令和のキッズ…
むやみに問題演習をする前に、まずは基礎知識をしっかりと習得し「正しい問題演習」を行っていきましょう。
②過去問演習
実施する時期によって変わりますが、主な目的は
・時間配分の体得
・問題形式や傾向を知る
・得意/不得意分野や現状の得点率の把握
となります。
「それは模試でもいいんじゃね?」という意見もあるとは思いますが、やっぱり模試って「ちょっと」違うんですよね。「ちょっと」ではあるんですけど確実に違いはあって、しかもその「ちょっと」が結構「大きい」です。(こいつは何を言ってるんだ……と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、わかる方にはわかる話だと思います)
そんなわけで、模試も補助的なツールとしてはもちろん有効なのですが、確度の高さで言えば「実際に出題された問題」である「過去問」が一番であることに疑いはありません。
「じゃあ過去問は何年分くらいやればいいの?」という話ですが、R☆Sの社会では
直近5年分の過去問
を重視しています。
これにはいくつかの理由がありますが、主として「社会はその科目性質上、毎年少しずつデータ等に変化があること」と「傾向・問題形式が毎年少しずつ変わっていること」の2つが挙げられます。例えば「以前はなかった国が今はある(and vice versa)」「昔は記号も手書きだったが、現在はマークシート形式である」といった具合です。今のものと離れた問題よりも、近い問題を解く方が効果は高いよね、ということです。
とは言え、5年より以前の過去問を解くことにも大いに意義はありますし、実際にR☆Sでも実施しています。あくまで「R☆Sの」「都立の社会対策は」「5年分を重視している」というだけの話ですので、塾に通っているなど、どなたかに指導を受けている人はそちらの先生の仰る方針を信じて取り組んでいきましょう。
1年分でも20年分でも、そこにちゃんとした根拠や実施目的があれば良いのです。
③「社会科」であることの意識
「社会」という科目はその名前の通り「社会」を扱います。私たちが生きているこの社会の「産業や気候」「歴史」「ルールや仕組み」といったものが対象です。つまり、
机の上や本の中だけでなく、日常のすべてから学ぶ機会がある
科目です。(他の科目もそうですよ!というツッコミはさておき)
実際に都立高校の問題でも、「日常から色んなことを意識していますか?」という問題が出題されます。(今回で言えば大問2の問1など)
もちろんそうした問題は「机の上で身につけた知識」でも解くことができますが、1つの問題に対する攻め方は多ければ多いほど「速く」「確実に」解くことができます。初対戦のピッチャーと対峙する時に「ストレートの球速」だけではなく「持っている球種」や「投球割合」のデータもあった方が打ちやすいのと同じことです。
今からでも決して遅くはないので、日常の様々なことに興味をもって過ごしてみましょう。皆さんが何気なく観ているバラエティー番組などにも「社会」の問題を解くためのヒントは散りばめられています。
「行動」を変えるというよりは、ほんの少し「意識」を変えるだけです。
というわけで、いかがでしたでしょうか。
R☆S生だけに伝えている禁則事項もあるのですべては書けませんでしたが、なんとなく「都立高校の社会」の雰囲気は伝わりましたでしょうか。
これを読んだ人が受験生であれば少しでも何かの参考になれば幸いですし、また、社会科の指導に携わっている人であれば「なるほどねえ」だったり「ちょっとそれは違うんじゃないの?」だったり、何かしらを考えるきっかけになっていれば有難い限りです。
それでは素敵な春休み(あるいは春期講習)をお過ごしください!
文責:高橋
Special Thanks:R☆Sゼミナール 第16期 中3生

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
