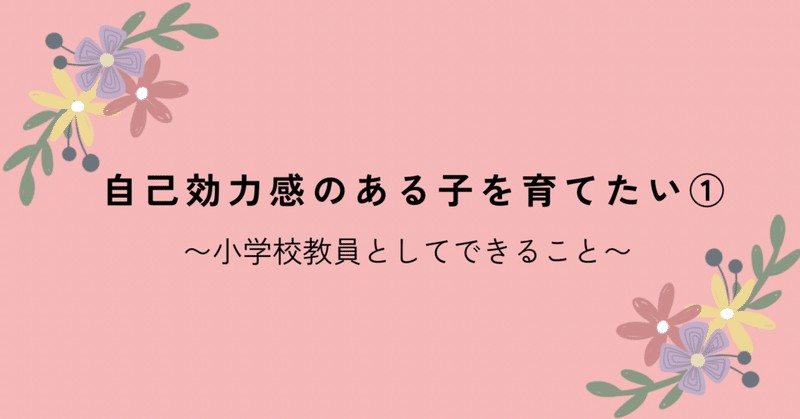
自己効力感のある子を育てたい①〜小学校教員としてできること〜
1.はじめに
こんにちは!2024年、早くも2週間が過ぎようとしていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?
私は今のところ体調を崩さず、元気にしています!いぇーい!
なぜ健康一つで大喜びしているかというと…
↓気になる方は前回記事をご覧ください(笑)
実は加湿器も買って、本格的に乾燥と戦っています…!
今年は本気ですよ…!!!
さて、余談はさておき…
今回は、2024年の目標の一つである、育てたい子ども像を明確にし、そこに近づくための手段を考える!について、
・私が育てたい子ども像とはどのようなものか
・どうしてそう考えるようになったのか
この辺りをお話ししていきます。
2.小学校教員として育てたい子ども像
「自己効力感のある子」を育てたい
前回記事を読んでくださった方は分かると思うのですが、一言で言うと、「自己効力感のある子」を育てたいのです!
自己効力感とは「自分はできる!」と考えられる力のことです。
よく聞く自己肯定感じゃないんかーい!と思った方もいるかもしれません。そうなんです、違うんです。
3.なぜ自己効力感なのか
①”小学校教員として”と考えると
もちろん、自己肯定感(すごーく簡単に言うと…どんな自分でも大好き!自分は自分のままでいい!と思える力。)を育むことができればすごいことでしょうし、育む必要もあると思います。
しかし、同じ子の担任ができるのは基本1年、せいぜい2年(ごくまれに3年)です。一人の小学校教員が、本当に子どもたちの自己肯定感を育むことができるのか?と思ったのです。自己肯定感って、1年でぐっと伸びるものではなく、何年もかけて自分の色んな面を知り、それを肯定されることを繰り返し経験しながら、少しずつ育まれていくものではないのでしょうか。
では、小学校教員は、出会った1年で何ができるのか。学級や学年、学校として集団でいるメリットを生かしてできることはないのか。そう考えたときに浮かび上がってきたのが自己効力感だったのです。
②子どもたちの様子を見ていると
小学生というのは、可能性無限大です。発想が自由なのです。一つ聞けば、あれやりたい、これやりたい、とたくさんのアイデアが出てきます。大人が、難しいからやめようと考えることや、そもそも選択肢の中になかったことまで、どんどん出ます。
楽しいな~、面白いな~、なんて思いながら話を聞いていると、ふと、「いや~無理っしょ。だるいだるい。」という声が聞こえてきました。
経験がある方もいらっしゃるでしょう。クラスに一人はいますよね、こういう子(笑)
その時はちょっとムッとする瞬間だったのですが(笑)、改めて考えると、こんな風に周りは変わらないと諦めて現状に文句ばかり言っている人見たことあるなって思ったと同時に、
そんな人生、つまらない!!!!!!!!!
私が関わった以上、最高の人生にしてやる!!!!
と、私の中の情熱が燃え始めたのです。
(※私はものすごく熱血女らしいです。きっと血の気が多い。笑)
私一人と関わって人生最高!となることは難しいだろというツッコミはさておいて、自分の力で、周りを・日本を・世界を、変えられるという気持ち(=自己効力感)をもつことができれば、きっと今より自分を好きになって、楽しい人生になるだろうなと思ったことも、きっかけの一つです。
③そんなこんなで…
細かく言えば他にも理由はもろもろあるんですが、主にこんな2つが理由で、私は小学校教員として子どもたちの自己効力感を育みたいなと考えるようになったのです。
4.おわりに
ということで、私が熱血女だと暴露したところで、今回は終了です。
いや違います、私の目標の一つが自己効力感のある子を育てるということと、そう考えたわけの話でしたね(笑)
次回からは、自己効力感を育むために今年度実践してきたことや、これから実践していきたいことを話していけたらと考えています。応援していただければ幸いです!
最後までお読みいただきありがとうございました!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
