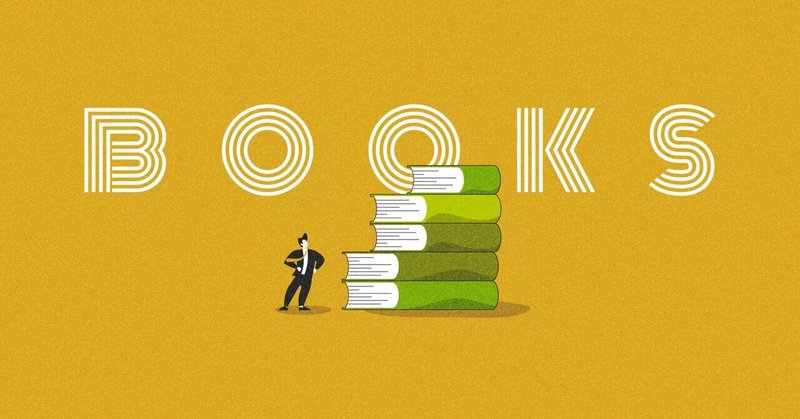
働き方・労働生産性について考える。 ブックレビュー vol.31 ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか
こんばんは。
今日も読書の秋2022の企画に準じて、今年読んだ本のレビューを書きます。
今日紹介する本はこちらです。

(タイトル)ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか
(著者)酒井隆史
(発行日)2022.1.
(発行所)株式会社講談社
(概要)
あの有名なブルシット・ジョブの解説本になる本です。
ブルシット・ジョブ自体は500ページにも及ぶので読むのがしんどいという人におすすめです。これを読んでから本編に挑んでもいいと思います。
(印象に残った点など)
1)100年前から労働者は、賃上げより短時間労働を志向していたこと、100年後には技術の向上とそれに伴う生産力の上昇によって1日4時間労働ですむこと
→最近の働き方改革から生まれたのかと思っていましたが、100年前から短時間労働を望んでいたことには驚きました。
2)"無意味な仕事"はストレスを悪化させる。ブルシット・ジョブとは仕事のための仕事である
3)無目的な遊びは他者から強制されると、不自由になる
→現状の日本の労働システムは9:00~17:00までのように労働時間が定められています。私もあるのですが、やるべき仕事が早く終わっても、17:00より早く帰宅できません。そのため、定時になるまで職場のPCでパソコンやフォルダの整理・誰もみない・きっちり書く必要もない議事録・マニュアルなどを作成していたり、まさに"仕事のための仕事"という無意味かつ時間の無駄としか思えない業務をやっています。これをしているときは、ストレス・不快感がたまっていくなと思っていました。
1)のような短時間労働・労働生産性の改善が日本で進まない理由は、まさに上記で書いたような労働時間を固定されていることが原因ではないかと思います。フレックス労働など導入する会社はありますが、するべき仕事が終わったら、定時よりも早く自由に帰宅できることが理想型かなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
