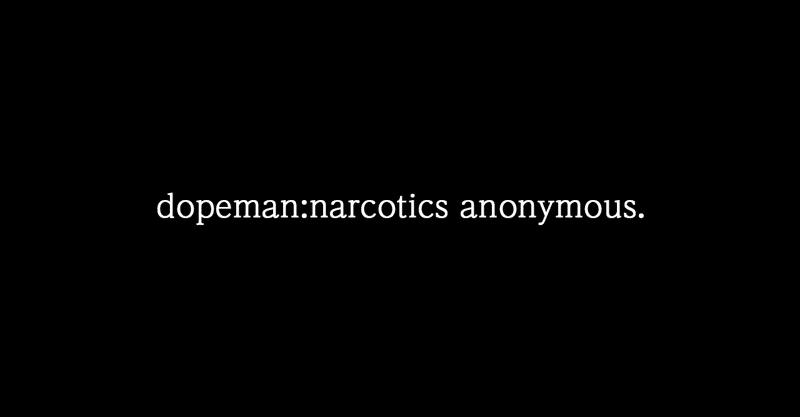
『dopeman narcotics anonymous.』#3 brotherhood part.3 吉上亮
#3 brotherhood part.3
スポーツ特待で学校に入ったのはいいものの、格段に優れた成績が出せてるわけじゃない。それはキャリアの行き詰まりを予感させた。高校から大学へ、大学からプロへ――間口はどんどん狭まっていく。要求される能力もどこまでも青天井で上がっていく。
親父が会社を俺に引き継がせようとしていることも分かっていた。俺をスポーツで大学まで行かせて、あわよくばオリンピックにも出られるようなトップアスリートの道を歩ませられるかもしれない、と親が子供によくする甘い期待を抱いてくれたのだろうが、それも年を経るごとに現実との修正を余儀なくされたんだろう。小さな会社だが、それでも経営をやれたということはある程度は世の中を正しく見ることができるひとだった。俺の親父は。
家業を継ぐか。俺は正直難しいだろうと思っていた。
弟にもそのことを話した。間違っても弟が会社を継ぐようなことがあったら困るという理由もあったが、そもそも時代のルールと親父の考える良きことのルールが修正できないくらいズレつつあった。
被害の緩和(ハームリダクション)という名目で推進されつつあった国策としての麻薬の完全合法化。そのためには依存者が適切に使用できる注射針が潤沢に供給される必要があったから、親父の会社が培ってきた精密技術は渡りに船だった。
だが、親父はその仕事を拒否した。俺は親父のことが今でも嫌いになれない。世渡り上手であることと世渡りが下手であることは別にどちからが優れているというわけでもない。だが親父が間違ったことは確かだ。継いでも先のない仕事をどう畳むのか。むしろ、俺はそのことについて考えざるを得なくなった。
そんなときに同級生だったヤツと再会したんだ。夜遅くの練習場で。
バイトで貯めた金を費やして、俺が深夜練習をやっているところにふらりとそいつは現れた。匂いがきつかった。何かに頓着しなくなった人間の匂いがした。何もかもが面倒になって家にも居場所がなくなったそいつは寝る場所を探していて、俺が借りている深夜の誰もいない練習場で眠らせてくれと言ってきたんだ。
野良犬みたいなヤツだった。そして害があるわけでもないから「別にいい」と応えた。俺は一人で練習を続けた。弓を構え、弦を引き、矢を放つ。その反復。練習没頭し、ふと我に返ったとき、視界の隅にぐずぐずになった奴がくうくうと無防備に眠ってる。悪い気はしなかった。そいつは弟みたいにすぐに腕を掴んできたりもしなかった。ただそこにいるだけの何の利益にもならない存在に不思議と心が安らいだんだ。ほんの少しの間だけ。
あるとき、そいつを忍び込ませてることが練習場の管理者にバレた。それで出禁になった。最初は好意で貸してくれていたが、別に大した成績を出すわけじゃなく宣伝にも使える見込みもないから打ち切られたんだろう。そこでちょうどいい理由が見つかった。
仕方ないことだ。俺は寝る場所を失ったそいつと夜の街を転々とした。誰にも邪魔されずに静かに眠れる場所を探し求めていたそいつは、同じくらい静かで集中したい練習場を求めていた俺にとっていつの間にか欠かすことのできない練習仲間になっていた。
街の夜。あらゆる闇の隙間。一晩だけなら誰も立ち入ることのない孤独な場所というものが、その日その日だけは存在していて、それは波の後に残る砂浜の一瞬の模様みたいなものだった。研ぎ澄まされた夜の静けさのなかで放った矢が的に当たる澄んだ音を耳が捉えるようになったとき、俺は不思議なくらいアーチェリーの技量が上達していた。
大会の成績は信じられないくらいよくなった。部活の上位メンバーを追い抜きレギュラーにも入ったが、本当に成績がよくなったのは個人競技のときだった。誰の繋がりも感じられない瞬間こそが、俺をゾーンと呼ぶべき領域に踏み入らせてくれた。
競技場でひとり弓を構えたとき、ふと寝息のような静かな音が聞こえてくる。そうすると心がどんな大きな会場でも落ち着いた。矢は狙った場所を必ず射抜いた。
大学進学にも繋がる全国大会が目前に迫り、その前日の夜に俺は親父に呼び出されて久しぶりに実家に戻った。その日だけは、いつものように練習場所を用意してくれたそいつと会う約束に断りを入れて。
夕食の席は豪勢だった。多分、とても奮発してくれていたはずだ。だって、弟とお袋が初めて、俺たちの家に来た時も同じ匂いがしたことを覚えていたから。
弟もお袋もいる席で、親父は未成年の俺にも酒を勧めたが、それを別に拒むことはなかった。翌日の授業中に頭が痛くなることがわかっていても練習が終わり夜が朝に向かって切り替わり始める時間に起き出したそいつと飲む安物の缶酒は慣れたものだったから、むしろ親父が注いだビールなんて上等なものは嬉しかったくらいだ。
親父は俺に会社を継いで欲しい、と初めて口にした。そうだろうなと思った通りだった。悪い気分じゃなかった。誰かに必要とされることが、たとえその道が行き止まりだったとしても。そして親父もまた自分が言っていることが間違っており、継がせるといいながら自分の代で会社を畳むことも考えていた。そのことを夜更けになってからボソリと呟いた。その話を聞かされたのは俺だけだった。お前たちに面倒を押し付けるつもりはない。
俺はどうしたらいいのだろう、と思った。自然と足は外へと向かった。約束をすっぽかしたそいつのいるはずのどこかへ向かっていた。そいつの静かな寝息が無性に聞きたくなったんだ。
その日の夜はいつもより深くとても冷たかった気がした。俺がそいつを見つけたとき、ごおごおと濁った寝息を立てていた。身体の何かの機能がおかしくなった異音を発していた。親父の工場の機械が壊れたときに似た音を聞いたことを思い出した。
壊れた音。死にかけた音。そいつは死にそうになっていた。あるいはまだ死んでいないのが不思議なくらいだった。
「……あれ、お友達?」
振り返った女は夜よりも濃い黒い髪をしていた。夜空に浮かぶ月が放つ耀きのように眩しく白い肌をしていた。美人なんてものじゃなかった。何かが違う。決定的に違う。人間ではない何かに俺は出会ってしまった。それは麻薬の花から生まれた魔性の怪物だった。
今、女の目の前でごおごおと濁った寝息を立て、眠りながら溶け、死んでいくそいつは様々な相手から麻薬を買っていたらしかった。そうなのだろうと何となくわかっていたが、事実を告げられると何かひとつの線が繋がるような気分になった。
薬物完全合法化が実現するということは、あるタイミングで、違法であるがゆえに途方もなく高価に売り捌かれていた麻薬が値崩れするということだ。極端なインフレによってそれまで価値のあった貨幣が紙くずの山と化すように。だから密売人たちは売り逃げを図った。そして完全合法化の前後の時期には、途方もない量の麻薬が日本各地に出回った。
供給量の爆発的な増加はそれ自体が値崩れを起こさせる。結局、子供が小遣いで買えるような値段で麻薬が出回ることになった。どんな効果をもたらすかも分からない粗悪な混ぜ物で大量の人間が脳味噌をグズグズにした生ける屍みたいにされた。
そいつも、そうやって崩れていったやつらにひとりだった。俺が弓を構えるたび、眠りながら肉体を腐らせていった。
俺は気づいていなかった。
本当にそうなの?
女が言った。
君は気にしていなかった。
そうだ。俺は頷いた。頷くしかなかった。
俺は、自分にとって居心地のいい相手だから、そいつがそこにいることを受け入れていた。だが、そいつがどうして俺の傍にいつも来るのか、その理由を考えたこともなかった。
助けてくれ、って言ってたんじゃないかな。
いや、それはない。
女の問いに、俺は即答した。そいつは助けて欲しいとは思っていなかったはずだ。罪悪感を紛らわせるためじゃない。俺もそいつも静かな場所を求めていただけだ。誰にも邪魔されず誰にも傷つけられることのない孤独な時間。一時だけでもそれが叶うなら、次の日もまた生きていくことができる。俺たちが過ごした夜は、それ自体が安らかな眠りだったんだ。
そして、そいつはもう醒めることのない眠りに落ちた。
どうしてこうなった?
混ぜ物のせいだね。普通の人間たちは名の知れた麻薬を忌避するけれど、何が混じってるか分からない半端な違法薬物のほうがむしろ効果が予測できないから危険なんだ。
詳しいな。
専門家だからね。
何の?
〈イカロス〉って知ってるかな。
ミノタウロスの迷宮。名工のダイタロス。太陽に向かって死んだ愚かな息子の名前。
よく勉強してるね。だけどここでの正解は違う。
〈イカロス〉は完全に新規な、これまで人類と薬物の歴史のなかでは存在することがなかった新たな時代を始め、そして終わらせる完全な薬物なんだ。
それを使ったら、そいつみたいになるのか。
あり得ない。この子がこうなっちゃったのはね、〈イカロス〉を盗んで売り捌こうとした馬鹿な密売人が粗悪な混ぜ物にして、それをばら撒いたからなんだ。私は〈イカロス〉の供給源だから、そういう阿呆はすぐに捕まえて報いを受けさせた。
報い?
全身の皮を剥いでから服に仕立て直して全裸になった彼に着せてやる。目玉と睾丸はどっちも引き抜いて上下の穴にそれぞれ嵌め直す。舌は切り裂いた喉から引き摺り出してネクタイにする。腹を捌いて零れ出した臓物を紐替わりにして四肢を縛って天井から吊るす為のロープにした。そして三日三晩を天日に晒して処刑は終わる。
俺は女の話を聞いている途中で反吐をぶちまけた。そこまでする必要があるのか、と俺は初めて本当の恐怖という感情を知った。助け起こしてくれた女は、そのくせこれまで嗅いだことのないようなとてもいい匂いがした。忘れられない月の花の香水だった。
ほら頑張って起きないと。女は囁いた。君にはやるべきことが残ってる。
そして、俺に弓と矢を渡した。
どうしろと?
死にたがってるその子を殺すんだ。
できません。
いいや、やれるね。君は終わりたがってる人間のことが本能的に分かるんだ。もう終わらせたいのに終わらせることができない。そういう苦しみに藻掻いている人間に正しいタイミングで引導を渡してあげられる。なぜなら、君はとても慈悲深い人間だからだ。
俺は反射的に弓を構え、そいつを撃った。もう半分くらい蝋みたいに溶けて人間ではない輪郭に変わっていたそいつを。一撃で頭を打ち抜いた。肉も頭蓋も信じられないくらい柔らかくなっていた。矢は頭を貫通し、地面にまで突き刺さった。
女はもうどこにもいなくなっていた。
殺さなければ、多分、俺は殺されていた。死にたくないから撃ったことは事実だ。しかし女の囁きもまた正しかった。そいつはずっと死にたがっていたのだ。いつか、自分が俺の構える弓の前に立ち、放たれる矢の標的となることを望んでいた。そう思ったとき、おぞましいほど爽快な気分になった。
俺には人を殺す才能があるのだと知った。
翌日、大会の決勝戦で俺は親父を撃った。終わりたがっていた親父の望みを叶えてやるためだ。親父が死んだことで会社は工場設備ごと資産の整理の対象になり、それらは親父の部下だった奴らが独立した会社に引き継がれた。ある程度の纏まった金がもたらされた。少なくともお袋が人並みに生活していくだけの。
弟は俺が面倒を見ることにした。弟は普通の世界で生きていくには問題を抱えすぎている。かといって、死にたがってるわけでもない。なら、面倒をかけないように生きていけるように何とかしてやるしかないだろう。
俺は刑務所で〈カルテル〉の派遣した人間と再び接触し、そこでスカウトを受けた。殺しそのものがテストだったのだと告げられた。〈カルテル〉の暗殺者(シカリオ)として生きることが天職であるかどうか分からないが、俺はもうそちらの道に行くしかなかったのだからそれを受け入れた。渡された〈イカロス〉のアンプルを自分に使い、能力を発現させた。
だが、それも弟がヘマをやってご破算になった。
そういえば、弟は元気にやってるか?
やってるなら、それでいい。
――何、俺たち兄弟が本当に依存してたものは、俺たち兄弟だって?
そうかもしれない。そうかもしれないな。俺はどうしても弟から離れられなかった。弟もそうだった。俺たちはお互いの存在を切り離すことができなかったんだ。
だけど、それなら俺たちは出会うべきじゃなかったのか?
家族にならなければよかったのか?
だが、俺たち兄弟は出会ってしまったんだ。
その事実は、あんたにだって変えられるものじゃない。
でも、〈イカロス〉なんてものがなかったら――とは思うよ。
だってそうだろう?
俺はどうでもいい。だけど、弟のあいつが……ドープマンになる必要なんてこれっぽちもありはしなかったんだ。
**********************************
原作:吉上亮[協力モンスターラウンジ]×漫画オギノユーヘイによる『ドープマン』マンガ本編は「くらげバンチ」にて連載中。https://kuragebunch.com/episode/3269754496830840237
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
