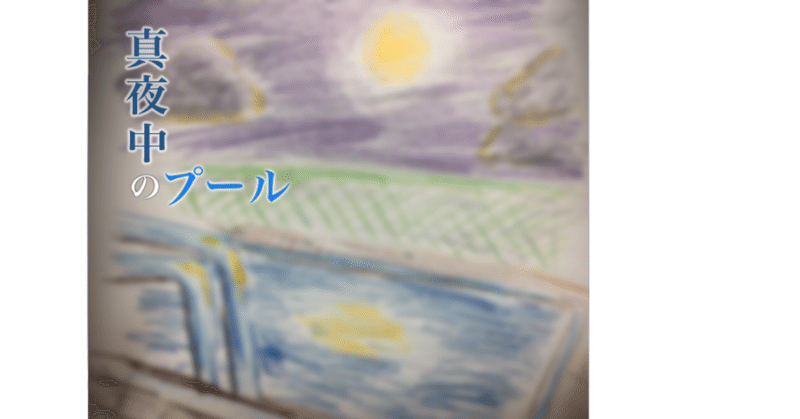
真夜中のプール
大学1年のお盆に遅めの新幹線で実家に帰り、自分が帰ってくるからと母親が気合いを入れて作った品数の多い夕食を食べ、今はほとんど荷物を運び出して何も無い自分の部屋でぼーっとしていた。
深夜1時、そばに置いていたスマホの着信音が鳴った。画面を見ると幼なじみのマサトからの着信。
「もしもし?ケンちゃん今日こっち帰ったんだろ?今から中学校集合だから!」
帰る日程を伝えてはいたが、急な呼び出しに戸惑いつつ、まぁきっと断っても家まで来そうだと思い、少し気だるそうに「......わーったよ。」と返答した。
「まぁ、断ってもケンちゃん家に押しかけて無理矢理連れてったけどな!それじゃ、中学校前の自販の前で!ツー…ツー…ツー…」
一方的に要件を告げられ、電話を切られた。やはり断るすべは無かったようだ。せっかくの帰省でゆっくりと過ごそうと思ったのも束の間、実家に着いて4時間後いきなり呼び出しを喰らった。本当に勝手な奴らだ。
寝室で寝ている親に気付かれないように、原付バイクを押して、もうエンジン音が聞こえないだろうと20メートルくらい離れた場所からキーを回してバイクに乗って中学校へ向かった。
約10分後に目的の自動販売機の光とその手前に3人の影が見えた。
遠くからだと自動販売機の光が逆光となり、誰だかわからなかったが、近づくと電話をかけてきたマサト、金髪で大きなピアス、夜中なのにサングラスという街で会ったら近づきたくない格好をしているテッペイ、チビで運動神経抜群のサトル(通称:サル)だと気付いた。三人とも中学時代からの友人だ。
「久しぶり!東京行ってんのに、お前全然変わってねーな。」
サルが、本当の猿みたいに目元と口元にシワを寄せた笑顔で言った。
「お前こそ、相変わらず猿っぽいな。」
と、言い返すと、
「うるへー。」
と今度は眉間にシワを寄せてサルが言い返してきたが、その表情も本当の猿の様に見えて、笑ってしまった。つられてマサトとテッペイも笑った。この空気感に懐かしさを感じながら、自動販売機の前でしばらく談笑していると、ヤンキー座りをしてタバコを吸っていたテッペイがいきなり、
「まぁ、世間話はこれくらいにしといて……ケン、今からプール入るぞ!」
と、立ち上がり短くなったタバコの火を足で消した。
「えっ!?マジかよ?!」
と、そのいきなりの提案に俺は驚いたが、マサトもサルも何食わぬ顔をしていた。地元の専門学校に通うマサト、高卒で就職したサル、現在無職のテッペイの三人は地元でしょっちゅう会って、プールに侵入することは何度も経験しているらしい。
その話を聞いて、地元で暮らしている三人とは違って、地元を離れて東京で暮らしをしている俺はなんだか取り残された様な感情を抱いた。
そんな軽い傷心に浸りながら、周りの動きに合わせて原付バイクを自動販売機から30メートルくらい離れた場所にある小さな空き地の隅に停めた。三人の後ろに付いて行きしばらく歩くと、中学校の屋外プールの側まで来ていた。
プールの四方がフェンスで囲まれており、フェンス上部には30センチメートルほど間隔を空けて2本の有刺鉄線が付いている。
「これ、登れねーだろ!?」
と、俺が言うと、
「甘いねケンちゃん、これには登り方があるんだよ。」
と、したり顔でマサトは言った。
三人は慣れてるようにプールの四方ある内の一つの角に向かい、俺もそれに付いて行った。
「ほら、この角には有刺鉄線がないだろ?」
と、マサトが言いながら、ちょうどプールの角の有刺鉄線の途切れたスペースを指差したが、それはギリギリ一人通れるくらいのスペースであった。
「こんなギリギリなトコ入るなんて危ねぇよ……。」と不安に考えていると、視界にサルが映り込みフェンスをよじ登りながらアラヨッと言った勢いで有刺鉄線の無いスペースを通り抜けて、本当の猿の様にジャンプして軽々とフェンスを通り越した。
フェンス越しに笑顔のサルがこちら側を見ている。自分が呆気にとられていると、後を追うように、テッペイ、マサトの順番で登り始め、最初に登ったサルが
「早くしろとよ!」
と急かしてくる。
このままじゃカッコ悪いと思い、恐怖心を押し殺しマサトの後を追いかけて自分も登った。フェンスの中に入ってすぐに「見つかったらヤバいんじゃないか?こんなの学校にバレたらどーする?大学とかバイト先にも連絡いくのかな?辞めさせられたりして。やべーよ……」などと、冷静になれば考え過ぎなことは分かるが、焦りから少しオーバーに不安になっていた。
しかし、その心理状況を悟られたく、あたかも平気そうな顔を作っていた。そんな不安をよそに、他の三人はポケットからスマホ、原付バイクの鍵、財布を出し、Tシャツを脱ぎ、ズボンを脱ぎ、気が付けばパンツ一丁になって仁王立ちしていた。
「何?もしかしてお前ビビってんの?」
と、テッペイに笑われたことに腹を立て、俺も負けじとパンツ一丁なった。
全員身に付けているのはパンツのみとなった時、マサトが
「行くぜー!」
と言った瞬間、自分以外の三人がパンツを脱ぎ捨ててプールにダイブした。素っ裸になることに若干の抵抗を感じてプールサイドに立ってた俺にサルの「早くしろよ~。」と言う声に煽られ、半ばヤケクソでパンツを脱ぎ捨ててダイブした。
勢い良く地面を蹴り上げジャンプして、水面に顔が着く直前に少し鼻を突く塩素のにおいが通り抜けた瞬間ザバーン!と、大きな水しぶきを立てて水中に潜り込む。まだ夜も暑さが厳しい火照った身体には若干冷たく感じる水温。
―――――気持ちいい。
本気でそう思った。世間から見たらちょっとしたイケナイコトをする背徳感から、少し大げさかもしれないが、社会からの解放の様なものを感じた。
水面から顔を出して「ぶはっ!!」と息を吐き出す。
立ち上がりながら、髪をかき上げて顔を拭って正面を見ると、三人が何やらニヤニヤした顔で水中を歩いて俺の方に近寄ってきた。俺の周りを囲み、気持ち悪いな......と思いながら見ていると、次の瞬間いきなり三人は水中に潜った。なんとなく良からぬ気配がして「ヤバい!」と思ったが、時既に遅し。
マサトに右腕、テッペイに左腕、サルに両足を持たれ、俺を産まれたままの姿で大の字に固められ、少し手足をジタバタと抵抗させたが、そのまま水上に持ち上げられ
「オイッ!やめろって、マジで、ちょっア゛ーーー……!!」
と叫びながら、水中に勢い良く投げられた。
鼻から水が入り、本気で死ぬかと思った。
「初めて深夜プールに来た洗礼だよ~ん。」
と、サルが無邪気に笑いながら言い、マサトとテッペイも声を上げて笑っていた。
鼻や喉に水が入って咳き込みながら、
「オイ!テメーら3対1は汚ぇぞ!」
と言い放ち、俺も笑った。
東京という都会にまだ馴染めてない田舎者な自分とのギャップ。高校までのようにクラスや部活がない大学で感じる、親密とは言い難い浅い人間関係。なんだか、そんな小さな悩みみたいなものが、この瞬間どうでもよく感じた。
それからしばらく、各々が好きな様に泳いでいた。
俺が水中から顔だけ出して浮かんでいると、マサトが平泳ぎで近寄ってきて、
「深夜のプールどうよ?案外気持ちイイだろ?それに、周りに通報とかされたらヤバイっていうちょっとしたスリルもあるから、面白いんだよね。」
と笑いながら言った。
「本当に通報されて、学校とかにバレたらやばいかもな。」
と、冗談ぽく言ったが束の間、車がプールの側を通った。俺はそれに焦って
「ヤバイ!車だ!」
と言うと、みんな動きを止めた。車が通り過ぎると、テッペイが馬鹿にした様に
「ケン、お前ビビり過ぎだぞ!?車が通り過ぎるくらいでビビんなよ。」
と言ってきて、またもう一台車が通り過ぎようとして
「ほ~ら、普通に車が通り過ぎるだけで、気づきゃしねーよ。」
とテッペイが偉そうに言っていると、通り過ぎようとしていた車がバックして俺たちの方を車のライトで照らしてきた。
「うぉ、やべーぞ!逃げろ!」
と、さっきまで偉そうにしていたテッペイが一番ビビってプールから出てパンツだけ穿いて逃げた。
次の瞬間サルがプールから出てパンツを穿き、脱ぎ捨てた衣類、財布、原付バイクの鍵、スマホを抜群な身体能力で回収し、自分とテッペイの分まで持って逃げ、フェンスを越えてテッペイに追いついていた。俺もマサトと共にサルに続いてパンツを穿いて荷物を持ち、フェンスを越えた。全員でまとまって逃げるよりも、二手に分かれて撒こうと全員が瞬時に判断してサルとテッペイ、マサトと俺で分かれて逃げた。
脳内BGMは、ミッション・インポッシブルのテーマである。
俺は走った。久々に全速力で走った。すると、グラウンドに生えているコケのようなものに滑り、膝から転んだ。持っていた荷物が一気に手から離れて四方に広がった。すぐに散乱した荷物をかき集めて立ち上がったり、また走った。
マサトと俺は学校の陰に隠れた。無我夢中で逃げていたので、アドレナリンが分泌されていて気付かなかったのか、隠れて少し落ち着いてくると左膝に痛みを感じた。見てみると、血が出ていて、薄っすら肉も見えていた。それを見てマサトは小さな声で笑った。
「いや、マジ必死で走ったらコケみたいなのが……」
と、恥ずかしながら小さな声でマサトに伝えた。
隠れていた場所からプールの方を覗くと、車から出てきた人影はプール付近をある程度見渡し、車に戻って、また車を走らせて行き、エンジン音は遠くなり、消えていった。
それからスマホでサル達に電話をし、もう大丈夫そうだと言うことと、さっき原付バイクを停めた公園に集まることを連絡した。マサトと俺は持って逃げた服を着て、俺はジーパンに膝の傷口から出る血がつかない様に、左裾を膝上まで捲った。マサトと俺は「テッペイはイカつい格好してるけど、実はチキンだぜ。」と言った具合の話をしながら公園へと向かった。
公園が見えてくると、先に着いてたサルとテッペイがこちらに気付き、手招きしているのが見えた。
みんな笑った。
僕らは大人になっていく。それに伴い、得るものがあるだろう。
しかし、失っていくものの方が多い気がする。
大人になったら、こんなことも出来ないだろう。
だけど、今日作った左膝の深い傷はきっと一生残るはずだ。
大人になっても、この傷を見ると今日この日のことを思い出して、忘れないだろう。
東の空は徐々に明るくなっていき、夜が明けていく。
また新たな一日が始まろうとしている。
この動物にエサを与えると喜びます。
