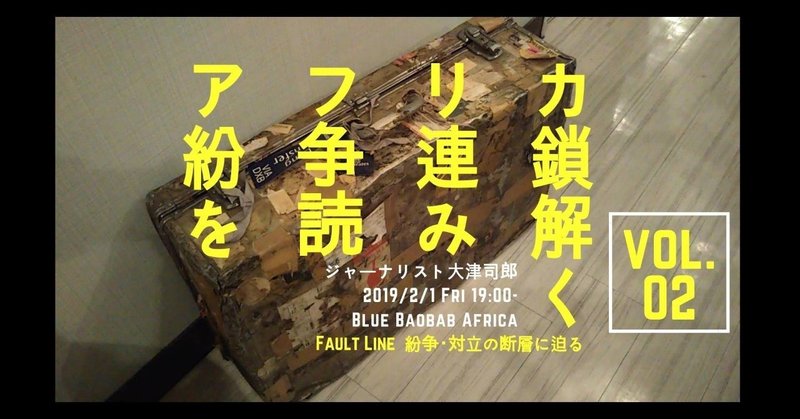
アフリカ紛争連鎖を読み解くvol.2 ~Fault Line~紛争・対立の断層に迫る
アフリカイベントに参加してきました。今回のテーマは紛争・対立。重いテーマです。
スピーカーは、フリージャーナリストの大津司郎さん。
大津司郎(おおつ・しろう)
フリージャーナリスト。ケニア、ウガンダ、ルワンダ、コンゴ、エチオピア、スーダン、チャド、ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエ、ナミビアなどの野生世界と時事問題の両面からアフリカを追求し続けている。

大津さんは、1970年に初めて船でアフリカへ。その後、1973年にチャドの飢餓を救済するために食糧を届けるプロジェクトに参加し、1975年に青年海外協力隊でのタンザニア赴任の際にスワヒリ語を習得したことから、日本のTV番組の現地コーディネーターとして活動を始めました。1990年には南アフリカでネルソン・マンデラ氏が釈放されたときにインタビューをしたことがあったそうで、20年以上も投獄されていたのにもかかわらず、マンデラ氏はニコニコして元気な様子だったのが印象的だったとか。そして、92年内戦直後のソマリアへ8ミリビデオを持って取材に行ったそうです。
会場では、93年のニュースステーションの特集「南部スーダン内戦」を取材したときの様子を、実際流れた番組を見せながら語ってくれました。
①スーダン内戦
イスラム原理主義化させようという政府と、それに反対する反政府ゲリラの戦い。大津さんは、難民キャンプの映像を見せながら、「このキャンプは、ピューリツアー賞をとったケビン・カーター氏が撮影した【ハゲワシと少女】が撮影された場所です」と教えてくれました。

TVには難民が飢餓や病気に苦しんでいるわきで、元農民や少年たちが兵士として訓練を受けている様子が映し出されました。さらに、干ばつのせいで、作物も水も不足し、国連からの救援物資が空から落とされるのみ。

この内戦は、「牧畜民(イスラム教徒)」VS「農耕民(キリスト教徒)」の戦いという図なのですが、きっかけは、アラブの春でカダフィ政権が崩壊した結果、洗練された武器が他国に流れていき、武器を手にした北側スーダンの牧畜民が水と草を求めて、南側の農耕民に襲い掛かったといわれています。

また、テロリストたち(ボコハラムなど)にとっては格好の対立であり、さらにスーダンの南側には石油資源が眠っているそうです。2011年に南スーダンは独立し、表向きには戦争は終わりましたが、まだ民族同士の対立は残っているそうです。

②ルワンダ大虐殺
大津さんは1994年のニュースステーションで流れた特集を見せながら、解説してくれました。
大津さんは新政府ができた後に取材に入ったそうです。日本の自衛隊もPKOとして1995年に参加していました。
映像には、世界最悪といわれたギタラマ中央刑務所に定員10倍の虐殺の容疑者が詰め込まれている様子が映し出されました。しかも少年たちもただ街を歩いていただけで捕まって収容され、大混乱の様子が映し出されていました。
また、5000人虐殺された教会の様子も映し出されましたが、当時の死体がそのまま放置されている映像は見ているだけで悲しくて涙が出てきそうになりました。こんなに恐ろしいことが人間にできるのかと思いました。
当時ルワンダの75%の子どもたちが、人を殺されたシーンを見てしまったそうで、精神的なサポートが必要不可欠だとインタビューに応えた医師が話していました。この大虐殺は計画的大量殺戮といわれ、欧米から流れてきた武器が後押ししたと言われます。

ただし、現在のルワンダはこの悲劇を乗り越え、素晴らしい経済発展を遂げました。アフリカのシンガポールと言われるくらいゴミ一つ落ちていない美しい街です。外国からの投資も入ってきています。
(現在のルワンダの首都キガリ)

③コンゴ紛争
2400兆円ともいわれる資源が眠っていると言われています。その資源を求めて、外国の企業や投資会社が入ってきています。
内戦が続くコンゴ(第1次コンゴ戦争(1996~1997年)、第2次コンゴ戦争(1998~2003年))では、10年間で540万人が飢餓、病気、戦争で死亡し、そして数十万人のレイプ被害者を出したと言われます。

この紛争の裏ではスマートフォンや電気自動車などに欠かせないレアメタルが発掘されていると言います。大津さんは2010年に取材をしたそうですが、「日本のメディアにはどこにも売れなかった」というビデオを見せながら話してくれました。
コンゴ民主共和国はベルギーの統治されていましたが、1960年に独立しました。高山地帯には鉱物資源が豊富な国です。そこにルワンダからの難民がコンゴに流入したと言われます。その難民キャンプができたところにレアメタルが眠っていたそうです。
資源はビシェ鉱山からゴマという都市に人が約50キロの鉱物が入った袋を背負って二日間かけてジャングルを歩いて降りてきます。特にコバルトなどは手で掘るため、子どもたちが労働者として働いているそうです。

ゴマに到着した鉱物資源を仲介人から外国人が買い、ほとんどが中国、イギリス、インドに送られるといいます。これらの資源は、大企業(テスラ、パナソニック、アップル、ソニー、サムソンなど)が買い占めに来ており、流通はほぼ中国人でまかなわれているそうです(そして70%が中国に流れている)。また最近は鉛の代わりに使われる安全なスズの市場価格が上がっていると言われています。
近年では、スマートフォンやタブレットなど世界的に需要が急増しているレアメタルですが、先進国でこのレアメタルの需要が高まれば高まるほど、テロリストに多くの資金が流れ込み、コンゴの犠牲者が増え続けるという構図が出来てしまっている。さらに、こどもが兵士として使い捨てられているという。
このようなレアメタルの資源争奪は、暴力、人権問題、土地問題を引き起こしているが、人が殺されても気にしない利益優先のコンフリクトミネラル(紛争鉱物資源)と言われます。

④日本のジャーナリズムとアフリカ問題
80年代はエチオピアの飢餓がきっかけで「We are the world」が歌われ、その後90年代のソマリア(ポスト冷戦)の頃までは日本のお茶の間にもアフリカの飢餓の子どもの映像が流れていたと、大津さんはいいます(そういえば、大人にガリガリのアフリカの子どもの写真を見せられ、残さないで食べなさい!と叱られた人も多いかも!)。
そして、93年にハゲタカと少女が撮影された時には、「写真撮ってるひまがあったら少女を助けろ!!」と苦情が届けられたほどセンセーショナルなニュースとなりました。そしてさらに、94年は映画「ホテルルワンダ」が公開されたことによりルワンダ大虐殺が知られます。
ここまでは「世界はひとつ」と感じられる空気があった、と大津さんは言います。
しかし、2001年9.11の米国同時多発テロ事件が起きて以来、世界が急に狭くなり、テロにフォーカスされるようになったと言います。さらにトランプ大統領になってからは「アメリカファースト」に代表されるように、日本を含む先進国では右翼がはびこり、自国のことでいっぱいいっぱいになってしまいました。
2017年にNHKのクローズアップ現代で、大津さんが取材したソマリア特集が流れたあと、外務省から大津さんに電話がかかってきて、「なんでそんな危ないところに行ったんですか?」と怒られたそうです。
【なぜアフリカを取材し続けるのか?】
上の問いに大津さんは、「人間が直面している困難の最前線がここにはある。この苦難の中にこそ、学ぶべきものがあるのではと思っている」と言います。ただ、日本のメディアには売れないので、日本人だけ知らないだけで、世界では普通のニュースなんです。つまり「日本人は国際情報を必要としていない島国だ」と言います。例えば北朝鮮は大陸の理論・考え方を持っているので、北朝鮮を理解したかったら、日本の視点では理解できないのです、と言います。
そして、一番犠牲になるのは「女性」と「子ども」。
アフリカの悲惨なニュースを見るたびに、ニュースステーションの久米さんが「またか」と言っていたが、「またか」なんです、と大津さんは言います。どうやったらこの「またか」という負のスパイラルから人類は抜けられるのか?
それを考えることが人類の進化の鍵ではないかと言います。
僕は、人間の欲望が丸出しのアフリカだからこそ、めちゃくちゃ面白いと思っている。
キーワードは、資源、汚職、中国、そして、フォルトライン(断層)。

また、アフリカの事情を、日本の戦国時代に例える人がいるが、それは違うと思う。日本の戦国時代は同じ文化・言語、そして二人称の世界(自分と相手)だった。しかし、アフリカ・中東・セルビアで起きている問題は、三人称(自分、相手、そしてヤツら)だ。周辺に武装集団(テロリスト)がはびこっていて、ハイエナのように紛争を利用しようと企んでいる。この第3者の存在をどうするのか?が問題になっている。
【学んだことは?】
自分には解決方法はまったく分からない。自分にできることは、いま皆さんの目の前で話しているということ、そして、自分が得た情報を伝える、ということだけ。
世界の事実を知って欲しい。
アフリカを取材したテープは日本のメディアには売れない。だから、日本人にはなかなか知ってもらう機会がない。しかし、外国ニュースメディアでは普通のニュースとして流れている。日本人だけ知らない。これをどう捉えるか。
この10年で日本人は海外に出ている人が40%減ったと言われている。しかし、中国の若者20万人以上がアメリカの大学で学んで、世界でも最新で最高の知能を母国に持ち帰っている。この差をどう捉えるか?
【難民=ネットワークという資産】
日本人は日本という国がないと生きていけないし、自分もそうだと思う。だけど、ソマリア人、アルメニア人、中国人などは、国がなくても、ネットワークだけで生きていける。「ネットワーク」という資産を持っている民族だ。難民を受け入れたドイツなどは、未来への投資としてネットワークを買ったのだと思う。日本はまだまだ外国人人材をどう登用するかでもめている。
【消費社会】
いま消費者は気候変動などの問題意識もあって、電気自動車やITの方向に進んでいるが、本当にそれは正しいのか?
「政治に善悪はないが、正誤がある」という言葉を聞いた。知らないことは悪ではないが、そのせいで方向性を間違えることがあると思う。
【なぜアフリカは平和に向かわないのか?】
植民地時代から続く「分断」がなくならない。
一度アフリカ人の男性に「お前ら、男がしっかりしないといけないじゃないか!」と言ったら、「すべての男は母から生まれる。だから、母がどのように男を育てるかがすべてのカギだ」と言われた。母親と息子の関係だ。決して父親と娘の関係ではない。
母親が甘やかして育てると息子は傲慢になり暴力を振るうようになる。それが暴力の根源になっているのかもしれない。
【世界はどこに向かおうとしているのか?】
以前は「ISISを倒せばいい」と言われていたが、今はよくわからなくなっている。
いまアフリカに、中国・ロシア企業が殺到しているが、日本は相変わらず国際極力としてしかアフリカに関わっていない。
これからどうなるのか、戦略が見えない。日本が思っているよりもはるかにアフリカは他国とガンガンビジネスをやっている。
【サバイバル・ポイント】
①ネットワーク:日本人はネットワークに弱い。中国人やソマリア人はネットワークがあればどこでも生きていける。
②テクノロジー:スマホをソマリアで購入したら、自分の通信情報が米国政府に筒抜けだった。エシュロンのように、ハッカーがサイバー傭兵として大量に雇われて攻撃を仕掛けてくる。
③セキュリティー:ソマリアではガードをカネで雇ったが、こういうところでは値切ってはいけない。値切った分だけ誰かカネを受け取れない末端の人がいることになり、最後の最後に安全が守られず、自分の首を絞めることになる。

会場の参加者は、アフリカに詳しい人たちが多く、質問のレベルが高かったです。また、アルジェリアでテロに巻き込まれた日揮のサバイバーだという男性や制服姿の高校生男子までいて、幅広い方が参加してらっしゃいました。
大津さんとは名刺交換させていただきましたが、謙虚で穏やかな印象なのに、非常に強いパッションを持った方だなあという印象を持ちました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
