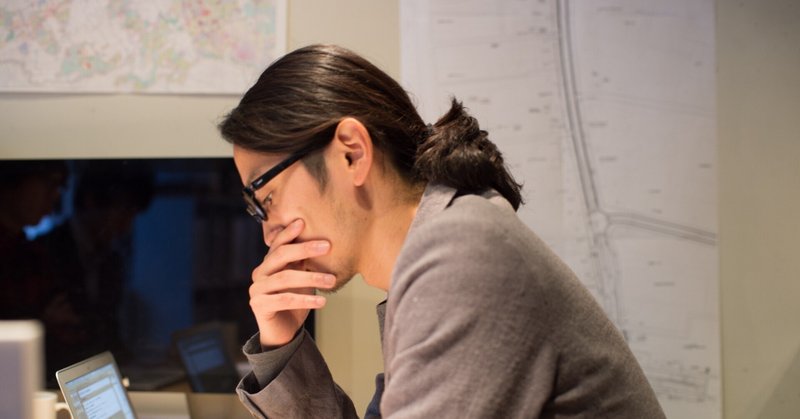
書評を書く/書いていただく
書評なるものを初めて書かせて頂いたのが2011年で10年と少しだったのでこれまでを振り返ってみる。最初は山崎亮さんの『コミュニティデザイン』の書評であった。
山崎亮『コミュニティデザイン』書評
2011-05-01刊行
コミュニティデザイナー、山崎亮氏の活動報告書である。本書の全体が今日の山崎亮氏、あるいはStudio-Lの活動がいかに形づくられたのかを記録するセルフ・ドキュメンタリー的な雰囲気を持っている。公園のデザインや小さな街の総合計画、地方都市のデパートの再生など、プロジェクトごとにドラマがあり、話し合いを続け、解決策を練っていく過程で、コミュニティも、山崎氏も、周囲のスタッフも、少しずつ成長していく様子が活き活きと描かれている。都市やコミュニティ、建築や造園に関わる人たちは、本書を通じて山崎氏が格闘してきた現場の臨場感や達成感を味わい、氏のパーソナル・ヒストリーを追体験することができるだろう。
山崎氏の自分語りふうにまとめられた本書ではあるが、プロジェクトの様々なドラマの背景を読みこんでいくと、山崎氏はやはり時代の申し子なのだと思う。氏は1973年という団塊ジュニアのピークに生まれ、転校生として全国を転々としつつ育ち、1995年の阪神大震災の経験を転機にコミュニティに関心を持ち、やがてコミュニティデザインという職能に出会う。そのプロセスは、1970年代という開発主義絶頂の時代からポストモダン的な価値の多様化へ、さらに1995年という転機を経て地方分権とともに地方都市のコミュニティがクローズアップされる時代へと至る、日本社会全体の大きな変化のプロセスと完全にシンクロしている。つまり、本書は山崎亮というひとりのデザイナーの歴史であると同時に、時代を語る本でもある。
ただし、意外と読み方の難しい本でもある。本書では「コミュニティデザイナー」という職業がどのようなかたちで機能しているかというロールモデルは示されているが、誰もが使えるようになるような、いわゆる方法論としては何も示されていない。また、「コミュニティデザイナー」の明確な定義とか、歴史的な位置づけ、批判的な検討など、いわゆる理論的な部分もない。つまり、これを読んだ人がどんなに山崎氏の活動に共感してコミュニティデザイナーを志したとしても、実際にその夢を果たすための具体的な道筋は示されていない。先輩の合格体験記を読んでも志望校に受かるための勉強にはならないのと同じで、本書はコミュニティデザインの体験記ではあっても、教科書ではない。
本書の後、山崎氏は多様な実践を重ねるとともに自らの職能を理論的に位置づけ、方法論を明らかにする、つまり、教科書を書くという段階に進むだろう。もちろん、山崎氏も推薦書に掲げる『まちづくりの方法と技術 コミュニティ・デザイン・プライマー』(ランドルフ・T.ヘスター/土肥真人, 1997)など、先行例は豊富にあるので、私たちが山崎氏の手によるコミュニティデザインの「教科書」を手にするのも時間の問題であろう。それが編まれていくプロセスで、なぜ今の日本にソーシャルデザイナーが必要なのか、コマーシャルなデザイナーとソーシャルデザイナーの違いは何か、どのようにすれば実際にソーシャルデザイナーの職能を拡大できるか、より多くの議論が巻き起こっていくだろう。
山崎氏の提唱する「コミュニティデザイナー」を目指すにせよ、異なる職業を目指すにせよ、山崎氏と同じ時代に生きる私たちにとって、本書が今という時代をつかみ、デザイナーという職能、あるいはデザインの役割の今後を考える上で大きなヒントになることは間違いない。若い世代には特に読まれたい。ただし、合格体験記と同じく、読み方には気をつけられたい。
若さに任せてやや遠慮のない書き方になってしまっているかもしれないが、山崎さんの活動に共感するからこそ、感じたことは書かなくてはと駆り立てられるようにして書かせて頂いた。メールしたら担当の井口さんに「ザ・書評という感じですね」と言われ、そうかと思ったことを思い出す。
山崎さんとはその後、『コミュニケーションのアーキテクチャを設計する』という対談集を出させて頂いた。
藤村龍至+山崎亮『コミュニケーションのアーキテクチャを設計する』
しばらく後にまた学芸出版のほうで書評をご依頼いただいた。
馬場正尊『RePUBLIC 公共空間のリノベーション』書評
2013-09-15刊行
「リノベーション」は、システムをリノベートできるか
「東京R不動産」で知られる建築家・馬場正尊氏による「公共空間のリノベーション」をテーマとしたマニフェスト的な作品集+事例集+アイディア集である。
「マニフェスト的な作品集+事例集+アイディア集」と少々説明的に書いたのは、本書の構成が読者にとって難しいと感じられるかも知れない、と感じられたからである。まず第一に、作品集をベースにしたマニフェストかと思いきや、自分以外の作品も先進事例として含まれている点。そして第二に、事例集かと思うとアイディアスケッチが並列されていて、現行の制度下では実現不可能なものも含まれている点である。
建築家によっては自らが設計した竣工作品以外はプレゼンテーションしない、という規範意識を持つ人もおり、建築系の読者はそのような規範に親しんでいるところもあるので、本書は自らの作品を含んだマニフェスト的な事例集であり、アイディア集であるから、他の建築家が出版するいわゆる「作品集」的な書籍とは少々異なる読み方を要求する点に注意が必要かもしれない(その点では山崎亮氏の『コミュニティデザイン』は自らの事例に限り、しかも実現したものばかりであるので、実は作品集のように読むことができる)。つまり本書は馬場氏の作品集というよりも、「実現できるかわからないが、こういう事例をもとにすると実現できるかも知れませんよ」という、いわゆる「企画書」的な書籍である、と理解するとわりとすんなり読める。そしてそれが本書の特徴でもある。
さらに本書を特徴付けているのは、既存建築物の増改築(いわゆる「リノベーション」)事例だけが掲載されているわけではなく、「アオーレ長岡」や「名護市庁舎」のような新築の事例も並列されており、制度や概念、組織などのような社会のシステムを「リノベート」することが含まれている点であろう。そこには馬場氏による既刊『都市をリノベーション』などで展開されてきた馬場流の概念の拡張が含まれている。
既存の建築物やシステムを前提としてそれらへの上書きを主題とするというロールモデルは、世代的なものもあるだろう。かつて塚本由晴氏と貝島桃代氏による「トーキョー・リサイクル計画──作る都市から使う都市へ」(『10+1』No.21所収)も「都市をリサイクル」すると宣言していた。同論考には東京都の公共施設のリストが含まれているなど、今日でいう公共施設マネジメントのような具体的な視点も含まれていたが、基本的には官僚組織からも、商業主義からも自由な立場で都市空間の可能性を謳う姿勢が強調されていた。
馬場氏やアトリエ・ワンの書籍を読むと、磯崎新氏の『建築の解体』と比較したくなる。磯崎氏は世界中の同時代的な動きを精力的に紹介しながら、既存のレガシー(遺産)システムを「解体」しようとした。「解体」にせよ、「リサイクル」にせよ、「リノベーション」にせよ、言葉は違うが、既存のシステムを否定し、新しいシステムの到来を高らかに宣言しているという構成には共通点がある。
もちろん、それに伴う強さと同時に、弱さもある。強さは発想の自由さ、弱さは実行力であろう。だがその弱さ、ナイーブさも、かつてのル・コルビュジエや磯崎がそうだったように、次第にキャリアが追いついていくことで解消されていく。いつしかアイディアは実現し、自らの事例が増え、「企画書」はいつか「作品集」へと変わっていくのである。本書は両者の中間点にあるのではないかと思う。
ただ、馬場氏の「リノベーション」に磯崎氏の「解体」にあったような歴史に対する解釈や批評はあまりない。もしそれらが加わったら分野を超えて理解がより大きく広がるのではないかと感じた。理論面では公共施設をめぐる状況、とくに制度や財政に対する分析が、批評面では馬場氏が経験した時代の転換、特に馬場氏が関わったという1996年の都市博中止が象徴するような、広告企画によって建設を煽動する社会からストック社会への移行への分析などが読んでみたい。
というのは、阪神大震災や東日本大震災を経験した日本社会では、投資額をとにかく低く抑えたい若者や民間のビルオーナーは別として、人命の保護に責任を持つ公共施設の保有者にとって古い構造物に対する信頼はあまり高いとは言えず、またライフサイクルの観点からも投資効率が疑問視されているなかで保存改修の意義は共有しにくい。さらに、バブル経済が崩壊し、虚構に満ちた社会が崩壊するトラウマについても、私のように少し下の世代にとっては具体的な実感がないため案外共有しにくいところもあるから、価値の転換、特になぜ馬場氏が企業社会からの自由をことさら強調するのか、前提への説明なしに共有できないところもあるからである。
とはいえ、新しい公共空間のあり方に関わる先進的な事例をこれだけ網羅的に集め、論じた本はこれまでほとんどなかった。公共空間のあり方について関心のある読者、特に公共空間を司る首長や行政職員には特に読まれ、議論されることを期待したい。私自身は本書の先進性に大いに刺激を受けるとともに、いつか馬場氏の立つ公共空間を使う立場というよりも、管理、経営する行政職員の立場に立った本を書いて、私なりの「RePublic」に挑戦してみたいと思わされた。
馬場さんとはその後、下記のトークイベントでディスカッションさせて頂いた。
馬場正尊「PUBLIC DESIGN 新しい公共空間のつくりかた』
出版記念トークイベント「パブリックをどう動かすか」
2015-4-21 東京・co-lab西麻布にて
馬場正尊×藤村龍至
http://www.gakugei-pub.jp/mokuroku/syohyo/back/2253.htm
そしてまたしばらく後に学芸出版のほうで書評をご依頼いただいた。
篠沢健太・吉永健一『団地図解 地形・造成・ランドスケープ・住棟・間取りから読み解く設計思考』書評
2017-10-10刊行
「拡大の時代としての戦後」を積極的に読む本
本書では団地を2つの観点で読んでいる。ひとつは団地をアノニマスなアーキテクトによる「設計物」として、そしてもうひとつは「歴史」としてである。
「団地」といっても本書が着目するのは「公団(日本住宅公団)」の整備した」団地である。公団が設立した1955年から宅地開発公団と合併し「住宅・都市整備公団」と名前を変える1981年以前の26年間、挙げられている事例はその前半に実現したものが多い。社会的にはいわゆる「55年体制」の確立以後、オイルショックまでの高度経済成長期にあたる。
本書によれば、同じ千里ニュータウンのなかでも大阪府営住宅の団地と公団の団地とでは設計思想が異なるそうだ。大阪府企業局の団地が新しい海外事例をそのまま取り入れるように設計されたのに対し(p.125)、公団の団地は漁村の集落のように、規範を守りながら徐々に進化するという(p.127)。新しいものを設計するというより、いわば「永遠の微調整」を続け、種を保存しながら進化するように漸進的に設計するのである。したがってプロジェクトひとつを取り出してもその意図するところがうまく見えないが、群として比較しながら読み解くことで設計者が何を改善しようとしたのか、何と闘っていたのか、背景が見えてくる。
巻末のURのOB中田雅資氏へのインタビューはそのような「寛容で創造的な設計組織像としての公団」という仮説の検証として読める。社内向けとはいえ「設計思想」として自社の設計物を自己分析しプレゼンテーションをしていたという点や「団地係」が細分化した専門家を繋いでコーディネートしていたという点など、「官僚的」と呼ばれる設計組織像とは大きく異なり、開放的で活発な協働がなされてた創造的な組織像が垣間見える。「官僚的」「均質」という紋切りの批判が見えなくしたかつての実態を再評価する視点は素晴らしい。
団地の設計に関して、社会的に記憶に新しいのは建築家による実験集合住宅だろうか。「公団」以後、1980年代から2000年にかけては建築家の起用が盛んだった。吉永氏も関わった「くまもとアートポリス」(1988-)や岐阜県営北方住宅建替(2000)などの例では「コミッショナー」あるいは「コーディネーター」という建築家を推薦する役割を任命された磯崎新が「目利き」として建築家を推薦する、というプロセスを経て山本理顕や妹島和世が起用され、それまでの規範に全く則らない革新的なプランの集合住宅が実現した。
これらの試みは団地の持つ均質性に対する批判から多様性に対するニーズに応えようとしたものだが、トップダウンのプロセスで実現されることもあって成果がむしろ均質に見え、むしろ標準設計をもとにして個別のプロジェクト毎にアレンジしていた時代のほうが却って多様性が感じられるのではないかという批評が本書の根底に感じられる。ポスト実験集合住宅の世代とも言える現在から見ると2つ前の世代の試みは新鮮に映るのは事実である。
ただ、1960年代の公団が組織として素晴らしかったのは事実だとしても、美化は危険だろう。1980年代に建築家が盛んに起用されたのは次第に硬直化した公団を含む諸組織のテクノクラシーに対するカウンター、過剰に構築されたシステムに対する破壊者として、建築家への役割が期待されたからであった。どんな素晴らしい組織でも時間が経てば硬直するし、それへの反省抜きに過去の実績を美化し過ぎると学ぶべきことを見失う。
そのように考えると、この本からの「学び」は私たちの何に活かされるのだろうか。団地設計の成功事例はこれから急成長する新興国の住宅整備の現場ではある程度活かされるかも知れない。またあるいは長らく続くデフレ経済状況の中でローコストへの追求が進み、高層板状の単調な中高層マンションの建設が相次ぐ日本では、1960年初頭より住宅設計のレベルが下がっていると言えるかも知れず、案外身近なところですぐに役立つのかもしれない。
しかし本書のような試みからの学びは、もっと大きなスケールで活かしたいものだ。我が国においてこれからの世代が考えなければいけない超高齢化社会や人口減少、都市の縮小とはつまり、団塊の世代が住空間とし、団塊ジュニア世代が育ってきた公団の作ってきた住空間を大胆に消去し、他の用途へ積極的に転換することを含む。前例のない状況に対し、緊急に、分野横断的に手法を再構築しなければいけないその状況は、本書が扱う公団の初期によく似ている。
団地だけでなく、1968年の霞が関ビルに端を発する巨大開発や、公団以後の戸建て住宅による1970年代以後の民間開発による郊外ニュータウンなど、日本には人工的な「設計物」として見なされていない「歴史的な」遺産がたくさんある。「縮小の時代としての今」の参照として「拡大の時代としての戦後」を積極的に「読む」作業は今後、活発化するのではないだろうか。その意味で、本書は他に先駆けて、「団地」という切り口からいち早く日本の戦後の建築史を批判的に再評価しようとした、先駆的な試みであると言えるだろう。
以上、最初の9年は全て学芸出版社関連の書籍だったのが、2020年に日経新聞から五十嵐太郎さんの新刊について初めて書評をご依頼いただくことになった。
五十嵐太郎『建築の東京』書評
2020-6-13 日経新聞掲載
「建築の東京」は取り戻せるか
建築史家、五十嵐太郎氏による「東京の建築」ではなく「建築の東京」、すなわち東京に建っている建築のことではなく、建築の政策や市場のことでもなく、建築家の東京への関わりが紹介される。著者が扱う話題の広さもあるが、それが意外なほど幅広いことにまず驚く。
著者が上京したという1985年はバブル最盛期、東京中が活力にみなぎっていた頃であろう。行政主導で東京の方向性を示し、フランスのミッテラン大統領の施策「グラン・プロジェ」にならい、ホールや美術館など公共文化施設の設計者に建築家を大胆に起用し、『建築MAP』がベストセラーになった。今思うと「建築の東京」の輝かしい時代であった。
青島都知事の当選によって丹下健三が提案したとされる「世界都市博」が中止された1995年を境に、建築を取り巻く状況は暗転した。その後の小渕・小泉時代の規制緩和政策により民間の不動産開発は活性化したが、欧米のみならず、北京やソウル、香港や上海、台北など他のアジアの都市に比べても、東京での建築家の活躍は限定的である。著者は「東京は経済原理を優先し思い切った冒険しない」「慢心している」と批判する。
「慢心」の最大の例は新国立競技場の一件である。ザハ・ハディドが国際コンペで選ばれたにもかかわらず提案が活かされなかった経緯は、ひとつの建築がこれだけ話題になったという意味で「建築の東京」にとって史上最大の事件であり、将来に禍根を残す出来事であったであろう。
少し引いて見るならば、建築家と都市の関係は、そのまま権力と建築の距離である。ザハ・ハディドがソウルで巨大な博物館を設計できたのは清渓川で高速道路を撤去することで人気を得たイ・ミョンバク市長が市民から大きな支持を得た結果である。東京でも日本橋の首都高速道路撤去が先であればザハの国立競技場が実現していたかも知れない。
あいちトリエンナーレの芸術監督を務めるなど美術家との交流も深い著者だけに、美術家は積極的に東京に提案しているのに建築家はなぜ提案しないのか、と建築家の責任も問う。建築家は往年のパリやソウルのように権力に保護されることを期待するよりも、ブルームバーグ市長時代のニューヨークのように建築家が都市の課題を明らかにし、政策を説明する力を発揮することで役割を見出すのも現代的な権力との付き合い方かもしれない。建築家を励まし、鼓舞する本である。
そしてその後週刊読書人、webちくまなど、書評が多く集まるサイトに書かせていただく事になる。
陣内秀信『都市のルネサンス〈増補新装版〉』書評
週刊読書人2021年10月29日号
わが国の底力が試される今、イタリアに学ぶこととは?
イタリア都市・建築研究の陣内秀信氏による「体験的イタリア都市論」である『都市のルネッサンス イタリア建築の現在』(中公新書、一九七八)の二回目の再刊行である。本書ではイタリアの都市といっても有名なローマ、ミラノ、フィレンツェではなく、ヴェネチア、チステルニーノ、ボローニャという、課題を抱えつつ、その取り組みによって再生を果たした都市が北、中部、南から一都市ずつ取り上げられている。
本書の魅力はまず、冒頭のフィールドワークでの数々のエピソードの散りばめられた留学体験記的な記述によって読者が著者のイタリアでの生活を追体験でき、気がつけば建築類型学のような専門的な議論についても体験的に理解できてしまう点にあるだろう。だが本書の興味深い特徴は、再刊行(二〇〇一)、再々刊行(二〇二一)時に都度書き加えられたまえがき、あとがきによって、一九七〇年代の著者の体験の読み方がどんどん更新されている点にあると思われる。
最初の刊行は一九七八年であり、著者がイタリアに渡った一九七三年の秋から五年後であった。当時のヴェネチア建築大学では都市と建築に関する研究で注目されていた。核となったのは建築類型と都市組織を互いに分かち難く結びついたものとして理解する「建築類型学」という方法論であった。都市と建築、ハードとソフト、計画と生活を切り離す近代主義的な方法論が全面化した時代にあって、近代主義に疑問を呈する一九七〇年前後の事態を打開するヒントを「イタリア建築の現在」に見ようとしたのだろう。
都市と建築を一体に考える方法論は、わが国ではいわゆる「町並み」に合わせた建築をつくる、あるいは建築によって町並みを復元する「コンクスチュアリズム(文脈主義)」と呼ばれる方法論として受け入れられた。二〇〇一年の再刊行時に『イタリア 都市と建築を読む』(講談社、二〇〇一)というタイトルで「読む」という側面が強調されたのは、わが国で文化財保護法改正による伝統的建造物保存地区の制定(一九七五)、都市計画法改正による「地区計画」制度の制定(一九八〇)年代以降の町並みブームの後で景観法が制定(二〇〇五)されようとしている矢先であった。
その後イタリアでは一九八〇年代に入ると、一九六〇―七〇年代に試行錯誤された方法論が実を結び、社会全体が輝きを取り戻していく。そこで推進力になったのは「建築類型学」をもとに一見特徴や構造のないまちを「読み」、特徴や構造を見出し、新たな意味を与えていく「都市再生」という方法論である。
今、わが国では著者の体験したこのイタリア流都市再生の方法論が待望されている。一九九〇年代以後本格化した経済のグローバル化の進展により、大都市への資本の投下が進み発展する一方で空洞化が進んだ地方都市では二〇一〇年代に入り、民主党政権から安倍政権に戻って始まった「地方創生」の取り組みが本格化し、観光政策とともに一定の成果が出た。いま同書が『都市のルネッサンス イタリア社会の底力』(古小鳥舎、二〇二一)と題して再々刊行を迎えたことの意味は、以上のように都市と建築をめぐる日本とイタリアの展開を比較してみると見えてくるだろう。
岸田新内閣は「デジタル田園都市構想」を掲げる。モデルにしたであろう大平正芳の「田園都市国家構想」(一九七八)には、確かに田中角栄の『日本列島改造論』(一九七二)のあと、工業化の後を見据えて定住圏を作ろうとしたり、テクノポリス構想や「頭脳分散立地」など、地域を単位に新たな経済循環をつくろうとする点など、そのコンセプトはイタリアにおける「テリトーリオ」や「キロメトロ・ゼロ」の考え方に重なる点も多い。
都市を読み、再生の方法論を見出すうえで、陣内氏がイタリアで学んだのは建築を主役した「建築類型学」であった。アメリカでは公民権運動からの展開で弱者の包摂を含めた「コミュニティデザイン」が確立された。それらに対して、わが国の「底力」となる方法論は何か。再々刊行にあたり与えられた同書のタイトルは、読者にそう問いかけている。
隈研吾『新・建築入門――思想と歴史』(ちくま学芸文庫版)書評
2022-7-19 webちくま掲載
本書は一九九四年一一月に発売された隈研吾の単著の文庫版である。隈氏は一九九四年の終わりから一九九五年の頭にかけて3冊の著書を上梓している。ひとつは一九七七―八四年に『SD』誌上に発表した論評をまとめた『建築の危機を超えて』、もうひとつは個別に発表した論説をまとめた『建築的欲望の終焉』で、『新・建築入門』は唯一の書き下ろしであった。
個人的な話で恐縮であるが、私は一九九六年の四月に大学に入学し、最初の夏休みに北海道を自転車で周る合宿のお供にと持参したのがこの書であった。旅先で読むのによいかなと思ったが、実際のところ、入門と言いながら当時の自分にはハイコンテクストな解説であった。
四半世紀ぶりに再読し、いくつかの発見があった。ひとつは、隈氏が冒頭でデリダの「脱構築」概念の相対化に頁を多く割いていることである。ちょうどその頃、建築界ではデコン(=脱構築)というスタイルが流行していた。水平垂直を崩し、地震で崩れたかのようなデザインを「脱構築」という概念で説明する者もいた。隈氏は本書で、そのような建築界の「脱構築」の受容、あるいは共振について違和感を表明している。
隈氏の違和感を後追いするように、本書が刊行された直後の一九九五年一月一七日、神戸を大震災が襲った。高速道路が横倒しになり、駅は陥没し、商店街が焼失するような凄まじい震災のリアリティのまえで、歴史の引用も、現代思想の潮流も、それらに共振した建築のデザインも無力であった。そしてこの年の三月、地下鉄サリン事件が起こった。一九八〇年代の後半は建築家の華やかな活躍が続いたが、その内実は虚構によって彩られた都市を、建築家がその虚構性を批判するポーズを取りながらまた新たな虚構を重ねるというものであった。隈の初期の代表作「M2」(一九九一)もまたそのような建築家のポーズとして提示されていたが、都市が物理的に崩壊し、オウム真理教がサリン事件を引き起こしたあとでは、そのようなポーズも完全に無力となった。
そんな一九九五年を経て、建築は大きな転換を迫られていた。隈は『新・建築入門』の執筆を経て、地方を行脚するようになった。木のルーバーで壁や屋根、内装や外装という分節や序列を超えて建築の全体を覆う「那珂川町馬頭広重美術館」(二〇〇〇)は建築界に衝撃を与え、ちょうど大学院生となり、多少は建築家の言説を理解するようになった私は、隈の確信に満ちた言説がとても魅力的に映った。今思えば、この頃の隈氏の動きは隈流の「脱構築」の模索だったのかもしれない。
隈が快進撃を始めることになる一九九五年以後のこの二五年は、経済のグローバリゼーションが進んで資本が流動化する一方、それに対抗するために地域主義が復活するという矛盾に満ちた時代であった。二〇〇〇年代初頭の表参道では、有名ファッションブランドが建築家に依頼して建築を実現する例が続いたが、建築家はよりリテラルに表層、立面そのものの意匠の提案を求められた。隈研吾はそうした矛盾に対して、表層に自律した建築ボキャブラリやパタン、理念を確立しつつ、建築やまち、社会などの深層に関わったり関わらなかったりすることで、世界とより「広く」関わることができた。そしてその方法論は新国立競技場にまで到達するのである。
文庫版あとがきで、この「一九九四年」という年は隈氏のプライベートにとっても大きな節目であったことが明かされている。「父親が入院したせいで一切出張も旅行もできず、ずっと机の前で、頭を使っていた」のだという。「コロナのせいで一切出張も旅行もできず、ずっとモニターの前で頭を使ってきた」私たちはいま、「一九九四年の隈研吾」を追体験しているのかもしれない。『新・建築入門』を再読した私たちは、どんなマップを手に次の時代へ泳ぎだすのだろうか。
そして今のところの最新の書評は下記のとおりである。最初の山崎亮さんの書評に戻ってきた雰囲気もあった。
松村淳『建築家の解体』書評
2022-7-22 webちくま掲載
復活する「巨船」のうえで建築の可能性を考えるために
松村淳は建築設計の実務経験があり、建築士資格も持つ社会学者である。新著『建築家の解体』はブルデューを用いて曖昧な建築家という職能を構成する建築「界」の構造を分析する。かつて1990年代から2000年代にかけて社会学者の上野千鶴子や宮台真司がしたような、建築家の職能の限界の指摘というよりも、可能性に着目し再構築しようとする当事者的な視点には共感を覚える。
私や松村が学生だった1990年代終わりから2000年代初めの建築界では他の分野と同じく近代主義や歴史、公共性など「大きな物語」が終焉を迎え、フィールドワークによって生活の細部やインテリアや庭に注目するなど「小さな物語」を扱うことが積極的に評価された時代でもあった。
なかでも個室の内部に現れる趣味の差異が街に集まる集団の趣味の総体として景観の差異を構成すると指摘し注目された森川嘉一郎の『趣都の誕生』(2003)は、その頃翻訳され話題となっていたブルデューの『資本主義のハビトゥス』(邦訳1993)からの影響が指摘されていた。
当時の建築界では既に1960年代末の学生運動の季節から25年以上が経過し、権威主義的な旧来の徒弟制度を強化するような非対称で閉鎖的な成績評価システムや研究室制度の在り方はだいぶ解体されていたものの、雑誌メディアはまだ強く、スターシステムはまだまだ強かった。
あれから25年が経ち、2020年代の建築界は社会学者の指摘を待つまでもなく、SNSでは新規着工数の減少や労働環境の悪化など建築に関する職能の限界を示唆する情報に溢れ、乱立するウェブメディアでは多くの建築家が登場し、大学では成績評価項目を事前に明示したり公開審査を行わなければ学生の意欲を持続できず、設計事務所では労働環境を改善して透明性を謳わなければ人材を確保できないというように、旧来のスターシステムの解体が進行している。
他方で現代の建築学生は手描き図面からCAD、さらに3次元CADからBIM、場合によってはプログラミングやAIなど、高度な技術を身に付けることも同時に求められ、「建築は必要ない」というメッセージと、「建築をもっと勉強しろ」という矛盾したメッセージが同時に与えられ硬直し、ベイトソンのいう「ダブルバインド(二重拘束)」に陥っている。
私もまた、建築界における旧来の権威主義やスターシステムに疑問を持つ一方で、上野千鶴子や宮台真司の一方的な建築家不要論にも疑問を持ち、建築家の在り方について当事者意識を持って考えてきた。10年ほど前から「ソーシャル・アーキテクト」なる職能像を掲げ、自らもそう名乗って活動している。特に建築教育に関しては20代から教育の現場に長く携ってきたことから学生の意欲の減退に歯止めをかけるべく市長を出題者に招いたり、評価に住民投票を取り入れたりすることで設計課題を政策課題に重ね、教育と社会の課題を同時に解こうと試みを継続してきた。
近年の大きな変化は気候変動やジェンダーといった大きな物語が復活し、さらにCOVID-19が大きな転換点となって、個人が各々の問いを立て、それぞれの現場で奮闘するのみでは行き詰まりが生じつつあることだ。建築界も再び近代主義の頃のように槇文彦がいう「巨船」に皆が乗って差異を競う時代に戻ってきたようにも感じられる。そのような時代に建築家という職能が政治的な正しさに回収されずにどのように社会に対して構えられるか、議論を深めたいところである。
そのような関心から、建築家の職能の歴史的背景を構造的に理解できる本書は広く読まれたいと考える。ただし、ここでも紹介される山崎亮や谷尻誠の活動や言説は、建築界で宣伝されればされるほど、学習意欲を失った学生が現状の評価に向き合わないで良いという免罪符として受け取られてしまうことがあるため、不用意に空洞化が加速するようなことがないように、その読まれ方には注意を喚起したい。
書いていただいた書評(でWeb公開されているもの)には以下のものがある。
藤村龍至『批判的工学主義の建築』書評
評者: 隈研吾
2014-11-23 朝⽇新聞掲載
既成インフラとの接続を提案
建築設計もweb2・0型にならって、ユーザーや市民が参加できる直接民主主義型にしなければいけないという、ありがちな主張の本かと思って読み始めたら、いい意味で予想を裏切られた。建築に限らず、その手の2・0型本は溢(あふ)れているのだが、ITにおもねった感じに、がっかりさせられることが多い。
しかし、若手建築家最強の論客で、東浩紀たちと福島第一原発観光地化計画で共働する著者は、大胆に、一線を越えて、2・0の先にいった感じがあって、すっきりした。
web2・0は、そもそも建築(アーキテクチュア)という、一種の空間構造化作業をモデルにした、情報空間の再編成だったのだから、建築が2・0にコンプレックスを抱く必要は全くなく、堂々と建築することに開き直れというのである。しかし、昔のように大きなハコモノを、建築家の独断で作ればいいといってはいない。設計の民主化の様々な実験もとりあげている。メンテに金のかからない既成インフラに建築を接続させれば、そこにユーザー、市民の参加が自動的に誘発され、大量のコンテンツが流れ込むという提案も目をひいた。「ソフト優先」などと弱音をはかずに、しっかりと、つながった建築を作ればいいのだ。
既成インフラの中で、著者はJRに期待をかける。駅と建築を有機的に複合させれば、2・0同様、あとは勝手にユーザーがコンテンツをアップしていくというのである。結果、福島と広島と沖縄をつなぐ国土軸と新幹線が連動し、さらに台湾からアジアへと延びれば、日本再生の新しいプラットフォームの道が開ける。戦前の「満蒙」へ延びる北西軸や、田中角栄の列島改造の北西論を90度回転させた希望の南西軸で、これぞ「列島改造論2・0」だとまで、いい切った。3・11後の暗い建築界に、一石を投じるのは間違いない。
読んだことのない読者に期待を抱かせ、著者を奮い立たせるようなテキストをいただき、いつかこんな書評を書けるようにならなくてはと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
